三、科挙を改革する その①
王安石は、各事業の成功と失敗が人材の良し悪しに左右され正に人材次第であることをとっくに理解していたので、《上仁宗皇帝言事書》の中で、彼は一連の人材の育成に対して、人材を如何選抜し、人材育成の方法は如何するかということを提案していたのだ。
兵が多くても戦争を出来る兵は少なく、官が多くても政治に取り組める者は少なく、兵員に無駄が有り、閑職も少なく無かった。これが宋の大きい双子の問題であった。員数ばかり多くても質が悪ければ、人ばかりいて役に立て無いということであり、彼らが余りに能力に欠けていたのであったが、このことは当時ばかりか後世にも存在する最大の問題だ。王安石は、人材不足が朝廷の封建官吏だけでは無く、民間も同様に人材に恵まれておらず、人材は社会全般で不足していたので、朝廷がそれに依って人民に幸福を齎すような良い政令を発しても、下の官吏は上手く実施に移す事が出来無いばかりか、却って小役人達がそれを悪用したので、逆に庶民の災渦の淵に追い込まれたのだ。幾ら良い経を唱えても、和尚の口が歪んでいては調子外れに為るのが落ちなのだと譬えられた。人材が不足していれば、法令は推進することが出来ず、何ごとも為すことは出来無いのだ。
そのため当面の急務は最大限に人材を育成することにあり、人材を育成するのに最も効果がある方法は教育で、教育を徹底する最も重要な手段は学校で、各種の学校を火急に適性に運営することが最も重点と為るのだ。王安石は古代を例にとって、国家から郷党まで凡て学校があり、学校には厳しく選ばれた教官がいて、学習内容は実用的な科目が多く、礼、楽、刑、政、或いは徳行や国を治めることの方策を説く先王の法があったと指摘した。
王安石は政権を握った後に、これらの構想を実践に付したのだ。彼は先ず科挙の制度を改革して士の制度を採用し、「声病対偶」の文を廃止して、詩や、文学の科目では無く、専ら経学で士に為ることを優先した。科挙の最終合格者は《詩経》、《尚書》、《易経》、《周礼》、《礼記》の中の任意の一科目を選択し、同時に、「兼経」を為すと称して《論語》、《孟子》を履修しなければならないとした。答案の作成に当っては先人の注釈をつける必要は無く、筋道に精通して、自分為りの理解の是非で合否を決めた。この改革は試験内容を飽く迄実用的なものにしようとしたものであり、建前として先王の道を使ったが、実際には王安石の新しい経学を主要な内容とするものだった。科挙の最終合格者は主として各種の官吏に任ずることになるので、試験内容は当然地方官の治績・行政の遣り方と関係がある礼、楽、刑、政を優先し、詩や文学の創作を重視し無いことと為ったのだ。
王安石のこのようの改革について、相反する意見があった。文学者の代表として、蘇軾が詩の創作は人の能力を判断するのに適当だと考えていたので詩を蔑ろにしたことに非常に不満をもち、経術は人格の判別や審査で優先順位を付け難く、然も、古来より辞賦を得た者達に非常に多くの名臣の輩出があったと主張したのだ。然し、士を採用するのに道学を取り入れることで有る程度彼らの不満を抑えたので、二程、朱熹などの道学の者達は詩の創作を止めることに即支持を表明したのだが、士を採用するに新学を用いたからというだけで不満を言ってはなら無いとも提言していたのだ。
王安石は更に各種の学校を創設することを強く主張して、最高学府の規模と権威を拡充して、最高学府の地位を高めて、地方でも州県毎に設けて学ばせるようにした。学校には教授の中に専門の学官を創設して経費の支出や支払いに責任を負わせ、貧乏な子弟でも公費を使って読書の機会を持つことが出来るようにした。同時に王安石は若い者でも専門の人材となれる構想を育んでいて、武学、律学と医学を設けて、国家が差迫って必要とする専門の人材を育成を計ったのだ。
科挙を通じて改革を実行し学校の設立・運営を強化したので、当時の教育制度としては前例の無い功績としては、国家の為に各分野で大量の人材を育成し、更にその人材を有効に活用した為に人材不足も解消され、あらゆる分野で官吏にゆとりが生まれ、文化事業の繁栄の条件をも造りだすことにも多大なる貢献をも為されたのだ。
王安石は、人材を育成するには間違い無く教育が重要であるとしたが、「教えること」だけでは不充分で、即ち人材の待遇と地位を高めて、更に「育成」する様にしなければ為らず、其れに依って生活を安定し、衣食に心配ごとを無くせば(贅沢な生活をさせることまではさらさら考えてい無かったことを確認しておく)働くことに専念出来ると考えたのだ。王安石はここで「清廉を維持する為に高給(?)にする」の構想を打出して、人材の育成に対して「財を持つことを許し、礼を簡素化し、法で裁く」ということをしなければならないこととした。先ず、財を持つことを許すでは、即刻、各種の人材に十分な俸禄を与えて、低級な官吏にも耕作をせずとも生活が成り立つように禄を十分に手当し、完全に衣食を保証して、位が上がっていくに連れて待遇を高めて、「貪ることを卑しみ清廉潔白で恥を知る心を養わせ」て、貪ら無いでも比較的楽に生活をすることが出来、高級な人材と高級な官吏については更に、彼らの子孫に一定の遺産を遺すことが出来る迄に彼らを厚遇し、彼らに後顧に憂いを残させ無いようにして上げようとしたのだ(子孫は自身で道を切り開くべきではないのか?)。既に財を築いていた場合は、厳しい制約を加え、それを使って法を無視する勇気を無くことにもしたのだ。禄を満足いくものにすることで、清廉潔白で恥を知る心を養って、恥知らずな汚職で法を犯すと、厳しい懲罰が科せられるようにしようとしたのだ(現在は碌も十分な上に貪るので始末が悪い)。
王安石のこの思想には大変な深謀遠慮が含まれていて、今日に措いても物凄く大きな価値を見い出せるものであったのだ。このような構想の後に、彼はこの構想を実施に移したのだ。当時の各階級での官吏の俸禄は全く低くて、高級な官吏を除いては大部分の者達に多く閑職があり、家族を養う力も無く如何しても一律に同じ待遇を受けなければならなかったので、これも、偏に『官が多く余っている』ことで棒級に偏りがあり、権力の大きな官の者達は、策を労して着服をなし、或いは不動産購入で利益を求めていたのだが、権限の小さな官は懐を肥やす充ても無く、露天商や行商を副業に持ち、甚だしきに至っては金をせびって生計を立てていたのだ。各階級の小役人達は大体が俸禄に頼らず、総て汚職によって私利を謀って生計の道を立てていたのだ。












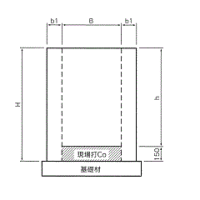







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます