現在、イスラエルとパレスチナ国の戦争状態があり、同時に力関係的にイスラエルのパレスチナ国に住む人々への一方的な破壊と虐殺になっているが、この問題について僕は特に知識を持ち合わせていないので、何かもっともなことを話すことも書くこともできない。ただここには僕なりの疑問があるので書いてみたい。現在のイスラエルからのパレスチナ国への攻撃は、人種差別の構造がある虐殺ではないか、ということである。この地域はかつてイギリスが植民地にしており、そして放棄した場所だが、ここにアメリカ・ヨーロッパ中心主義による人種差別の構造が戦略的にも無意識的にも残存させられていて、それがこの虐殺を可能にしているのではないかということだ。アメリカ、イギリスやドイツなどヨーロッパの先進国はイスラエルを支持しているが、それはイスラエルを「出先機関」としてアラブ諸国を統制しようという、アメリカ・ヨーロッパ中心主義の下心によるのだろう。むしろイスラエルの「ユダヤ人」は怒るべきなのではないか。「ユダヤ人」は、ヨーロッパでは反ユダヤ主義の中で迫害され、ナチには絶滅政策によって虐殺されたわけだが、今はアラブ諸国の支配のための「出先機関」として使われている。そして、アメリカ・ヨーロッパ中心主義の後ろ盾は、パレスチナの人々を「動物のような人間」(human animals)と呼んで虐殺を正当化しようとしている。これはナチが「ユダヤ人」を、その動物性による蔑視によって非人間的な存在として管理したことの相似的な表現だといわなければならないだろう。
ジャック・デリダも言っていたと思うが、人間を動物と呼ぶこと自体が問題なのではなく、動物を劣位な存在として名指すイデオロギーの中にこそ、人間を「動物のような存在」として差別し殺す口実が与えられている。この「動物」を人間よりも劣位な存在と見做すパースペクティヴこそ、人間中心主義としての、アメリカ・ヨーロッパ中心主義と繋がっているものだといえる。このように、ナチ・ドイツの時に「ユダヤ人」が動物性の中で虐殺された問題は、アメリカ・ヨーロッパ中心主義の問題でもあったはずなのだ。にもかかわらず、イスラエルは「ユダヤ人」を虐殺したはずのそのパースペクティヴの中で、こともあろうにパレスチナの人々を劣位(動物)において虐殺しようとする。これではイスラエルはナチを批判できなくなってしまうのではないだろうか。かつて「ユダヤ人」が迫害され虐殺された、その当のアメリカ・ヨーロッパ中心主義をイスラエルは「代行」してしまっているのである。しかも、それはイスラエルの「宗主国」となっているアメリカやヨーロッパの先進国によるイスラエルの統治・管理を通して実現される。イスラエルはそのようなかつて自分たちを苦しめたアメリカ・ヨーロッパ中心主義を「代行」させられ、しかもアメリカ・ヨーロッパによるアラブ世界の統治と石油支配のための片棒を担がされているのは、イスラエル自身にとっても本来は屈辱的なことなのではないのだろうか。そういう意味では、イスラエルとパレスチナ国との今回の戦争と虐殺は、アメリカ・ヨーロッパに大半の責任があるはずである。そのはずなのに、アメリカやヨーロッパは「イスラエル支持」という差別心を恥じることなく表明している。ただしこの場合の差別心とは、イスラエルもパレスチナ国もともに、アメリカ・ヨーロッパ中心主義に利用され管理され、同時に差別されているということだ。イスラエルもまた、アメリカ・ヨーロッパによって植民地化されている。
そもそもイスラエルは、その歴史的な在り方からして、アメリカ・ヨーロッパ中心主義の「他者」のはずではなかっただろうか。それはパレスチナの人々と共有している歴史のはずである。アメリカ・ヨーロッパ中心主義は、そのような本来は「他者」であるはずの人々と場所を統治し、搾取し収奪するために、イスラエルとパレスチナ国とを利用している。勿論、力関係からしてイスラエルの圧倒的な軍事力による虐殺は、イスラエルの責任ではあるが、イスラエルを利用してアラブ世界と石油を支配しようとしている、アメリカ・ヨーロッパ(中心主義)こそ批判されるべきだろう。もちろんここにはおこぼれにあずかろうとしている日本も含まれている。イスラエルとパレスチナ国の間に争いを継続させ、アラブ世界を常に不安定化することが、資本主義の目的であり、アメリカ・ヨーロッパ中心主義がその覇権を維持するための方策といえるだろう。このように考えれば、本来はアメリカ・ヨーロッパ中心主義こそ、イスラエルの「敵」だというべきではないか。
今回、様々な「虐殺」が報道され、SNSでその様子が拡散されていた時、それ自体で右往左往するのはおかしいと思っていた。勿論、「虐殺」には反対である。しかし大西巨人『神聖喜劇』にもあったように、「戦争」に「勝つ」ためには「殺して分捕る」が必須であり、どのような非人道的なことをしようとも、多く殺した方が勝ち、ということがある。戦争に勝つためなら、人は手段など絶対に選ばないのだ。この厳然たる「戦争」の存在論は押さえておかないといけない。なにがしかの「情」や悪い意味での「道徳」は、結局そこで起こっている「虐殺」の厳然たる事実を見失わせてしまう。この戦争の「殺して分捕る」という収奪は、戦争の基本であり、資本主義(帝国主義)の原理だからである。そして、この収奪と搾取は、イスラエルとパレスチナ双方の国からの、そしてアラブ世界からの収奪と搾取であり、それによって資本蓄積をおこなっているのは、アメリカ・ヨーロッパ中心主義とそれのおこぼれを狙う「同盟国」(もちろん日本も)たちである。「オリエンタリズム」は健在だということだろう。
さて、ディルタイを読み進めている。『全集』の第二巻の「草稿」を読んでいてさらに理解が深まったと思う。やはり、ディルタイは、精神科学と自然科学は別のものとしながらも、その双方を表象可能にしている、意識や心理の「論理学」には共通性を見出そうとしている。確かにディルタイは、精神科学が自然科学に「従属」しているところがあるとはいう。それは自然科学が何よりもまず「体系」を必要とする科学であるためで、精神科学も自然科学同様に「体系」が必要だからである。精神科学は自然科学の「論理」を借りて来るという言葉は、このことを言うのだろう。しかしながら、ディルタイは、精神科学は自然科学とは違った独自の「体系」を持っているともいう。この精神科学と自然科学の同一性と差異を説明するには、やはりその「体系」を可能にしているのは、意識や心理の「論理学」という共通の論理的地盤(超越論的条件)があるといわなければならないだろう。ディルタイは今のところはっきりとそうとはいわないのだが、「草稿」を読むとこう解釈をせざるを得ない。
ジャック・デリダも言っていたと思うが、人間を動物と呼ぶこと自体が問題なのではなく、動物を劣位な存在として名指すイデオロギーの中にこそ、人間を「動物のような存在」として差別し殺す口実が与えられている。この「動物」を人間よりも劣位な存在と見做すパースペクティヴこそ、人間中心主義としての、アメリカ・ヨーロッパ中心主義と繋がっているものだといえる。このように、ナチ・ドイツの時に「ユダヤ人」が動物性の中で虐殺された問題は、アメリカ・ヨーロッパ中心主義の問題でもあったはずなのだ。にもかかわらず、イスラエルは「ユダヤ人」を虐殺したはずのそのパースペクティヴの中で、こともあろうにパレスチナの人々を劣位(動物)において虐殺しようとする。これではイスラエルはナチを批判できなくなってしまうのではないだろうか。かつて「ユダヤ人」が迫害され虐殺された、その当のアメリカ・ヨーロッパ中心主義をイスラエルは「代行」してしまっているのである。しかも、それはイスラエルの「宗主国」となっているアメリカやヨーロッパの先進国によるイスラエルの統治・管理を通して実現される。イスラエルはそのようなかつて自分たちを苦しめたアメリカ・ヨーロッパ中心主義を「代行」させられ、しかもアメリカ・ヨーロッパによるアラブ世界の統治と石油支配のための片棒を担がされているのは、イスラエル自身にとっても本来は屈辱的なことなのではないのだろうか。そういう意味では、イスラエルとパレスチナ国との今回の戦争と虐殺は、アメリカ・ヨーロッパに大半の責任があるはずである。そのはずなのに、アメリカやヨーロッパは「イスラエル支持」という差別心を恥じることなく表明している。ただしこの場合の差別心とは、イスラエルもパレスチナ国もともに、アメリカ・ヨーロッパ中心主義に利用され管理され、同時に差別されているということだ。イスラエルもまた、アメリカ・ヨーロッパによって植民地化されている。
そもそもイスラエルは、その歴史的な在り方からして、アメリカ・ヨーロッパ中心主義の「他者」のはずではなかっただろうか。それはパレスチナの人々と共有している歴史のはずである。アメリカ・ヨーロッパ中心主義は、そのような本来は「他者」であるはずの人々と場所を統治し、搾取し収奪するために、イスラエルとパレスチナ国とを利用している。勿論、力関係からしてイスラエルの圧倒的な軍事力による虐殺は、イスラエルの責任ではあるが、イスラエルを利用してアラブ世界と石油を支配しようとしている、アメリカ・ヨーロッパ(中心主義)こそ批判されるべきだろう。もちろんここにはおこぼれにあずかろうとしている日本も含まれている。イスラエルとパレスチナ国の間に争いを継続させ、アラブ世界を常に不安定化することが、資本主義の目的であり、アメリカ・ヨーロッパ中心主義がその覇権を維持するための方策といえるだろう。このように考えれば、本来はアメリカ・ヨーロッパ中心主義こそ、イスラエルの「敵」だというべきではないか。
今回、様々な「虐殺」が報道され、SNSでその様子が拡散されていた時、それ自体で右往左往するのはおかしいと思っていた。勿論、「虐殺」には反対である。しかし大西巨人『神聖喜劇』にもあったように、「戦争」に「勝つ」ためには「殺して分捕る」が必須であり、どのような非人道的なことをしようとも、多く殺した方が勝ち、ということがある。戦争に勝つためなら、人は手段など絶対に選ばないのだ。この厳然たる「戦争」の存在論は押さえておかないといけない。なにがしかの「情」や悪い意味での「道徳」は、結局そこで起こっている「虐殺」の厳然たる事実を見失わせてしまう。この戦争の「殺して分捕る」という収奪は、戦争の基本であり、資本主義(帝国主義)の原理だからである。そして、この収奪と搾取は、イスラエルとパレスチナ双方の国からの、そしてアラブ世界からの収奪と搾取であり、それによって資本蓄積をおこなっているのは、アメリカ・ヨーロッパ中心主義とそれのおこぼれを狙う「同盟国」(もちろん日本も)たちである。「オリエンタリズム」は健在だということだろう。
さて、ディルタイを読み進めている。『全集』の第二巻の「草稿」を読んでいてさらに理解が深まったと思う。やはり、ディルタイは、精神科学と自然科学は別のものとしながらも、その双方を表象可能にしている、意識や心理の「論理学」には共通性を見出そうとしている。確かにディルタイは、精神科学が自然科学に「従属」しているところがあるとはいう。それは自然科学が何よりもまず「体系」を必要とする科学であるためで、精神科学も自然科学同様に「体系」が必要だからである。精神科学は自然科学の「論理」を借りて来るという言葉は、このことを言うのだろう。しかしながら、ディルタイは、精神科学は自然科学とは違った独自の「体系」を持っているともいう。この精神科学と自然科学の同一性と差異を説明するには、やはりその「体系」を可能にしているのは、意識や心理の「論理学」という共通の論理的地盤(超越論的条件)があるといわなければならないだろう。ディルタイは今のところはっきりとそうとはいわないのだが、「草稿」を読むとこう解釈をせざるを得ない。











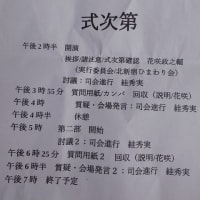








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます