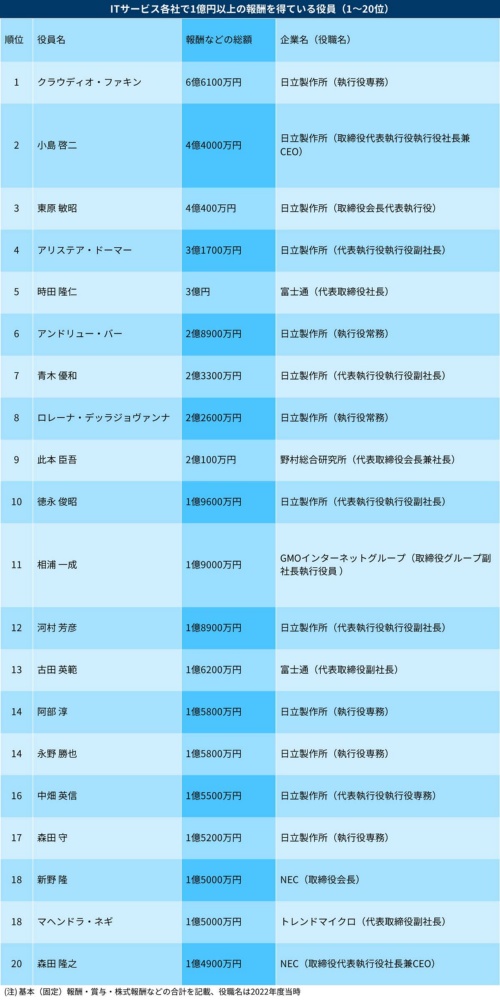最近、またお馬鹿youtuberたちが、無邪気にBRICS通貨が米ドルにとってかわると、無邪気なデマを流しています。 注意報発令します。 お馬鹿ではなく、ちゃんとした人の話を聞きましょう。 何ケ月も前から答えは出ています。
2023年4月28日付け記事より引用
実現可能性が低い BRICS 共通通貨構想~最大の懸念材料はブラジルの親米回帰
三菱UFJ銀行 リサーチ&コンサルティング(日本有数のシンクタンク)
調査部 副主任研究員 土田 陽介https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/04/report_230428_01.pdf
○ブラジルのルラ大統領は中国の習国家主席との会談に臨んだ際、米ドルへの依存を低下さ
せるために、BRICS間での貿易決済に用いるための共通通貨を創設する構想を持ちかけた。
○とはいえ、人民元の国際化を図りたい中国の立場からは、BRICS 共通通貨などを挟まず
に、そのまま人民元と各国の通貨の直接の交換量を増やしていく方が望ましいはずであ
る。
○それにブラジルでも、ルラ大統領の後任が親米右派の政治家となれば、「米ドル支配から
の脱却」というムードが和らぎ、BRICS 共通通貨構想は一気に萎むこと予想される。
(1)BRICS 共通通貨の創設を主張するブラジルのルラ大統領
ブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルヴァ大統領(ルラ大統領)が、いわゆる BRICS間での共通通貨の発行に野心を燃やしている。
4月中旬にルラ大統領は中国を訪問し、習近平国家主席との会談に臨んだが、その際に、米ドルへの依存を低下させるために BRICS 間での貿易決済に用いるための共通通貨を創設する構想を持ちかけた。
またルラ大統領は、4月26日、訪問先のスペインでも BRICS 共通通貨を創設する構想に積極
的な態度を示した。
これに先立ち、1月にルラ大統領は、アルゼンチンのアルベルト・フェルナンデス大統領に対して、あくまで貿易決済にのみ限定される「デジタル通貨」の発行を検討するとはしながらも、共通通貨の創設を呼びかけた経緯がある。
なぜルラ大統領は共通通貨構想を推し進めようとしているのか。最大の理由は、それが長年にわたる「米ドル支配からの脱却」につながる可能性を持つためである。
中南米諸国では米ドルが広く流通しており、米国の経済運営の影響を強く受けるため、経済運営の自律性に乏しい。その回復こそ経済の安定につながるというのが、ルラ大統領の主張である。
こうした反米的な経済観は、中南米諸国の左派政権の伝統である。言い換えると、右派政権の場合、基本的に親米的な経済観を持つことが多い。反米と親米を繰り返すというのが、中南米諸国の政治の大きな流れである。生粋の左派政治家であるルラ大統領には「米ドル支配からの脱却」こそブラジル経済を安定させるという信念があるのだろう。
なお3月24日には、BRICS 銀行として知られる新開発銀行(NDB)の次期総裁に、ジルマ・ル
セフ元大統領が就任することも決定した。ルセフ元大統領もルラ大統領と同じ労働党出身の大物政治家である。BRICS の実質的な「盟主」の座を狙っているかはさておき、左派政権の下でブラジルが新興国の連帯の強化を謳っていることは確かである。
(2)共通通貨の発行でも改善が見込みがたい通貨の安定性
共通通貨を発行する場合は、理論上、様々な前提を満たす必要があるが、それは①経済の構造(つまり発展段階)を収斂させること、②経済の運営を収斂させること、の2点に要約することができる。
①の前提に従えば、例えば貿易取引や資本取引が自由化された国と管理された国による通貨統合は、理論的に難しいということになる。
また②の前提に従えば、物価や金利の水準が近しくなるように、経済の運営を変えていく必要がある。
さらに、ある国で経済の不均衡が深刻化した(例えば財政危機や国際収支危機が生じた)とき、加盟国間で迅速に所得移転が行われる必要がある。2010年代前半に生じた欧州債務危機
は、この前提を満たしていないために生じた危機である。
ルラ大統領は、BRICS 諸国が貿易決済に用いる共通通貨を「デジタル通貨」で発行し、各国での通貨は引き続き独自で流通させるかたちを念頭に置いている模様である。またユーロに参加した欧州連合(EU)の諸国のように、経済運営を厳しく制限されることがないよう、共通通貨と各国通貨との間の為替レートが変動することを前提としているとみられる。
ルラ大統領は、いわば、ソフトな通貨統合を志向していると考えられる。とはいえ、そうしたソフトな通貨統合を図るならば、通貨統合に伴うデメリットが軽くなる反面で、得られるメリットも弱くなる。
とりわけ、加盟国間で為替レートが変動し続けるなら、為替リスクが払しょくされず、BRICS の経済圏としての一体性はそれほど向上しないことになる。
それに、共通通貨と各国の通貨との為替レートが、引き続き各国の経済の基礎的条件(ファンダメンタルズ)に応じて決定されるため、高金利政策を維持しない限り、ブラジルのような高インフレ体質の国は為替レートを安定させることができない。
そうしたルールベースの政策運営が、バラマキ志向が強い左派政権の下で可能か、大きな疑問が残る。
(3)信用力がある人民元を発行する中国の意向は不明
そもそも、BRICS 間で共通通貨を発行するとして、信用力の中心となるのは中国にならざる
をえない。
すでに中国は世界二位の経済力を持っており、2020年代末には米国の経済規模を追い抜くとの観測もある。
中国の意思はさておき、BRICS 諸国が共通通貨に期待することは、その発行を通じて人民元の信用力を共有することにあると考えられる。
確かに中国は、人民元の国際化を望んでいる。国際決済で人民元が使えれば中国にとって有利であるし、いわゆる CIPS(人民元決済システム)もそうした観点で整備されてきた制度である。
とはいえ、中国は中国が望むかたちで人民元の国際化を図っているのであり、それと BRICS 共通通貨の発行の推進は、必ずしも重なり合うものではない。
それに、人民元の国際化を図りたい中国の立場からは、BRICS 共通通貨などを挟まずに、そのまま人民元と各国の通貨の直接の交換量を増やしていく方が望ましいはずである。
確かにブラジルなど他の BRICS 諸国は、共通通貨を発行することで中国の信用力を間接的に得ることができるが、一方で中国がそうしたかたちでの信用力の提供に前向きか定かでない。
他方で、いくらソフトなかたちとはいえ、共通通貨を発行することで、BRIC 間で非対称な経
済ショックが発生した際に、そのコストを中国が負いかねないリスクもある。
具体的には、仮にブラジルで国際収支危機や財政危機が生じた場合、中国がその波を、金利の上昇や通貨・株式・債券の価値の下落というかたちで強く被る可能性があるということである。
今の中国に、こうしたリスクを抱えてまで BRICS 間で共通通貨を発行する意思があるとは考
えにくい。繰り返しとなるが、中国が人民元の国際化を図っているとはいえ、その動きとブラジルのルラ大統領が提唱する BRICS 共通通貨の発行は、必ずしもベクトルが合致するものではない。
中国は中国自身の戦略に基づき、人民元の国際化を図るはずである。
(4)最大の懸念事項はブラジルの親米回帰
BRICS 共通通貨に関わる最大の懸念事項は、その推進を図るブラジルで親米政権が誕生する
ことに他ならない。
ルラ大統領の後任に、その前任であるジャイール・ボルソナロ前大統領のような親米右派の政治家が就任すれば、「米ドル支配からの脱却」というムードが和らぎ、このBRICS 共通通貨構想は一気に萎むと予想される。
EU の通貨統合は、各国の主要政党の間で、その政治的な立場を乗り越えて実施されたプロジ
ェクトである。
そしてそれは、「ヨーロッパ統合」という極めて大きな目標が共有されたことで可能になった側面が大きい。
そうした政治的な立場を超えた国民的な合意が、今のブラジル社会、ひいては BRICS 諸国の社会で形成されるとは考えにくい。
中国とインドの関係から考えても、両国が BRICS 共通通貨の導入に前向きになることはない
だろう。
中国とインドは新興国の両雄であるが、両国の関係は是々非々であり、必ずしも常に友好的ではない。政治的には国境紛争を抱えているし、経済的にも摩擦を抱えている。
現職のナレンドラ・モディ首相の後任が親米寄りの政権となる可能性も残っている。
このように整理していくと、BRICS 共通通貨の発行は、政治的にも経済的にも非常にハードルが高い試みであることは明らかである。ルラ大統領はアルゼンチンとの間で共通通貨を発行し、それをさらに中南米全土に広げる構想も抱いているが、それが結実する可能性もまたかなり低いといわざるを得ない状況である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
米ドル体制を脅かすのは、現時点では中国の人民元(CIPS決済システム)、長期的にはEUのユーロですよ。 ブッシュ政権でのイラク戦争も本質はEUがアメリカに奪われた世界覇権をとり返すために、
フランスのシラク大統領が暗躍し、イラクのフセイン大統領に石油決済を米ドルからユーロ決済にするようそそのかし、フセインが野の話に乗ったために、アメリカが激怒しただけの話です。
フランスはいつも、欧米一体とヨーロッパ主義でアメリカに対抗する一面を持っています。
リンカーン、ケネディ、安倍元首相暗殺の共通点 https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/62b46eec87d1a18e8da9195e4d353d64
9.11テロの真実とイラク戦争そして世界覇権を狙うEUー1https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/2404c5d99053d41d9735652c8d690f6a
2003年イラク戦争の真実https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/e818fde0d5a37c2746fe6b54b8105a56
2003年イラク戦争の真実ー2 基軸通貨、食料、水
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/7beca659ddfbddd31282c9415c0651fa
今回は、西側先進諸国から経済制裁で困ったプーチン・ロシアが、ドル決済ではなく、アジア決済同盟」(ACU)での共通通貨BRICS通貨?で決済しましょうと呼びかけたのがキッカケ。
ACUの参加国は、
バングラデシュ、ブータン、イラン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ、ミャンマー
と失礼ながら世界経済を語るには、インドを除きあまりにしょぼすぎます。
また、プーチン・ロシアのGDPはブラジルや韓国より小さく、世界のGDPの2%しかないというしょぼさ。
アホがBRICS通貨を金本位制にするとかデマを流しているが、アメリカが金本位制を辞めたのは、世界経済に見合う金の絶対量が地球上にないからです。
それで江戸時代から圧倒的に世界No.1の石油埋蔵量、生産量を誇るアメリカが石油本位制のドル基軸通貨体制としました。これをペトロダラーシステム’と呼びます。
石油埋蔵量、生産量が世界N0.2のサウジアラビアに対し、安全保障および王家の安全をアメリカが保証するので石油決済をドルで行うよう約束して、ドルは盤石な世界の基軸通貨となったのです。
このくらいは、高校生レベルの話。 最近のyoutuberはアホばっかりです。
『何事も失敗の原因の本質は、無知と根拠なき楽観!』
Renaissancejapan