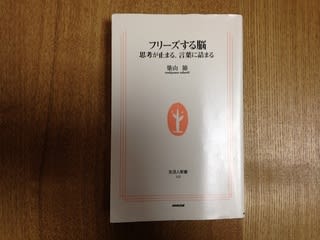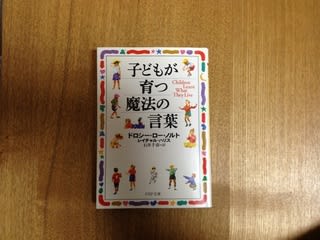今週の書評です。
今週のチョイスはこちら・・・

「明治を支えた賊軍の男たち」 ~ 星亮一 著
日本の歴史に輝しくその名を残す「明治維新」。
我も我もと誰もが薩長になびく中、旧幕府出身者は「賊軍」として社会の片隅に追いやられ、
悲惨な状況に追い込まれた。
ただし、そんな状況のなかから「しぶとく這いあがり」、政治経済、学術の各世界で
トップに上り詰めたたくましい人々が何人もいた。
・財界のトップとなった 渋沢栄一。
・学術の歴史に名を残す 福沢諭吉。
・歴代最強の総理大臣と言われる 原敬。
などなど・・・
直接の幕臣ではない 「野口英世」なども含めて全部で紹介されていますが10人紹介されています。
このメンバーが旧幕臣だったというのも、ちょっとした驚きでした・・・。
本書はそんな「賊軍の男たち」にスポットライトを当て、その生き様を紹介している。
各人に共通するのはその 「不屈の精神力」である。
たとえ逆境にあっても誇りを失わず、志を失わず近代日本の中心人物にまで上り詰めていく。
現代に置き換えてみると、ちょっと考えられないようなサクセスストーリーばかり。
なかなか痛快で面白い。
彼らがおかれた逆境のことを考えれば、今の日本人がおかれている逆境なんて
大したことはないのだと思いました。
いまの混沌とした日本の状況は、実は幕末のころに少し似ているのかも。
どんな逆境におかれても、決して悲観することはない。
むしろ自己の成長にとって「逆境は歓迎すべきこと」なのでしょう。
彼らの生き様を読みながら、そんなことを考えさせらたのでした・・・。