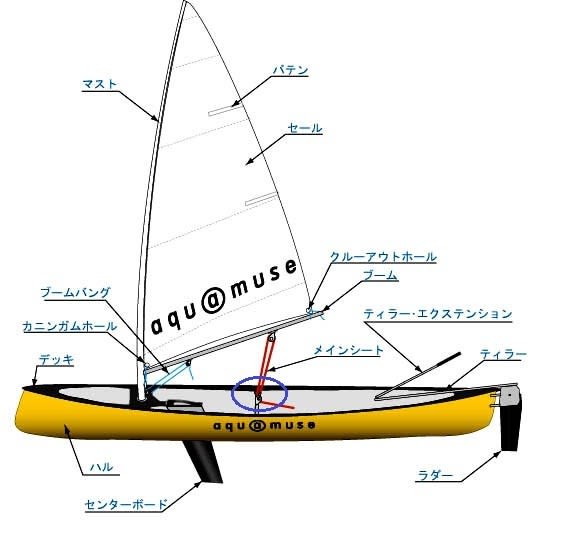除雪に適した長靴は何か問題につき、高田の一斉除雪で一定の結論をみた(笑)

多くの人が私と同じ「作業長靴」を履いていたのは、恐らく農林水産建築方面の人が、普段の仕事用の長靴で除雪していたことが第一。
この長靴は筒の部分の太さが絶妙で、ズボンを中に入れるにしても余裕があり、太すぎないから歩き易く、底と足首に柔軟性があるのでハシゴで屋根に上る、滑りやすい屋根の上で歩くことに適していて、かつ値段もそこそこで耐久性もあるから現場の人に人気があるのだ。
ライニングは薄い布張りだけでも、新潟くらいの寒さだったら防寒靴底を入れて厚い靴下を履けば事足りるし、除雪以外にも農作業や災害ボランティアと季節を問わず使えるのが有難い。
この長靴の筒上部に2本の横筋と斜めの筋が入っているのは飾りではなく、各自が好きなところで切って使ってくださいという配慮であるらしい。この配慮は、フクラハギの太い相撲取り体形にとってもありがたいと思う。
雨合羽はズボンの裾をマジックテープでアジャストできるタイプを選んでいるのは、スパッツ無しで深雪に入っても裾から雪が入らないため。
第二に、ライニングのある防寒長靴は、寒い中で動かず立っているようなスキー場リフト作業員や交通誘導員には向いても、除雪作業はとにかく汗をかくから蒸れるし、内部結露が乾きにくい。また柔軟性が劣るので屋根の上の作業に向いていないこと。
こんな理由で、作業長靴が好まれているのではないか。
検索したら仙台の「弘進ゴム工業の作業長靴」であるらしく、カラーリングは黒・青・白・黄色・赤と5色のラインナップ!
私が白を選んでいるのは、暑い時期でも比較的涼しいからデス。
流通している長靴の大部分はPVC製やEVC製などの塩化ビニール系の素材で、歩くだけでマイクロチップをまき散らしているから、長持ちする作業長靴は、粗大ゴミの減量にも役立っていると思う次第。
ちなみに作業長靴には爪先ガード有りのタイプと無しのタイプ2種類があり、有りの方は長く使っていると爪先ガードの付根から裂けてくるし、無しの方が軽くて柔軟性があるので、私は無しのタイプを愛用している。
茶色いゴム製ブーツは、日常用とバイク用にアウトドアショップで買った長靴だが、選定理由は作業長靴と同じく歩き易く足入れがし易い他に、自然素材の長靴を普段履きにしたかったことが一番の理由。
英国製と思い込んでいたのだけど、これもネット検索したら弘進ゴム工業製だったと判明した。相性がいい会社なのね。
確か12,000円くらいで買ったハズだが、すでに20年近く愛用しているので安い買い物だと思うし、現在は18,000円と値上がりしているようだ。
天然ゴム100%だと1シーズンくらいしか保たないと思うので、なにがしかの添加物は入っていると思うが、バイク屋さんに教えてもらって、たまに保革ワックスを塗って手入して20年も履いているので、長持ちする分はエコだと思う。