









県外在住の糸魚川出身の皆様へ

今年もホタルイカが浜にあがる季節になりました。







帰宅したら玄関に海藻のアオサが置いてあった。

田舎では誰かが黙って山菜や海産物を置いていくのはよくあるが、最近は送り付け詐欺の話も聞くのでとりあえず冷蔵庫に保管。
夜遅い時間になって高校美術部の後輩、居酒屋を経営するT君からの贈り物である旨のメッセージが入ってひと安心。
漁師さんから魚を頂いた翌日だから、感激もひとしお。漁師さんも大変だけど、居酒屋も大変だろうにねぇ。
昨夜のNHK「逆転人生」で、借金地獄から脱出して、同じ境遇の中小企業経営者のために経営コンサルタントになった吉川博文さんが、「経営破綻して自己破産したり自殺する場合は、ほとんどが自滅なんです。孤独ではないと寄り添う人の存在が大事なんです。」と提言していた。
大変な時にこそ、心を寄せる誰かに親切にするし、親切にされた人はまた誰かに親切にして助け合う。
助け合いの輪が広がって、みんなでガンバロウな!と心が一つになっていく。
ワンチームや統合という言葉は、トップダウンではなく、何か大変な時期に底辺から湧き上がってきた方が自然だ。
心を寄せて孤独でないことを教えてくれたみなさん、ありがとう。
この気持ち、誰かにバトンタッチしなきゃね。




親不知の漁師、松沢船長が、セイカイ(ウスメバル)、アジ、そして初めて見る八角という珍しい魚を持ってきてくれた。



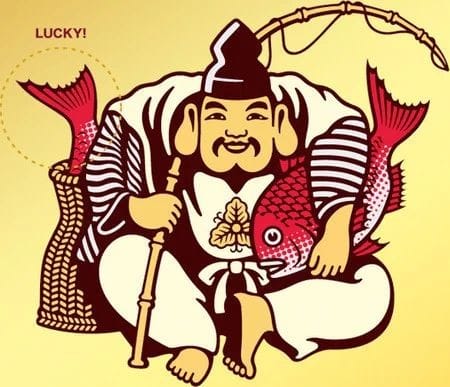
朝刊に高校時代の体育の先生が出てたので、県外在住の同窓生のために!

江戸時代の戯歌に「糸魚川に過ぎたるもの三つあり、豆腐、玄白、稚児の舞い」というのがあり、これは片田舎の糸魚川であっても水が美味いので豆腐が美味い!相沢玄白という名医がいる!4月10日のけんか祭りの後に奉納される稚児の舞いが雅である!という自慢だが、親父が世話になっている「デイサービスひのき文庫」を加えてみたい。



元旦に初めてのお客さん。

最初に来たのは、おさななじみの直子嬢夫妻

直子嬢が帰ったすぐ後に同じくおさななじみのふさ子嬢の夫婦が相次いでやってきて、縄文オカリナを買いに来てくれた。
元旦に2名の弁天様(!)の訪問とは春から縁起がいい。

直子嬢のご主人はマレーシア人のイスラム教徒だから、イスラム式のお正月の祝い方や挨拶を質問・・・特にないそうです(笑)

二人が買ってくれたのは遮光器土偶オカリナ
同級生っていいな!
年末恒例の包丁研ぎをしていたら、3年前の糸魚川大火でボランティアに来ていた栃木の藤久保氏が復興の様子をわざわざ観に来てくれた。

糸魚川のお節料理に欠かせないのが寒ブリの刺身だから、包丁研ぎは大事な年末行事。普段使っていない包丁も研いで椿油を塗り込んでおく。
私が気にはなっていたのは高齢被災者の現状であったので、商家に入ってその後の状況を聞いたら、大部分の方は復興住宅に入居したり近くの老人ホームに入居したとのことで一安心。

大きな駐車場を持つ「にぎわい広場」に立つ藤久保氏は各地の災害ボランティアで飛び回っている人

広場の地下は、消火用の水が足りなくて海水まで使った大火を教訓として消火用貯水槽になっているそう。

最初は店舗の場所が変わっていたので気付かなかったが、話を聞かせてくれた商家のご婦人は、私がボランティアで入った老舗仏具屋さんの焼け跡から探し出した焼け焦げた婚約指輪の持ち主その人であることが判明した。
あの瓦礫の山から想像もできない復興振りに胸が熱くなった。

昔は年末になると人でごった返していた本町通りは、郊外の大型店に圧されて随分前からシャッター街になってはいたが、車がない世帯でも生活ができて駅に近いという利点もある。

古い町並みが残る路地
往時の賑わいの復活は無理にしても、静かな住宅街なりの活気が戻ってくれればいい。
映画「仁義なき戦い」の菅原文太のラストの名セリフの「山守さん、まだぁ弾ぁ残っとるがよぅ・・・」
これから始まる新しいまち作り。