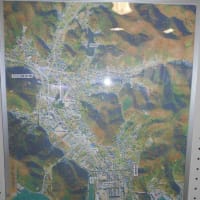「山本瀧之助」ゆかりの地を巡る
―ゆかりの地ガイド―
日時:平成25<2013>年5月18日(土)9:00~12:00
参加者:8名
講師:上田靖士 福山市文化財保護指導員
[今回の巡回コース]
1.山本瀧之助生家⇒2.旭観音⇒3.南泉坊⇒瀧之助が通った道(亀山八幡鳥居道・
村役場・みかど本館横道)⇒4.鞆渡橋(5.枝広邸)⇒千年郵便局⇒6.大越峠道⇒
7.大越地蔵堂⇒8.根引倶楽部(番号は今回廻った場所)
[巡回コースの内容]
1.山本瀧之助生家[説明版]
母屋は、約50年以上の建物で、父孫次郎が建てたものであり、向って左側の倉庫風
の建物は、瀧之助が建てたもので書斎として使用していた。
向って右側の建物は、昭和10<1935>年の写真には、載っていない。
瀧之助が生家を離れていた時期は、明治24<1891>年の1年間は、松永に下宿して
いた。明治34<1901>年9月下旬から翌年5月29日までの約8ヶ月間、目の治療の
ために上京している。
その間には、常石小学校へ約17年間通っている。
明治25<1892>年~明治43<1910>年の内、上京中の期間は、8ヶ月間。
全国巡回青年講習会を実施していた昭和3<1928>年の1年間の出張は、
196日間に及ぶ。(内、同年3月の場合には出張25日間で神石郡2日、芦品郡5日を含む)
2.旭観音[標柱(3)]
『田舎青年』の草稿の裏に「旭観音」神仏助之の落書きがある。
明治29<1896>年正月の日記には、旭観音に詣でている。
3.南泉坊[標柱(4)]
子どもの頃からの遊び場となっていた。浄土信仰の講話を耳にしていたのではないか
と思われる。特に「一日一善」などは、その表れではないかと考えられる。
境内にある、木斛(もっこく:別名:あかみずき)の大木は、珍しい。
[通勤道]
常石小学校への通勤道として、考えられるコースとしては、
亀山八幡鳥居道⇒千年小⇒村役場(亀山八幡鳥居下右手)⇒
みかど本館横道⇒鞆渡橋⇒大越坂道(旧道)⇒根引道
[長谷川新右衞門道久の墓]
墓とあるが、没後150年後に顕彰碑として建てられたもの。
「中継ぎ表の考案」
藺草の織機を考案したものと考えられる。それまでの機織機は、二人で藺草を織っ
ていたものが、一人で出来るようになり、しかも捨てていた短い藺草を使用出来るよう
に考案されたものである。
今回この南泉坊で、特に感じたのは、「金子みすず」の言葉に表される、
感情とか感覚が似ていると感じ取った。
この地域全体で共有されている信仰(浄土・お講の存在)を窺い知ることが解かる。
瀧之助の葬儀もこの寺で行われている。
(亡くなった日は、昭和6<1931>年10月26日)葬儀は、
昭和6年10月27日(午後5時から執り行われている。)
草深尋常小学校(第14尋常小学校⇒千年尋常小学校⇒千年小学校)に入学・卒業
明治22<1889>年10月~明治24<1891>年5月の間、1年6ヶ月雇いとして勤める。
[千年小学校][標柱(5)]
4.鞆渡(ともわたり)橋[標柱(7)]
常石小学校へ勤める通勤で毎日この道を通る。
この場所より見える草深磯新涯の農作業の進捗状況が『千年村日記』に記されている。
稲まだあるのは、8・9枚、い草植えたるは2枚のみ、田植え盛りなり 等々
大正年間に、鞆~尾道への巡航船が通うようになり、その船が常石から鞆へ向う道の
意味を含んでいる。そのためこの橋の名が付いた。
5.枝広邸[標柱(8)]
庭園内の構成、中庭の構成、馬小屋跡の説明を聞く。
[千年郵便局][標柱(9)]
千年村に於ける郵便事業は、土生から始まった。
明治23<1890>年6月22日高田家が開始される。
それ以前の郵便局は、山南郵便局から配達されていた。
「吉備時報」の最終号はここから発送されている。
瀧之助が外部との連絡には、郵便局を利用している。
『千年村日記』には、
明治32<1899>年6月22日昨日より郵便局開始、
6月23日高田局長曰く、まだ知らぬ人あります。
常石の方へ言って下さい。山南と同じ取り扱いと
この様にこの時代には、郵便局が千年に開始された事を知らない人達がいたことが判る。
6.大越峠道[標柱(10)]
大越峠は、現在大きく広げているが、当時の道は山と山の谷間となっていた道を徒歩
で通っていた。
『吉備時報』を10年間続けて、その中で述べた要旨を『地方青年団体』
に表し、青年団活動の集大成とした。
常石小学校へ通う道であり、また尾道へ『吉備時報』の広告を取りに行った道であり、
その道中に思考を重ねた道でもある。
7.大越地蔵堂[標柱(12)]
大越地蔵堂の前面は、現在公園となっているが、この公園のある場所は、「大越池」
があった。その名残が東側に残っている。
[瀧之助ふれあいロードマップの看板(11)]
峠坂道を登り切った所から、前方には眺望が一気に広がり、横島・田島が一望に見え、
その開放感が味わえたと思われる。
大越地蔵堂には、二枚の棟札が残り、延享4<1747>年7月再建、念仏講助力
安政2<1855>年6月再建、「大地震の翌年6月に棟上げ」とある。
現在の建物は、昭和51<1976>年にコンクリート造りになっている。
明治29<1896>年2月7日の日記には、
「学校に行く途中、浜岡にて先生大坂よりの
手紙に接す・・・・・余り嬉しくて弁当を忘れる。
手紙を繙く(ひもとく)こと都合4度なり」とあり、
余程の嬉しさが伝わって来る。
8.根引倶楽部[標柱(14)]
[大越浜]は、丁度「根引倶楽部」から下に見える浜であり、『吉備時報』の印刷や
広告取りに尾道へ出かけた場所である。
『吉備時報』21号「日曜日と足」の記事で、
「1ページの広告あてに雨中を3里歩くもものにもならず・・・・」
「尾道に行き店頭にてオジギ行く幾十回広告予定に達す」
とあり、『吉備時報』を発刊するために広告収入で行っていた事が判り、
その苦労が目に見えるようです。
概略以上(文責 鳳来)

(山本瀧之助 生家)

(瀧之助生家で解説風景)

(旭観音)

(旭観音 標柱)

(身近に有った南泉坊)

(南泉坊 山門より)

(南泉坊での解説風景)

(南泉坊の標柱)

(長谷川新右衞門 道久 墓)

(鞆渡橋での解説)

(現在の鞆渡橋)

(枝廣邸での解説)

(枝廣邸)

(枝廣邸 馬小屋跡)

(大越坂(左側 現在の道 右手旧の道))

(解説風景)

(大越地蔵堂)

(「瀧之助ふれあいマップロード」 看板)

(「根引倶楽部」での解説)

(根引きからの眺望)