[「草深の唐樋門」と深草新涯の干拓関連遺跡の歴史散策]
(福山市文化財協会 令和2年12月11日)
①沼隈のこと 航空写真・ルート案内図
ここ沼隈町は、広島県で唯一、半島と名の付く地形の先端部にあります。
半島は、三面が海に面し、長く大きく突き出た陸地の地形を指し、小さい物を埼・鼻・岬と呼びます。
(南に響灘、西に松永湾、東に芦田川河口)
沼隈町は人口11,000人足らずの、小さな町ですが、
(内海町2,334人)平家伝説など古い歴史に育まれた地域です。
今日は、江戸時代の干拓事業の痕跡がそのまま残る県の史跡「草深の唐樋門」を
中心に、干拓に係る現地を、散策して巡りましょう。
5kmほどのコースですが一般道路を歩きますので、
周囲の安全に気を付けてください。
沼隈町は、明治22年の町村制施行の時、
草深村・能登原村・常石村が合併して千年村となりました。
その後、昭和30年(1955)、山南村と千年村が合併して
人口11,861人の沼隈町となりました。
そして、(神辺町に次いで遅く)平成17年(2005)に福山市と合併しました。
町制の時代が50年間と長かったため、多くの施設が沼隈町時代にできた施設を引き継いいます。
ここの支所庁舎・公民館(S53)、500人収容のコンサートホール・サンパル
(H1竣工こけら落としにN響の公演を機にサンパルオーケストラが設立されて
以後定期演奏30回を重ねております。
毎回N響メンバーの協賛出演が続いております。
(バイオリンのコンマス篠崎・チェロの木越・フルートの甲斐さん達))、
沼隈図書館(H10)、消防署、枝広邸(H1)、道の駅(H8)・そば処(H4)、等。
市内の小さな町としては、持ち得ないような施設があります。
② 山南川
沼隈半島の最高峰熊ヶ嶺(438m)の西にある馬背山(298m)の北側を山北(瀬戸町)、
南側を山南と呼びます。山南川は馬背山を水源に持つ全長12㎞ほどの川です。
350年前までは支所を含めてこの場所は、山南川の河口の海でした。
この堤防も山南川の延伸に伴い、敷名山側に新たに築堤し50町歩の干拓地が造成されました。
400年前、芦田川は、神島橋の北あたりから、
大きく東に湾曲し福山駅辺りから箕島方向に流れ込んでいました。
勝成公は河口に浮かぶ常興寺の丘を城地に選び、
芦田川の流路を現在のように、沼隈半島沿いに付け替え、
5代75年の間で、広大なデルタを次々に干拓していきました。
当時この鞆渡橋は山南川の西側の常石・松永方面から草深・鞆方面への
唯一の橋(木造)でした。
現在の橋は昭和46年にかけ替えられたものに変わっています。
[瀧之助標柱]を設置しています。
その廻りには、そば処・道の駅・ハーブガーデン―沼隈町の施設など、
今は、指定管理団体が運営しています。
枝広邸は、幕末から明治にかけて3代続いていた医者の家であり、
明治時代の、瀧之助日記には、「枝広の先生が馬で往診に行く」とあり、
当主が大阪に転出に伴い沼隈町に寄贈され、町が京都の大工に書院造りの建物、
中根金八(足立美術館の庭園)監修の庭園を平成元年に整備し、
文化施設の場として活用され現在に至っています。
枝広邸内の庭園は、「心」字池とし、そこには汐が満ち引きする観月楼があり、
立派な茶室も備えてあります。
千年中学校―2022年に義務教育一貫校へ移行することになり、
千年・能登原・常石・内海・内浦小、千年・内海中の7校が統合し
義務教育一貫校へと変わってしまいます。
常石小は、イエナ教育を指向されていて、新校舎の開設は、
2024年にできる予定であるり、2021年からどの地区からも千年小へ入校できる。
新学校名は、「想青学園」(そうせい)となり、
歴史ある「千年」の地名もここでも消えていきます!
内海大橋は、取り付け道路を含め832mあり、
中央部分が大きく湾曲している珍しい橋です.
H1年完成、当時107億円、離島振興策として架橋されました。
中央部が大きくカーブした珍しい橋で、特に夕陽に浮かぶシルエットが
見事な撮影スポットです。
内海町、―田島、江戸時代から300年西海捕鯨の島で、
横島。人口2300人余り。
常石―常石造船、セブ島・中国舟山に造船所を持つ独立系の造船所、
三井造船と提携 20万トンの修繕ドック、建造量2,000億
切り妻屋根を持つ外観は船というより海を漂う建築物のような、
瀬戸内クルーズ船、「ガンツウ」3,000㌧、10ノット(時速約20㎞)、
定員19室38名、乗員40名の豪華クルーズ船です。
三原沖では、漁師が取れたてのタコを小舟で手渡ししている光景が
TV放映されていました。、散歩用12人乗りのボート(20ノット)備
(1ノット=1時間に1海里(1852m)、10ノットは時速約19㎞)
(ガンツウ写真)幹部社員の社宅
千年藤―『平家物語』巻4の「還御」の項に、
治承4年(1180)高倉上皇が厳島参詣の帰り敷名の泊りで<
松の枝に巻きついた藤の花を見つけ採りに遣わせ、お供の大納言隆季に
「此花にて詠あるべし」と命じ、隆季が詠んだ
「千とせ経ん君がよわいに藤波の松の枝にもかかりぬるかな」
に因みの千年村の村名とした。
(上皇さんが、いくとせも長生きなされるように、藤の花が目出度い
松の枝に巻きついて咲いている事か)(千年藤の由来となる)
③大堤防を築く為の土の取り出し場所
全長1,5㎞の頑丈な堤防を創る為に、膨大な土が必要でした。
敷名山の東側にあたる土生・矢川地域の山裾を切り崩し、
延長された山南川の堤防や、干拓地の堤防に
も運ばれたものと考えられる。
そして東側の山裾(樋の上)、更に茂美の小島、寄り宮からも船で、
運ばれたものと思であろう。
堤防は、大潮の時、多少陸化した沖に、松丸太を打ち込み、
丸太や竹などの粗朶を敷き、その上に竹籠などに石を入れで
堤防の芯を造り、土砂を積み上げて築堤したと考えられる。
(明治期に造られた旧東京駅の基礎に末の食いだ沢山打ち込まれていた)
築堤10年位後の延宝2年(1674)には、堤防が切れている。
(このとき藩内各所の堤防が切れている)
六郡志には、「草深の堤防を石積で補強」とある。
江戸中期以降は、堤防表面を石で覆うようになっていった。
元禄15年の草深下絵図には、堤防上に松並木らしき絵が描かれている。
(草深村下絵図・阿伏兎土産)
福山沖の干拓は、東西、両側に平行する堤防を沖に向かって伸ばし、
その先端を繋ぐ方法で干拓しているが、
草深新涯は、東西の山地を利用し、沖に堤防を造るだけで干拓されている。
⑤で話す
④ 沼隈の商業地域 海抜0,5m表示の電柱
海抜=その地域の干・満潮の平均海面値
標高=東京湾の干・満の平均海面値
ここ草深新涯のほぼ中心地域も、当然ながら、
かつては海底であったところで、江戸期(宝永2年・富士山の大爆発があった頃)
には1,5mの津波が瀬戸内にも来襲している。
(「常の潮より高きこと5尺」の文書)
大潮の満潮時を想定すると、護岸が耐えられるのか、今から心配である?
福山の干拓地を含め防災対策は他人ごとではない!
干拓地域が広大な福山市は、県の津波ハザードマップによれば、
死者は7000余人で県内で最も多い。
防災訓練の避難場所が海抜0,5mの支所でいいのであろうか?( おかしい・・・一考を願う)
貝塚は、信じられない程内陸部で発見されている。
そのラインが海岸線(海)であった。
それが浸水想定ラインでもある。(写真・草深新涯の移り変わり)
地球温暖化がもたらす異常気象により、100年に一度の巨大台風が毎年来襲し、
想定外の豪雨や暴風や、高潮をもたらしている。
自然の営みに為すすべもないが、人は少なくとも温暖化を止めなくては!
⑤ 大土手(潮受け堤防)、 ③から
海を仕切る堤防。土地の人はのどかに、桜土手と呼んでいる。
田中新田が出来るまでは、草深新涯を守る大切な護岸(堤防)であった。
西側は山南川の堤防に接続している。長さ約1500m
堤防西詰の春辺橋を渡ると海岸沿いに敷名・常石に至り、現在そこには排水機場がある。
➅悪水路・内海(汐回し水路)
海に陸地(土地)を人為的に作る方法には、「干拓」と「埋め立て」があります。
埋め立ては、神戸のポートアイランドや沖縄の辺野古の米軍基地そして、
福山では日本鋼管福山製鉄所の敷地などのように護岸を先に作って海を仕切り、
内側に大量の土砂を運び込み陸地を創る方法。(工場用地・住宅地)
干拓地は、河川が運ぶ土砂によって堆積した遠浅の海岸線を
堤防で仕切り、海水を排水する事で現れた海底が陸地になるので、
埋め立てのような大量の土砂の搬入は必要でない。
併し元は海底であった土地の為、多くの塩分が残っているので
農地にするには塩分を除去しなければ耕作できない。
江戸時代には、新たな耕作地に、「鍬下八年」と言って、八年間は、年貢を掛けなかった。
灌漑用水と雨水で染み出した塩分を含むその水を悪水と呼び、
これを何年もかけて樋門から海に放出する事で塩分を希釈させる。
オランダ(ネーデルランド=低い土地)は国土の30%が海面より低い土地で
国土の20%は13世紀以降干拓で造成された国土。
「世界は神が造り給われたがオランダはオランダ人が造った」
アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス等は国土の3割が森林、
日本は僅か3割が平地の国です。
2022年福山城は築城400年を迎えます。
江戸幕府は、大名を米の石高によって統治していました。
水野勝成公は、10万石で転封されましたが、
実質の収穫は3000石それを割っていました。
その為水野家五代に亘って、城の南の遠浅の干潟を積極的に干拓し、
耕地は15万石の実収にさせています。
(野上新開・深津・引野・多治米・川口・草戸・笠岡吉浜・松永)
(日本の大都市の多くは、大河が氾濫の度に流域の土砂を大量に
搬送してできた沖積平野を干拓して立地している)
⑦草深の唐樋門 (修復写真3枚・パンフ・棟札)
草深の磯新田は4代勝種の寛文年間(1661~1672)、
本庄重政の普請奉行の差配で造成された農業用地が、
目的の干拓に於いては、塩分の除去が至上命題です。
雨水と灌漑用水を干拓地に流し塩分を希釈させ、塩分を含んだ水(悪水)を、
干潮時に海に放流し、満ち潮を干拓地に流入させない施設が樋門の機能です。
遠浅で、干満の差の大きい(1,5~4m)瀬戸内は干拓に適していた。
干拓工事の最重要施設となる樋門は、大土手の東端にある地山から連なる
岩盤の地形を選んで設置されている(自然の岩盤の一部が見える)。
海からの水圧は、1.5m幅の樋蓋3門で受けている。
そして樋蓋は1尺1寸(33㎝角)4本の石柱(花崗岩)に彫られた溝に
はまり上下する。両端の石柱は、石垣に支えられているが、
中2本の石柱は、水中から自立している。
元禄9年(1696)の修理に際し、「中柱2本羽目板共に石に取替」とある。
設置時は木製であった樋門の部分は全て石に取り換えられている。
中柱の内側には、両岸の石垣に両端を深くはめ込まれた幅広で分厚い石を、
上下2本差し渡され設置され、石柱を背後から支えている。
上部は羽目板、下部は羽目石となって現状になっている。
元禄の修理では両側の石垣も築替、更に中柱4本を立てて
「巻轆轤」据え付けた、と書かれている。
当時の轆轤は現存しないが、その痕跡は中柱に認められる。
安永3年(1774)の修理では、大引物、梁などの他、
各部分で「根継ぎ」や羽目板の取り換えなどが行われている。
「日本土木史」には、「面積50町歩あり」・「元禄年間に再築す」との記事が
ある事からも、磯新涯並びに唐樋門の造成年代を
寛文頃(1661~1672)とする事は、妥当とされる。
元禄15年(1702)「草深村下絵図」には、
「唐樋」との記載が見られる。
石柱下部の状態は判別できないが、岩盤に受け口の穴を掘り、
石柱を差し込んで自立させているものと思える。
(石柱上部で受ける同等の反力を受けている。)
石柱に彫られた溝(ガイドレール)にはめ込まれた3枚の樋蓋(樋門)が
受ける水圧は、3重の梁と、2重の大引物の組み合わせによって支えられている。
そしてこれらの構造物(500丸太等の用材)は、土中に埋め込まれた左右の切石に
受け止められ左右の地盤にいなされている。(受け止められている。)
3枚の樋蓋が受ける水圧は、潮位3m位とすると静荷重(平時の満潮時)で凡そ3トン位か?
台風や津波など動的に受ける水圧の力はその何倍も掛かるのであろう。
今、河口堰や水門工事の大規模な土木工事を見るにつけ、
350年近く前、石と材木で造り上げた先人の知恵に驚くばかりである。
(当時、こうした堅牢な樋門工事がなされた背景には南蛮
渡来の技術があると思われる。
万治1年(1658)山口の熊毛郡平生干拓の樋門は
南蛮樋と呼ばれている。
ここではオランダ技法の轆轤が使われた事で
南蛮と呼ぶと説明されている。)(南蛮樋門写真)
静荷重・動荷重、(釘・樋蓋、金槌・台風時の波浪、
氷の上に乗るだけで割れないが、飛び上がって乗ると割れる)
一日に4回必ずある干満が切り替わる時に樋蓋の開閉をする樋番の仕事は、
干拓地に住む人たちの生命財産を守る極めて重要な作業である。
その為か樋の堂の屋根は本瓦葺である。
(伝承技術としてユネスコの無形文化遺産に指定される。令2・12月)
樋蓋は、悪水側の水圧と海からの水圧が等しい時でないと、上げ下げ出来ない。
(即ちそのタイミングは、悪水側と海水面とが等しい時)。
(水没した車のドアーが開かない)
下がらなくなった時は、掛矢で樋蓋をたたいて降ろすか、
布団を投げ込んで隙間をふさいだという。
(轆轤は巻き上げる装置で、降ろす力は全くない。
下げる力は樋蓋の重さと、かけやで叩くだけである。)
田中新田―昭和22年にはじまる。
戦後の復員や引揚者で人口が増加し、食糧増産のため着工したが、
軟弱地盤で堤防の陥没事故や台風で決壊などで難工事(9年間延べ11万人)となる。
昭和31年に21町歩の干拓が完成した。
このため、300年間、新涯の生活を守ってきた唐樋門と堤防は役目を終え、
道路として残り、唐樋は隘路となるも放置され元のまゝでその現場に残った。
10年の間に日本経済は産業構造が変化し高度成長期に入り、
干拓地は水田化されることなく(八日谷ダムからの水路は、通水されることなく、
ポンプアップされ60町歩のブドウ団地への灌漑用に転用された。)
工業用地として造船関連企業(常石鉄工)が立地している。
⑧干拓地を示す地名
樋の上―樋門の傍(大門にもある) 阿引―網を引いていた(地引網か?)
洲の端―砂州の先端
浜組―干拓以前は浜辺であった
汐入―汐が満ち引きしていた(大津野の地図)
⑨草深村当時の中心地、浜組
明治期に村役場、草深小学校、映画館などがあった。
寄の宮神社(草深村の村社・亀山八幡神社、末社・畳表神社(昭和28年)が在る)参道口
(備後表の生産)
奥組 南泉坊―中継ぎ表考案の長谷川新右衛門の碑、瀧之助、梵のこと
山本瀧之助の生家
柏迫池への800mの新溝造成 ろうそくでレベルを測る
➉新川 奥組川の流路の延長 灌漑用水の確保
干拓地の塩分を抜くためには、雨水と灌漑用水を流すことで
長い期間をかけて希釈する必要が有る。
草深新涯への灌漑用水は、山南川の井出からの取水と、
以前は二つの池であった柏迫池を一つの池にし、
更に深い山を背負う奥組集落から800mの新溝を造り
(ローソクでレベルを測り)池に水量を確保し、
新涯の北端部に新設した新川に流した。
この新川は、干拓地盤に土盛りして直線の450mの新溝を造った為、
天井川となっている。
それでも足りず、隣村の菅野池から分水(池の中に分水石がある)
させてもらっていた。
⑪用水(川)の立体交差
磯新涯の用水確保の為、隣村の菅野池から分水を受けているが
新川と直交する為、新川の下を通って新涯へ流されている。
⑫山南川の護岸対策 「水はね」
かつてこの辺りは河口であった。草深新涯を干拓する為、
山南川を延伸(延長)させる必要が有った為に、
流路を急カーブさせられている。
直進してくる水の勢いから堤防を守る為、この石組のコブ状のもの(水ハネ)を
設け、緩衝させている。
流れの障害になるように思えるが、現代工法で改修されていた図書館前の護岸は、
先の西日本豪雨で破損した。以前は、何カ所にも見られた水ハネですが、
今はここだけに残り見ることができる。
これより下流の山南川は干拓時に延伸された堤防である。
⑬沼隈図書館 (平成10年完成)
唐樋門の十分の一模型
勝成入封400年記念事業として昨年(令和元年)
福山市の「入封400年プロジェクト・沼隈」に参画。
江戸時代前期と確認され、県内唯一現存する干拓関連施設の唐樋門の機能や構造を、
多くの方にいつでも見て貰える教材として、
唐樋門の模型創りが有効であると提案し実現した。
福山工業高校建築家3年生6人と指導教諭が、
半年かけて制作した十分の一スケールの模型は、
周辺の水路、石垣、橋等を配し、1,000枚を超える瓦も一枚ずつ張り付けた
精密で忠実に再現されている。
参・文化財ふくやま55号
山本瀧之助記念室
⑭当時の山南川の災害対策
延長された堤防の決壊を防ぐため左岸(干拓地側)の堤防を高くしてある。
右岸側の遊水地に越水させるように作られている。
越流提(えつりゅうてい)という。
芦田川の御幸(七つ原)の辺りでは水位がある高さに達すると、
1m弱の幅で敢て堤防を切って、決めら
れた地域を遊水地にする慣行があったとされる。
16世紀初、芦田川の河口の港町として栄えた草戸千軒は、
土砂の堆積で水没、衰退していった集落。
江戸時代、利根川の支流の一つであった荒川(墨田川)は、
頻繁に洪水に見舞われ、幕府は、右岸の堤防を0.5m低く作り遊水地に
流して堤防を守ろうとし、そこに住んではならないと定めた。
ところが人口が増え肥沃な土地にやがて多くの人たちが住み繁栄してきた。
明治43年の大洪水で政府は本来遊水地であった所を守る為、
流路を大きく東に寄せた人工の流路を造ったのが荒川放水路である。
東京に流れる利根川・多摩川は200年に一度、その他の大河は
150年~100年に一度の大雨を想定して整備されている。
100年に一度の大雨が毎年発生する昨今の(温暖化による)異常気象下では
対応しきれない。
国土の30%が海面より低いオランダでは、高潮とライン川等の上流域での
豪雨が同時発生した場合を考え万年に1度に備えるデルタ計画を策定している。
堤防を高くする、土砂を掘るなどの「垂直型」だけでなく、
遊水地、河幅を広くするなど「水平治水型」発想を組み合わせ、
ハードの強化だけでなくは、自然に対応したしなやかな発想(レジリエンス)が
必要であるとされている。
江戸時代の人口増と停滞
国土の7割が山地の日本、定住を始めた弥生時代の人口は59万人位だったといわれている。
平地は大雨が山を削り谷を造り川を為して海に土砂を堆積させた所であり、
そこに人は住んだ。貝塚は、信じられない程内陸部で発掘されているが、
そのラインが当時の海岸線(海)であった。
平安時代頃の人口は800万人位であったとされる人口は、
江戸初期頃は、耕地が200万町歩で人口1500万人位とされている。
(勝成公入封時福山の人口は12,678人)
1700年代(5代綱吉、元禄の繁栄)には耕地は300万町歩に増え、
人口は3000万人と倍増している。
戦いが無くなり、干拓など新田開発が進み農家の次男・三男が入植し、
3~5年の鍬下年季にも守られて、一家を構えることが出来る様になった
ことによるからであろう。
新田開発が峠を超えてからは人口は200年間は押しなべて
3000万人を大きく超えることは無かった。
(鎖国で閉鎖経済下、農薬・肥料・新品種等の農業技術の進展は少なかった。)
開国、維新と時代は移り、化学肥料、農薬、品種改良など農業生産性、
食糧供給は向上しその後の人口増に対応していったが、
どう間違ったのか?一次産業の農業は、日本の高度成長の過程でとり残され、
休耕田だらけの食糧自給率30%台の農耕民族となってしまった。
これからの日本の農業や如何に?!
異常気象による想定外の大雨による被害は、水にしてみれば、
ごく自然に低い所を選んで海に納まろうとするだけである。
浸水想定来ラインは、嘗ての海岸線ラインである。
有史以来2000余年の間に、人は人の都合で自然に抗って、
海水面に侵食していって繁栄してきた。
そして今人は、悠久な自然の営みの気まぐれな気象現象に
生命を脅かされている。
「命の水」ともなる水と上手に付き合う為に、
「水は常に高い所から低い所(海)に流れる」という摂理
を忘れてはならない。
[本文の構成は、清水幹男さん提供です]
[現地に於いて解説は、本会の清水幹男さんと、村上訓代さんです。]
[映像は、yutubeへ掲載]
[https://youtu.be/bDnaX8am0BQ]
<映像は、25分21秒有ります。>
https://youtu.be/bDnaX8am0BQ
(福山市文化財協会 令和2年12月11日)
①沼隈のこと 航空写真・ルート案内図
ここ沼隈町は、広島県で唯一、半島と名の付く地形の先端部にあります。
半島は、三面が海に面し、長く大きく突き出た陸地の地形を指し、小さい物を埼・鼻・岬と呼びます。
(南に響灘、西に松永湾、東に芦田川河口)
沼隈町は人口11,000人足らずの、小さな町ですが、
(内海町2,334人)平家伝説など古い歴史に育まれた地域です。
今日は、江戸時代の干拓事業の痕跡がそのまま残る県の史跡「草深の唐樋門」を
中心に、干拓に係る現地を、散策して巡りましょう。
5kmほどのコースですが一般道路を歩きますので、
周囲の安全に気を付けてください。
沼隈町は、明治22年の町村制施行の時、
草深村・能登原村・常石村が合併して千年村となりました。
その後、昭和30年(1955)、山南村と千年村が合併して
人口11,861人の沼隈町となりました。
そして、(神辺町に次いで遅く)平成17年(2005)に福山市と合併しました。
町制の時代が50年間と長かったため、多くの施設が沼隈町時代にできた施設を引き継いいます。
ここの支所庁舎・公民館(S53)、500人収容のコンサートホール・サンパル
(H1竣工こけら落としにN響の公演を機にサンパルオーケストラが設立されて
以後定期演奏30回を重ねております。
毎回N響メンバーの協賛出演が続いております。
(バイオリンのコンマス篠崎・チェロの木越・フルートの甲斐さん達))、
沼隈図書館(H10)、消防署、枝広邸(H1)、道の駅(H8)・そば処(H4)、等。
市内の小さな町としては、持ち得ないような施設があります。
② 山南川
沼隈半島の最高峰熊ヶ嶺(438m)の西にある馬背山(298m)の北側を山北(瀬戸町)、
南側を山南と呼びます。山南川は馬背山を水源に持つ全長12㎞ほどの川です。
350年前までは支所を含めてこの場所は、山南川の河口の海でした。
この堤防も山南川の延伸に伴い、敷名山側に新たに築堤し50町歩の干拓地が造成されました。
400年前、芦田川は、神島橋の北あたりから、
大きく東に湾曲し福山駅辺りから箕島方向に流れ込んでいました。
勝成公は河口に浮かぶ常興寺の丘を城地に選び、
芦田川の流路を現在のように、沼隈半島沿いに付け替え、
5代75年の間で、広大なデルタを次々に干拓していきました。
当時この鞆渡橋は山南川の西側の常石・松永方面から草深・鞆方面への
唯一の橋(木造)でした。
現在の橋は昭和46年にかけ替えられたものに変わっています。
[瀧之助標柱]を設置しています。
その廻りには、そば処・道の駅・ハーブガーデン―沼隈町の施設など、
今は、指定管理団体が運営しています。
枝広邸は、幕末から明治にかけて3代続いていた医者の家であり、
明治時代の、瀧之助日記には、「枝広の先生が馬で往診に行く」とあり、
当主が大阪に転出に伴い沼隈町に寄贈され、町が京都の大工に書院造りの建物、
中根金八(足立美術館の庭園)監修の庭園を平成元年に整備し、
文化施設の場として活用され現在に至っています。
枝広邸内の庭園は、「心」字池とし、そこには汐が満ち引きする観月楼があり、
立派な茶室も備えてあります。
千年中学校―2022年に義務教育一貫校へ移行することになり、
千年・能登原・常石・内海・内浦小、千年・内海中の7校が統合し
義務教育一貫校へと変わってしまいます。
常石小は、イエナ教育を指向されていて、新校舎の開設は、
2024年にできる予定であるり、2021年からどの地区からも千年小へ入校できる。
新学校名は、「想青学園」(そうせい)となり、
歴史ある「千年」の地名もここでも消えていきます!
内海大橋は、取り付け道路を含め832mあり、
中央部分が大きく湾曲している珍しい橋です.
H1年完成、当時107億円、離島振興策として架橋されました。
中央部が大きくカーブした珍しい橋で、特に夕陽に浮かぶシルエットが
見事な撮影スポットです。
内海町、―田島、江戸時代から300年西海捕鯨の島で、
横島。人口2300人余り。
常石―常石造船、セブ島・中国舟山に造船所を持つ独立系の造船所、
三井造船と提携 20万トンの修繕ドック、建造量2,000億
切り妻屋根を持つ外観は船というより海を漂う建築物のような、
瀬戸内クルーズ船、「ガンツウ」3,000㌧、10ノット(時速約20㎞)、
定員19室38名、乗員40名の豪華クルーズ船です。
三原沖では、漁師が取れたてのタコを小舟で手渡ししている光景が
TV放映されていました。、散歩用12人乗りのボート(20ノット)備
(1ノット=1時間に1海里(1852m)、10ノットは時速約19㎞)
(ガンツウ写真)幹部社員の社宅
千年藤―『平家物語』巻4の「還御」の項に、
治承4年(1180)高倉上皇が厳島参詣の帰り敷名の泊りで<
松の枝に巻きついた藤の花を見つけ採りに遣わせ、お供の大納言隆季に
「此花にて詠あるべし」と命じ、隆季が詠んだ
「千とせ経ん君がよわいに藤波の松の枝にもかかりぬるかな」
に因みの千年村の村名とした。
(上皇さんが、いくとせも長生きなされるように、藤の花が目出度い
松の枝に巻きついて咲いている事か)(千年藤の由来となる)
③大堤防を築く為の土の取り出し場所
全長1,5㎞の頑丈な堤防を創る為に、膨大な土が必要でした。
敷名山の東側にあたる土生・矢川地域の山裾を切り崩し、
延長された山南川の堤防や、干拓地の堤防に
も運ばれたものと考えられる。
そして東側の山裾(樋の上)、更に茂美の小島、寄り宮からも船で、
運ばれたものと思であろう。
堤防は、大潮の時、多少陸化した沖に、松丸太を打ち込み、
丸太や竹などの粗朶を敷き、その上に竹籠などに石を入れで
堤防の芯を造り、土砂を積み上げて築堤したと考えられる。
(明治期に造られた旧東京駅の基礎に末の食いだ沢山打ち込まれていた)
築堤10年位後の延宝2年(1674)には、堤防が切れている。
(このとき藩内各所の堤防が切れている)
六郡志には、「草深の堤防を石積で補強」とある。
江戸中期以降は、堤防表面を石で覆うようになっていった。
元禄15年の草深下絵図には、堤防上に松並木らしき絵が描かれている。
(草深村下絵図・阿伏兎土産)
福山沖の干拓は、東西、両側に平行する堤防を沖に向かって伸ばし、
その先端を繋ぐ方法で干拓しているが、
草深新涯は、東西の山地を利用し、沖に堤防を造るだけで干拓されている。
⑤で話す
④ 沼隈の商業地域 海抜0,5m表示の電柱
海抜=その地域の干・満潮の平均海面値
標高=東京湾の干・満の平均海面値
ここ草深新涯のほぼ中心地域も、当然ながら、
かつては海底であったところで、江戸期(宝永2年・富士山の大爆発があった頃)
には1,5mの津波が瀬戸内にも来襲している。
(「常の潮より高きこと5尺」の文書)
大潮の満潮時を想定すると、護岸が耐えられるのか、今から心配である?
福山の干拓地を含め防災対策は他人ごとではない!
干拓地域が広大な福山市は、県の津波ハザードマップによれば、
死者は7000余人で県内で最も多い。
防災訓練の避難場所が海抜0,5mの支所でいいのであろうか?( おかしい・・・一考を願う)
貝塚は、信じられない程内陸部で発見されている。
そのラインが海岸線(海)であった。
それが浸水想定ラインでもある。(写真・草深新涯の移り変わり)
地球温暖化がもたらす異常気象により、100年に一度の巨大台風が毎年来襲し、
想定外の豪雨や暴風や、高潮をもたらしている。
自然の営みに為すすべもないが、人は少なくとも温暖化を止めなくては!
⑤ 大土手(潮受け堤防)、 ③から
海を仕切る堤防。土地の人はのどかに、桜土手と呼んでいる。
田中新田が出来るまでは、草深新涯を守る大切な護岸(堤防)であった。
西側は山南川の堤防に接続している。長さ約1500m
堤防西詰の春辺橋を渡ると海岸沿いに敷名・常石に至り、現在そこには排水機場がある。
➅悪水路・内海(汐回し水路)
海に陸地(土地)を人為的に作る方法には、「干拓」と「埋め立て」があります。
埋め立ては、神戸のポートアイランドや沖縄の辺野古の米軍基地そして、
福山では日本鋼管福山製鉄所の敷地などのように護岸を先に作って海を仕切り、
内側に大量の土砂を運び込み陸地を創る方法。(工場用地・住宅地)
干拓地は、河川が運ぶ土砂によって堆積した遠浅の海岸線を
堤防で仕切り、海水を排水する事で現れた海底が陸地になるので、
埋め立てのような大量の土砂の搬入は必要でない。
併し元は海底であった土地の為、多くの塩分が残っているので
農地にするには塩分を除去しなければ耕作できない。
江戸時代には、新たな耕作地に、「鍬下八年」と言って、八年間は、年貢を掛けなかった。
灌漑用水と雨水で染み出した塩分を含むその水を悪水と呼び、
これを何年もかけて樋門から海に放出する事で塩分を希釈させる。
オランダ(ネーデルランド=低い土地)は国土の30%が海面より低い土地で
国土の20%は13世紀以降干拓で造成された国土。
「世界は神が造り給われたがオランダはオランダ人が造った」
アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス等は国土の3割が森林、
日本は僅か3割が平地の国です。
2022年福山城は築城400年を迎えます。
江戸幕府は、大名を米の石高によって統治していました。
水野勝成公は、10万石で転封されましたが、
実質の収穫は3000石それを割っていました。
その為水野家五代に亘って、城の南の遠浅の干潟を積極的に干拓し、
耕地は15万石の実収にさせています。
(野上新開・深津・引野・多治米・川口・草戸・笠岡吉浜・松永)
(日本の大都市の多くは、大河が氾濫の度に流域の土砂を大量に
搬送してできた沖積平野を干拓して立地している)
⑦草深の唐樋門 (修復写真3枚・パンフ・棟札)
草深の磯新田は4代勝種の寛文年間(1661~1672)、
本庄重政の普請奉行の差配で造成された農業用地が、
目的の干拓に於いては、塩分の除去が至上命題です。
雨水と灌漑用水を干拓地に流し塩分を希釈させ、塩分を含んだ水(悪水)を、
干潮時に海に放流し、満ち潮を干拓地に流入させない施設が樋門の機能です。
遠浅で、干満の差の大きい(1,5~4m)瀬戸内は干拓に適していた。
干拓工事の最重要施設となる樋門は、大土手の東端にある地山から連なる
岩盤の地形を選んで設置されている(自然の岩盤の一部が見える)。
海からの水圧は、1.5m幅の樋蓋3門で受けている。
そして樋蓋は1尺1寸(33㎝角)4本の石柱(花崗岩)に彫られた溝に
はまり上下する。両端の石柱は、石垣に支えられているが、
中2本の石柱は、水中から自立している。
元禄9年(1696)の修理に際し、「中柱2本羽目板共に石に取替」とある。
設置時は木製であった樋門の部分は全て石に取り換えられている。
中柱の内側には、両岸の石垣に両端を深くはめ込まれた幅広で分厚い石を、
上下2本差し渡され設置され、石柱を背後から支えている。
上部は羽目板、下部は羽目石となって現状になっている。
元禄の修理では両側の石垣も築替、更に中柱4本を立てて
「巻轆轤」据え付けた、と書かれている。
当時の轆轤は現存しないが、その痕跡は中柱に認められる。
安永3年(1774)の修理では、大引物、梁などの他、
各部分で「根継ぎ」や羽目板の取り換えなどが行われている。
「日本土木史」には、「面積50町歩あり」・「元禄年間に再築す」との記事が
ある事からも、磯新涯並びに唐樋門の造成年代を
寛文頃(1661~1672)とする事は、妥当とされる。
元禄15年(1702)「草深村下絵図」には、
「唐樋」との記載が見られる。
石柱下部の状態は判別できないが、岩盤に受け口の穴を掘り、
石柱を差し込んで自立させているものと思える。
(石柱上部で受ける同等の反力を受けている。)
石柱に彫られた溝(ガイドレール)にはめ込まれた3枚の樋蓋(樋門)が
受ける水圧は、3重の梁と、2重の大引物の組み合わせによって支えられている。
そしてこれらの構造物(500丸太等の用材)は、土中に埋め込まれた左右の切石に
受け止められ左右の地盤にいなされている。(受け止められている。)
3枚の樋蓋が受ける水圧は、潮位3m位とすると静荷重(平時の満潮時)で凡そ3トン位か?
台風や津波など動的に受ける水圧の力はその何倍も掛かるのであろう。
今、河口堰や水門工事の大規模な土木工事を見るにつけ、
350年近く前、石と材木で造り上げた先人の知恵に驚くばかりである。
(当時、こうした堅牢な樋門工事がなされた背景には南蛮
渡来の技術があると思われる。
万治1年(1658)山口の熊毛郡平生干拓の樋門は
南蛮樋と呼ばれている。
ここではオランダ技法の轆轤が使われた事で
南蛮と呼ぶと説明されている。)(南蛮樋門写真)
静荷重・動荷重、(釘・樋蓋、金槌・台風時の波浪、
氷の上に乗るだけで割れないが、飛び上がって乗ると割れる)
一日に4回必ずある干満が切り替わる時に樋蓋の開閉をする樋番の仕事は、
干拓地に住む人たちの生命財産を守る極めて重要な作業である。
その為か樋の堂の屋根は本瓦葺である。
(伝承技術としてユネスコの無形文化遺産に指定される。令2・12月)
樋蓋は、悪水側の水圧と海からの水圧が等しい時でないと、上げ下げ出来ない。
(即ちそのタイミングは、悪水側と海水面とが等しい時)。
(水没した車のドアーが開かない)
下がらなくなった時は、掛矢で樋蓋をたたいて降ろすか、
布団を投げ込んで隙間をふさいだという。
(轆轤は巻き上げる装置で、降ろす力は全くない。
下げる力は樋蓋の重さと、かけやで叩くだけである。)
田中新田―昭和22年にはじまる。
戦後の復員や引揚者で人口が増加し、食糧増産のため着工したが、
軟弱地盤で堤防の陥没事故や台風で決壊などで難工事(9年間延べ11万人)となる。
昭和31年に21町歩の干拓が完成した。
このため、300年間、新涯の生活を守ってきた唐樋門と堤防は役目を終え、
道路として残り、唐樋は隘路となるも放置され元のまゝでその現場に残った。
10年の間に日本経済は産業構造が変化し高度成長期に入り、
干拓地は水田化されることなく(八日谷ダムからの水路は、通水されることなく、
ポンプアップされ60町歩のブドウ団地への灌漑用に転用された。)
工業用地として造船関連企業(常石鉄工)が立地している。
⑧干拓地を示す地名
樋の上―樋門の傍(大門にもある) 阿引―網を引いていた(地引網か?)
洲の端―砂州の先端
浜組―干拓以前は浜辺であった
汐入―汐が満ち引きしていた(大津野の地図)
⑨草深村当時の中心地、浜組
明治期に村役場、草深小学校、映画館などがあった。
寄の宮神社(草深村の村社・亀山八幡神社、末社・畳表神社(昭和28年)が在る)参道口
(備後表の生産)
奥組 南泉坊―中継ぎ表考案の長谷川新右衛門の碑、瀧之助、梵のこと
山本瀧之助の生家
柏迫池への800mの新溝造成 ろうそくでレベルを測る
➉新川 奥組川の流路の延長 灌漑用水の確保
干拓地の塩分を抜くためには、雨水と灌漑用水を流すことで
長い期間をかけて希釈する必要が有る。
草深新涯への灌漑用水は、山南川の井出からの取水と、
以前は二つの池であった柏迫池を一つの池にし、
更に深い山を背負う奥組集落から800mの新溝を造り
(ローソクでレベルを測り)池に水量を確保し、
新涯の北端部に新設した新川に流した。
この新川は、干拓地盤に土盛りして直線の450mの新溝を造った為、
天井川となっている。
それでも足りず、隣村の菅野池から分水(池の中に分水石がある)
させてもらっていた。
⑪用水(川)の立体交差
磯新涯の用水確保の為、隣村の菅野池から分水を受けているが
新川と直交する為、新川の下を通って新涯へ流されている。
⑫山南川の護岸対策 「水はね」
かつてこの辺りは河口であった。草深新涯を干拓する為、
山南川を延伸(延長)させる必要が有った為に、
流路を急カーブさせられている。
直進してくる水の勢いから堤防を守る為、この石組のコブ状のもの(水ハネ)を
設け、緩衝させている。
流れの障害になるように思えるが、現代工法で改修されていた図書館前の護岸は、
先の西日本豪雨で破損した。以前は、何カ所にも見られた水ハネですが、
今はここだけに残り見ることができる。
これより下流の山南川は干拓時に延伸された堤防である。
⑬沼隈図書館 (平成10年完成)
唐樋門の十分の一模型
勝成入封400年記念事業として昨年(令和元年)
福山市の「入封400年プロジェクト・沼隈」に参画。
江戸時代前期と確認され、県内唯一現存する干拓関連施設の唐樋門の機能や構造を、
多くの方にいつでも見て貰える教材として、
唐樋門の模型創りが有効であると提案し実現した。
福山工業高校建築家3年生6人と指導教諭が、
半年かけて制作した十分の一スケールの模型は、
周辺の水路、石垣、橋等を配し、1,000枚を超える瓦も一枚ずつ張り付けた
精密で忠実に再現されている。
参・文化財ふくやま55号
山本瀧之助記念室
⑭当時の山南川の災害対策
延長された堤防の決壊を防ぐため左岸(干拓地側)の堤防を高くしてある。
右岸側の遊水地に越水させるように作られている。
越流提(えつりゅうてい)という。
芦田川の御幸(七つ原)の辺りでは水位がある高さに達すると、
1m弱の幅で敢て堤防を切って、決めら
れた地域を遊水地にする慣行があったとされる。
16世紀初、芦田川の河口の港町として栄えた草戸千軒は、
土砂の堆積で水没、衰退していった集落。
江戸時代、利根川の支流の一つであった荒川(墨田川)は、
頻繁に洪水に見舞われ、幕府は、右岸の堤防を0.5m低く作り遊水地に
流して堤防を守ろうとし、そこに住んではならないと定めた。
ところが人口が増え肥沃な土地にやがて多くの人たちが住み繁栄してきた。
明治43年の大洪水で政府は本来遊水地であった所を守る為、
流路を大きく東に寄せた人工の流路を造ったのが荒川放水路である。
東京に流れる利根川・多摩川は200年に一度、その他の大河は
150年~100年に一度の大雨を想定して整備されている。
100年に一度の大雨が毎年発生する昨今の(温暖化による)異常気象下では
対応しきれない。
国土の30%が海面より低いオランダでは、高潮とライン川等の上流域での
豪雨が同時発生した場合を考え万年に1度に備えるデルタ計画を策定している。
堤防を高くする、土砂を掘るなどの「垂直型」だけでなく、
遊水地、河幅を広くするなど「水平治水型」発想を組み合わせ、
ハードの強化だけでなくは、自然に対応したしなやかな発想(レジリエンス)が
必要であるとされている。
江戸時代の人口増と停滞
国土の7割が山地の日本、定住を始めた弥生時代の人口は59万人位だったといわれている。
平地は大雨が山を削り谷を造り川を為して海に土砂を堆積させた所であり、
そこに人は住んだ。貝塚は、信じられない程内陸部で発掘されているが、
そのラインが当時の海岸線(海)であった。
平安時代頃の人口は800万人位であったとされる人口は、
江戸初期頃は、耕地が200万町歩で人口1500万人位とされている。
(勝成公入封時福山の人口は12,678人)
1700年代(5代綱吉、元禄の繁栄)には耕地は300万町歩に増え、
人口は3000万人と倍増している。
戦いが無くなり、干拓など新田開発が進み農家の次男・三男が入植し、
3~5年の鍬下年季にも守られて、一家を構えることが出来る様になった
ことによるからであろう。
新田開発が峠を超えてからは人口は200年間は押しなべて
3000万人を大きく超えることは無かった。
(鎖国で閉鎖経済下、農薬・肥料・新品種等の農業技術の進展は少なかった。)
開国、維新と時代は移り、化学肥料、農薬、品種改良など農業生産性、
食糧供給は向上しその後の人口増に対応していったが、
どう間違ったのか?一次産業の農業は、日本の高度成長の過程でとり残され、
休耕田だらけの食糧自給率30%台の農耕民族となってしまった。
これからの日本の農業や如何に?!
異常気象による想定外の大雨による被害は、水にしてみれば、
ごく自然に低い所を選んで海に納まろうとするだけである。
浸水想定来ラインは、嘗ての海岸線ラインである。
有史以来2000余年の間に、人は人の都合で自然に抗って、
海水面に侵食していって繁栄してきた。
そして今人は、悠久な自然の営みの気まぐれな気象現象に
生命を脅かされている。
「命の水」ともなる水と上手に付き合う為に、
「水は常に高い所から低い所(海)に流れる」という摂理
を忘れてはならない。
[本文の構成は、清水幹男さん提供です]
[現地に於いて解説は、本会の清水幹男さんと、村上訓代さんです。]
[映像は、yutubeへ掲載]
[https://youtu.be/bDnaX8am0BQ]
<映像は、25分21秒有ります。>
https://youtu.be/bDnaX8am0BQ











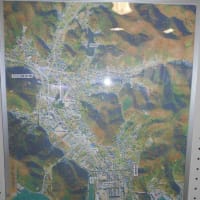








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます