10月の声を聞くと町内の氏神である、寄の宮(亀山)八幡宮の
祭礼が、始まる。
祭礼の当夜は、だんじり(山車)が引き組みの地域から町内を巡り、
寄の宮(亀山)八幡宮まで引き上げる。
その間、お宮では、神楽が奉納される。
引き組みは、それぞれの地域が年毎に決まっていて、
その年の引き組み担当地域がだんじり(山車)を各地域を回り、引き廻す。
見所の最後の引き場所は、寄の宮(亀山)八幡宮の鳥居から、
お宮の本殿のある山頂までの傾斜のある坂道を、
引き上げるのが、最大の見せ場となる。
それと、本殿前の山門の石段と、本殿前の広場に引き上げた後に
その広場で、だんじり(山車)を廻す時の勇壮さが引き組み最大の
見せ場になる。
この行事の当夜が始まりで、次の日には、
子供神輿と大人神輿が地域を練り歩く。
子供神輿は、午前中に、午後からは大人神輿が地域毎三躰出て、
町内を練り歩いた後、鳥居の所と、本殿前の広場で、
三躰の神輿が廻すのが見せ場となる。
若者同士の神輿の廻しあいは、見る人々の熱気や感情を呼び起こし、
自然と体中が熱くなり、見ている人々も自然とその熱気に包まれる。
この頃の都会の祭りは、車で運ぶ神輿が多く、人が担ぎ練り歩く祭りが
少なくなって来た中で、古くからの祭りの方法が残っている、この様な
祭りも見応えがある。
しかし、引き手・担ぎ手にとって、次の日には体中が痛くなる。
10月は、神無し月、出雲では神有り月となる。

(引き組み全員集合)

(町内を引き回る)
「ホラヤレ!!ホラヤレ!!」

(ご祝儀の披露)
「東西東西!!差し出された御花、御覧の通り金一封、右は御贔屓と下さいます、
○○さまより引き組み青年団の丞に下サーーる。
高こうは御座いますが、花の御礼!!」
(返礼の歌の後に)
「これ御礼に、セーノヤートコサ、セノヨーイヤサ!!」

(てんびんの下を通すだんじり(山車))
[引き手を揃える場合]
「ホラホンサのサじゃーー、イヤホウエンヤ!!」
今年のだんじりは、お宮の本殿前に上がったのは、午前1時を廻っていました。
引き組みの皆さん、大変お疲れさまでした。











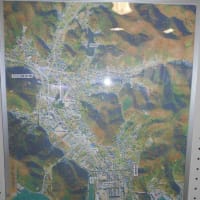








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます