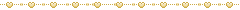やっと、できました。
長かった。
書き始めたのは一年前で。
途中なんともならなくて止まっちゃって。
そのまま放置。
つい先日、ようやく動き出してくれたものの。
相変わらずの表現力不足に追い込まれる私。
昨夜。
歌うまキッズを見つめるすばるの瞳が優しくて、優しすぎて、愛おしくて。
夜中に一気に進めたものの。
はぅー(>_<)
言葉って、難しい。
そんな作品ですが。
もしお読みいただけたら幸いです。
STORY.43 秋桜
小さな手をひきながら歩く散歩道。
乾いた風が、可憐な花の上を渡ってゆく。
濃い紅、薄い紅、ときおり混ざる白。
駈け出そうとする舞音の姿が、そこに溶けていきそうだ。
「あの歌は、こんな季節の歌だったのよね」
傍らで、ゆっくりと彼女がぽつり。
「あの歌?」
舞音を目の端に入れつつ、俺は彼女に問い返す。
「大好きだったの・・・」
彼女が花に視線を移す。
「でも、聞けなくなったし歌えなくなったわ。おかしいわね」
「なにそれ。わからへん。俺、知ってる歌?」
「どうだろう、もうずっと前の歌。それこそ、生まれるか生まれないかくらいの頃の」
「そんな古い歌、なんで知ってんねん」
「母が、口ずさんでた。こんな季節になると・・・」
「へぇ・・・あ!あかん!あかんで、舞音!! そっちは危ないって!」
わき道へ逸れようとする舞音を追いかけて、その会話はそこで途切れたままになった。
「ぱーぱ、あえ」
抱っこした舞音が指差した先に小さな教会。
華やかなドレスと、にぎやかな笑顔があふれる真ん中に。
ひときわ目立つ白い衣装。
「ああ。結婚式やな。お嫁さんや、舞音。奇麗やな」
「およめしゃん。まのも、あれ、きゆ」
「んあ? きゆ? 何を・・・あぁ、ウェディングドレスか」
「まの、きえゆ?」
「んー、着れるっちゃ着れるやろけど。もっとおっきィなってからやな」
「まの、おっきィ」
「いやいや、まだ、そんな急いでおっきィならんでもええで。ゆっくりでええから」
「まま、おっきィ」
「そやな、ママはおっきィな」
「まま、きた?」
「んー、ママか、ママはな・・・」
「着なかったわ」
俺の後ろから、彼女が舞音に話しかける。
「舞音は着れるといいわね」
そう言いながら、舞音の頭をくしゃくしゃっと撫でた。
「そしたら・・・」
彼女が言い淀む。
「そしたら、なに?」
続く言葉を聞きたくて、俺は尋ねる。
「あなたは花嫁の父ね」
話を遮るように、彼女が、笑って見せた。
なぁ。
やっぱり、着たかったはずやんな。
一生に一度の、ウェディングドレス。
俺は、着せてやれんかったもんな。
豪華な式も、祝いの席も、
二人きりの旅行さえ。
女の子が憧れるだろう、そのすべてを。
振り切って。
俺と「共に」と誓っただけで、一緒に暮らし始めた彼女。
あの時、それでいい、と彼女は言った。
「あなたが、そばにいてくれるだけで十分だから」と。
「幸せにする、なんて言わないで。
私は私で、幸せくらい見つけられる。
あなたがいたら、幸せをみつけられるから」
その言葉どおり。
彼女はいつも、幸せを描いたようにふんわり笑う。
我慢することも悔しいことも、しんどいことも、
すべて呑み込んで。
言葉や気持ちがすれ違う時ですら。
その静かな物言いは変わらない。
・・・・・・変わらない、っていうのはちょっと違うな。
すれ違うほど、より静かになっていくからな。
言葉や口調が、じれったいほど丁寧になってくよな。
実をいうと、あれ、
俺、ちょっと怖いねん。
感情ぶつけてくれた方が、なんぼかマシやな、って思うわ。
風が、カーテンを揺らした。
秋の陽が、リビングに降り注ぐ。
温かくもあり、涼しくもある、その陽だまりの中で。
お昼寝してる舞音に付き添って、
身体を横たえている彼女。
やんちゃな舞音につきあって、あれこれ世話焼いて。
毎日毎日、疲れてるんやろうな。
起こすん、可哀そうやねんけど。
時間的なこともあるしな。
「なあ、ちょっと、ええ?」
彼女の側に座り込んで、軽く肩を揺する。
「え? あ、ごめん、寝ちゃってた」
「風邪ひくで」
「う、うん・・・」
まだ、ぼんやりした頭で、目をこすりつつ彼女が俺を見る。
「どうしたの?こんな時間に。もう今日の仕事、終わったの?」
「んー、仕事は終わったっていうか・・・」
ほんまは、今日は仕事違うたんやけど。
それは、まだ、内緒や。
「舞音、今起こしたら泣くやんな」
「んー。起こしたくないのが本音だけど、なに?」
「ちょい、出かけへん?」
「今から?」
「手伝うて欲しいこと、あんねん」
「なに?」
「今日してた撮影のな、女の方のモデルがアカンことなってもうて」
「アカンことて?」
「ま、いろいろとな。で、その代役、手伝うてほしいねん」
「モデルなんて出来ないよ、私」
「ええねん、任せときゃええようにしてもらえるし」
「舞音、どうすんの」
「舞音も一緒や。舞音抱っこして、ちょい笑ってくれてたら、そんでええから」
「えー・・・?」
尻込みする彼女。
当たり前っちゃ、当たり前なんやけど。
「1回だけ、頼むから」
顔の前で両手合わせて、必死に頼む。
「しょうがないなぁ・・・じゃあ、舞音を起こして泣かなかったらOKしたげる」
「また、そんな無理難題だすなや・・・」
俺は、苦笑う。
せやけど、これ、引き受けんかったら話にならん。
「まのん?」
小さく呼びかけてはみたものの、起きる気配は無い。
俺は、そぉっと舞音の頭から頬のあたりを撫でる。
寝汗まではかいてへんけど、
ちいさな頬のじんわりとした温かさが手のひらに伝わる。
舞音の表情が少しだけゆがんだかと思えば、
ぱちりと、小さな目が開いた。
あかん。
泣くパターンか、これ。
きょとんと。
不思議そうな顔で、俺を見てる。
舞音、そのまま、そのままやで。
泣かんといてや。
くるんと体勢かえて腹ばいになったかと思うと。
なにかを探す舞音。
「まーまぁ・・・」
あー・・・
あかん。
俺は慌てて舞音を抱きかかえた。
「ただいま、舞音。よう眠れたか?」
いきなり抱きかかえられて、びっくりした舞音。
みるみる顔つきが歪む。
あかん。
抱いたん、失敗やったか?
「お出かけしよか? 舞音、お外好きやろ?」
いきなり本題入ってしもたやん。
子供相手に、なに焦ってんねん。
「あ、先になんか飲むか? ジュースか?ミルクか?それともお茶か?」
こらえきれずに。
俺の隣で、彼女がくすりと笑った。
「へたくそ」
なんやねん、下手言うなや。
下手、ちゃうわ。
「舞音、泣いてへんで。俺の勝ちやろ?」
先手必勝や。
泣き出す前に、こっちが勝ちやってことにしとかんとな。
「まぁ、泣いてはいないわね。しょうがない、付き合ってあげる」
よしよし。
うまいこといったで。
「舞音、パパとママとお出かけしようね」
そういって彼女は俺の手から舞音を抱きとった。
「汗かいてるから着替えだけさせるわね」
「あー、ええ、ええ、面倒くさい。どっちみち向こうで着替えるんやから、そのまんまでええわ」
彼女の腕の中の舞音をもう一度抱き取って、彼女を促す。
あっちの手こっちの手と渡されても、舞音はきょとんとしたままや。
ちょうどええ。
そのまま、大人しぃしとってくれよ。
頼むで、舞音。
貸し切ったのは植物園の中の小さなガーデンテラス。
木々の葉が、風に揺れて小さく音をたてる。
葉の影がゆらゆら。
足元に小さな影を作る。
時折あがる噴水の水は、夜になればライトを映して虹色に変化するらしいけど。
昼間の今はまだ。
太陽の光を集めて、ガラス玉みたいに水面に散らばってゆくだけ。
「お、用意出来たか?」
控え室のドアを少し開けて、俺は覗き込んだ。
『覗かないのよ!』
馴染みのメイクさんの声が飛んでくる。
「ええやん、ちょっとくらい。俺、主役やぞ」
『そのちょっとを我慢するのが男でしょう?』
苦笑混じりに言いながら、俺と入れ違いに部屋を出て行った。
部屋に入った俺は、
壁の大きな鏡の中に真っ白なドレスを着せられて、どこか不安そうな顔の彼女を見つけた。
「なんて顔してんねん」
近寄って話しかけようとしたとき、
足に思い切り鈍痛。
「痛ッ、なんや」
下を見ると、ニコニコの舞音が俺の足にしがみつくように体当たりしてた。
「ぱーぱッ!」
「お、舞音。べっぴんさんやな」
「まの、きえ?」
「きえ・・・?おぅ、綺麗やな、可愛いで」
「およめしゃん、みたい?」
薄いピンクのドレスを着せられた舞音。
髪までくるくる巻いてもらって、リボン付けられて。
「お嫁さんっていうより、お姫様やな。パパの大事なお姫様や」
俺は舞音を抱き上げて、彼女に近づいた。
いつもの笑顔は、そこにはなくて。
困ったような、戸惑ったような、不安そうな色。
「なんて顔や」
純白のドレスに不似合いな表情。
バレたか?失敗やったか?
「え、だって・・・これじゃ舞音抱っこできないじゃない」
そっちかぃ。
なんの心配やねん。
「舞音は俺が抱っこしてるから、ええやん。なー?舞音」
俺に顔を寄せて舞音がくしゃくしゃな笑顔になる。
「ほら、舞音みたいに笑ってみ?」
「笑うなんて出来ないもんー。撮影なんて、やっぱり無理ぃー」
「アホやな、いつもみたいにしてたらええねん。まんまでええから」
「まんまって言ったって、カメラ、慣れてないもん」
俺が言った撮影って言葉を、
疑いもなく思い込んでる彼女が、たまらなく愛おしいわ。
「そんなん、俺かて未だに慣れてへんわ。顔引きつってるなって、よう言われるし」
「・・・ああ、確かにね、そうね」
何かを思い出したかのように、彼女が少し笑った。
「あ、なんや笑うなや。笑うとこちゃうやん」
彼女が俺の顔をじっと見てくる。
「何や」
「そばにいてくれるのよね?」
「当たり前やん、俺がおらへんかったら意味あらへんし」
「うん。じゃあ、頑張る」
「・・・普通でええから。そのまんまが魅力なんやから」
俺は彼女の手を取って、上から包むように舞音の手と重ねた。
「俺だけやない、舞音も一緒や」
安心したように、彼女が微笑んだ。
『ご案内します』
頃合を見計らったかのように、スタッフの声がかかった。
俺はブーケを彼女に手渡す。
濃淡のピンクと白を取り混ぜて、
秋桜だけでアレンジした、素朴で可愛らしいブーケ。
「これ・・・」
彼女が俺を見上げる。
気づいたかな、気づかれたかな。
あの日、彼女が思い出した歌の、タイトルと同じ花やからな。
扉の前に立つ。
音楽が流れ始める。
まだ不思議そうな表情の彼女。
まぁ、わからんでもないが。
俺かて、ドッキドキやで。
うまいこと、いったらええねんけど。
俺は彼女を横目に、小声でささやく。
「大丈夫、俺がいてる」
彼女の手が強く握り返してきた瞬間、
扉が開いて、強い光が俺たちを包んだ。
シャッター音の代わりに耳に飛び込んでくるのは、
「おめでとう」の声。
強い光は撮影のライトではなく。
大きなガラス窓から注ぎ込んでくる、滲んだ赤い夕日。
目の前には。
俺のメンバーと。
少しのスタッフと。
それから、彼女の親。
びっくりしたんやろな。
彼女の動きが止まって、ピクリとも動かへんようになった。
「なに・・・これ・・・」
絞り出すような、震える声が漏れた。
「分からん?結婚式」
「・・・誰の?」
「アホやな、そんなん、聞くか?」
「撮影は・・・?」
「してるよ、ほら、あそこで」
小さなビデオカメラを片手に、メンバーが妙な動きでアピールしてる。
何してんねん、画面ブレるやろ。
ちゃんと撮らんかぃ。
ことを理解した彼女の瞳から、みるみるうちに涙が溢れ出す。
「ああああ、アカンて。泣くなや、泣き顔みたいんとちゃうんやから」
「まーま、ないちゃ、めーっよ」
小さな手で、舞音が彼女の涙を拭おうとする。
「まーま、きえいねー。およめしゃんみたいー」
「みたい、ちゃうで。お嫁さんや、パパの、自慢のな」
ああ。そうや。
こんな。
将来がどうなるかさえ漠然とした、不安定な。
そんな仕事をするしか能のない男のところに。
覚悟ひとつで嫁に来たんやもんな。
いつでもどこでも、誰にやって。
胸張って自慢したる。
俺の嫁や。
「大好きやで」
舞音越しに彼女にささやく。
「・・・ばか」
照れたように彼女は笑って。
「ありがとう」
俺の手を、もう一度握り返してきた。
伝わる温もりが優しく、俺の身体に流れ込んでくる気がした。
「だから、この花だったのね」
「お義母さんに聞いてん」
少ない出席者に隠れるようにして。
彼女の母は一生懸命に拍手をしてくれていた。
「秋桜・・・」
嫁ぎゆく娘と、送り出す母の。
ゆっくりとした愛情を紡いだ旧い歌。
いつか。
彼女も舞音と、そんな一日を迎えるんやろな。
ふんわり。
温かい。
柔らかな。
包み込む。
秋桜のような。
その笑顔を。
任せてくれるか?
頼られるんは苦手やった俺やけど。
どこまで出来るんか、頼りになるんかも分からんけど。
この手で。
守りきれるものなら全力で。
守りきってみせるから。
彼女の母の笑顔が、彼女に重なり。
彼女の笑顔が、
舞音に重なってゆく、命のつながり。
彼女の手の中の秋桜が、
かすかに揺れた。
まるで微笑っているかのように。
Fin.











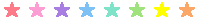


 だったのよぉ
だったのよぉ