
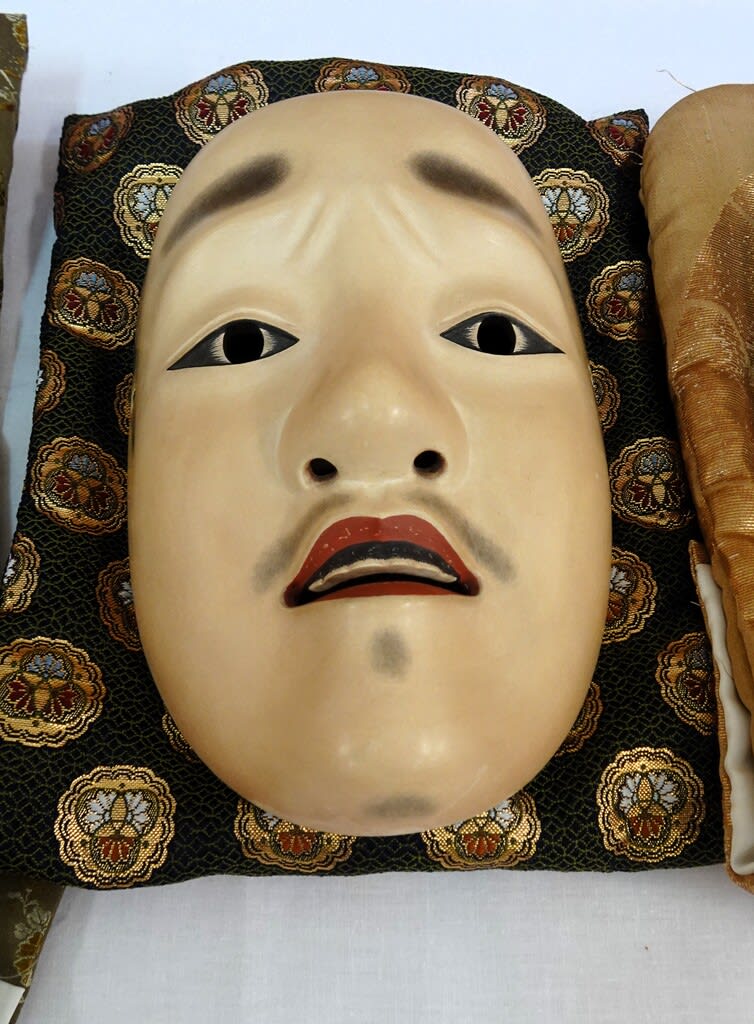


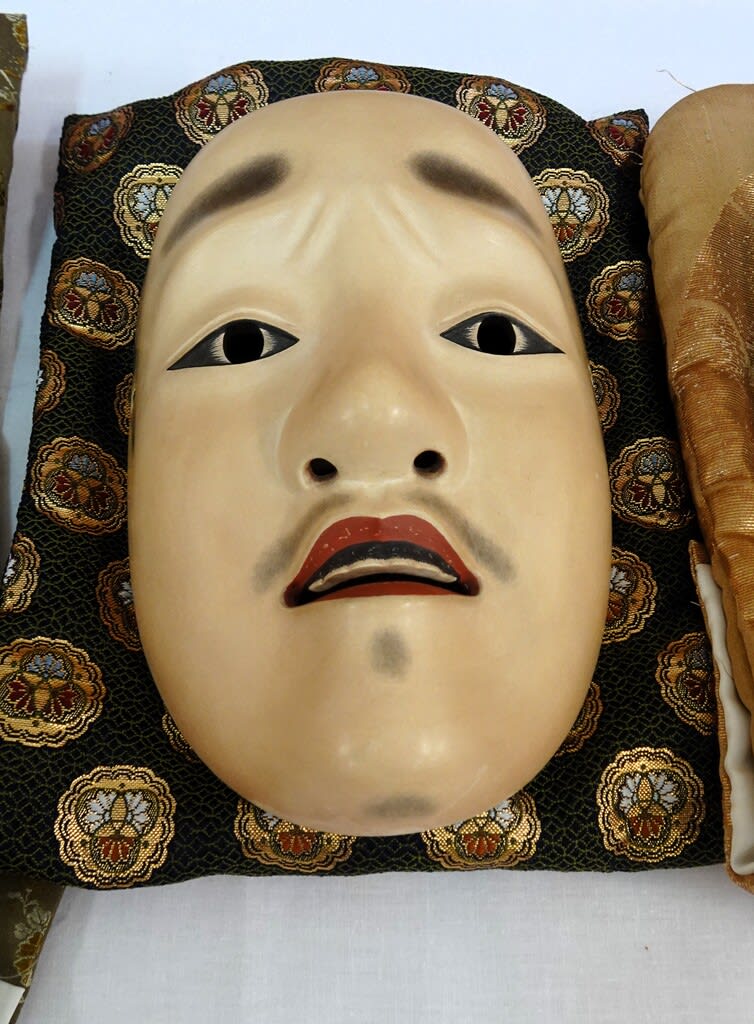


本文とは何の脈絡もないが北海道大沼公園
読書があまり好きでない私が
こんなタイトルの本を買った、
2024年版、
光村図書発行で
日本文芸家協会編 とある、
この手のエッセイ集は以前には
文芸春秋社発行で
日本エッセイスト・クラブ編として
出版されていた、
私が持っている限りでいえば
1983年版から2006年版まで
20数年に亘って出版された、
読書の習慣の無い私も
このシリーズだけは毎年買って
読んでいた、
もっとも私の読書嫌いには例外が有って
エッセイなどの比較的短い読み物に
はむしろ関心は大ありだった、
性格からくるものかどうかは
分からないが長編を読み切るだけの
根気が無いだけなのかもしれない、
話を旧ベスト・エッセイに戻そう、
❜83年初版のエッセイ集「耳ぶくろ」には
錚々たる顔ぶれが名を連ねていた、
野坂昭如、開高健、新藤兼人、
金子兜太、阿川弘之、澤地久枝
酒井大岳、金田一春彦、井伏鱒二、
昭和を代表すると言ってもいい程の
人気作家から映画監督、俳人、
宗教家、言語学者などなど
いずれ劣らぬ有名人の名を見ることが出来る、
このシリーズの影響もあってか
私も内面をエッセイと言う手段で
表現したいと思うようになり
20年ほど前からブログを始め
今日に至っている、
始めた頃からの1,000篇に及ぶ作品群は
ブログサイト提供側の終了と共に
移転作業に失敗して消失した、
魂を注いでいただけに大きな傷となった、
有名、無名人の心に残るエッセイの幾つかを
いづれ紹介したいと思っている。

安楽寺の参道
こんな帯封のキャッチフレーズが目に留まり
この本を買いに出かけた、
丸橋 賢 作の
「はじまりの谷」と言うタイトルの小説、
著者は現在80才、
これが処女作なんだと言う、
しかも作者は私と同じ高崎市内に住んで
昭和初期の上州の山村が舞台だと言う、
文芸に些かの興味を持つ私としては
買わない訳にはいかない一冊であった、
最寄りの本屋は数年前に閉店、
已む負えず10キロほど離れた前橋市内の
大型スーパーマーケットの一角にある
本屋に行った、
本屋になど滅多に行かない、
読書の習慣が身についていない、
たまに買うのは短編集とかエッセイ集、
その他は旅に関する本くらいなもの、
本の探し方からしてよく分からないので
店員に聞いたら持ってきてくれた、
支払いも自分で機械を操作する仕組み
のようだ、
書いてあることをよく読めば
自分で出来ないことでもないが
先ほどの店員が丁寧に教えてくれた、
帰ってからチビリチビリ読んでいる、
内容は
昭和初期の山村に暮らす
純粋無垢の少年と隣に住む
家族から疎外された老人との交流、
老人は自然の中で
力強く生きる術を伝えるのが
使命であるかのように少年に接する、
九州生まれの私とは舞台は違えど
時代の共通性から
共感するものの多い内容であった。

ブログネタに事欠いて
昔 作った歌(短歌)を取り上げることにしたが
お許し願いたい、
❝花咲けば カタバミ草も 愛おしき
梅雨の晴れ間の 庭の草取り❞
取っても取っても庭にはびこるカタバミ草
チョット油断するとプランターや植木鉢の中にまで
わがもの顔で根を張ってしまう、
でも開いた花をよく見ると意外ときれい、
こじんまりしてシンプルで雑草扱いするには
申し訳ない気分にもなる、
そんな心情を歌ってみた。

富士の裾野に山荘を持つKさんから
メールが届いた、
敷地内の草刈りに来たら
雑草の中にホタルブクロを見つけて
昔私が作った歌(短歌)を思い出したとのこと、
名誉なことだ、
素人の作った歌を思い出すほど
私の歌はインパクトがあったと言うのだから
名誉でなくて何であろう ?
歌の全容までは思い出せないので
教えて欲しいと言う文面、
はて どんな歌であったか?
記憶をたどってみるが
出だしが出てこない、
ホタルブクロに田舎の母を重ねて作った歌だが、
自分の歌とは言え
きちんと整理して保管しているわけではない、
何を見ればいいか一瞬迷った、
そこで頭に浮かんだのは20年ほど
前まで所属していた
短歌会の100回記念の作品集、
「群馬三枝短歌会」 2005年10月発行
あった、
よかった!
❝たとうれば ホタルブクロか 郷(くに)の母
紫うすく うつむきて咲く❞
自作の解説はしない、
読んでくれた皆さんの解釈に
委ねることにしよう。