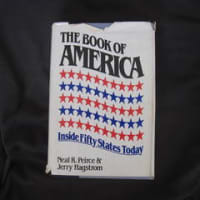自分の好きな人に初めて手紙(恋文)を書いたのは人によっていろいろであろう。そしてその懐かしい思い出はそれぞれの人がしっかりと持ち続けていることであろう。殆どの人は中学生や高校生の時にそのような経験を持っていることであろう。しかし私は高校を卒業するまでそのような経験はない。しかし、私は何と小学六年生の時に「恋文の代筆」をしたことがあるのである。
先日郷里で中学の同窓会があったあと、有志がまた集まって昔話をした。そこでいろいろなクラスメートの話がでたが、N君の話も出た。N君は先生も時々手を焼く番長であった。
N君について私の思い出も話した。私はN君に頼まれて恋文の代筆をしたことがあるのだ。何と小学校の6年生の時である。
一学年に2組だけしかない小さな小学校だったが、N君と私は1組。そして2組にK子さんという可愛い女の子がいた。勉強もよくできたし、終戦前に東京から縁故疎開して来たようで、洗練された都会っ子という感じであった。
あるとき、N君が神妙な顔をして私に頼みごとがあるというのである。何かというと、番長の彼にも似合わずおずおずと、自分のために手紙を書いてくれないかいう。どういう手紙か?と聞くと、しばらくためらった後、K子さんあてに書いて欲しい。自分はK子さんが好きなので気持ちを伝えたいのだという趣旨のことを言ったと思う。
具体的にどういう風に書くのかと聞くと、彼は私に任せると言う。
私自身、他の男子生徒と同じようにK子さんには関心を持っていた。どうしようかと思ったが、もし私ならこう書くだろうというような文を書いてやった。
N君はその通りで良いといい、彼は彼の「子分」の(仮称)A君に言って、昼休みの時間にその手紙を隣の組のK子さんのところに届けさせた。
そしてN君と私はA君が帰って来るのを待った。
「どうだった?K子は手紙をちゃんと読んだ?」とN君はA君に聞いた。
「K子はちゃんと読んだよ。」A君は答えた。
「それでK子は何か言ったか?」N君は意気込んでA君に聞いた。
「何も言ってなかったけど『この手紙、本当はM君が書いたのじゃないの?』ってK子が言ってたよ。」
とA君は答えた。M君とは私のことである。
私はそれを聞いて、何か私の思いが彼女に通じたのではないかとちょっと嬉しいような気がした。
N君もN君で自分の気持ちをK子さんに伝えたことで満足しているようだった。
勿論、この手紙はK子さんには無視されたのだが、N君と私にとって幸いだったことは、K子さんが
このことを担任の先生に訴え出たり、親に言ったりしなかったことである。
もし担任の先生にでも訴え出たりしたら、結構問題になったかもしれない。N君と私が自分達の担任の先生にしぼられるだけではなく、場合によっては親まで学校に呼び出されることになったかもしれない。
先週郷里での集まりでこの話をしたところ、誰もそういうことがあったということを知っている友人はいなかった。
その席にK子さんもいて私の前に座っていた。誰かがK子さんに、「K子さんは覚えている?」と聞いた。
「ええ、ちょっとは覚えている。」とK子さんは笑って答えた。
「本当はMちゃんがその手紙を書きたかったんじゃないの?」
男の友人が私に言った。
「70%か80%くらいそうかも知れないね。」と私は笑って答えた。
小学校6年生の12歳の私がシラノ・ド・ベルジュラックの役を演じたというわけだ。K子さんというロクサーヌ姫への恋文の代筆をしたのだ。
戯曲「シラノ・ド・ベルジュラック」では最後にはロクサーヌ姫はシラノの気持ちを理解して大団円になるのだが、私達の話しは、K子さんが「N君の恋文」を握りつぶしてそれで終わりということである。
この「ロクサーヌ姫」は、今回会ったときも、昔と変わらない美しい可愛らしい女性であった。よき妻、よき母であり、もうお孫さんもいるよき祖母のようだった。
また彼女がいろいろなことにしっかりとした卓見を述べるので、目を見張るような思いで私は聞いていた。
50年以上前の他の誰も知らない共通の記憶を思い起こす稀有の機会を持ったのは、何とも嬉しいことであった。
20歳近くなるまで恋文など書いたことがない私が、12歳の時に恋文を代筆したことがあるというお話である。
画像;筆者撮影