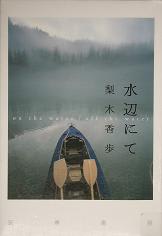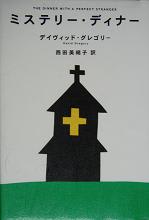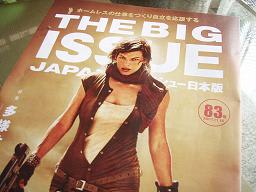
「いいもの、買ってきてあげたー♪」
帰宅した夫が得意そうにバッグからだしたのは・・・
『THE BIG ISSUE JAPAN』
前々から、週2大阪に出かける夫に頼んでいた‘お土産’です。
はんなさんのブログでこの雑誌を知って以来、見かけたら
買って来てくれるように頼んでいます。
この雑誌は、ホームレスの方の社会復帰に貢献することを
目指して、1991年イギリス・ロンドンではじまり数カ国で
発行されているそうです。
販売者は、最初10冊の雑誌を無料で受け取り、その売上
3000円を元手に140円原価の雑誌を今度は仕入れて
販売します。差額の利益を蓄え住居を得て自立することが
目標なのです。
アメリカでは以前からホームレスのみが販売できる新聞
(street newspaper)があっったそうですが、これを
事業として展開した人って、すごい!
日本では2003年大阪で日本版が発売され、今では
他の都市にも拡大しているようです。
まだ、手にとられたことのない方。・・・300円で記事も
興味深いものが沢山あります。
ぜひぜひ、見かけたら買ってみてください♪
(今回は特に表紙とインタヴュー記事が『5th エレメント』
以来、大好きなミラ・ジョヴォヴィッチ・・・
表紙裏にはコンテンツと併記で、『ビッグイシュー行動規範』が
表記されています。
― この雑誌の販売員さんは、公共的に迷惑にならないように
配慮しながらの販売行為で真面目にお仕事をしてるんだなぁ。
こんないい雑誌を気軽に買って、読んで、間違いなく(ほかに
流用されたり、搾取されることなく)真面目なホームレスの
方のお役に立てるなんて・・・
これからも、出来る限り購読したいと思う雑誌です。