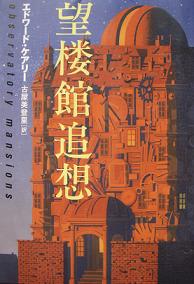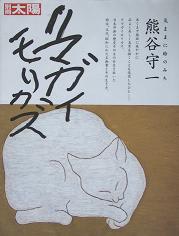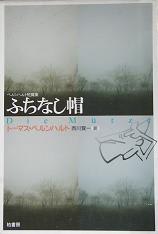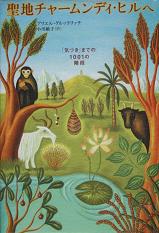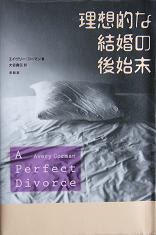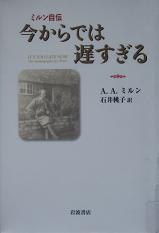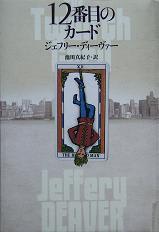へなちょこ探検隊―屋久島へ行ってきました (幻冬舎文庫)
写真&イラスト満載。
著者は、 『君はおりこう みんな知らないけれど』で
UPしたことのある銀色夏生。

なんていっても、屋久島だし興味深々で、読み始めた。
タイトルどおり、内容は計画の段階から、
同行者頼りで優柔不断なへなちょこぶり。
最終日の『沢登り』をパスしちゃたり・・・
わたしですら、え~~!!と
唸りたくなるほどの軟弱さ。
でも、さすが物書き。
ちょっとした休憩時の同行者の視線の先を追っていたり
なにげない旅行記の合間にリアルな描写が垣間見える。
で、最後にイラストに書き込まれた言葉。
で、結局、屋久島は
どうだったのか
と言うと、
木が緑が多く
水もきれいで、
自然たっぷりの島.
特別なものは
感じなかったけど
気持ちいいところ
でした.
ええ~~。
憧れの屋久島への熱が冷めるようなまとめ。
それなら、わたし、信楽の山を歩けば充分ーー?
そういえば「君は・・・」に較べると
ユルい全体の感じも、旅の感動がなかったから??
いえ、いえ。
それでも<旅を終えて>を
読んでいると、作者にも魅かれるし
屋久島もやっぱり訪ねてみたくなる。
・・・わたしは、どんな風に感じるだろうかと。
この後、TVでスタジオジブリ関連で
女優の鶴田真由が屋久島を訪れていた。
ガイドとして、伐採が行なわれていたころ
森に住んで子供時代を過していた人が同行していて、
途中小学校跡に足をとめたり古い写真も出たりして
番組は興味深かった。
屋久島。。。きっといつか、行くぞっ。
はげみになります♪ ぽちっ、ぷりーず。