加藤楸邨句集『望岳』論
楸邨の〈目〉
永田満徳
『望岳』は加藤楸邨の遺句集で、平成八年七月三日に発刊された。個の内面の掘り下げという人間追求を第一義とし、停滞を嫌い、七十歳になっても句材を求めて海外を旅するほどの俳句一途の俳人であった楸邨の最後の句集ということで、集大成の意味をもつものではないかとひそかに期待しつつ、全句四四五句を精読した。果たしてその期待にたがわない句集であった。
この『望岳』が特に晩年近く楸邨と親しくしていた大岡信によって組まれたことは適任であったし、句集にとって幸運であったと言わなければならない。というのは、大岡が朝日新聞に発表した「加藤楸邨を悼む」という文章から、楸邨の最も良き理解者は他でもなくまさしく大岡自身であったことが否応なく伝わってくるからである。大岡はそこで、加藤楸邨が天性の俳人ではなかったが、武骨、不器用な作者としてそのままみごとに全面開花し、円熟した俳人であったと述べている。この文章が、故人に対して実に愛情と敬意のこもった追悼文であるのはむろんのことだが、短い文章ながら数多くの楸邨論の中でも際立つものである。しかも、『望岳』の評としても立派に通用するもので、新たな評を付け加える必要のないほどである。ただ、私なりに『望岳』の印象として特徴的なことに触れてみたい。
まず、そこには〈目〉に関する語彙が数多く見受けられ、楸邨俳句を理解する上での一つのキーワード的な役割を果たすのではないかと思われる
草にたふれし石像の目を蛾がかくす
蟇あるく動かざる目をたたく雨
楸邨の〈目〉への注意、ありてい言えば嗜好を如実に示しているのがこの両句である。
鳴かずゐる笹鳴の目を感じをり
出目金の破璃越しの目と睨みあふ
埋み火の底に蛇笏の目がありき
極月の征く友の大きな目がありき
四句とも他者の〈目〉を描いているが、一・二番の句は動物にさえ人格を感じる感覚の鋭さが感じられ、三・四番の句は対象が人間であれば〈父の目を以て嫁ぐ子を末枯に〉〈闇冴えて先生の目が前後左右〉という以前の句と同様に、〈目〉でその人自身を象徴する奥行の深い表現となっている。
母、我を孕りし時、山梨県猿橋を越えしといふ、一句
目ひらけば母胎はみどり雪解谿
母胎にて見しは九月の甲斐駒か
〈母胎〉という語のある句を拾い出してみると、いずれも〈目〉〈見〉など視覚に関する言葉である。この句集から「 見る」 という動詞を見つけ出すのがそれほど難しくないのは、視覚的な体験が原初的なものであったからに他ならない。ここに「 人間探求派」 に加えられながら、彼らと違った独特の地歩を築いていった秘密がある。
この原初的な視覚体験が楸邨の俳句観と不可分の関係にある。「真実感合」という俳句理論で大切なことは、「見て見て見抜いて客観写生の限界から飛躍する」 表現を希求したことにある。この〈見て見て見抜く〉力の根源こそが原初的な視覚体験であり、視覚的な言葉へのこだわりである。楸邨自身、芭蕉の「見えたる光いまだ心に消えざるうちにいひとむベし」の〈見えたる光〉を捉えるものは、知的なものでは割り切れない根源的な本能的な、一種のデモンだと述べていることと関連していよう。視覚言語の偏用は生得的なものだったのである。
ところで、『望岳』が昭和六十一年、つまり知世子夫人歿年から楸邨歿年までの句であることの意味は大きい。妻に対する愛情が一貫して深く、妻の俳句的才能を伸ばし、同好の士のような間柄であった楸邨にとっての知世子夫人の死は、この句集の一つの主題を成しているとさえ言えよう。
打ちもらしたるごきぶりや遺影が笑む
忘れ霜つねに言ひたき遺影のロ
かぎろひて知世子圓空を撫でてをり
一人身になった楸邨の〈目〉が知世子夫人だけでなく自分自身に向けられてくるとき、「人聞探求派」の句だけに読んでいて心が痛む。
風鈴とたそがれてゐしひとりかな
餅を噛むこのときまつたくひとりなり
「ひとり」「ひとつ」などの〈一〉という数字に類縁の語が頻出するのも特色である。これらは孤独の相を帯びていて、最後まで自分を詠むことをやめなかった一俳人の老いの姿を余すところなく描いている。老いた永井荷風を知ることはできないが、老いた加藤楸邨を知ることはできる。そこに小説家と俳人の違いがあるとしても。
楸邨の写真を見ると、「目」は決して大きくなく、むしろ細目に近い。しかし、この目こそが多くの秀作を残し、大岡をして「楸邨はやはりあっぱれ天下第一等の俳人だった」と言わしめているのだと思いたい。















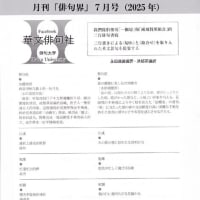
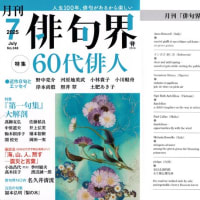


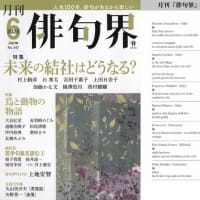





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます