今日は趣を変えて、「運」というものについて常日頃私が考えていることを披露したい。
先の金沢滞在時読んだ故直木賞作家・色川武大の「うらおもて人生録」はなかなか含蓄に富んで面白かったのだが、ギャンブルの神様(色川武大には阿佐田哲也の別名義で「麻雀放浪記」<ギャンブル小説の最高峰>がある)と畏れられた故人が、若いときに賭場という生きるか死ぬかの修羅場で身につけた運にまつわる法則は、普通の人が生きてゆくための技術とセオリーにもつながるようだ。
彼が説いているのは8勝7敗説で、以下本書から抜粋すると。
人生を相撲の星勘定で考えると
15戦全勝を狙ってはいけない。
8勝7敗を良しとすべき。
理想は、「9勝6敗ぐらいの星をいつもあげる」こと。
それには運をコントロールしなければならない。
運とは実力以外の全ての要素であり、運は使い果たせばやがてゼロになる。
運は一生を通じて見ると誰でもプラスマイナスでゼロになる。
そして、どんなに優れたバクチ打ちでも常に勝ち続けることが出来ない。
ならば
「運をロスしない」こと、
「大負け越しになるような負け星をさけていく」ことが大切≒言い換えると、「適当な負け星」を引き込む工夫。
→8勝って、7捨てるセオリー。この神経をフォームとして身につけよ。
8勝7敗を良しとすべきで理想は9勝6敗という、人生の勝ち負けに対する彼なりのセオリーだ。実際、色川は麻雀などでも勝ち過ぎるときは警戒して、わざと負けたりしていたという。つまり、そこで運を使い果たしてしまうと、本業(作家業)のほうに回らなくなるとの懸念だ。飛行機事故で夭折した向田邦子のことを、「あの人はツキすぎていた」と述懐したとのことで、つまり運を全部使い果たしてしまったから、不慮の死を遂げたといいたかったんだろう。五味康祐も、柴田錬三郎も、麻雀が強すぎた、後者はつきにつきまくっていたといわれるが、両者とも早死にした。
自分に照らし合わせてときどき考えることがある。私は一体、どこで運を使い込んでいるのだろうと。何ゆえに、本業(作家業)ではついていないのかと。棚からぼた餅式に大金が降ってくることが二度あったゆえ、経済的には恵まれていることになる。また、若いときは破綻家庭で育ち苦労したが、インドに渡ってからは、ホテル業に成功し、家庭にも恵まれ、自分にはもったいないくらいのよき息子に恵まれた(とんびがたかを産んだとはこのこと)。
毎年一、二度は日本に帰国も出来、最近金沢に副ベースも作れた。
医者と実業家の弟二人に恵まれている。
インドでアッパーミドルクラスの生活を送れる。
などなど。
上を見れば切りが無いが、現地に貧困者があふれている苛酷な現実を見ると、比較的恵まれているのだろう。
現地の宿経営に関してはそれなりの苦労があったが、これも戦前戦後を生きてきた祖父母、父母世代の苦労に比べると、苦労のうちに入らないだろう。
多産だった昔の女性は病死か戦死、事故死で子供の一人や二人亡くしているし、母方の祖母は福井空襲、敗戦、戦後の農地解放で地主階級からの没落、福井大震災で三女喪失と、大変な苦労をしている。父方の祖母は三人もの子供に死なれている(うち一人は戦死。四男だった私の父が長男としての責を負うことになった)。
というわけで、私は本業以外のところで運を使い果たしていることになり、肝心のところに回ってこないということだ。
アルフィーのリードヴォーカルの桜井さんが、自分は運が悪い、ついてないとおっしゃってたが、たとえば、貝を食べるといつも石に当たる、トイレに行くと紙が切れかけていた、レストランでオーダーした食事が散々待たされた挙句品切れといわれたなど、小さな不運の連続、私に言わせれば、アルフィーというバンドグループで大きな成功を納めていて、彼一人だけ妻帯者、もうここで運を使い果たしている、日常生活の些細な不運が続くのはバランスをとるためで、でないと突然死という致命的な終局に見舞われないとも限らないから、そういう小さな悪運が積み重なってちょうどいい具合にバランスが取れているのだから、ある意味安心ということである。
坂崎さん、タカミーは、いまだに独身、特に独身主義者ということでもなく、そういう話もいくつかあったようだが、還暦越えて独り身というのはある意味不運、で、ここでミュージシャンとしての大成功とのバランスをとっているのだろう。タカミーは育った家庭が厳格で、父との葛藤もあったみたいだったが、それもバランス、最後は相殺ゼロになるというから、あまりにツキすぎているときは警戒が必要だ。
よく芸人さんなんか、ツキを逃さないため、大金が入ったときは、付きの者など目下にばら撒くとよいといわれるが。
もうひとつ、故森瑤子のケース。死の何年か前に本人がエッセイで書いていたことだが、このごろツキすぎて自分がこうなってほしいと思うことがどんどんかなう、怖いくらいって、あったな。十五年で150冊。流行作家としてもてはやされた故人だけど、夫との確執があったし、両者ともに不倫もあったようだ(死後は娘と英国人父のとの間で遺産争議)。
結局、大成功しているように見える人でも、それはそこのレベルで不運を抱えているということ、でないと、つきっぱなしで上り詰めると、運を使い果たして、肝心要の寿命が危うくなる。
それにしても、この年になると、キャリアの差ってのが顕著に見えてきて、同じ人間なのに、なんでここまで開きがあるんだと、落差に悲観したくもなるが、ツキすぎても怖いので、比較的恵まれてる自分はそこそこんところで運不運のバランスをとってるんだと無理に自分に思い込ませて、劣等感を拭い去る。
なんにしても、死ねばみなしゃれこうべ。
遅いか早いかだけの話で、老いて病を得て死んでいくのはこの世のことわり。
そういう意味では、この世は公平に出来ているんである。
*以下、色川武大のウイキから一部引用。
学校生活になじめず、小学生時代から、学校をサボって浅草興行街に出入りし、映画や寄席、喜劇などに熱中する。あまりに学校をサボるので塾に通わされたが、そこもまたサボって寄席に通っていた。
アメリカ映画のスタッフの名前を覚えて各人の出世や退職などを見守ったり、実在の相撲の力士や野球選手の名前を書いたカードを作り、サイコロを振って勝敗をつける独自のゲームを考案して、その「一人遊び」に熱中したりした。相撲ゲームには20代半ばまで熱中した。後年、競輪に熱中するようになると、実在の競輪選手4000人のカードを作り、それを使ったゲームにも熱中した。
1945年に終戦を迎えるが、無期停学処分のままだったために進級も転校もできず、結果的に中学を中退。父親の恩給が止まったため、生活のため以後5年ほどかつぎ屋、闇屋、街頭の立ち売り、博徒などの職を転々とし、アウトローの生活へ身を投じる。
後に執筆した『麻雀放浪記』の主人公「坊や哲」や「女衒の達」さながらのバクチ修行をし、サイコロ博打や麻雀の腕を磨く。稼いだ時は上宿へ泊まり、文無しになった際は野宿をした。このギャンブル没頭時代に、後に彼の人生自身の哲学となる「ツキの流れを読んでそれに従う」「欲張りすぎず、(相撲でいえば)九勝六敗を狙う」などの考えを身につける。
1953年(昭和28年)には桃園書房に入社。事実上アウトローの世界より引退。『小説倶楽部』誌の編集者として藤原審爾や山田風太郎のサロンに出入りをする。特に、藤原には「人生の師匠」とまで傾倒していた。
この頃の色川は(本人は「顔も声も悪い」と言ってはいたが)痩身の美男子であった。また山田によると「円形恐怖症」で、リンゴ、卵、ボールなどを怖がったという(のちの『怪しい来客簿』では「山が怖い」と書かれている)。
この頃から既に後に病名が判明するナルコレプシーの兆候があり(著者注。伊集院静の「いねむり先生」は色川がモデル、本はこちら)、山田宅や藤原宅で麻雀が催されると自分の番が来るまでに寝てしまい、その度に起こされていたという。なお、麻雀の玄人であったことがばれないよう、トップにはならず「いつも、少しだけ浮く」という麻雀を打っていた。吉行淳之介はその打ち方を見て不審に感じ、のち阿佐田哲也名義で『麻雀放浪記』が刊行された際、「この作者はおそらく色川武大だ」と直感したという。
1978年(昭和53年)には『離婚』(著者注.超お薦め!)で第79回直木賞を受賞する。この作品は事実とフィクションが入り混じった内容で、孝子夫人(著者注.73年に結婚した従姉妹で若い頃東宝から映画女優としてのスカウトがきたほどの美人)は「小説のとおりの人物」と人から思われ、人間不信になり自殺まで考えたという。
先の金沢滞在時読んだ故直木賞作家・色川武大の「うらおもて人生録」はなかなか含蓄に富んで面白かったのだが、ギャンブルの神様(色川武大には阿佐田哲也の別名義で「麻雀放浪記」<ギャンブル小説の最高峰>がある)と畏れられた故人が、若いときに賭場という生きるか死ぬかの修羅場で身につけた運にまつわる法則は、普通の人が生きてゆくための技術とセオリーにもつながるようだ。
彼が説いているのは8勝7敗説で、以下本書から抜粋すると。
人生を相撲の星勘定で考えると
15戦全勝を狙ってはいけない。
8勝7敗を良しとすべき。
理想は、「9勝6敗ぐらいの星をいつもあげる」こと。
それには運をコントロールしなければならない。
運とは実力以外の全ての要素であり、運は使い果たせばやがてゼロになる。
運は一生を通じて見ると誰でもプラスマイナスでゼロになる。
そして、どんなに優れたバクチ打ちでも常に勝ち続けることが出来ない。
ならば
「運をロスしない」こと、
「大負け越しになるような負け星をさけていく」ことが大切≒言い換えると、「適当な負け星」を引き込む工夫。
→8勝って、7捨てるセオリー。この神経をフォームとして身につけよ。
8勝7敗を良しとすべきで理想は9勝6敗という、人生の勝ち負けに対する彼なりのセオリーだ。実際、色川は麻雀などでも勝ち過ぎるときは警戒して、わざと負けたりしていたという。つまり、そこで運を使い果たしてしまうと、本業(作家業)のほうに回らなくなるとの懸念だ。飛行機事故で夭折した向田邦子のことを、「あの人はツキすぎていた」と述懐したとのことで、つまり運を全部使い果たしてしまったから、不慮の死を遂げたといいたかったんだろう。五味康祐も、柴田錬三郎も、麻雀が強すぎた、後者はつきにつきまくっていたといわれるが、両者とも早死にした。
自分に照らし合わせてときどき考えることがある。私は一体、どこで運を使い込んでいるのだろうと。何ゆえに、本業(作家業)ではついていないのかと。棚からぼた餅式に大金が降ってくることが二度あったゆえ、経済的には恵まれていることになる。また、若いときは破綻家庭で育ち苦労したが、インドに渡ってからは、ホテル業に成功し、家庭にも恵まれ、自分にはもったいないくらいのよき息子に恵まれた(とんびがたかを産んだとはこのこと)。
毎年一、二度は日本に帰国も出来、最近金沢に副ベースも作れた。
医者と実業家の弟二人に恵まれている。
インドでアッパーミドルクラスの生活を送れる。
などなど。
上を見れば切りが無いが、現地に貧困者があふれている苛酷な現実を見ると、比較的恵まれているのだろう。
現地の宿経営に関してはそれなりの苦労があったが、これも戦前戦後を生きてきた祖父母、父母世代の苦労に比べると、苦労のうちに入らないだろう。
多産だった昔の女性は病死か戦死、事故死で子供の一人や二人亡くしているし、母方の祖母は福井空襲、敗戦、戦後の農地解放で地主階級からの没落、福井大震災で三女喪失と、大変な苦労をしている。父方の祖母は三人もの子供に死なれている(うち一人は戦死。四男だった私の父が長男としての責を負うことになった)。
というわけで、私は本業以外のところで運を使い果たしていることになり、肝心のところに回ってこないということだ。
アルフィーのリードヴォーカルの桜井さんが、自分は運が悪い、ついてないとおっしゃってたが、たとえば、貝を食べるといつも石に当たる、トイレに行くと紙が切れかけていた、レストランでオーダーした食事が散々待たされた挙句品切れといわれたなど、小さな不運の連続、私に言わせれば、アルフィーというバンドグループで大きな成功を納めていて、彼一人だけ妻帯者、もうここで運を使い果たしている、日常生活の些細な不運が続くのはバランスをとるためで、でないと突然死という致命的な終局に見舞われないとも限らないから、そういう小さな悪運が積み重なってちょうどいい具合にバランスが取れているのだから、ある意味安心ということである。
坂崎さん、タカミーは、いまだに独身、特に独身主義者ということでもなく、そういう話もいくつかあったようだが、還暦越えて独り身というのはある意味不運、で、ここでミュージシャンとしての大成功とのバランスをとっているのだろう。タカミーは育った家庭が厳格で、父との葛藤もあったみたいだったが、それもバランス、最後は相殺ゼロになるというから、あまりにツキすぎているときは警戒が必要だ。
よく芸人さんなんか、ツキを逃さないため、大金が入ったときは、付きの者など目下にばら撒くとよいといわれるが。
もうひとつ、故森瑤子のケース。死の何年か前に本人がエッセイで書いていたことだが、このごろツキすぎて自分がこうなってほしいと思うことがどんどんかなう、怖いくらいって、あったな。十五年で150冊。流行作家としてもてはやされた故人だけど、夫との確執があったし、両者ともに不倫もあったようだ(死後は娘と英国人父のとの間で遺産争議)。
結局、大成功しているように見える人でも、それはそこのレベルで不運を抱えているということ、でないと、つきっぱなしで上り詰めると、運を使い果たして、肝心要の寿命が危うくなる。
それにしても、この年になると、キャリアの差ってのが顕著に見えてきて、同じ人間なのに、なんでここまで開きがあるんだと、落差に悲観したくもなるが、ツキすぎても怖いので、比較的恵まれてる自分はそこそこんところで運不運のバランスをとってるんだと無理に自分に思い込ませて、劣等感を拭い去る。
なんにしても、死ねばみなしゃれこうべ。
遅いか早いかだけの話で、老いて病を得て死んでいくのはこの世のことわり。
そういう意味では、この世は公平に出来ているんである。
*以下、色川武大のウイキから一部引用。
学校生活になじめず、小学生時代から、学校をサボって浅草興行街に出入りし、映画や寄席、喜劇などに熱中する。あまりに学校をサボるので塾に通わされたが、そこもまたサボって寄席に通っていた。
アメリカ映画のスタッフの名前を覚えて各人の出世や退職などを見守ったり、実在の相撲の力士や野球選手の名前を書いたカードを作り、サイコロを振って勝敗をつける独自のゲームを考案して、その「一人遊び」に熱中したりした。相撲ゲームには20代半ばまで熱中した。後年、競輪に熱中するようになると、実在の競輪選手4000人のカードを作り、それを使ったゲームにも熱中した。
1945年に終戦を迎えるが、無期停学処分のままだったために進級も転校もできず、結果的に中学を中退。父親の恩給が止まったため、生活のため以後5年ほどかつぎ屋、闇屋、街頭の立ち売り、博徒などの職を転々とし、アウトローの生活へ身を投じる。
後に執筆した『麻雀放浪記』の主人公「坊や哲」や「女衒の達」さながらのバクチ修行をし、サイコロ博打や麻雀の腕を磨く。稼いだ時は上宿へ泊まり、文無しになった際は野宿をした。このギャンブル没頭時代に、後に彼の人生自身の哲学となる「ツキの流れを読んでそれに従う」「欲張りすぎず、(相撲でいえば)九勝六敗を狙う」などの考えを身につける。
1953年(昭和28年)には桃園書房に入社。事実上アウトローの世界より引退。『小説倶楽部』誌の編集者として藤原審爾や山田風太郎のサロンに出入りをする。特に、藤原には「人生の師匠」とまで傾倒していた。
この頃の色川は(本人は「顔も声も悪い」と言ってはいたが)痩身の美男子であった。また山田によると「円形恐怖症」で、リンゴ、卵、ボールなどを怖がったという(のちの『怪しい来客簿』では「山が怖い」と書かれている)。
この頃から既に後に病名が判明するナルコレプシーの兆候があり(著者注。伊集院静の「いねむり先生」は色川がモデル、本はこちら)、山田宅や藤原宅で麻雀が催されると自分の番が来るまでに寝てしまい、その度に起こされていたという。なお、麻雀の玄人であったことがばれないよう、トップにはならず「いつも、少しだけ浮く」という麻雀を打っていた。吉行淳之介はその打ち方を見て不審に感じ、のち阿佐田哲也名義で『麻雀放浪記』が刊行された際、「この作者はおそらく色川武大だ」と直感したという。
1978年(昭和53年)には『離婚』(著者注.超お薦め!)で第79回直木賞を受賞する。この作品は事実とフィクションが入り混じった内容で、孝子夫人(著者注.73年に結婚した従姉妹で若い頃東宝から映画女優としてのスカウトがきたほどの美人)は「小説のとおりの人物」と人から思われ、人間不信になり自殺まで考えたという。

























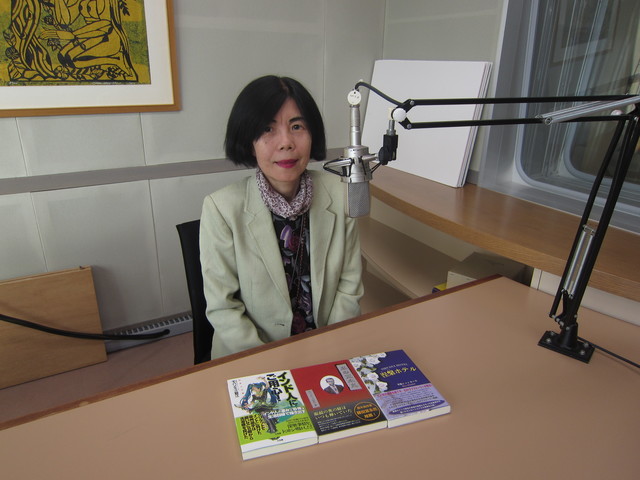

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます