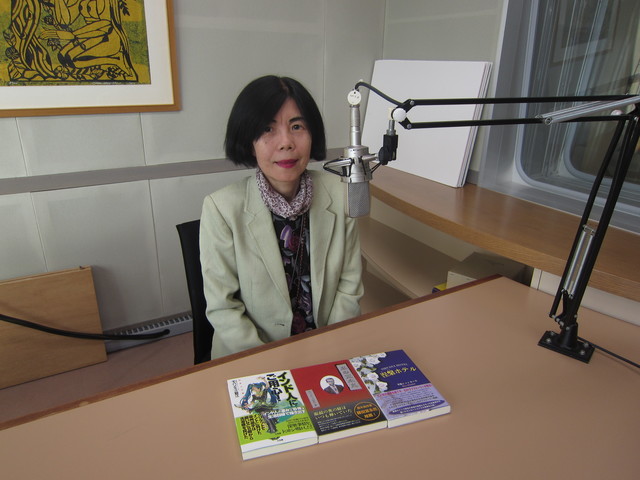六月に入り、雷雨、小雨、曇天とすっかりモンスーンの兆し。
雨に打たれたせいか、万年風邪引きの夫からうつされたせいか、夏風邪気味。
あんなに寒かった金沢では一度も風邪をひかなかったのに、こっちに帰って来て今年最初の風邪。
早速塩湯うがいや揚げにんにくのかけらで改善を図っているが、二日目の今日は目がしょぼしょぼ、だるい。
少し休めということかもしれない。
五月のミッドサマーを通過した気の緩みもあるかもしれないが、やはり、これまでの猛暑が雨で気温降下、初老の体が変わり目についていけないこともあろう。
雨が降ったら俄然涼しくなるはずが、そうでもなく、熱帯のじっとりと熱い雨で、湿度が飽満、不快指数100%、高湿度ってのは、菌も繁殖しやすいし、体の敵。
坐骨神経痛もちの私には低気圧もしんどく、青菜に塩の体たらく。
やはり、インドは苛酷だなあ。
金沢は雪で厳寒、これもしんどかったが、やっと通り過ぎてこれからいい季節に入る四月半ばに炎暑のインドに戻ってきてしまったわけだから、なんだか日本でもインドでも最悪の季節に飛び込んだようで、病み上がりにはつらい。
冷房をつけると、寒すぎて、つけないと暑い。
天井にとりつけた大型とんぼ扇風機があるが、生ぬるい風を送ってくるので、エアコンつけて、冷えすぎると消して、しばらくしてまたつけての繰り返し。
閑話休題。今読んでいるのは「吉原江戸図聚」。
以下、アマゾンの内容紹介から引用。
江戸風俗画の研究と模写に打ち込んできた著者が、肉筆浮世絵、版画、黄表紙や洒落本の挿絵など、全盛時の吉原を描いた二百五十余点の絵画資料を精確に復元し、それぞれに平易な解説を付す。登楼のしくみ、廓内の風景、遊女の生活と風俗、吉原の年中行事など、いまは失われた吉原遊廓の全貌を鮮やかによみがえらせる画期的労作。
トップカスタマーレビュー
5つ星のうち 4.0江戸文化としての吉原
投稿者 kh VINE メンバー 投稿日 2002/10/23
形式: 文庫
こういう本が文庫で手に入るとは嬉しいかぎりです。年中行事、遊女の生活など吉原の風俗がことこまかに描かれております。なかには心中の仕損じ、相対死、おろし(堕胎)、私刑、折檻といった悲惨なものもありますが、墨の、細い描線で描かれた絵図の美しさのため、どこか夢幻の世界の話でも聞いているような気になってしまいます。ここにあるのは江戸の文化としての吉原でありまして、歌舞伎に昇華される美の原型、現実そのものではありません。われわれにとっては、江戸文化のお勉強としての吉原でしょうか。文章のですます調は、悲惨を語っても、どこか優雅。真夏に手足をしばり、押し入れへ入れて、蚊に食わせる蚊責めなんぞもございましたそうで。へい。
いやあ、詳しいです。
実はこの分厚い文庫(656ページ)、私のメントーともいうべき人が吉原について書きたいと洩らしたら、プレゼントしてくれたのだけど、重宝している。
吉原をテーマにした小説は何冊も出ているので、私はちょっと視点を変えてと思っているが、この六年ほど山谷を常宿にしているせいで、この界隈はほぼ周り尽くし、吉原も無論三度も周遊済み、地図が載っていても少なからぬ土地勘があるので、役立っている。
お大尽の舟が通った山谷堀跡とか、周辺の待乳山聖天とか、吉原入り口手前の通り(日本堤)の左脇にある見返り柳(遊客が帰りしな、名残惜しそうに振り返ったことからこの名がある)、全部知ってる。
それにしても、この本は面白い。
現在はソープ街と化している吉原だが、今昔吉原比べも面白い。
絵だけ見てると、おいらんの髪型や衣装の豪華さにため息が漏れそうになるが、実態は苦しいことや悲しいことが多かったんだろうな。楼主によるせっかんとかもあったみたいだし、男装して逃げる遊女もいたらしい。
心中とか相対死(違う場所で同じ時刻に共死)もあって、生き残ると、日本橋で三日さらし者になってに転落、それと避妊手段がなかった当時、下級遊女が孕むと、原始的な手段で堕胎を強要されたりと、実態は遊郭地獄絵図だ。
子持ちおいらんもいたらしいが(女児は遊女見習い、かむろになった)。
おいらん道中など華麗の極みだが、絵のように美しいうわべの下には醜悪、悲惨きわまる現実があったんだろう。
実に興味深い一冊で、お薦めです。
ちなみに、吉原細見(案内書)の版元が蔦屋とあったけど、今のツタヤって、まさかここからきてるんじゃないだろうな?
雨に打たれたせいか、万年風邪引きの夫からうつされたせいか、夏風邪気味。
あんなに寒かった金沢では一度も風邪をひかなかったのに、こっちに帰って来て今年最初の風邪。
早速塩湯うがいや揚げにんにくのかけらで改善を図っているが、二日目の今日は目がしょぼしょぼ、だるい。
少し休めということかもしれない。
五月のミッドサマーを通過した気の緩みもあるかもしれないが、やはり、これまでの猛暑が雨で気温降下、初老の体が変わり目についていけないこともあろう。
雨が降ったら俄然涼しくなるはずが、そうでもなく、熱帯のじっとりと熱い雨で、湿度が飽満、不快指数100%、高湿度ってのは、菌も繁殖しやすいし、体の敵。
坐骨神経痛もちの私には低気圧もしんどく、青菜に塩の体たらく。
やはり、インドは苛酷だなあ。
金沢は雪で厳寒、これもしんどかったが、やっと通り過ぎてこれからいい季節に入る四月半ばに炎暑のインドに戻ってきてしまったわけだから、なんだか日本でもインドでも最悪の季節に飛び込んだようで、病み上がりにはつらい。
冷房をつけると、寒すぎて、つけないと暑い。
天井にとりつけた大型とんぼ扇風機があるが、生ぬるい風を送ってくるので、エアコンつけて、冷えすぎると消して、しばらくしてまたつけての繰り返し。
閑話休題。今読んでいるのは「吉原江戸図聚」。
以下、アマゾンの内容紹介から引用。
江戸風俗画の研究と模写に打ち込んできた著者が、肉筆浮世絵、版画、黄表紙や洒落本の挿絵など、全盛時の吉原を描いた二百五十余点の絵画資料を精確に復元し、それぞれに平易な解説を付す。登楼のしくみ、廓内の風景、遊女の生活と風俗、吉原の年中行事など、いまは失われた吉原遊廓の全貌を鮮やかによみがえらせる画期的労作。
トップカスタマーレビュー
5つ星のうち 4.0江戸文化としての吉原
投稿者 kh VINE メンバー 投稿日 2002/10/23
形式: 文庫
こういう本が文庫で手に入るとは嬉しいかぎりです。年中行事、遊女の生活など吉原の風俗がことこまかに描かれております。なかには心中の仕損じ、相対死、おろし(堕胎)、私刑、折檻といった悲惨なものもありますが、墨の、細い描線で描かれた絵図の美しさのため、どこか夢幻の世界の話でも聞いているような気になってしまいます。ここにあるのは江戸の文化としての吉原でありまして、歌舞伎に昇華される美の原型、現実そのものではありません。われわれにとっては、江戸文化のお勉強としての吉原でしょうか。文章のですます調は、悲惨を語っても、どこか優雅。真夏に手足をしばり、押し入れへ入れて、蚊に食わせる蚊責めなんぞもございましたそうで。へい。
いやあ、詳しいです。
実はこの分厚い文庫(656ページ)、私のメントーともいうべき人が吉原について書きたいと洩らしたら、プレゼントしてくれたのだけど、重宝している。
吉原をテーマにした小説は何冊も出ているので、私はちょっと視点を変えてと思っているが、この六年ほど山谷を常宿にしているせいで、この界隈はほぼ周り尽くし、吉原も無論三度も周遊済み、地図が載っていても少なからぬ土地勘があるので、役立っている。
お大尽の舟が通った山谷堀跡とか、周辺の待乳山聖天とか、吉原入り口手前の通り(日本堤)の左脇にある見返り柳(遊客が帰りしな、名残惜しそうに振り返ったことからこの名がある)、全部知ってる。
それにしても、この本は面白い。
現在はソープ街と化している吉原だが、今昔吉原比べも面白い。
絵だけ見てると、おいらんの髪型や衣装の豪華さにため息が漏れそうになるが、実態は苦しいことや悲しいことが多かったんだろうな。楼主によるせっかんとかもあったみたいだし、男装して逃げる遊女もいたらしい。
心中とか相対死(違う場所で同じ時刻に共死)もあって、生き残ると、日本橋で三日さらし者になってに転落、それと避妊手段がなかった当時、下級遊女が孕むと、原始的な手段で堕胎を強要されたりと、実態は遊郭地獄絵図だ。
子持ちおいらんもいたらしいが(女児は遊女見習い、かむろになった)。
おいらん道中など華麗の極みだが、絵のように美しいうわべの下には醜悪、悲惨きわまる現実があったんだろう。
実に興味深い一冊で、お薦めです。
ちなみに、吉原細見(案内書)の版元が蔦屋とあったけど、今のツタヤって、まさかここからきてるんじゃないだろうな?