こんばんわ。
昨日は沢山のポチをいただきありがとうございました。
このところ貨車ネタがちょっとしたブームになっているようなので、今日もちょこっと語っちゃいます。
皆さんは、貨車のブレーキについてどのくらいご存知ですかね?電車や気動車、客車については雑誌などでも取り上げられますので、どのようにしてブレーキが動作するか位はご存知かと思います。
貨車についても走り装置の区分で言うブレーキは基本的に同一ですが、手ブレーキとなると、せめて旧型客車を知っている世代の方でないと、ピンと来ないかもしれませんね。
貨車は電車や客車などと違い、突放入換やハンプ入換などの動作を伴いますし、どの貨車も単独で留置する可能性がありますので、各車両に手ブレーキが付いています。
貨車のブレーキの役割は大きくは3つに分けられると思います。
1つは、列車として走行の際、機関車からの指令で減速或いは停止の際の緊締による転動防止。
2つ目は、入換時における減速又は停止の手段。
3つ目は、留置の際の転動防止。
ちなみに、電車・気動車は運転席のある車両、客車は「フ」や「ニ」の付く車掌室が付いた車両に手ブレーキを備えています。ただし、貨車とは違い、入換時に減速装置として想定しているわけではありません。
また、手ブレーキの基本構造としては、3つの形態に大別されます。
1つ目は、ハンドブレーキ。貨車の台枠上に添乗するスペースを有し、丸いハンドルをクルクルと回すことによりチェーンを巻き取り、機械的に車輪を締め付ける方式。
2つ目は、側ブレーキと呼ばれる、ブレーキてこに体重を掛けることにより、機械的に車輪を締め付ける方式。
3つ目は、床下設置のハンドブレーキ。構造は1つ目のハンドブレーキと同一ですが、手ブレーキの取り付けスペースなどの構造上の都合で床下に付いているハンドルを水平方向に回して機械的に車輪を締め付ける方式。このタイプは、床下のブレーキハンドルをしゃがんで回すことになり、もちろん添乗装備をしていないため、突放禁止(もちろんハンプ通過も)となっています。※ただし、添乗可能な貨車と同一行動で入換を行う場合は、添乗可能な貨車でブレーキを操縦することができるので、ハンプ通過や突放入換も可能となっています。
前置きが長くなってしまいましたが、今日は2つ目の「側ブレーキ」について写真をご覧いただきながら語ってみます。

ワム80000で例示いたしますが、斜めに上に向かっている棒がブレーキてこになります。上端に置くに押し込んで引っ掛かる部分があり、これを「受け」と言います。走行中に不用意に下に落ちないようになっているわけですね。これは、ブレーキがかかっていない状態を示しています。

こちらは、逆に下に落ちてブレーキが掛かっている状態を示します。
受けに収まっている状態から少し上に上げ、手前に引き出すと、白いガイドに沿って下に落ちます。見にくいですが、ガイドにはギザギザが付いており、これに引っ掛かるツメを添乗側にひっくり返すとツメが咬むようになり、てこに体重を掛けることによって下方に固定され、てこの作用でブレーキが掛かるわけです。
ちなみに、ブレーキを外す時は、ツメに付いたおもりを反対側にくるっと回し、体重を掛けるとツメが外れ、てこが開放されます。
入換の際は、このような動作を1回1回繰り返しながら行われるわけですね。

こちらは参考までにチキ6000の例示です。左側面の手前から少し入ったところに添乗ステップと取っ手があります。上部に構体が無いため、取っ手が貨車の床部分から上に立ち上がっています。これは、荷役を行う時に取っ手を破損してしまう恐れがあるため、ピンを抜くと床面と同じ高さに収納できるようになっています。
ワムやトラのように側板に取っ手が付いていると、ぶら下がり乗りができるので楽なのですが、このタイプは股下くらいの高さの取っ手に掴まって添乗することになるため、後傾姿勢となって非常にバランスも悪くなり、長時間の添乗はキツくなります。
お気付きかもしれませんが、ブレーキ装置に掛かる部分は取っ手やステップなどが白く塗装されています。これは、黒色が中心の貨車の中でブレーキの位置を視認しやすくするための措置です。入換手から見れば、常に命がけの作業となりますので、この部分は非常に大きなポイントになるわけです。
ちなみに、冷蔵車のように車体が白の貨車についてのみ、ブレーキの取っ手を黒く塗っています。白に白では判らなくなりますからね。
言葉で説明するのは非常に難しいですね。
現在はハンプ・突放入換がなくなってしまいましたので、貨車を減速させる目的で手ブレーキを扱うことはなくなってしまったと思います。したがって、留置の際の転動防止の手段ということになってしまいましたね。
もし、貨車を自由にいじらせてくれるところがありましたら、ブレーキの動作を実演したビデオでもアップしたいところですね(笑)。
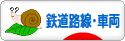
にほんブログ村
昨日は沢山のポチをいただきありがとうございました。
このところ貨車ネタがちょっとしたブームになっているようなので、今日もちょこっと語っちゃいます。
皆さんは、貨車のブレーキについてどのくらいご存知ですかね?電車や気動車、客車については雑誌などでも取り上げられますので、どのようにしてブレーキが動作するか位はご存知かと思います。
貨車についても走り装置の区分で言うブレーキは基本的に同一ですが、手ブレーキとなると、せめて旧型客車を知っている世代の方でないと、ピンと来ないかもしれませんね。
貨車は電車や客車などと違い、突放入換やハンプ入換などの動作を伴いますし、どの貨車も単独で留置する可能性がありますので、各車両に手ブレーキが付いています。
貨車のブレーキの役割は大きくは3つに分けられると思います。
1つは、列車として走行の際、機関車からの指令で減速或いは停止の際の緊締による転動防止。
2つ目は、入換時における減速又は停止の手段。
3つ目は、留置の際の転動防止。
ちなみに、電車・気動車は運転席のある車両、客車は「フ」や「ニ」の付く車掌室が付いた車両に手ブレーキを備えています。ただし、貨車とは違い、入換時に減速装置として想定しているわけではありません。
また、手ブレーキの基本構造としては、3つの形態に大別されます。
1つ目は、ハンドブレーキ。貨車の台枠上に添乗するスペースを有し、丸いハンドルをクルクルと回すことによりチェーンを巻き取り、機械的に車輪を締め付ける方式。
2つ目は、側ブレーキと呼ばれる、ブレーキてこに体重を掛けることにより、機械的に車輪を締め付ける方式。
3つ目は、床下設置のハンドブレーキ。構造は1つ目のハンドブレーキと同一ですが、手ブレーキの取り付けスペースなどの構造上の都合で床下に付いているハンドルを水平方向に回して機械的に車輪を締め付ける方式。このタイプは、床下のブレーキハンドルをしゃがんで回すことになり、もちろん添乗装備をしていないため、突放禁止(もちろんハンプ通過も)となっています。※ただし、添乗可能な貨車と同一行動で入換を行う場合は、添乗可能な貨車でブレーキを操縦することができるので、ハンプ通過や突放入換も可能となっています。
前置きが長くなってしまいましたが、今日は2つ目の「側ブレーキ」について写真をご覧いただきながら語ってみます。

ワム80000で例示いたしますが、斜めに上に向かっている棒がブレーキてこになります。上端に置くに押し込んで引っ掛かる部分があり、これを「受け」と言います。走行中に不用意に下に落ちないようになっているわけですね。これは、ブレーキがかかっていない状態を示しています。

こちらは、逆に下に落ちてブレーキが掛かっている状態を示します。
受けに収まっている状態から少し上に上げ、手前に引き出すと、白いガイドに沿って下に落ちます。見にくいですが、ガイドにはギザギザが付いており、これに引っ掛かるツメを添乗側にひっくり返すとツメが咬むようになり、てこに体重を掛けることによって下方に固定され、てこの作用でブレーキが掛かるわけです。
ちなみに、ブレーキを外す時は、ツメに付いたおもりを反対側にくるっと回し、体重を掛けるとツメが外れ、てこが開放されます。
入換の際は、このような動作を1回1回繰り返しながら行われるわけですね。

こちらは参考までにチキ6000の例示です。左側面の手前から少し入ったところに添乗ステップと取っ手があります。上部に構体が無いため、取っ手が貨車の床部分から上に立ち上がっています。これは、荷役を行う時に取っ手を破損してしまう恐れがあるため、ピンを抜くと床面と同じ高さに収納できるようになっています。
ワムやトラのように側板に取っ手が付いていると、ぶら下がり乗りができるので楽なのですが、このタイプは股下くらいの高さの取っ手に掴まって添乗することになるため、後傾姿勢となって非常にバランスも悪くなり、長時間の添乗はキツくなります。
お気付きかもしれませんが、ブレーキ装置に掛かる部分は取っ手やステップなどが白く塗装されています。これは、黒色が中心の貨車の中でブレーキの位置を視認しやすくするための措置です。入換手から見れば、常に命がけの作業となりますので、この部分は非常に大きなポイントになるわけです。
ちなみに、冷蔵車のように車体が白の貨車についてのみ、ブレーキの取っ手を黒く塗っています。白に白では判らなくなりますからね。
言葉で説明するのは非常に難しいですね。
現在はハンプ・突放入換がなくなってしまいましたので、貨車を減速させる目的で手ブレーキを扱うことはなくなってしまったと思います。したがって、留置の際の転動防止の手段ということになってしまいましたね。
もし、貨車を自由にいじらせてくれるところがありましたら、ブレーキの動作を実演したビデオでもアップしたいところですね(笑)。
にほんブログ村
















チキの連結面(端梁)両端にある白い2本線は、突放されて流れてくる貨車を連結面から見て「こっちの側面に側ブレーキがついているよ」という目印だと聞いたことがあります。
昔は片側にしか側ブレーキがない貨車があったそうですので、ブレーキのない側に待機してしまったら大変なことになります。
>ブレーキの動作を実演したビデオ
私の近所(山梨県)では、韮崎運動公園にEF15とともにトラが3両展示されて自由にさわれるようになっています。
ここなら可能かもしれませんね。
やはり雨の日や雪の日は大変だったと聞いてました。
私も足踏みブレーキって、やってみたかったでした。
ブレーキ掛けながらギャグを言ってると、貨車が滑ってブレーキがかからないなんて事に(笑)
初コメありがとうございます!
貨物ネタは大概の方がついて来れますが、貨車ネタとなると相当マニアックな世界ですし、触れることが出来ない分野ですから、反応が気になってしまうんですよね。そういった意味で、このようなネタに反応していただける方がいらっしゃって、非常にうれしいです。
ブレーキ位置のマークですが、仰るとおりでございます。段取りの悪い突放入換より、むしろ予断を許さないハンプ入換のためにあるのではないかと考えます。
いわゆる黒屋根貨車(無蓋車も含む)は片側しか付いてませんので、これがあることで重要な目印となります。ちなみに、ハンドブレーキタイプのコンテナやタンク者などには、このマークは付いていません。
韮崎ですか?ちょっと遠いですね・・・。展示品は使って良いのかビミョーなんですよね。それと、錆付いていると機能しない場合もあります。やはり、昔を思い出して現役のワム8で試してみたいですね。
またいつでもお越しください。
雪の日はつま先が冷たくてキツかったですね。それと、雨というより夕立が大変でした。屋根に当たった雨がしぶきになるので、後方で添乗していると前が全く見えないんですよね。何時ぶつかってしまうかドキドキしながら乗ってましたよ。
ブレーキが滑るより、足を滑らせて転落してしまうのではないかそちらの方が心配です。
私なんぞ所詮耳学問と言いますか、本に書いてあることを鵜呑みにしているだけと言いますか、経験に基づくお話は大変貴重です。
わかりやすい解説ありがとうございます。
内情を知らない方からすれば難しい話かもしれませんが、経験上の話なので、自分的には何ら難しい内容ではありませんので、気になさらなくて結構です。
ただ、言葉だらけの記事はブログとして非常に見づらいでしょうし、読む方が苦痛を感じてしまうだろうということ、されど、どのように記述すれば内容が読者に伝わるかということ、この辺りの表現方法の方が格段に難しいですね(笑)。
なんとなくハンプを検索していたら
ここのサイトにぶつかりました
私は昭和52年から9年間国鉄に居まして
そのうち5年間東海道線の一般駅にて構内指導掛をやっていました
なので懐かしく拝見いたしましたが
通常レール運搬用チキは2両でペアにしていましたね
古いチキは片側ブレーキなので2両で対角線に側ブレーキが来るようにしていたようです
真ん中の解放てこは誤動作しないように針金で固定していました
あとワム8以前のワムはステップがクレーチングではなく板張りになっているので雪が積もったり霜ですべる事が多かったですね
とっぽう車両に飛びつくときは
腕が変な格好になるので振られたりひざを手摺でぶつけたり嫌なものです
あと雨が上がった後のシートを被ったトラやトキ
引き上げたり突放時に添乗していると滝のように水を被る事がありました
10両くらいの積載貨車を一人でブレーキ掛けて留置車両にやんわり当てるのは結構難しいですよね
1両だけでは止まらないし・・・
コキ50000の手ブレーキの効きの悪さは何とか改良してほしかったです
これはこれは、私の先輩に当たる方ですね。ようこそいらっしゃいました。ブログをやっていてかなりのメンバーが集結していると思いますが、構内入換経験者の方というのはまず珍しいですね。
私は大宮操のハンプしか経験が無いので、レールを積んだチキはあまりお目に掛からなかったように思います。そんなセオリーがあったのですね。チキ×2のものといわゆるチッチキチの3連がありましたね。ハンプでは1両のみの空車や、珍しいところではタンク(戦車)を載せたヤツがハンプを落ちてきて驚いたことがありました。夜でしたし、カメラを常備していたわけでもないので、残念ながら記録には残っていません。
さすがに経験者の方なので、リアルにご存知ですね。チキはステップが奥まっていて、さらい棒を差し込む枠が飛び出しているので、私も何度かヒザをぶつけたことがあります。あれがまた痛いんですよね。久し振りに思い出しました。
ちょうど私がハンプにいた最後の年、大雪にやられまして、ヒドい目に遭いました。雨の日に逆乗りしてステップで足を滑らせ、後ろ向きに引きずられたこともあります。若かったし体力もあったから良かったですが、今この歳であれをやったら、命を落としていた可能性が高いです。
カテゴリの大宮操車場にハンプの様子を詰めてありますので、お時間のあるときにゆっくりご覧ください。またのコメントをお待ちしています!