こんばんわ。
ネタを段々消化してしまって、地味ネタが目立ってきました。
出来るだけ季節モノを・・・と考えると、アップするのも日々悩んでしまいます。
さて、ほんと地味ですけど、知っている人は知っている、急行「白馬」をご紹介いたします。といっても1枚だけなんですけど 。
。
急行「白馬」の歴史は古く、昭和29年にも遡るらしいです。この頃の記録は見つかりませんが、おそらくは蒸気機関車が牽く客車だったのでしょう。
その後気動車急行として新宿~糸魚川間を結んでいました。単独時代もあり、その後、急行「アルプス」や「かわぐち」とも併結されていたようです。
昭和43年10月の改正で一旦廃止となりますが、昭和46年に金沢~松本間を結ぶ気動車急行として復活(臨時?)。途中、信濃森上止まりなどの変遷がありながらも、昭和57年11月改正で廃止となるまで、大糸線を走る唯一の直通気動車急行として活躍していました。
ちなみに、北陸本線内の金沢~糸魚川間は、上下とも急行「しらゆき」に併結されていました。

昭和56年7月22日 大糸線内にて キハ58系 急行「白馬」
撮影地は記録に残っていないのですが、大糸線最後の旧型国電を撮影に行った際に撮ったものです。なのでもちろん電化区間です。
キハ58+キハ28+キハ58の3両編成で、全部の車輌が冷房車の豪華版。中間にキハ28を介することにより、3両分の冷房電源の供給を可能とした合理的な編成です。
大糸線内は3両編成ですが、需要を考えれば適当なセンでしょう。北陸本線内は「しらゆき」と併結されるため、12両の堂々たる編成となります。
ヘッドマークも無く、サボも撮っていなく、なんらインパクトのないキハ58系の写真ですが、大糸線内であるからこそ、急行「白馬」を主張できる1枚です。
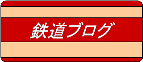
にほんブログ村 ↑ちょっと塗分けが違うけど・・・。
ネタを段々消化してしまって、地味ネタが目立ってきました。
出来るだけ季節モノを・・・と考えると、アップするのも日々悩んでしまいます。
さて、ほんと地味ですけど、知っている人は知っている、急行「白馬」をご紹介いたします。といっても1枚だけなんですけど
急行「白馬」の歴史は古く、昭和29年にも遡るらしいです。この頃の記録は見つかりませんが、おそらくは蒸気機関車が牽く客車だったのでしょう。
その後気動車急行として新宿~糸魚川間を結んでいました。単独時代もあり、その後、急行「アルプス」や「かわぐち」とも併結されていたようです。
昭和43年10月の改正で一旦廃止となりますが、昭和46年に金沢~松本間を結ぶ気動車急行として復活(臨時?)。途中、信濃森上止まりなどの変遷がありながらも、昭和57年11月改正で廃止となるまで、大糸線を走る唯一の直通気動車急行として活躍していました。
ちなみに、北陸本線内の金沢~糸魚川間は、上下とも急行「しらゆき」に併結されていました。

昭和56年7月22日 大糸線内にて キハ58系 急行「白馬」
撮影地は記録に残っていないのですが、大糸線最後の旧型国電を撮影に行った際に撮ったものです。なのでもちろん電化区間です。
キハ58+キハ28+キハ58の3両編成で、全部の車輌が冷房車の豪華版。中間にキハ28を介することにより、3両分の冷房電源の供給を可能とした合理的な編成です。
大糸線内は3両編成ですが、需要を考えれば適当なセンでしょう。北陸本線内は「しらゆき」と併結されるため、12両の堂々たる編成となります。
ヘッドマークも無く、サボも撮っていなく、なんらインパクトのないキハ58系の写真ですが、大糸線内であるからこそ、急行「白馬」を主張できる1枚です。
にほんブログ村 ↑ちょっと塗分けが違うけど・・・。
















大糸線というと今では南小谷というトコ=昔、私は仲間らと大阪より「シュプール」に乗ってこの駅で下車し、そこから栂池温泉まで松本電鉄のオンボロモノコックバスで行った記憶があります=で電化区間の東日本線と非電化区間の西日本線に分かれるので知られてます。
また、高校のときにも合宿で松本より穂高までその年の秋[注:昭和61.11の国鉄最期のダイヤ改正]に昼間の定期急行としては廃止となる「アルプス」に乗って行った記憶があります(ウル覚えですが、たしかモハ164-848号=この後に確か松本から日根野に飛ばされ、西日本の車として紀勢西線ローカルに使われてそこで生を終えた=に乗ってました)。
因みに私はキハ58系の写真撮ってないか探したところ、たまたま神戸の三宮の駅前を撮った写真にさりげなくこのDCが写ってたのがあって、何気なく撮ってたのに偶然にもこのようなカタチで出くわした事には、ホント嬉しい限りです。
それでは、この辺にて失礼いたします。
色の組み合わせだけで気分出るじゃないですか♪
思わずポチしますよ。
カネが無いんであずさは乗りませんでした。
しらゆきは全車冷房じゃ無いのに白馬は3両ながら冷房付きでしたね。
需要は金沢-松本であったんでしょうかね?
しらゆきの方はというと秋田で何両か切り離して仙台からのきたかみ5連を連結して青森へ行くんでしたね。
当時、北陸から避暑に行く列車として人気の高い感じでしたよ。
まだ、立山黒部アルペンルートも高額だったので、それなりの需要も有ったのでしょうね。
関西からだと、やはりスキーと言えば白馬・栂池あたりが手頃な場所なんでしょうね。それでも、関東から見た上越とは比べ物にならないくらい遠いですね。
この時代だと、大糸線の電化区間を走るディーゼルは他に無く、地味ながらも存在感はあったのかもしれません。私的には異形式が連結されていた方が良いんですけどネ。
本当は色々作りたいんですけどね。写真扱いなんで、登録と、その都度データを照合して拾うのがちと面倒なんですよ。
ありがとうございます。
詳しくは知りませんが、「しらゆき」編成と「白馬」編成は、所属が違っていたのでしょうね。東北では非冷房でも構わないコンセプトで、急行運用と言えども殆どが非冷房でした。一方、多少の時代差はありますが、東海は西日本では、普通列車と言えども殆どが冷房化されていたみたいですしね。格差と言うよりは、たまたま地域差が出てしまうコンビだったのでしょう。
私も飯田線へ撮影に行っている頃は、良く夜行の「アルプス」に乗りましたよ。最後のときは189系グレードアップ車になってましたね。
今のように道路が発達していないですから、昔はどの地方区間でも需要があったのでしょうね。ローカル急行網が発達していたのも、その辺りの理由で十分稼げたんでしょうね。
しかし、フル区間乗車なんて、なかなかレアな行動をしてますね。確かに、昔の写真を見ると、キハ55系が謳歌していたみたいですね。
南小谷を越えて走る列車は、往時でも数少なかったのですね。金沢とを結んでもどの程度の乗客が乗るものなのか想像もつきませんが、通しで乗るよりも地域内や区間ごとに乗客が入れ替わるような列車だったのかもしれません。
国鉄時代の多層建て列車のお話を聞きますと、本当に複雑なダイヤをどのようにして作っていたのか、不思議にも感じます。長距離を走る列車は今では少なくなってしまいましたが、遠くの行き先を目指す列車には夢があったのだと思いますし、そこに分割・併合が繰り返されていくとなれば、趣味的にも興味を惹かれます。
風旅記: https://kazetabiki.blog.fc2.com
昭和54年の時刻表を見ると、南小谷の境界を越える普通列車は2往復ありましたが、区間はいずれも信濃大町~糸魚川間であり、全線を踏破するのは急行「白馬」だけでした。
昔の急行列車は今では想像が付かないような奇怪な区間を走行するものが多くあり、記憶に残るところでは「大社」「火の国」「フェニックス」など、前線を乗りとおす旅客は到底いないだろうと思われる列車があります。
いずれも始終点を基準としての需要を拾っていたのでしょうけど、旅好きにはたまらない設定であったことも間違いないと思います。