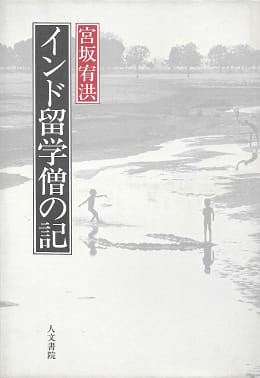先日買った本を読み終えた.宮坂宥洪・著『インド留学僧の記』.
プーナ市へ留学した著者が,サンスクリット研究と,日々の暮らしを通して体験した,インド社会の風俗や身分制度,宗教,教育にまつわる現況を,つぶさに紹介するエッセイ集.そこでは,インドの人々が,急速な近代化の波に圧されつつもなお,質素でかつ,独特の秩序に徹底した,伝統的な生活スタイルを保っていることが語られる.その整然ながらもリアルな文体から,現地の活気と大らかな情景が手に取るように伝わってくるのは魅力.言葉の節々にどうしても,氏のインド贔屓がにじみ出ているのは,気にならないではないが.
宮坂宥洪: インド留学僧の記
人文書院,1984,
ISBN4-409-41024-5
プーナ市へ留学した著者が,サンスクリット研究と,日々の暮らしを通して体験した,インド社会の風俗や身分制度,宗教,教育にまつわる現況を,つぶさに紹介するエッセイ集.そこでは,インドの人々が,急速な近代化の波に圧されつつもなお,質素でかつ,独特の秩序に徹底した,伝統的な生活スタイルを保っていることが語られる.その整然ながらもリアルな文体から,現地の活気と大らかな情景が手に取るように伝わってくるのは魅力.言葉の節々にどうしても,氏のインド贔屓がにじみ出ているのは,気にならないではないが.
宮坂宥洪: インド留学僧の記
人文書院,1984,
ISBN4-409-41024-5