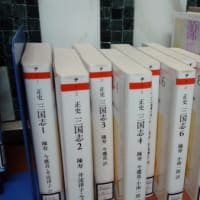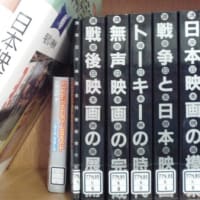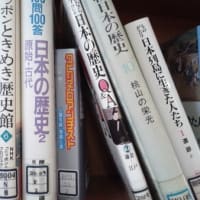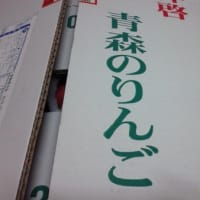何かのプロフェッショナルでは、ありません。
が、子どもに関わることについて、幅広く、は、
勉強してきたような気がします。
が、NPOとかボランティアということについても、
実践から理論を辿りなおす形で、勉強してきたような気がします。
昨年から、障害児について、とりわけ発達障害について、
チャイルドラインではあまり接点のなかった層の
子どもたちに関わるとりくみに近いところに身を置くようになりました。
頭でっかちになりたくなくて、
出会う人たちのお話、支援したり、当事者だったり、親だったり…
をいっしょうけんめい聴くところからはじめて、
半年以上の時間がたって、大丈夫本を読んでみても。
異なる価値観とか、ここは同じでここは違う。
とか、まるごと、ごろっと知識だけにのみこまれないだろう
ベースができた気がしたので、
ソフトなところから、読みはじめています。
一冊目は藤井茂樹・宇野正章『発達障害 共生への第一歩』
二冊目は茂木俊彦『障害児教育を考える』
どちらとも、読んでいて、あぁ、ちいさな「ことなり」なのだなぁ。
ちいさなことなりが、大きくくくられて別々にされようとしている
差別化、区別化、細分化、排除…の、形が
あらわになったのが「発達障害」の枠組み。
そして、子どもたちは、それを個性というよりも、
やはり、障害として、苦しまなくてはならない状況にあって、
だから、親たちもがんばらなくてはならない状況にある。
諸外国で進む、ひとりひとりに手当していく教育では、
そのひとりひとりの中に、LDとか、ADHDとか、自閉症とか、含まれていて
当たり前に対処の方法が考えられていて、だからすすんでいる。
日本は、遅れていて、その数多の一人ひとり異なるニーズの子どもたちへの
対処の方法から、発達障害はこれ、○○の場合はこれ、
と、いうように諸外国の対応例をひいてくるので、
対応例がどんとおっきくうつる。
きっと、根本的に違うんだ。
大事なのは対処の方法、じゃなくて、
「ひとりひとり手当する」ことが当たり前に確立しているかどうか。
そこを変えたい。
発達障害かいなか、知的障害なのか身体障害なのか、
あるいは、貧困なのか、被災なのか、社会的養護なのか…等々
に関わらず、すべての子どもにとって、ひとりひとりに手当が行き届く
教育のあり方が、ずっとずっとず~っと、この国には必要なんだ。
そう主張する人たちが、常に一定居つづけて、
それでも、根本をしっかりと変えていくところにまで
手を尽くしきれない頑強な仕組みが日本の教育の中に根を張っている。
てごわいな。
でも、知ってる、ということが、大事。
そこに、挑みたい、という気持ちでいる、それが大事。
それにしても、茂木俊彦さんの『障害児教育を考える』良い本でした。
が、子どもに関わることについて、幅広く、は、
勉強してきたような気がします。
が、NPOとかボランティアということについても、
実践から理論を辿りなおす形で、勉強してきたような気がします。
昨年から、障害児について、とりわけ発達障害について、
チャイルドラインではあまり接点のなかった層の
子どもたちに関わるとりくみに近いところに身を置くようになりました。
頭でっかちになりたくなくて、
出会う人たちのお話、支援したり、当事者だったり、親だったり…
をいっしょうけんめい聴くところからはじめて、
半年以上の時間がたって、大丈夫本を読んでみても。
異なる価値観とか、ここは同じでここは違う。
とか、まるごと、ごろっと知識だけにのみこまれないだろう
ベースができた気がしたので、
ソフトなところから、読みはじめています。
一冊目は藤井茂樹・宇野正章『発達障害 共生への第一歩』
二冊目は茂木俊彦『障害児教育を考える』
どちらとも、読んでいて、あぁ、ちいさな「ことなり」なのだなぁ。
ちいさなことなりが、大きくくくられて別々にされようとしている
差別化、区別化、細分化、排除…の、形が
あらわになったのが「発達障害」の枠組み。
そして、子どもたちは、それを個性というよりも、
やはり、障害として、苦しまなくてはならない状況にあって、
だから、親たちもがんばらなくてはならない状況にある。
諸外国で進む、ひとりひとりに手当していく教育では、
そのひとりひとりの中に、LDとか、ADHDとか、自閉症とか、含まれていて
当たり前に対処の方法が考えられていて、だからすすんでいる。
日本は、遅れていて、その数多の一人ひとり異なるニーズの子どもたちへの
対処の方法から、発達障害はこれ、○○の場合はこれ、
と、いうように諸外国の対応例をひいてくるので、
対応例がどんとおっきくうつる。
きっと、根本的に違うんだ。
大事なのは対処の方法、じゃなくて、
「ひとりひとり手当する」ことが当たり前に確立しているかどうか。
そこを変えたい。
発達障害かいなか、知的障害なのか身体障害なのか、
あるいは、貧困なのか、被災なのか、社会的養護なのか…等々
に関わらず、すべての子どもにとって、ひとりひとりに手当が行き届く
教育のあり方が、ずっとずっとず~っと、この国には必要なんだ。
そう主張する人たちが、常に一定居つづけて、
それでも、根本をしっかりと変えていくところにまで
手を尽くしきれない頑強な仕組みが日本の教育の中に根を張っている。
てごわいな。
でも、知ってる、ということが、大事。
そこに、挑みたい、という気持ちでいる、それが大事。
それにしても、茂木俊彦さんの『障害児教育を考える』良い本でした。