10月5日と12日の両日桐友会活動実施したが、5日はペンタのエイト同居に伴うナックル艇格納の条件整備、12日はよりレベルアップ目指す漕艇実練を実施しました。これは後程コメントするとして、初めに、今戸田コースで珍しい風景が見られるので、それを記す。戸田コースに新鋭水陸両用戦車登場つうと、かっての独ソ東部戦線に新鋭T-36初登場した時みてえなサプライズだが、先に画像で紹介するが、戦車でなく水藻刈取特殊収集車輛で、世界に2台しかないつう代物です。

特殊車輛を投入せざる得ないほど水藻の繁茂が深刻で、とりわけ行きの1コース、帰りの6コース近辺は、オールが水藻に絡み取られるような状況で、練習に支障が出ている。ビッグイベントの大会も近く、何とか特殊車輛投入の成果でることを期待している。
5日の桐友会活動は、艇移動キャリア2台をナックル艇の下部にあてがい、そのままスライドさせて引き出すという新構想と、そのための機材整備に終始したが、成功の見通しが立った。12日の漕艇実練のクルー配置は、C兼コーチ内野、S橋爪、3大木、2富安、B藤波であったが、当日実練は、内野コーチのプリンシプルが色濃く出た。部分漕ぎあるいは特殊漕ぎは、キャッチ漕ぎ・フイニッシュ漕ぎ・ミドル漕ぎ・腕漕ぎ・脚漕ぎ・片手漕ぎ・ノーフエザー漕ぎ・から漕ぎ・1本漕ぎ等多々あるが、本日は内野コーチは1本漕ぎに重点おいた。1本漕ぎは、ローピッチ漕ぎとも言われるが、1本1本間隔をあけて漕ぐ練習法である。1本漕いだらハンザウエー、リカバリーして、ハンドルが膝上まで来たところで動作止め、艇進行が停止するまで体を静止させる。この時、脚は軽く力抜く程度でよい。ほぼ艇が停止状態になったら、次のone stroke を漕ぐ練習法である。本方法では、体の各部の動作の緊張と脱力、フオワードやブレードの状態などが実感できる練習法であるが、何より、艇のバランス感覚をクルー各自が自覚できる、最良の練習法である。内野コーチは、バランス感覚を深く把握しているとか、漕艇のスキルやパワーは、つまるところバランス感覚に現れるという理論の持ち主である。この辺は、以前紹介したSteve Fairbairn も同じ考えで、”Rowing Notes"に於いて次のように述べている。
”The hands hold the oar balanced on the feather as long as possible. The longer the oar is held balanced on the feather, the better. The blade shoujd be turned square just before the end of the forward swing.・・・”( Rowing Notes、 1926、P14)
たかがバランス、されどバランスちゅう感じで、これはナックル艇から更にシェル艇にシフトした時に、よりポイントとなる。12日の実練は、実練のグレードアップに繋がる課題画)出された日となった。













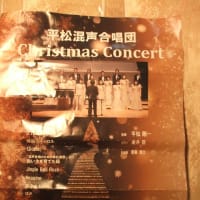










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます