前々号で、泉福寺の大鐘は一旦戦争に供出されたと記したが、具体的には近くに存在した、
当時軍需工場であったK・K三菱金属桶川製作所に、金属素材として提供されたのである。当社は現在は三菱マテリアル桶川製作所と改名してるが、桐漕会々長の寺下氏はかって同社の社員であり、この桶川製作所へも相当出入りしていたとか、同社桶川製作所の内実には詳しい。 戦時下に軍需工場としての三菱金属桶川製作所が生産していたのは、ゼロ戦の引き込み脚であり、当時数千の社員・工員が従事していた。ゼロ戦の二大生産メーカーといえば、三菱重工業と中島飛行機であったが、その中島飛行機K・Kが航空機増産のための工場用地として眼を付けたのが当桶川であり、三菱金属の南側に隣接する広大な土地を、工場予定地として確保し
ていた。新工場建設の直前に敗戦となり、工場予定地はそのまま放置され松林となっていたが、その松林が切り売りされた際に購入して造成したのが、現在の小生の宅地である。造成前の松林風景を画像で示す。

桶川の軍需工場は、三菱金属も重要だが、むしろより特記すべきは三井精機である。我が国の精密測定器工業(precision)・精密機械工業の歴史は、三井精機の歴史と言われるくらい
当三井精機が該業界で果たしてきた役割は大きい。三井精機は、1928年(昭和3)に東京の蒲田区雑色町195に、津上退助が資本金15万円で設立した、測定器具製作会社の津上製作所がルーツである。当社は製品需要増につれ暫時業容も拡大し、資本金増等会社も成長したが、1936年(昭11)に創業者津上退助が退社することになり(津上氏は同時に新潟・長岡に別個に津上製作所を設立、現在の東証一部(株)ツガミ)、これに伴い改名する必要が起き、東洋精機(株)となった。日中戦争の開始の頃より、当社の精密機器製作技術は軍部の注目するところとなり、とりわけ海軍との関係が深まった。具体的には、海軍艦艇の魚雷発射装置の特殊部品の製作であり、何百気圧もの高圧酸素を扱う特殊技術を駆使した。当社は、又この頃三井財閥の融資を仰ぎ、三井の傘下に入った。1941年(昭16)の大平洋戦争開戦直前の10月に、更に業務を拡大すべく、国鉄(現JR)高崎線桶川駅の西口に隣接する15万坪の工場用地を入手し、東洋精機(株)桶川製作所建設に着手した。同時に、同じ三井資本系統の三井工作機(株)と合併することになり、この際新社名をと、三井精機工業(株)と変更した。これが現在の社名である。三井精機は、魚雷関連等兵器部門は主として東京・本社方面で製作し、桶川製作所では精密機器製作関連の技術を生かし、航空機等兵器製作に必要な工作機械関連部品を製作した。これら製品の納入先は、主に中島飛行機であったから、当桶川製作所も立派な軍需工場であった。
敗戦と同時に、三井精機も平和産業への切り替えを迫られたが、元来が精密測定機器製作で起業した会社であり、平和的産業の技術蓄積もあり、それらを生かして新たなスタート切った。とはいえ、山あり谷あり紆余曲折経て、オート三輪(オリエント号)生産で社員給与を稼いだりした。その後、魚雷関連高圧空気取扱い技術を活かして産業用高圧コンプレッサー生産に活路を見出し、又本業の精密機器生産企業として軌道にのったのは、昭和30年代後半であった。更に業容拡大目指し1981年(昭56)には、桶川工場を桶川から荒川越えて20キロ西方の、越辺川に隣接する埼玉県比企郡川島町に移転し、三井精機川島工場と改称 し、現在二至っている。現当社の所在地は、自然的な山林原野が良好に保存されてる静謐な環境保護地区であり、精密機器生産には最適な地である。隣接する越辺川には、例年コハクチョウが飛来するが、今年も多数が遊弋していた。現在の当社正門前とコハクチョウの2葉の画像をアップするが、小生も経営史学会の会員として三菱金属や三井精機には関心持ち、深く検討する計画もあるので、チャンスあったら又報告したい。















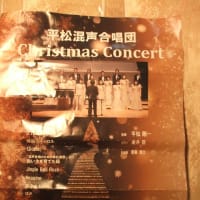










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます