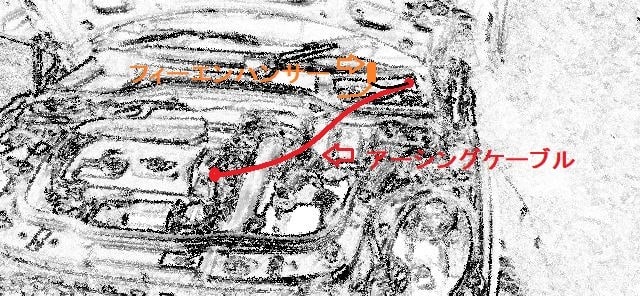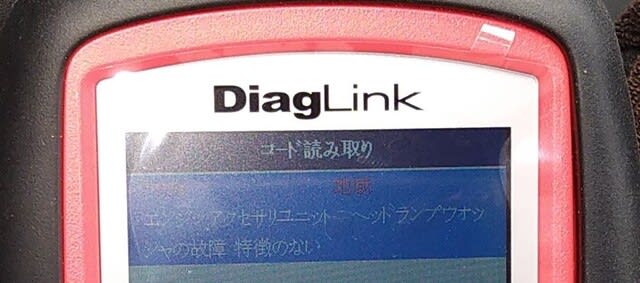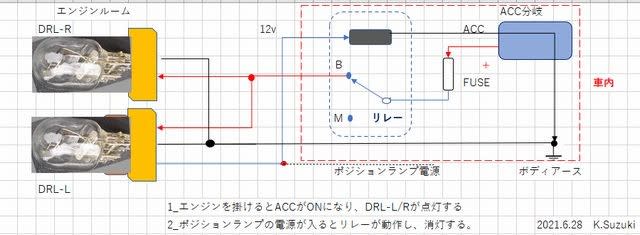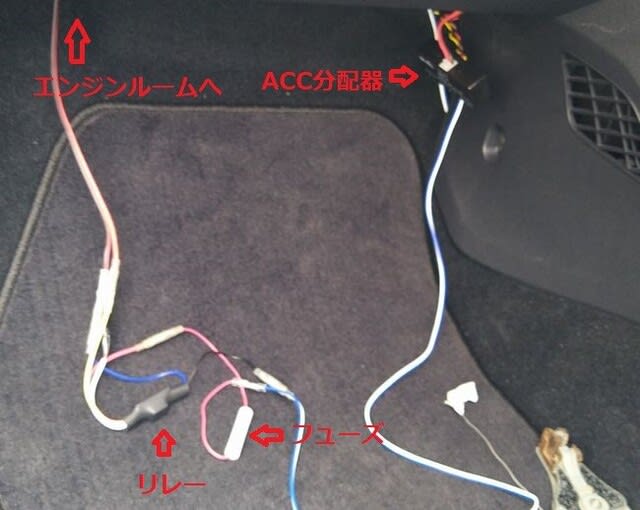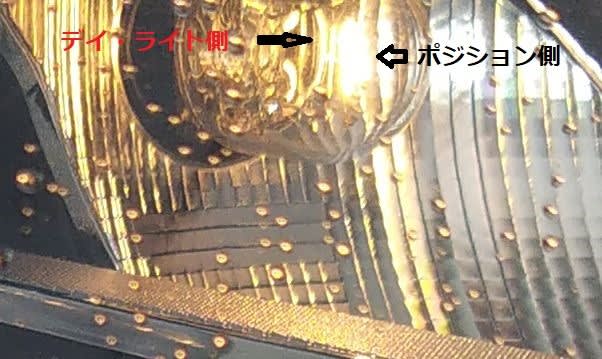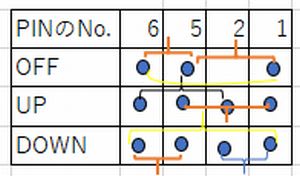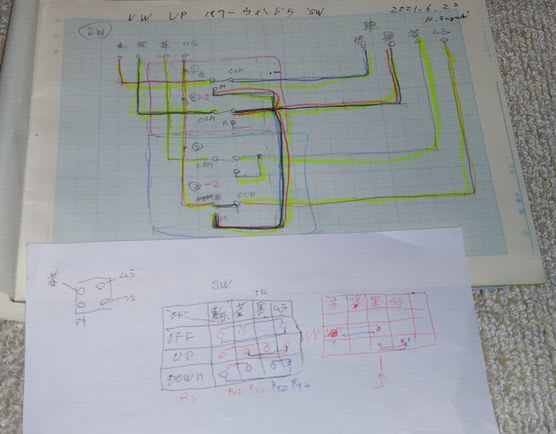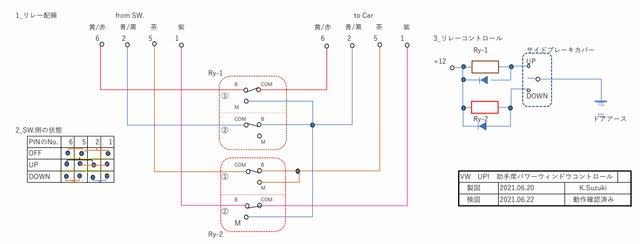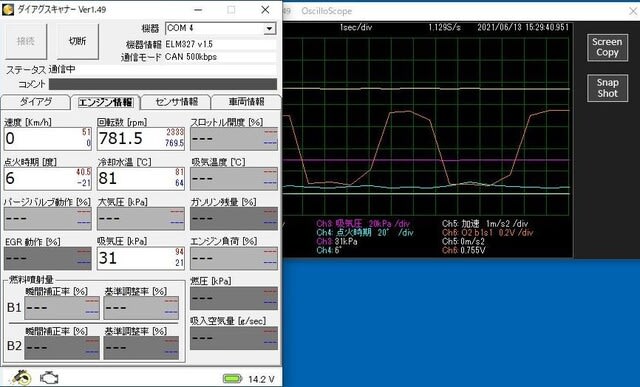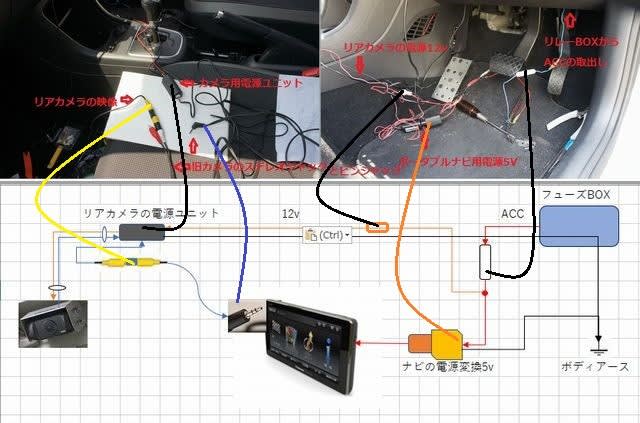中古のUP!を4/25から乗り始めて、約1,000km程走りました。
なかなか良い車です。
でも、2DINのカーナビが付けられない・・・。
FIAT500に付いていた2019年の地図が載ったCarrozzeriaが
倉庫で眠っています。
今朝までの状態は、カーステレオと地図の更新がデキないポータブルナビ。
※カーステレオは、4/26にAliExpressから買った1DINのパネル(3,753 円)を
買った頃は、これで十分かと思っていましたが、やっぱり2DINの
カーナビを付けようとweb.を調べたら、UP!POP!KIT!が売切れていました。
元来、UP!POP!KIT!は、安くなったとは言っても、4万円以上掛かるから
1DINのを改造すればできる。
(FIAT500も かなり難しい事をやって可能にしたから→
ココ)
実は、1DINのパネルを買った時から、少しづつ考えていた。
2週間前にほぼ考えがまとまったのですが、イロイロと忙しく
なったので、放っておいた。
上の写真のように赤枠のところが2DIN(100mm)高さ。
緑枠のがエアコンユニットの現在の位置
黄枠にエアコンユニットを移動して2DINのサイズを確保する。
でもコレをやるためには、センターパネルを正確にカットしないと
できません。
分解してエアコンユニットから寸法を出し、マジックで位置出し
なんとかカット(微妙に小さめにして、後はヤスリ掛け)
※ゴミが入らないように、養生しておく。
ヤスリでエヤコンユニットの幅ピッタリにする。
カーナビをセットする前に、メーターユニットをバラして
車速パルスの線を出します。
※偶然でしたが、ODDメーターが7,777kmでした。(コレはラッキー♪)
事前に分解して、コネクターを確認して、Web.上を探したのですが
なかなか無くて、同じぐらいPOLO(6R)のコネクターと共通部品らしい
という事が解ってきた。
メーターを分解し、水色の32pinコネクタのピンク色のストッパーを
外すと、32pin白色の内部コネクタが出てくる。
そこの9pin(茶色の線)にエレクトロタップを使い分岐する。
これで、2万円もするCAN-BUSも買わなくても済む。
後から車速パルスの確認したら、動いていた。
各部の配線をして、ナビを押し込む。
ほぼ想定内にできました。
左の空きスイッチ部分にUSB端子も付けました。(音楽用)
スマートフォンは、Bluetoothで繋ぎ(音楽と電話用)
今回、TVとリアカメラの配線はしていません。
(TVは見ないから・・・。でも、配線しますよ。時間が掛かる)
(リアカメラもバックソナーが付いているから・・・。
これも、配線しますよ・・・。)
リモコンも、学習させて使用可能です。
(マウスを反転して、コラムリモコン)
今日の仕事で
①UP!POP!KIT!;44,220
②CAN-BUSユニット;約2万円
6万円以上の節約です。
自分で出来るって、幸せな事です♪。