ラックスマンのLPレコードプレイヤー
重い! 兎に角重い!!
移動は諦めて、設置場所で撮りました。

LUXMAN PD-350 全景 (アクリルカバーを閉じた状態)
シッカリしたカバー(蓋)です。ラックスのレゴが入っています。
往年のラックスファンは「LUXMAN」ではなく、「LUX」の呼称に馴染みがあります。

PD-350 全景 (アクリルカバーを上げた状態)
◎PD-350の特徴
①LPレコード吸着式
LPレコードとターンテーブルの間の空気を抜き、LPレコードがターンテーブル(重量は9.5kg)が一体化する。
吸着時にLPレコードの反りが修正され、回転時の波打ち現象が軽減されるので、カートリッジのトレース時の上下動は減ります。
これはトーンアーム、カートリッジの負担を減らし、その能力を活かすことができます。
*LPレコードを重量級のスタビライザー(重石)を乗せ、押さえつけても、LPレコードの端はフリーです。歪み矯正効果はあまり期待できません。
LPレコード吸着の利点に着目したのはマイクロとラックスでした。
マイクロ方式は吸引ポンプを常時駆動方式。ポンプの稼働音が気になりました。
ラックス方式は吸着力が弱まると再稼働する方式。普段は音はせず、稼働時の音も静かでした。
②ターンテーブルの構造
アルミと黄銅鉱(真鍮)のハイブリッド
金属は固有の共鳴音があります。爪で弾くと分かります。一度鳴ると、鳴り止むまでに時間が掛かる。
その共鳴音をカートッリジが拾う可能性がある。
一般的な対処方法は、ターンテーブルの上に厚手のゴムシートを載せる方法
ガラス、銅、マグネシューム等を使った製品がありました。
ラックスは異種金属を組み合わせて、この響きを軽減しているのです。
③ターンテーブル駆動方式
ベルトドライブ
ダイレクトドライブ方式と比較し、モーター軸への負担が少ない。重量級のターンテーブルが使える。
ターンテーブルの下に磁気発生源がないので、カートリッジへの影響が少ない。
駆動ベルト:純正品は伸びの小さいアラミド繊維製ベルト 今は、汎用品のゴムベルトを使っています。
④別電源(エアー吸着回路内蔵)
交流電源は本体から離して、装置のS/N比を改善している。
またエア吸着回路が別なので、稼働時の振動も回避される。
④トーンアーム
アームレス仕様。好みのアームを選んで付ける。
各社特有の取り付けアームに合わせた仕様のトーンアームベースは別売。
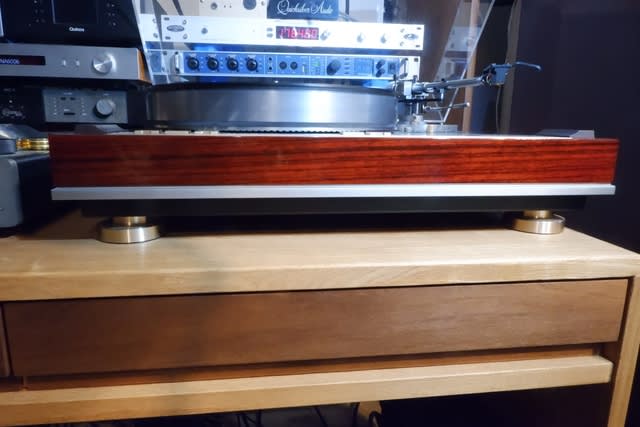
水平方向から
真鍮?製の立派な脚が付いています。

専用別電源(レコード吸着回路内蔵)
別売品です。
電源部を本体と離して置くことができるので、S /N比の向上に役立っていると思われます。
レコード吸着装置が組み込まれています。吸着力が落ちると、自動的に動作する。
吸着力を維持している時は動作音はしません。吸引時も存在を忘れるほどです静かでした。
経年劣化のため、吸着システムは故障してしまいました。普通のウエイトで押さえていました。

本体背面の様子
別電源と繋がる電源コード、吸着用のエアーホースが出ています。

右側からの画像
ピカピカに磨き上げられた天然木とヘアーライン仕上げのアルミ板のコンストラストが美しい。
・トーンアーム
SAEC WE-407 Wナイフエッジ、スタチックバランス型。
LUXMAN PD-350の概要は「オーデイの足跡」 https://audio-heritage.jp/LUXMAN/player/pd350.html をご覧ください。
・追加情報
その後、既存の吸着システムを諦め、外部に吸着ポンプを設けることにより、LPレコードは吸着できています。
*LUXMAN PD-350 吸着システム復活 2020-10-11 13:07:31 | オーディオ
◯オマケ(寄り道)
LUX(MAN)のLPレコードプレイヤーの特徴は美しいデザインであることです。
LPレコードプレイヤーでは、PD-444(ダブルアーム仕様)シリーズは工業デザイン的も意欲的な製品でした。
CD時代を迎え、LPレコードプレイヤーの製造から撤退したのは1980年代半ばでした。
PD-350は当時のLUXの最終解答的製品です。
現行LPレコードプレイヤーはPD-151。
PD-171(A)シリーズは今は廃番になっています。
PD-151はPD-171(A)の価格を抑えた廉価版と思われます。
LUXMANがLPレコードプレイヤー製造を再開し、PD-171(A)を2010年代に出しました。
LPレコードプレイヤーの製造休止期間は約25年あったことになります。
PD-171(A)が出た時の感想です。
音の比較をした訳ではありませんが、PD-350には及ばない。
①機能の簡略
あれほど拘っていたLPレコードの吸着機能を省略した。メンテナンス上のことも考慮した可能性はあります。
②外観
アルミと木目の融合はなくなりました。機能中心で遊び心がなくなってしましました。無機質な製品になってしまいました。
デザイン的にはPD-444シリーズに近い印象。
製造コストの制約が大きいのだと思います。遊びに振り向ける余裕がなくなった。
この動きが波及したのか、単なる偶然か
テクニクス、アキュフエーズがLPレコードプレイヤーを出しました。
重い! 兎に角重い!!
移動は諦めて、設置場所で撮りました。

LUXMAN PD-350 全景 (アクリルカバーを閉じた状態)
シッカリしたカバー(蓋)です。ラックスのレゴが入っています。
往年のラックスファンは「LUXMAN」ではなく、「LUX」の呼称に馴染みがあります。

PD-350 全景 (アクリルカバーを上げた状態)
◎PD-350の特徴
①LPレコード吸着式
LPレコードとターンテーブルの間の空気を抜き、LPレコードがターンテーブル(重量は9.5kg)が一体化する。
吸着時にLPレコードの反りが修正され、回転時の波打ち現象が軽減されるので、カートリッジのトレース時の上下動は減ります。
これはトーンアーム、カートリッジの負担を減らし、その能力を活かすことができます。
*LPレコードを重量級のスタビライザー(重石)を乗せ、押さえつけても、LPレコードの端はフリーです。歪み矯正効果はあまり期待できません。
LPレコード吸着の利点に着目したのはマイクロとラックスでした。
マイクロ方式は吸引ポンプを常時駆動方式。ポンプの稼働音が気になりました。
ラックス方式は吸着力が弱まると再稼働する方式。普段は音はせず、稼働時の音も静かでした。
②ターンテーブルの構造
アルミと黄銅鉱(真鍮)のハイブリッド
金属は固有の共鳴音があります。爪で弾くと分かります。一度鳴ると、鳴り止むまでに時間が掛かる。
その共鳴音をカートッリジが拾う可能性がある。
一般的な対処方法は、ターンテーブルの上に厚手のゴムシートを載せる方法
ガラス、銅、マグネシューム等を使った製品がありました。
ラックスは異種金属を組み合わせて、この響きを軽減しているのです。
③ターンテーブル駆動方式
ベルトドライブ
ダイレクトドライブ方式と比較し、モーター軸への負担が少ない。重量級のターンテーブルが使える。
ターンテーブルの下に磁気発生源がないので、カートリッジへの影響が少ない。
駆動ベルト:純正品は伸びの小さいアラミド繊維製ベルト 今は、汎用品のゴムベルトを使っています。
④別電源(エアー吸着回路内蔵)
交流電源は本体から離して、装置のS/N比を改善している。
またエア吸着回路が別なので、稼働時の振動も回避される。
④トーンアーム
アームレス仕様。好みのアームを選んで付ける。
各社特有の取り付けアームに合わせた仕様のトーンアームベースは別売。
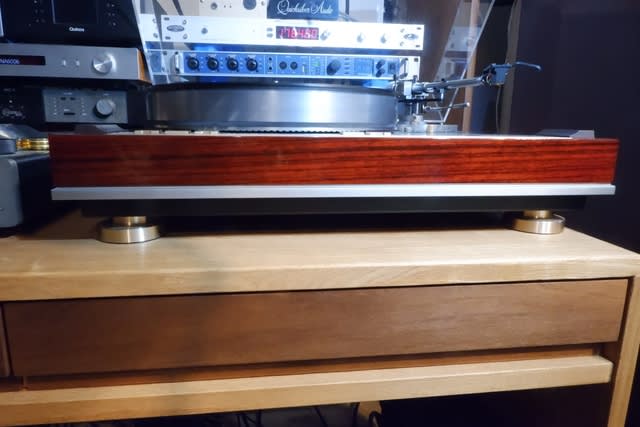
水平方向から
真鍮?製の立派な脚が付いています。

専用別電源(レコード吸着回路内蔵)
別売品です。
電源部を本体と離して置くことができるので、S /N比の向上に役立っていると思われます。
レコード吸着装置が組み込まれています。吸着力が落ちると、自動的に動作する。
吸着力を維持している時は動作音はしません。吸引時も存在を忘れるほどです静かでした。
経年劣化のため、吸着システムは故障してしまいました。普通のウエイトで押さえていました。

本体背面の様子
別電源と繋がる電源コード、吸着用のエアーホースが出ています。

右側からの画像
ピカピカに磨き上げられた天然木とヘアーライン仕上げのアルミ板のコンストラストが美しい。
・トーンアーム
SAEC WE-407 Wナイフエッジ、スタチックバランス型。
LUXMAN PD-350の概要は「オーデイの足跡」 https://audio-heritage.jp/LUXMAN/player/pd350.html をご覧ください。
・追加情報
その後、既存の吸着システムを諦め、外部に吸着ポンプを設けることにより、LPレコードは吸着できています。
*LUXMAN PD-350 吸着システム復活 2020-10-11 13:07:31 | オーディオ
◯オマケ(寄り道)
LUX(MAN)のLPレコードプレイヤーの特徴は美しいデザインであることです。
LPレコードプレイヤーでは、PD-444(ダブルアーム仕様)シリーズは工業デザイン的も意欲的な製品でした。
CD時代を迎え、LPレコードプレイヤーの製造から撤退したのは1980年代半ばでした。
PD-350は当時のLUXの最終解答的製品です。
現行LPレコードプレイヤーはPD-151。
PD-171(A)シリーズは今は廃番になっています。
PD-151はPD-171(A)の価格を抑えた廉価版と思われます。
LUXMANがLPレコードプレイヤー製造を再開し、PD-171(A)を2010年代に出しました。
LPレコードプレイヤーの製造休止期間は約25年あったことになります。
PD-171(A)が出た時の感想です。
音の比較をした訳ではありませんが、PD-350には及ばない。
①機能の簡略
あれほど拘っていたLPレコードの吸着機能を省略した。メンテナンス上のことも考慮した可能性はあります。
②外観
アルミと木目の融合はなくなりました。機能中心で遊び心がなくなってしましました。無機質な製品になってしまいました。
デザイン的にはPD-444シリーズに近い印象。
製造コストの制約が大きいのだと思います。遊びに振り向ける余裕がなくなった。
この動きが波及したのか、単なる偶然か
テクニクス、アキュフエーズがLPレコードプレイヤーを出しました。




















