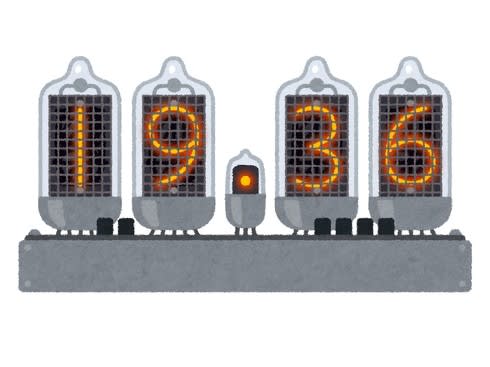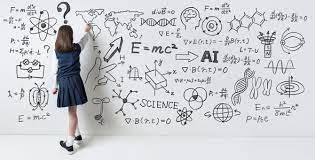生活様式や価値観が目まぐるしく変わる現代。テクノロジーの進化によって、それはますます加速度を増している。10年後、日本の未来はどう変わっているのだろうか? 我々が今から準備、そして覚悟しておくことは? 専門家に聞いた。
203X年の日本を覆う不穏で不都合な未来
世界の製造業は原材料の産地に継続的な投資をしている。それを怠った国内チョコレートメーカーは瀕死の状態に!?(写真はイメージ)
世界が変化の速度を増していくなか、10年後の日本はどうなっているのか。社会の持続可能性に配慮するサステナビリティ経営などに詳しい夫馬賢治氏は、次のような未来予想図を語る。
「中国やインド、東南アジア諸国の経済力がはるかに強まり、日本企業も外資に買収されることが増えます。そのため、今以上に外国語習得の必要性が高まるでしょう。そして日本のお家芸だった製造業も、その頃には競争力が激減。10年後には新興国発のイノベーションが日本を席巻し、国内の雇用を脅かすようになります」
SDGsの取り組みに疎い日本企業
また、昨今の世界的な企業では、SDGs(持続可能な開発目標)を重視した経営を推進しているが、この分野での日本企業の取り組みは遅く、海外勢に大きく水をあけられている。その悪影響は、まず食品に表れるという。
「10年後は日本企業製のチョコレートが食べられなくなる恐れがあります。日本の大手企業が輸入しているカカオは、ガーナやコートジボワールの森林を焼き畑農業して栽培されたものですが、現地にはもう焼く森がありません。この30年でコートジボワールの森林は8割が消えました。
海外企業のネスレやゴディバは現地の農家に未来に持続可能な農法を直接指導していますが、日本の企業はそうした努力にはいまだに無頓着です。原料は日本の商社がどこかから調達してくるから、それを買えばいいという発想なんです」
最近でこそ、日本でもSDGsが叫ばれてきたが、企業側の努力は鈍いまま。原材料輸入に頼りきりの国内企業に勤める人は、身のふり方を考えたほうがいいかもしれない。
日本の人口動態から見る未来
今起こっている日本的雇用の崩壊、世代間格差の拡大、現役世代の収入が高齢世代に吸い上げられる現象などは、20年以上前に指摘されていたことばかりです。人口動態を踏まえれば’20年代にこうなることは誰でもわかるのに、政府は無策のままでした。
ということは、今の人口構成から10年後、20年後の日本も見えてくるわけです。『人生100年』が現実のものとなれば、生涯現役が当たり前になります。能力のある人は長く働き、年金しか頼みの綱がない人との“老老格差”がどんどん開いていくでしょう」
あらゆる差別をなくしていくと、必然的に能力主義の社会になる
しかも、これは高齢者間だけの問題ではない。近年はさまざまな場面で性別や年齢差などでの差別が是正され、リベラルな社会が実現されつつあるが、皮肉なことにこれが格差を拡大していく。
「あらゆる差別をなくしていくと、必然的にメリトクラシー(能力主義)の社会になります。評価基準として認められるのは学歴、資格、経験だけで、これらの有無が格差拡大に繋がっていきます。
現在の40~50代は、来るべき能力主義社会と生涯現役社会のために、専門性や実績をつくることに奮闘する期間。これまでの日本社会は、会社に所属することが生活保障でしたが、今後は違います。50代でフリーランスになり、80歳くらいまでシームレスに働き続けることが人生設計の常識になるでしょう」 いずれにせよ「今と同じ農法や工業技術では、現状の生活水準の維持は不可能」(夫馬氏)なのだ。
夫馬賢治氏
【戦略・金融コンサルタント・夫馬賢治氏】 サステナビリティ経営・ESG投資コンサルティング会社のニューラルCEO。近著、『データでわかる2030年地球のすがた』(日本経済新聞出版)、『ESG思考』(講談社)
橘 玲氏
【作家・投資家・橘 玲氏】 小説から評論、投資術など幅広いジャンルで執筆。『言ってはいけない残酷すぎる真実』(新潮社)、『上級国民/下級国民』(小学館)など著書多数 <取材・文/沼澤典史(清談社)> ―[[10年]生き残り戦略]―
沼澤典史