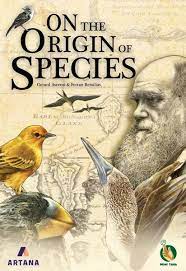東アジアではかなり異質だった礼文島の縄文人、古代DNAで一目瞭然の結果が明らかに(ナショナル ジオグラフィック日本版) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/d5786378396d4c0e87a976ebbf76188dd587413e
古代日本列島人のDNA研究のトップランナーで、国立科学博物館の特別展「古代DNA」の監修者である神澤秀明さんに、作家で科学ジャーナリストの川端裕人さんが取材した連載の第3回
国立科学博物館の特別展「古代DNA―日本人のきた道―」の船泊23号の展示コーナー。40代の女性で、礼文島の縄文人だ。(写真:ナショナル ジオグラフィック 日本版編集部)
国立科学博物館の生命史研究部研究主幹、神澤秀明さんは、日本における古代人類のゲノム研究の第一人者だ。古い骨のDNAを読む研究は、まず細胞内に数が多く読みやすいミトコンドリアDNAで1990年代から試みられるようになり、さらに2010年前後には、いわゆる「次世代シークエンサー」による技術革新で、核DNAも対象となった。神澤さんは、いわば「核DNA世代」として、キャリアの初期からこの分野に携わっている。
【関連画像】異質な礼文島の縄文人、一目瞭然の結果
大学院時代の研究が、そのまま、核DNAを読みゲノムを決定する研究室設備の立ち上げから始まったという点でも、草創期を知る人物だ。
「大学院でDNAのことをやり始めるまでは、新潟大学の理学部生物学科で、アルテミア(水田などでもよく見られるホウネンエビ)というエビの1種の研究をしていたんです。環境が悪いと、長期間乾燥に耐える休眠卵(シスト)を産むんですが、それを水に入れるとまたちゃんと発生が進みます。その原因を知るためにたんぱく質の構造とかを調べていました。修士課程では別の研究をやりたいと思い、いろいろ調べているうちに、現代人のDNA研究についての本を読みました。興味を持って、著者だった国立遺伝学研究所の斎藤成也先生のところに行ったのがきっかけです」
斎藤成也さんは、多くの一般書の著者としても知られるが、神澤さんが読んだのは『DNAから見た日本人』(ちくま新書)だったという。これは現代人のDNAについて語ったもので、神澤さんのテーマとなる古代人のDNAの話ではなかった。
「古代DNAの研究の提案をされたのは斎藤先生です。遺伝研でもラボを立ち上げたいと言われ、2009年に斎藤先生の研究室に入って、1年かけて設備を整えました。その間、まずインダス文明の遺跡から出てくる牛の骨を分析してうまくいかなかったり、試行錯誤しました。実は、その時点では、まだ次世代シークエンサーが使えなかったんです。だから、最初は核DNAではなく、ミトコンドリアDNAを見ていました。スバンテ・ペーボさんらによるネアンデルタール人のゲノム論文が出たのは、斎藤研に入った翌年で、そんなに古い人類のゲノムが決定できるのかと驚きました。研究室に入ったときには、こんなことになるなんて思っていなかったというのが正直な感想です」
いわゆる次世代シークエンサーが登場したのは2006年頃で、それを利用した古代DNA研究が実を結び始めたのがその数年後だ。のちにノーベル生理学・医学賞を受賞することになるスバンテ・ペーボさんたちが、ネアンデルタール人のゲノムを決定したと「サイエンス」誌に発表したのが2010年である。ちょうど神澤さんが、自ら研究設備を整えて、研究に乗り出そうとしていた時期に重なる。
それでは、遺跡から出てきた古い人骨のDNAを抽出して配列を読み、ゲノムを決定するには、具体的にどのような手順を踏むのだろうか。
神澤さんは、つくば市の国立科学博物館・自然史標本棟に収められている標本を見ながら、手順を説明してくれた。
「古い人骨の一部を削って薬品処理し、核DNAやミトコンドリアDNAを抽出します。骨のどこから試料をとるのかというところから、様々な検討が必要です」
DNAを抽出するためには、少しだけとはいえ、標本を破壊しなければならない。だから、形態の研究に与える影響が少なく、なおかつ、DNAが充分に抽出できる部位が望ましい。当初は、臼歯や大腿骨の骨幹部をよく使ったそうだ。2014年には、頭蓋骨の内耳がDNAの抽出に向いているという論文が出て、その後は、内耳を使うことも増えた。
「古い人骨から、一部を削って、DNAを抽出する作業は、クリーンルームで行う必要があるんです。コンタミ(コンタミネーション=汚染)を防ぐためです。科博にもクリーンルームがあって、そこを使っています」
ということで、同じ棟の一つ下の階にあるクリーンルームに案内してもらった。前室までは入れてもらい、頭から足の先までを覆うクリーンウェアの着用の仕方も実演してもらえた。露出部分を極力少なくするため、ヘアネット、マスク、ゴーグル、手袋は必須だ。特に手袋は、様々な場所を触れるたびに頻繁に替える必要があるので、替える時に地肌が剥き出しにならないよう、最低でも二重にするそうだ。
そしてクリーンルームに入ると、コンタミに極力気をつけながら、削り取った試料からDNA抽出キットを使って抽出する。そこに含まれているDNAは微量なので、いわゆる「PCR装置」を使ってDNAを増幅する必要がある。分析にたる充分なDNAを得たら、いよいよ次世代シークエンサーで、塩基配列を読むことになる。
次世代シークエンサーの装置は、デスクの上に置ける程度の筐体におさめられており、試料をセットすれば、あとは自動で塩基配列を読んでくれる。
ただ、その配列データを、そのままゲノムデータとするわけにはいかない。というのも、読まれたものは、ヒトだけにかぎらずバクテリアなどのものも含まれ、また、ヒトのものでも古いものほど断片化しているからだ。骨の持ち主のDNA断片を正しくよりわけ、パズルのようにつなげ合わせる作業をしないと、意味のあるものにはならない。
次世代シークエンサーが読んだ塩基配列のデータ。(写真=内海裕之)
神澤さんは、次世代シークエンサーで得たデータを、ノートパソコンの画面で見せてくれた。DNAを構成する4種類の塩基、アデニン (A) 、グアニン (G) 、チミン (T) 、シトシン (C) が、どんなふうにつながっていたか、画面いっぱいにひたすら表示したものだった。
「こちらが、配列情報なんですけど、たとえば、ここに73塩基という非常に短い配列が示されています。私たちが扱うDNAの断片は、本当に短いものだと、30塩基、40塩基ぐらいの長さしかないんです。100塩基を超えるものはあるにはあるんですけれども、全体からいうとそんなに多くはないです」
ヒトのゲノムは、32億塩基(対)ほどある。しかし、古代DNAの場合、それが、せいぜい数百塩基(対)、場合によっては数十塩基(対)にまでバラバラになってしまっているというのである。それらが、全体の中でどのあたりのものなのかを知るためには、まるでジグソーパズルに挑むような作業が必要になる。それを人力で行うことは無理なので、コンピュータを使う。ここから先は、生命情報工学(バイオインフォマティクス)的な様々な手法を駆使して、ゲノムに迫ることになる。
古代DNAの研究は、ぎりぎり残っているDNAを読み取って行う、まさに限界に挑むような作業が必要になる。得られる情報の不完全さにまつわる苦労は絶えない。しかし、それらをうまく制御すると、過去への窓が開かれる。21世紀にいながらにして、縄文時代のヒトのゲノムを垣間見ることができるのだ。
「2、3カ月かけて行ってきた実験の結果として、分析結果が出てきたら、食い入るようにチェックしたり、どう解釈したらいいのかいろいろ考えます。仮説を裏付ける結果が出ても、相反する結果が出ても、どちらも楽しいです。必ず試みる分析の中に、主成分分析というものがあるんですが、それを見るときは、特にわくわくしますね」
主成分分析は、この連載の中で、日本列島人がどのような由来を持つのか理解するために鍵となるものなので、ここで説明してもらおう。前回、古代DNA研究からわかることを列挙した中で、あえて、これだけは語らずに今回に回した。
「古い人の骨からゲノムが決定できれば、それを様々な地域の現代人や、様々な時代の人と比較できますよね。具体的には、例えば、一塩基多型があるとわかっている場所を数万カ所調べると、数万“次元”のデータが得られるわけです。しかし、私たちには、直接的にそれを理解することはむずかしいので、多次元空間が持つ情報をできるだけ損なわずに低次元にまとめる方法を使います。それが、主成分分析です」
ナショナル ジオグラフィック日本版
船泊23号と他の様々な地域の現代人のゲノムを比べた「主成分分析」。Anthropological Science Vol. 127(2), 83–108, 2019の図を一部改変。(画像提供:神澤秀明)
神澤さんは、たくさんの点がプロットされた図を見せてくれた。これが、主成分分析の結果を表示したものだ。多次元のデータを、二次元にまとめて理解しやすいようにしてあるという。
具体的には、それぞれの点が、一個人を表し、点と点の距離が、遺伝的な距離を表している。縦軸と横軸は、違いがわかりやすくなるように解析ソフトが選んだものなので、それぞれが何を意味するかというよりは、各点の間の距離や位置関係が、重要な情報ということになる。

「この図は、船泊23号のゲノムと、他の様々な地域の現代人を比べたものです。船泊23号のゲノムは、大陸の東アジア、本土日本、沖縄本島の現代人から見て、かなり離れたところにあります。でも、その中では、現代のアイヌ集団にまず近くて、沖縄、本土日本の集団というふうに続きます。この結果は、従来の縄文人と本土日本、沖縄、大陸の東アジア人との関係をめぐる説と整合するものだったんです」
この図を見るだけで、船泊23号が、現代の東アジア人から見るとかなり異質な存在だったことが直感的に理解できる。図にプロットされている大陸アジアの人たちはかなり隔たっており、日本列島の現代人のうち本土や琉球列島の集団はそれよりも近い。そして、地理的に予想される通りアイヌ集団は一番近いものの、少し「ズレ」がある。こういった「距離感」や、ズレ方の違いが一目で見てわかるのが主成分分析の利点だ(一方で、横軸や縦軸が何を意味するかは自明ではない)。
そして、今や、古代の人骨から得られたゲノムは、船泊23号のものだけではない。神澤さんがキャリアの初期から縄文人のDNAを読んできたけれど、さらに弥生時代や古墳時代についても研究の対象を広げ、その一方で、縄文時代よりも古い旧石器時代の人たちのゲノムを読むことにも挑戦している。それは、ここ数万年、日本列島に住まってきた人たちの歴史の一側面を解き明かす、壮大な研究だ。
次回からは、縄文時代や弥生時代といった各時代ごとに、ゲノムの知見を織り込んで見るとどんなことが言えるのか、現時点までの「到達点」を教えてもらおう。今回ざっくりと紹介した研究手法を使った、現在進行中の研究であり、すなわち「日本人のきた道(科博の特別展「古代DNA」の副題)」というテーマに肉薄することになる。