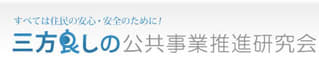たいがいの本なら、どうしてそれを読もうとしたのかという心の動きを覚えているものだが、まれに「あれ?なんでコレ買ったんだろ?」という本ある。最近ではこの本がソレ。
 |
学ぶ意欲の心理学 (PHP新書) |
| 市川伸一 | |
| PHP研究所 |
Kindleライブラリーに鎮座しているのをチラと見てはいたが、なぜそこにあるのかよくわからないまま、しばらく放っておいた。
とはいえ、タイトルからしてキライな類の本ではない。
さて、読んでみるか、とページをめくる。教育心理学関係の本のようだ。何やかにやがあり、しばらくぶりの本読み。さあ、スタートだ。
文中、「動機づけ」に関する2つの実験が紹介されている。
まずは、「ハーローの猿」。
・・・・・・・・・・
たとえば、サルに知恵の輪のようなパズルを与えておきます。サルはそれ自体をおもしろがって一生懸命内発的に解くわけです。その後、「解けたらエサを与える」というように条件を変えてみます。サルは、今度は解けたらエサがもらえるので、ますます一生懸命解く。ところが、その次にまた「エサを与えない」という条件に戻してみると、最初あれほど(エサなしでも)おもしろがっていたパズルに見向きもしなくなってしまうという現象があるんです。これはハーロー(H.F.Harlow)という人の有名な実験です。(Kindleの位置No.379あたり)
・・・・・・・・・・
つづいて「デシの大学生」。
・・・・・・・・・・
基本的なブロックを組み合わせて、何か目標となる図形を作り上げる「ソマ」というパズルがあるそうです。(略)
デシは、ある群の大学生には報酬なしでこれを解かせました。別の群の被験者たちにはこれを一つ完成させるごとに1ドルという報酬を与えることにしました。その後に、どちらの群にも休憩時間を与えます。休憩時間はこれを解き続けてもいいし、他に雑誌なども置いてある部屋なので、それを読んでいてもかまわない。何もせずに休んでいてもかまわない。さて、その休憩時間にいったいどれくらいソマを続けて解くだろうかという時間を測ってみたわけです。すると、報酬を与えられない群は、休憩時間になってもこれを解き続けたのです。ところが、報酬をもらった群では、休憩時間にこれをやる人がぐっと減ってしまった。(No.392あたり)
・・・・・・・・・・
この2つの実験は、「もともと内発的にやっていた活動に、外から報酬を伴わせると、かえってその活動自体の興味が損なわれてしまう」という現象をあらわしていると著者は言う。
・・・・・・・・・・
結局のところ、本人が報酬それ自体を目的にするか、報酬は自分の仕事の質の高さを認めるものとして捉えるかが重要になってきます。報酬それ自体が多すぎると、「自分は報酬がたくさんもらえるからこれをやっている」というふうになりかねない。先ほどのハーロー実験のサルとか、デシ実験の大学生のように、活動それ自体のおもしろさがだんだん薄れてしまう。しかし、自分の仕事の質の高さの証明として高い報酬が得られたのだと考えれば、むしろいい仕事をする方向に意欲が向かうわけです。(No.828あたり)
・・・・・・・・・・
このくだりを読んでいるあいだ、わたしが思い浮かべていたのが、高知県優良建設工事施工者表彰のことだ。その場合の報酬には、「名誉」や「評判」、「実績に対する期待としての信頼」、それらが渾然となって醸成されるブランドイメージなど、いろいろ様々のメリットがあろうが、現実的な報酬として最たるものは「受注」だろう(人それぞれでしょうがね、あくまでもわたしの場合です)。総合評価方式入札制度における企業評価点および技術者評価点のアップが受注につながる。
そこで考えてみる。
「報酬=受注」としたとき、わたしは「自分は報酬がたくさんもらえるからこれをやっている」という考えにとどまってはいないか。「自分の仕事の質の高さの証明として高い報酬が得られたのだ」と考え、「むしろいい仕事をする方向に意欲が向か」い、さらにそれを継続させようとしているか。
少しだけ考え、「うん後者だな」と断定した。
うん、今のところは後者でまちがいない。
だが、この先どうなるか、それはわからない。
すでにこの12年間、惰性の芽は摘んでも摘んでも顔を出してきており、ときにそれは抑えようもなくふくらんで来そうになることもあった。今もそうだ。
惰性に陥らないための自分自身や他人、そして組織への動機づけ。
「できるのか?オマエに」
別のわたしがアタマの真上から声をかけてくる。
「できるかできんかわからんけどヤルしかないわ」
と返答する。
とかナントカ、心の動きの一部始終をブログという場で広言して晒す。
これもまた、わたしのわたしに対する「動機づけ」。
自分に対する動機づけ、他人に対する動機づけ、組織に対する動機づけ。
内発的動機づけ、外発的動機づけ。
動機づけ。
動機づけ。
動機づけ。
わっ、アタマのなかを「動機づけ」という言葉がぐるぐるぐるぐる回りだした。
さてと、この思考、どうやって終いをつけようか。
しばらくグルグルするしてみるしかなさそうだ。
↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。