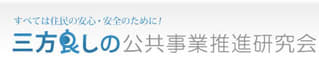リコーがジアゾ複写機の消耗品(感光紙)の販売を終了するそうだ。
「へ~まだあったんだ青焼き」と軽い驚きを覚えるわたし。
「ん?まだなんかあったんじゃないか?」と資料室をガソゴソすると、青焼きの丈量図とマイラーフィルムに描かれた原図が数枚、すぐ見つかった。

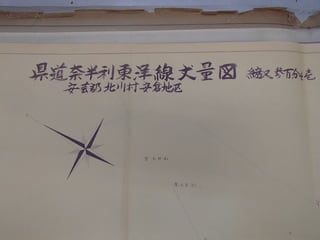
な、なつかしい・・・・
今はなき県道奈半利東洋線(現国道493号)、わが社の花形かつドル箱路線。
そんなことはどうでもいい。青焼きだ。
折しもこんなその歴史について、こんな文章を読んだばかりのわたしだ、おすそ分けしよう。
図形を図形のまま扱うことに再挑戦したのが、フランスの数学者・物理学者のガスパール・モンジュ(Gaspard Monge)(1764-1818)である。デカルトから150年経っていた。彼は、3次元の図形(立体)を2次元の紙の上にどうしたら数学的に正確に描けるかを考え、画法幾何学を1795年に創始した。彼のおかげで、設計者などの頭の中にある3次元的な機械や構造物のイメージを、他人に間違いなく伝達できる製図という手法が確立していったのである。ちょうど、18世紀末から19世紀初めは英国から始まった産業革命の真っ只中であり、設計した機械や構造物を速く正確に作るためには欠かせぬ技術となった。
ただ、画法幾何学によって製図はできるようになったが、多くの図面を安く印刷する方法がなかった。大きな画面に印刷するためには非常にお金がかかったため、19世紀は大きな画面をコピーできず、原図のみか、手で書き写す必要があった。この問題を解決したのが、英国のサー・ジョン・ハーシェル(Sir John Herschel)(1792-1871)である。(略)彼は、1842年に青図(ブループリント)と呼ばれる青写真技術を発明し、19世紀後半から20世紀初め頃から非常に大きな図面を安くコピーできるようになった。(『CIM入門-建設生産システムの変革-』矢吹信喜著、理工図書、P.43~44)
まさに必要は発明の母。
あのアンモニアの匂いを思い出しながら、170年前の発明に感謝しつつ、「青焼き」と3Dモデル、2つの時代に生かされたことにもまた感謝するわたしなのだ。
矢吹信喜
理工図書
↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
有限会社礒部組が現場情報を発信中です
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。