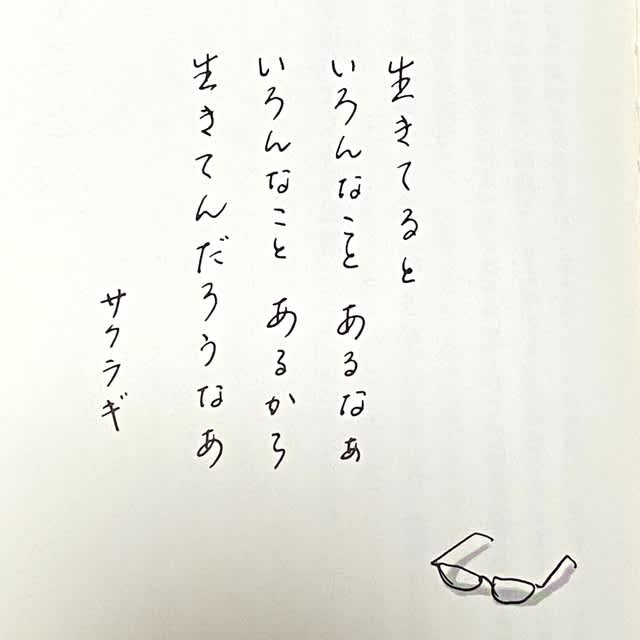「おきようよ」
孫2号の声に目を覚まし時計を見ると、まだ5時20分だ。
いつもなら起きている時間だとはいえ、せっかくの休みである。まして、きのうとおなじく今朝も寒い。ほんの数分だけ躊躇したがせっかくのご指名だ。誰がこの家でいちばんの早起きかをよく理解している彼の明晰さに免じて、起きてやることにした。
朝餉をいっしょに食い、ほどなくしていると三々五々と皆が起きてきた。お役御免とばかりに部屋にこもって読みかけの本をめくる。
『ドイツ電撃戦に学ぶ OODAループ「超」入門』(夕撃旅団、パンダ・パブリッシング)である。
連休に入り、OODAループに関する書籍をたてつづけに読んでいる。
『OODAループ思考[入門]』(入江仁之、ダイヤモンド社)
『プロジェクトを成功に導くOODAループ入門』(鈴木道代、スローウォーター)
『PDCAよりOODAか?違います』(なんとなくなシンクタンク)
につづいて、これが4冊目だ。
OODA LOOP。ウーダループと読む。ジョン・ボイドという人が編みだした理論らしい。
ジョン・リチャード・ボイド(1927~1997)。米国の軍事研究家。戦闘機パイロットとして朝鮮戦争に従軍。その後「戦闘機兵器学校」で教官を務め、学生と勝負をするたびに、どんな不利な位置からでも40秒で逆転できたことからついた異名が「40秒ボイド」というから、なんだか西部劇の主人公みたいだ。48歳で空軍を退役したあと、軍人年金だけを受け取って研究生活に入り、独自にたどり着いた結論がOODAループだという。
******
人間行動学の一種ともいえる「OODAループ理論」には、大きく2つの過程があります。
まず第一過程で、人間が行動を行うまでの手順を一般化し4つの段階に分けます。すなわち、1.情報を得る「観察」(Observations)、2.そこで得た情報の「方向づけ」(Orient)、3.情報に基づく「判断」(Decision)、そして最後に4.「行動」(Action)と、人間の行動は常に四段階を経ているとし、これらの頭文字を取ってOODAループと呼ぶのです。(『ドイツ電撃戦に学ぶ OODAループ「超」入門』、Kindleの位置No.37)
「人間が何らかの行動をとるときは、このループを無意識に必ず回してから行動に入る」、というのがボイドの主張なのです。(No.47)
ただし、これだけなら、言われてみればそうかもしれない、で話は終わってしまいます。
しかし、この第一過程を基に「OODAループを高速に回転させると、”行動も同時に高速化されるため”、スポーツやゲームにおいて敵に対し一方的に優位に立てる」、というのがOODAループ第二過程の運用であり、こちらが理論のキモになってきます。(No.57)
******
といっても、スポーツやゲームや、ましてや戦闘で勝つために読んでいるわけではない。
******
OODAループはアメリカ空軍大佐のジョン・ボイドが提唱した、敵に先んじて確実に勝利するための基本理論です。当初は、戦闘機パイロットとしての経験に基づいた、まさに一瞬の戦闘に勝つためのものでした。しかし、その後ボイドが諸科学の知見を取り入れて汎用性を持たせた結果、OODAループは戦略、政治、さらにビジネスやスポーツにまで広く活用され、「どんな状況下でも的確な判断・実行により確実に目的を達成できる一般理論」として欧米で認められるようになりました。(『OODAループ思考[入門]』、Kindleの位置No.10)
******
そう、ここ2ヶ月ほどつづいている「ためにする読書」の一環である。
せっせと仕込みをつづけてきたものが、ようやっとアタマのなかで形づくられてきたような気がしている。
さてと、そろそろまとめに入ろうか。いやその前に・・・窓の外を見ると、孫らが遊んでいる。春の光がまぶしい。[観察]。考えが変わった。[方向づけ]。弁当をもってピクニックにでも行くか。[判断]。うん、思い立ったら行動だ。さあ行くべ。[行動]。
あらあら、結局、原っぱに寝ころんでビールでも呑むのがオチなんぢゃないのか?
別のわたしがそう問いかけたが、思い直しはしない。
なんたって、OODAループは速やかに回すべしなのだもの。