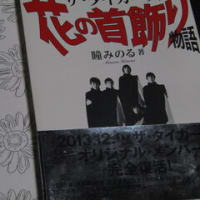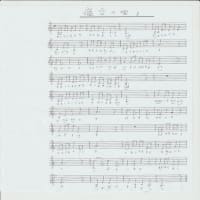夏目漱石を読むという虚栄
3000 窮屈な「貧弱な思想家」
3300 明示しない精神
3350 「覚悟」宣言
3351 暗流の「その人」
『こころ』は出来事の羅列のように思える。「然しこれはただ思い出した序(ついで)に書いただけで、実はどうでも構わない点です」などといった居直りみたいな文が出ているほどだ。
『こころ』を面白がる人は、「ただ思い出した序(ついで)」というのが虚偽であることを感知しているはずだ。あるいは、この「序(ついで)」が文脈の代りをしていると感じる。暗流。そうした何かを感じ取っている。辻褄の合わない言葉と言葉、出来事と出来事を通底する何かがあるような気にさせられている。読者は非文芸的暗示にかかっているわけだ。
作者による非文芸的暗示は、冒頭の第一文である「私は常にその人を先生と呼んでいた」(上一)に仕掛けられていた。「その」が罠だ。
〈その〉は、「「或る」の意に近く用いられることがある」(『広辞苑』「その」)というが、本文の「その」は、もっとごみごみした感じだ。玄関開けたら、きのうのご飯。
<私は、その男の写真を三葉、見たことがある。
(太宰治『人間失格』「はしがき」)>
これも書き出し。「その男」は変だが、〈ある男〉に置き換えたら、違和感はなくなる。
<……その女は、私の、これまでに数知れぬほど見た女の中で一番気に入つた女であつた。
(近松秋江『黒髪』)>
これも書き出し。この「その女」は〈ある女〉に置き換えられない。また、「……」があるから、「その」が指す言葉はここに含まれるように思える。この「その」は異様だ。ただし、この異様さは「私」の性向を表現したもののようで、聞き手の好奇心を刺激する。逆に、不快になる人がいるかもしれない。
ちなみに、「遺書」は「……」で始まる。P文書も「……」で始めるべきだろう。
<話し手が、空間的、心理的に、聞き手の側にあると考える人や物などをさし示す。
(『日本国語大辞典』「そ‐の」)>
P文書の聞き手Qは「その人」という言葉に接した瞬間、Sを知人のように感じる。Qは、いつからか、Pと「先生」のP的意味をも共有している。
<僕は最近真理先生を知った。真理先生という人がいることは僕は友達から随分前から知らされていた。しかし僕は食わず嫌いで、逢(あ)いたいとは思わなかった。
(武者小路実篤『真理先生』一)>
この「僕」はQに相当する。「友達」がPだ。『こころ』の作者は、懐疑的Qを予め排除している。「真理」などの言葉を冠しないのも、読者に警戒されないためだ。
3000 窮屈な「貧弱な思想家」
3300 明示しない精神
3350 「覚悟」宣言
3352 『猫の皿』
『こころ』は『猫の皿』に似ている。道具屋は猫の皿を手に入れてやろうと目論んで、猫を欲しがる。猫に興味があったのではない。そのことを猫の飼い主は察していた。飼い主こそが詐欺師なのだが、飼い主を騙そうとした道具屋に相手を責める資格はない。
Sは、腹の探り合いや騙し合いなどを会話と思っていたようだ。Kの大言壮語を許容していたのは、そのせいだ。また、同様に、自分の知ったかぶりも正当化していた。
「淋しい人間」は嘘つきだ。Sの叔父も嘘つきだった。父母も嘘つきだった。Kの家族も同様だろう。Pの家族も嘘つきだ。嘘つきに育てられると「淋しい人間」ができあがる。Sは、この真相を隠蔽し、「現代」のせいにしている。作者は、この隠蔽工作に加担している。読者も加担せねばならない。私にはできない。
Pは、Sに対して婉曲に、何かについて執拗に問い続ける。それに対して、Sは「不得要領」の答えを返すばかりだった。「覚悟」宣言はその一例だろう。SはPの魂胆を察していたらしい。だが、私にPの魂胆は知れない。『猫の皿』における皿に相当する何かを想像することが、私にはできないのだ。
Sの体験の中でPにとって「参考になるもの」(下二)が何なのか、不明。Sの考える〈Pにとって「参考になるもの」〉と、青年Pが求めていた「参考になるもの」と、「遺書」読了後のPにとって「参考になるもの」が同じなのかどうか、そうしたことさえ不明。
Pは、「遺書」読了後、〈自分が探し求めていたのはこれだったか〉と思うのかもしれない。『こころ』の読者は、このPに擬態せねばならないのだろう。ところが、P文書の語り手Pは「遺書」の感想を語っていない。だから、作者が表現しなかったことを読者は忖度せねばならないことになる。本当に私たちが忖度せねばならないのは、個人としてのNの魂胆だろう。Nは、言語技術の未熟な〈構ってちゃん〉だった。しかも、〈頑固ちゃん〉だった。
小説に限らず、Nの表現は忖度を期待したものだ。随筆でも、日常会話でも、論文でも。
<『文学論』は完成した整合性をもつ書物ではない。それは進化論の枠組みと、意識の心理学とビュー・ブレア以降の修辞学の方法と、そして漱石個人の、ときに凡庸すぎ、ときに鋭すぎる読みが不安定に結びついたシステムである。それが失敗しているのか、成功しているのかなどということは、私にとってはどうでもいいことだ。私にとっての魅力はその不安定さにある。その不安定さの中に漱石の無惨な失敗の痕跡を認めると同時に、その不安定さの中に漱石の放棄してしまわざるを得なかった可能性を見ることのうちに、その魅力はある。
もし敵対し、反抗し、否認すべきものがはっきりと見えていたならば、漱石はこのような不安定なシステムを残すことはなかっただろう。私の推測しうる限りでは、彼には当時の英文学研究のレベルと動向を適確に判断する知識があったとは思えない。
(富山太佳夫『ポパイの影に 漱石/フォークナー/文化史』)>
私にとっての苦痛が、夏目宗徒にとっては「魅力」であるらしい。
「不安定さ」を「可能性」と瞞着する人を、私は私の読者として想定しない。
3000 窮屈な「貧弱な思想家」
3300 明示しない精神
3350 「覚悟」宣言
3353 「金魚売らしい声」
Sは「恋愛は罪悪」という話を自分から始めておきながら、都合が悪くなると、「この問題はこれで止(や)めましょう」と勝手に打ち切る。Pは反抗できない。
「この問題」の追究は、この前の回(上十三)で終わったような感じだ。ところが、実際にはそうではなかった。Pは打診を続けたらしい。そのあたりのことが茫洋としている。
「然し先生はそれぎり恋を口にしなかった」に続いて、次のような話が始まる。
<年の若い私は稍(やや)ともすると一図(ママ)になり易(やす)かった。少なくとも先生の眼にはそう映っていたらしい。私には学校の講義よりも先生の談話の方が有益なのであった。教授の意見よりも先生の思想の方が有難いのであった。とどのつまりをいえば、教壇に立って私を指導してくれる偉い人々よりも只(ただ)独(ひと)りを守って多くを語らない先生の方が偉く見えたのである。
「あんまり逆上(のぼせ)ちゃ不可(いけ)ません」と先生がいった。
(夏目漱石『こころ』「上 先生と私」十四)>
「稍(やや)」は〈動(やや)〉が適当。
「少なくとも」は意味不明。
「とどのつまりをいえば」の「をいえば」は不要。
「只(ただ)」の被修飾語が決まらない。「独(ひと)りを守って」は意味不明。
「あまり逆上(のぼせ)ちゃ不可(いけ)ません」という言葉を読んで、私は見えない壁にぶつかったように感じた。どうして、ここにSが? 実際の会話はどこから始まったのだろう。また、どうやって始まったのだろう。不明。
語り手Pの回想が、突如、過去の事実として語られる。こんなことは不合理だ。三人称の語りなら、ありうる。だが、一人称の語りでは不合理だ。勿論、作者が〈語り手Pは怪しい〉という表現をしているわけではない。だから、本当に怪しいのは作者だ。
<その時生垣(いけがき)の向うで金魚売らしい声がした。その外には何の聞こえるものもなかった。
(夏目漱石『こころ』「上 先生と私」十四)>
こんなことを覚えているのは、おかしい。覚えていたとしても、語る必要はない。
この無音の描写は、Sと静とPの霊的関係が成立したことを暗示している。この後に始まる「覚悟」宣言は、霊感の持ち主にとってのみ価値のあるものだろう。
「かつてはその人の膝(ひざ)の前に跪(ひざま)ずいたという記憶」に始まり、「自由と独立と己れとに充(み)ちた現代に生れた我々は、その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならないでしょう」(上十四)で突き放したように終わるSの長台詞、「覚悟」宣言の意味は、普通に読む限り、不明なのだ。意味不明だからこそ、霊感の持ち主にとって価値があるのだ。ただし、これを盗み聞きしているはずの静に、どのように感じられたか、不明。
「覚悟」宣言は呪文のようなものだ。
(3350終)
(3300終)