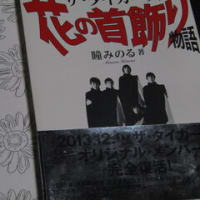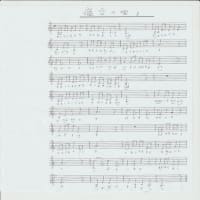夏目漱石を読むという虚栄
3000 窮屈な「貧弱な思想家」
3300 明示しない精神
3340 「覚悟」宣言の前後
3341 『転失気』
「自由と独立と己れとに充(み)ちた現代」の真意は、〈冷たい人だらけの「現代」社会〉などだろう。ところが、Sはこのようにわかりやすく表現しなかった。なぜか。わかりやすく表現すると、真相が明るみに出てしまいそうだったからだ。
真相とは、〈Sは冷たい人だから、静から冷たくされる〉という物語だ。また、〈Kは冷たい人だったから、Sから冷たくされた〉という物語だ。
〈現代社会では人と人の絆が失われがちだ〉というのは常識だろう。しかし、〈現代社会では人と人の絆が完全に断ち切られてしまい、それを修復することは不可能なので、諦めて泣いて暮らしながら死ぬのを待つしかない〉と言い切るのは非常識だ。
Sは、後者のような、非常識な「覚悟」を暗示している。虚偽の暗示だ。彼自身、信じていない「覚悟」を暗示している。誇張、嫌味、皮肉であり、要するに駄々をこねている。甘ったれている。そうした自覚があるから、明言できないのだ。絆を修復する可能性について考察する能力の不足を自他に対して隠蔽しているのでもある。
こうした真相の隠蔽に、作者は加担している。だから、読者も加担せざるを得ない。
「覚悟」宣言について、〈自己疎外〉だの〈実存的不安〉などといった難解な用語を用いて解釈を施すことは、できなくはないのかもしれない。しかし、そんな解釈は便所の落書きにだって施すことができるのではないか。だったら、『こころ』の作者の独創性や特異性などについて考察したことにはならないはずだ。
<医者の言った「転失気」という語が「屁(へ)」のことと知らなかった和尚が、その意を尋ねに行かせた小僧から「盃」のことだと嘘を教えられ失敗する。
(『広辞苑』「転失気」)>
「転失気」には四つの意味がある。
- 屁(へ)が肛門まで来て、外に出ないで、音が内へ反転すること。(『日本国語大辞典』の説)
- 外に出る屁(へ)。(「医者」の説)
- 盃。(「小僧」の嘘)
- 吞酒器。(「和尚」の造語)
『日本国語大辞典』が正しいとすると、「医者」は間違っていることになる。しかし、作中では正しいから、問題にする必要はない。「小僧」は邪気のある嘘をついたが、愉快ないたずらっ子だ。「和尚」は嘘をついている。ただし、単純な嘘ではない。自己欺瞞だ。彼は自分の嘘に騙されている。軽薄才子だ。
「覚悟」宣言の①に相当する意味、つまり作品の外部における意味は、私にはわからない。②に相当するSの意味は不明。③に相当するPの意味も不明。④のように「覚悟」宣言の内容についてわかったように論じる人々は「和尚」の仲間だ。
3000 窮屈な「貧弱な思想家」
3300 明示しない精神
3340 「覚悟」宣言の前後
3342 「現代一般の誰彼(だれかれ)」
「覚悟」宣言を聞かされたPは「或強烈な恋愛事件」を連想する。その理由は不明。しかも、その「事件」を否定した。おかしな展開だ。
<「かつてはその人の前に跪ず(ママ)いたという記憶が、今度はその人の頭の上に足を載せさせようとする」と云った先生の言葉は、現代一般の誰彼(だれかれ)に就いて用いられるべきで、先生と奥さんの間には当てはまらないもののようでもあった。
雑司ケ谷にある誰だか分らない人の墓、――これも私の記憶に時々動いた。
(夏目漱石『こころ』「上 先生と私」十五)>
この「言葉」は意味不明だ。だから、「誰彼(だれかれ)」あるいは「先生と奥さん」に適用できるとか、できないとか、そういう話は、私には理解できない。
しかも、唐突に「墓」の話になる。この「墓」はKのものだ。「遺書」を読んだ後、〈あのときの「先生の言葉」はKの「墓」と関係があったのだな〉と思うのなら、わからなくもない。だが、特に情報がないのだから、奇妙だ。Pは超能力者か。そうかもしれない。
「覚悟」宣言の前後の話を要約してみよう。
1 PはSを「見付出し」(上一)て接近する。その理由は不明。
2 PはSと「懇意」(上三)になる。その理由は不明。
3 静に教えられた「墓地」(上四)で、PはSに会う。出来過ぎ。
4 Sは自分と静が「最も幸福に生れた人間の一対であるべき筈(はず)」(上十)と語る。
5 Sは「恋は罪悪」(上十二)と語る。Pにも意味不明。
6 Sは「覚悟」(上十四)を宣言する。意味不明。
7 PはSの「覚悟」の由来として、「或強烈な恋愛事件」(上十五)を仮定する。
8 Pは、Sの「覚悟」とからKの「墓」(上十五)を連想する。不可解。
9 静は、PにSとの不和と関連したKの「変死」(下十九)について仄めかす。
ここまでが「上」の前半に相当する。
「上」の後半では、Pは探偵のようになり、「恋愛事件」と「変死」を関係づけようとする。「下」では、SはPに誘導されたみたいに〈静とSの「花やかなロマンス」〉と〈Kの自殺の物語〉を綯い交ぜにしようと頑張る。しかし、しくじり続ける。結局、「この不可思議な私というもの」(下五十六)が主人公であるところのSの「自叙伝」(下五十六)は完結しない。そして、「遺書」は終わる。同時に『こころ』も終わる。Pは再登場しない。
作者は何をしているのだろう。作者は、「現代一般の誰彼(だれかれ)」が抱く疎外感と、Sに特有の「この淋しさ」とが、同種のものであるのかないのか、わからなくなったのだろう。
〈「この淋しさ」は「現代」の人々にとって不可避だ〉というのが作中の真理なら、「花やかなロマンス」と絡めて話を作る必要はない。Kに対する違和感を主題にすればいいだけだ。なぜ、作者は物語を二本立てにしたのか。どちらもまともに作れないからだ。
3000 窮屈な「貧弱な思想家」
3300 明示しない精神
3340 「覚悟」宣言の前後
3343 『茶の湯』
静はPに「よく男の方は議論だけなさるのね、面白そうに。空の盃(さかずき)でよくああ飽きずに献酬(けんしゅう)が出来ると思いますわ」(上十六)と言う。「覚悟」宣言に至るSとPのやりとり対する揶揄と考えられなくもない。読者にとっては、そのように感じられる。
Pは静を賢い女性と思っているらしいが、小賢しいだけだ。ただし、そのように解釈すると、『こころ』は作品として解体する。作者は、〈静は男同士の空威張りの根底にある「明治の精神」に気づいていない〉と暗示している。ただし、静にも「明治の精神」はある。つまり、彼女も軽薄才子だ。「最も強く明治の影響を受けた私ども」(下五十五)の一人だ。
男同士の〈「献酬(けんしゅう)」ゲーム〉は、『蒟蒻問答』ではない。『茶の湯』だろう。
男たちは意味不明の言葉を交わす。相手の発した言葉の意味を理解できていないのに、理解できたふりをして応じる。だから、そのときの自分の言葉の意味も理解できていない。馴れ合いに慣れた連中は、腐れ縁を断ち蹴れない。だが、いつかきっと同行不能になる。ゲイでもない限り、あるいはゲイでもか、きつい上下関係、主人と奴隷のような関係が確立していない限り、殺し合いになる。ありふれた話だ。『こころ』は、根暗の軽薄才子たちの思想的自己破産の露呈だ。普通の意味での作品にはなっていない。
<その時彼の用いた道という言葉は、恐らく彼にも能く解っていなかったでしょう。私は無論解ったとは云えません。然し年の若い私達には、この漠然とした言葉が尊(たっ)とく響いたのです。
(夏目漱石『こころ』「下 先生と遺書」十九)>
「その時」は無視。「彼」はKだ。〈「言葉は」~「解って」〉は意味不明。「言葉」は〈「言葉」の意味〉などの不当な略だろうが、断定はできない。「能く解っていなかった」とする根拠は隠蔽されている。傲慢なKのことだから、〈僕には「能く解って」いるぞ〉と語ったのかもしれない。青年Sは、〈「能く解って」いないからこそKは偉い〉という理不尽な感想を抱いたのかもしれない。とにかく、不可解。
Nは〈清狂〉という言葉を知っているはずだ。Kは一種の狂人だ。超俗的で狂っているみたいだからこそ、Kは偉い。ところが、Sは、そのように語らない。おかしい。
「無論」は変。〈賢い自分に解らないのだから愚かな相手には「無論」わかるまい〉という話なら、わからなくもない。「云えません」は怪しい。青年Sは「解った」とKに言ったのか。言いたくても言えなかったのか。不明。過去のSが語り手Sに変身し、〈Pに「云えません」〉という話にすりかえている。語り手Sは怪しい。この種のすりかえは、『こころ』に散見する。作者は怪しい。怪しがらない夏目宗徒は怪しい。
「然し」は怪しい。「年の若い」ことは理由にならない。若気の至りなら、「解った」と信じ、威張って明言したろう。〈自分は偉い〉と思いあがるのが若者だ。「言葉が尊(たっと)とく響いた」は意味不明。「言葉の重み」(下三十六)と同種の表現らしいが、これも意味不明。
「道」ゲームは「向上心」ゲームに発展する。だが、Kは自作のどのゲームもクリアできず、新しいゲームを構想することもできず、自信を喪失して自殺した。くだらない男だ。
(3340終)