いやあ、残念。もっと長く頑張ってもらいたいものでした。
**********
文楽の豊竹嶋大夫さん引退へ 来年初め 人間国宝不在に
朝日新聞 2015年10月21日03時09分
人形浄瑠璃文楽の人間国宝、豊竹嶋大夫(とよたけしまたゆう)さん(83)が来年初めに引退することが分かった。来年1月の大阪公演と2月の東京公演が最後の舞台となる見通しだ。嶋大夫さんが引退すると、現役の文楽太夫に人間国宝はいなくなる。21日に会見を開く予定。
嶋大夫さんは愛媛県出身。1948年に十代豊竹若大夫に入門し、二代呂賀大夫を名乗って初舞台を踏んだ。54年に四代呂大夫を襲名。一時文楽の世界を離れたが、68年に復座し、八代嶋大夫を襲名した。94年に太夫最高位の切場(きりば)語りとなった。時代物に加え、人物の「情」を繊細に表現する世話物でも高い評価を得て、今夏、人間国宝の答申を受けた。
【亀岡典子の恋する伝芸】苦難の時代、乗り越え人間国宝に 片岡仁左衛門、豊竹嶋大夫、井上八千代に共通する「謙虚さ」
産経新聞 2015.7.20 16:00
「浄瑠璃を語ることは辛いだけ」嶋大夫
先日、今年、人間国宝に認定される方々が発表されました。
伝統芸能では、歌舞伎の片岡仁左衛門さん(71)、文楽太夫の豊竹嶋大夫さん(83)、京舞井上流五世家元の井上八千代さん(58)。3人とも関西に本拠があったり、関西で生まれ育ったりと、上方にゆかりの人たち。精進と修業を積み重ね、高い芸境に達し、後進の育成にも力を注いでいる実力者ばかりです。普段、関西で演劇を担当している身として、こんなうれしいことはありません。
というのは、上方の伝統芸能は戦後、それぞれの分野で厳しい時代があったからです。特に嶋大夫さんや仁左衛門さんはそういう低迷の時代をもろに経験しているので、とりわけ深い感慨があったのでは、と想像してしまいます。
嶋大夫さんが入門したのは戦後、昭和23年。故郷の愛媛で聞いた竹本越路大夫さんらの浄瑠璃に圧倒されたのがきっかけだったそうです。何が何でも浄瑠璃を語りたいと、親や兄の大反対を押し切って、焼け野原の大阪に出て来て、豊竹若大夫さんに弟子入り。師匠の家に住み込んで修業する厳しい内弟子生活を6年も経験しました。
文楽自体もその頃、二派に分裂。食べていくことすら厳しい苦難の時代だったそうです。嶋大夫さんは昭和30年に一度退座して他の仕事に就きますが、やはり浄瑠璃が忘れられないと、再び文楽に復帰しました。それだけ浄瑠璃が好きで好きでたまらず、その奥深さに引かれていたのでしょう。
だからこそ、記者会見で気持ちを聞かれても、「浄瑠璃を語ることは辛いだけです。千秋楽で、ようやく、やれやれ、とうれしさがこみあげてきます」と話していたのでしょう。
「歌舞伎俳優をやめようと思った」仁左衛門
仁左衛門さんもまた、青年時代、上方歌舞伎の低迷期で苦難の時代を送ります。関西の歌舞伎公演はほとんどない時代。仁左衛門さんの父で同じく人間国宝だった十三世片岡仁左衛門さんは当時、私財を投げ打つ覚悟で「仁左衛門歌舞伎」を旗揚げしました。そんな父とともに関西で奮闘、昭和39年、その「仁左衛門歌舞伎」で上演した「女殺油地獄(おんなころしあぶらのじごく)」の与兵衛、翌年には中座で「義賢最期(よしかたさいご)」の義賢などを演じ、「関西に孝夫(当時、片岡孝夫)あり」と一躍、注目されます。仁左衛門さんは東京に出ていき、その端正で美しい容姿と確かな実力で、当代きっての人気スターになっていったのです。
会見でも「当時、歌舞伎俳優をやめようと思ったこともありました」と明かした仁左衛門さん。「思いとどまらせてくれたのは、お客さまの熱い拍手や声援でした」。
江戸歌舞伎から上方歌舞伎まで幅広い役どころを誇る仁左衛門さんですが、普段の言葉はやわらかな関西弁。特に七月の松竹座での歌舞伎公演には深い思い入れがあり、毎年のように出ずっぱりともいえる舞台を勤めています。
今年も、昼夜にわたって大奮闘、特に夜の部の通し狂言「絵本合法衢(えほんがっぽうがつじ)」では、タイプの異なる2つの悪役を演じ分け、舞台に悪の華を咲かせています。
芸には自分のすべてが出る
今回、3人の記者会見に出席して感じたのは、3人ともが、自分を導いてくれた師匠や先人たちへの感謝の言葉を真っ先に口にしたことと、芸の道の厳しさでした。人間国宝という最高の地位に上りつめた3人ですが、芸に対する謙虚さを忘れないところも共通しています。
おそらく、そういう謙虚さこそが、彼らの芸を高みに導いていったものかもしれません。嶋大夫さんは「芸には自分のすべてが出る。浄瑠璃を聞けば、その人がどんな人間かわかる」と言いました。
それは芸能者だけでなく、私たちすべてに言えることかもしれないと、自省したものでした。
**********
嶋大夫師の語りを聴いたのは、人形浄瑠璃文楽初心者なもので、今年の5月の東京公演の第二部『桂川連理柵』の「帯屋の段」の時だけです。世話物のおかしさを十二分に語ってもらって、大笑いしながら舞台を楽しむことができました。この人の語りは、いついつまでも聴いていたいと、そのとき思ったものです。
残念ながら、9月の東京公演には出られることがなく、楽しみにしていたので、すごく寂しい思いをしました。
というわけで、嶋大夫師の素晴らしさを十二分に味わうチャンスもなくなったようです。それでも、2月の東京公演だけは、絶対に聞き逃さないようにします。
大変な覚悟で舞台に上がり続けた師の心意気を、引退しても若手に伝えていってもらえたらと願ってやみません。2月まで、体調をきをつけて、がんばってもらえることを願っております。













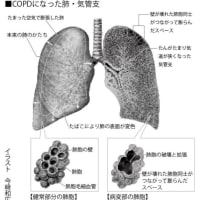
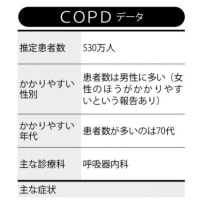




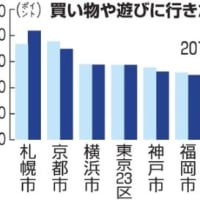
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます