
「蟲師」 蒼井 優
監督・脚本:大友克洋
原作:漆原友紀『蟲師』(講談社『アフタヌーン』連載)
配給:東芝エンタテインメント
主演オダギリジョー、(ギンコ)
蒼井 優(狩房探幽 かりぶさ たんゆう))、
江角マキコ (ぬい)
大森南朋 (虹郎 こうろう)
李麗仙 (薬袋たま みない たま)
りりィ
コミックと映画の感想・・・
コミックは、まだ全部を読んでいない・・。
アフタヌーンKC2巻
「やまねむる」
山のヌシが巨大な老猪(いのしし)の姿で現れる。
ふと、「もののけ姫」を思い出した。
「蟲師」は、日本古来の伝承を踏まえながら、“蟲”の介在した物語として、
新しい物語を紡ぎだしているのだろうか・・?
しかし、コミックのあとがきを読むと、今回は偶然、
マタギの言い伝え「サカブ」(山神の声)と少しだぶったようだが、
基本的には、原作者 漆原友紀の創作のようだ。
まったくのオリンジナルで
「ゲゲゲの鬼太郎」とは違った“妖怪” -蟲- の世界を創り出した。
すごい人だと思う。
この人はきっと小説も書ける人だ。
アフタヌーンKC2巻
「筆の海」
蒼井 優の狩房探幽が良かった。
蒼井がスクリーンに現れると、画面がぱっと明るくなる。
ギンコのクールさに探幽のきらめき、
このふたりのエピソードをもっと膨らまして、撮って欲しかった。
コミックのあとがきに―「筆の海」の舞台背景は、有名なカルスト台地―とあり、
秋吉台だとすぐに分かった。
なぜ、秋吉台と明記しないのだろう・・?
山口県の秋芳(しゅうほう)、美東(みとう)両町にまたがる国内最大のカルスト台地で、
何度か行った事がある。
原作者のふるさとは山口県岩国市で、フジテレビTVアニメ「蟲師」の長濱博史監督は、
イメージ作りのため、スタッフを引き連れて、岩国市を訪れたそうだ。
ちなみに、映画「蟲師」で、
淡幽が住む屋敷として使われたのは、信長の部下であった桑原氏の邸宅とのこと。
関が原の近くだ。
[ロケ地へ行こう]全国のロケ地へGo!
アフタヌーンKC3巻
「眇の魚」(すがめのうお)
ちなみに、眇眼とは、独眼のこと。片目のこと。Yahoo辞典より
例文
(矯(た)めつ眇(すが)めつ
あるものを、いろいろの方面からよく見るようす。「作品を―眺める」)
“母親と行商の旅をしていた少年ヨキ(ギンコ)は、崖崩れに遭い母親を失う。”
ギンコの生い立ち、原点が初めて明かされる。
ぬいとギンコとトコヤミの因縁話は、難しい。
ヨキ 「蟲師だったんだろ?
こんな恐ろしい蟲、
どうして生かしておくんだよ
ぬい 「畏れや 怒りに
目を眩まされるな
逃れられる
モノからは
知恵あるわれわれが
逃れればいい。」
ヨキに蟲師としての能力を見たぬいは
蟲師の基本を教え、蟲と共存する術を教えていく。
ぬいの江角マキコは頑張っている。
まさしく汚れ役で、沼に入りドロだらけになる。
本来、江角は、大柄だし、
蟲が寄りつきそうにもないほど
もともとが男っぽい。
「ショムニ」のイメージがまだ強くある。
しかも、大女優だ。
よほど作品に惚れ込んだのだろう。
P.S.-1
狩房探幽の活躍が、もっと観たい。
探幽主役で、「蟲師2」を作って欲しいくらいだ。
P.S.-2
監督大友克洋ということで、期待をして観にいった。
ぬいとヨキが暮らした庵で、前の池にはトコヤミと銀こが棲んでいる。
.ロケ地は、滋賀県 菅山寺・朱雀池。
山奥の撮影困難な場所で、
たどり着くまでに1時間も山道を歩かなければならない・・・。
重い機材はヘリコプターで運んだり、大変な撮影だった。
CGの作業もあり、撮影は、HD(ハンディカム)ビデオカメラが
メインと思うが、
小回りを効かして細部まで良く撮っている。
ただ、大きなスクリーンに投影すると
多少、奥行きが浅く、後ろの光景がぼやけぎみに映るのは、ビデオの限界か?
P.S.-3
そもそも蟲(むし)とはなにか?
そこに疑問を持った原作者、漆原友紀が、辞書で調べると、
「人、動物、植物以外のもの・・・ 」とあった。
だったら妖怪変化の類も、もしかしたら、その正体は、蟲だったのかもしれない。
そして、新しい“蟲”の定義を
作者は創作として、作り出す。
定義
蟲(むし)とは
“「みどりもの」とも呼ばれ、この世のあらゆる生命よりも命の源流に近いもの。
「生」と「死」の間、「者」と「物」の間にいるもの。
人の中には見える者と見えない者が居る・・・。
その姿形等は多種多様で、動植物型のものやどちらともつかないもの、
虹や火など自然現象に近いものまで様々で、
姿形は違えど実際の生物と全く同じ性質を持ったものすらいる。”
公式HPより

















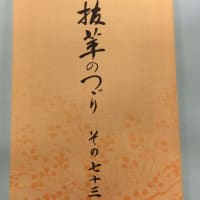


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます