今日の朝、『目がテン』という番組を見ていたのだが方言についての話題ので内容が怪しげな感じであった。東北弁の話者からの視点では関西弁は聞き取りにくいのだ。私は関東の人だが関西弁のイントネーションで話されると重要なところがどこかわからなくなってくる。ちっともそのことに踏み込まずありえないだろうという実験を繰り返していた。
少し余計なこというと、昔からだが、メディアは意図的に正確な情報を伝えないそのようなエンターテインメント番組を作っているように感じられる。正確なことを知っている人間とそのメディアを見ている人間を区別したいという作り手側の職業意識が本当にあったりするのだが、その考えは正しくないと断言できる。推論の方法がまず正しくないし、実際に結果が目的通りではなく、自らの意志に反することを正しいと信じる人を周囲に続出させて行動範囲や信頼関係を狭めるという逆作用が発生しているとしか見えない。気のせいかもしれないがデュオバンや小保方さんの事件が彼らの意志と反するもので最近より一層ひどくなっている気がする。人が間違ったことをやっていて、自分だけ適切なことをやっているとアドバンテージが高くなって勝者となれる可能性がある状況があるわけだが、テレビ番組で広めるとガリレオ状態になってしまうのではないかという懸念もなくはない。また、ガリレオが勝利した場合、今までの前提が正しくなかったということは立場を崩すことになるため、本当に金を払って、人間を動かして横車を押してくる場合があるのだが、その際に普通の人間はそのようなことに加担するには障壁が高すぎるため必ずと言ってよいほどに暴力組織に依頼することになる。禁酒法などの経験則から、必要を感じることに規制ができることは暴力組織にとって利益がやってくるきっかけになる可能性は高いと考える人もいるようで、積極的に規制したい内容に関する事件を起こして規制を設置するという謎の人物も実物の話しぶりでは本当にいるかもしれないのだ。先輩が誤ったことをしたと自己認識し始めると、後輩に誤った教育をして自分より信頼性を挫いて発言権をなくさせるようなニグレクトを働く場合があるのだが、発言の内容にその影が見えたら撤退や逃走は他の場所で生きられるめどがあれば英断かもしれない。
話を元の方言に戻すが、方言の単語や品詞の変化がなくなってもイントネーションというのが結構残っている場合がある。イントネーションが表しているのは大抵何かと考えてみると、『どこが重要か』や『どんな感じなのか』ということであろう。そのイントネーションが異なるということは重要な点や感覚が多少異なっていることを表していないかと最近の私は感じている。講義が眠かったのもそのせいかもしれない。











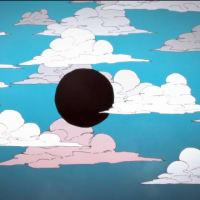
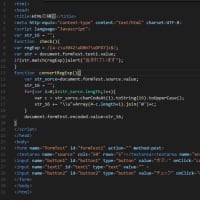







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます