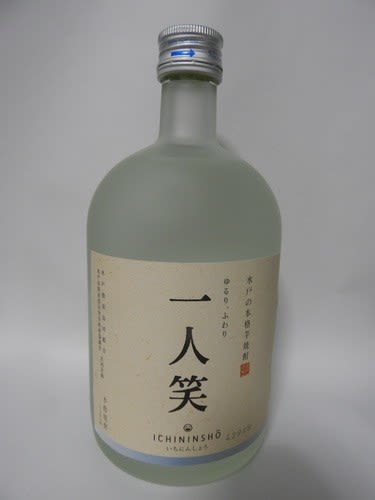水戸八幡本殿(八幡町8-54)
大変はなやかで、装飾的な斗栱(ときょう)です。棟梁が自分の腕を見てくれといっているようです。通り肘木(とおりひじき)などに地方的特徴が出ているそうです。

仏性寺本堂(栗崎町1984)
柱の上にある斗(と 桝(ます)の意味)が大斗(だいと)、それ以外を小斗(しょうと)というそうです。八角堂(国の重要文化財)なので、普通と角度が違っています。

天神社本殿(常照寺脇 元吉田)
大斗上にある栱(きょう 肘木(ひじき))に乗る3つの斗を、平三斗(ひらみつど)というそうです。この写真の場合、支えている斗は柱の上にないので、大斗ではないようです。

桂岸寺本堂(松本町13-19)
装飾的な尾垂木(おだるき)が突き出ています。

日吉神社本殿(見和2)
本殿廻廊を支える床下にも斗栱が見られました。