2018/11/26, 看護士OG、・ブリュッセル国際コンクール日本酒部門最高のプラチナ賞、・フランスの日本酒コンクール「クラマスター」で金賞、全国の酒蔵は登録数は1500以上、稼働しているのは1200程度、女性杜氏の進出、=竹田聡=、●山口県で初の女性杜氏(とうじ)が誕生した。中四国エリアでは、これで6人が現役で働くことになる。伝統的な日本酒製造の現場では従業員の高齢化と後継者不足を背景に、女性杜氏がじわりと増えつつある。細やかな気配りとセンスを武器に、かつては女人禁制だった「蔵」に新風を巻き起こしている。看護師をやめ、90年続く酒蔵で杜氏となった新谷文子さん(新谷酒造の本社)21日、東京のベルギー大使館で10月に開かれたブリュッセル国際コンクール日本酒部門の授賞式が行われ、新谷酒造(山口市)の純米酒「わかむすめ月草」が最高のプラチナ賞を獲得した。社長の義直氏(49)と杜氏である妻の文子さん(40)が営む二人だけの蔵の腕試しだった。山口市徳地で1927年から続く酒蔵が、杜氏の引退で廃業の危機に陥ったのが2005年。看護師をしていた文子さんが義直社長と結婚した翌年だった。社長が杜氏として跡を継ぐことにしたが、二人とも酒造りの知識に乏しく、途方に暮れた。思い切って「獺祭(だっさい)」で成長しつつあった旭酒造の桜井博志社長(現会長)のもとに駆け込み、相談した。桜井社長は「うちに来て3年勉強すればいい」と勧めたが、「休業が不安だったのか、そんないい話を断ってしまった」と文子さんは今もぼやく。熟慮の末、量産品から高級品に移行して製造を再開した。再び危機が訪れたのが16年。老朽化した蔵の梁が壊れた。投資して蔵を改装するか、廃業か。当時まだ看護師をしていた文子さんは退職し、本格的に蔵に入ることを決めた。新しい技術を学び、自身での酒造りに取り組んだ。これが今年5月のフランスの日本酒コンクール「クラマスター」で金賞を受賞。方向は間違っていないと確信した。日本酒業界は男社会。どこへ行っても紅一点が珍しくない。「若い女性が日本酒に関心を持ち出している時にもったいない。繊細さや細やかさなど、女性ならではの酒造りが広がっていいはず」と力を込める。●文子さんと交流のある島根県出雲市の旭日酒造の副杜氏、寺田栄里子さん(43)は蔵元の長女で、就任から8年。女性杜氏については「もろみの管理や麹の細かい変化を感じ取れる能力がある」とみる。蔵仕事は肉体的に厳しいが「周囲の助けを求めていい」と説く。●岡山県真庭市の御前酒蔵元辻本店の杜氏、辻麻衣子さん(41)は07年から杜氏を務める。「自分のいいと思うやり方で、おいしいものができた時が楽しい」と語る。男女にかかわらず「周囲はライバルではない。開き直ってやってほしい」とエールを送る。●このほか広島県東広島市の今田酒造本店では、社長の今田美穂さんが15年前から杜氏を務める。島根県大田市の一宮酒造では社長の次女の浅野理可さん(28)が17年に杜氏に就任した。●徳島県三好市の三芳菊酒造では馬宮亮一郎社長が、フリー杜氏の宇高育子さんを招いて3年目に入った。宇高さんは09年に廃業した愛媛県四国中央市の篠永酒造で、四国初の女性杜氏として知られた人材だ。三芳菊の場合、長女と次女が東京農業大に進み、いずれ家業を継ぐ見込み。「女性が働きやすい蔵になるため、下地を作っておきたい」というもくろみがある。●全国の酒蔵は登録数は1500以上あるが、稼働しているのは1200程度とみられ、年々減っている。後継者難はもとより、蔵人や杜氏の高齢化も著しい。もはや男社会などとうそぶいていられない状況にあり、女性杜氏の進出は必然とさえ言える。●全国の女性杜氏(とうじ)の第1号は、白牡丹酒造(広島県東広島市)に工場長として勤めた水野いさえさんとされる。1985年に杜氏として認められ、2014年に引退した。以前は蔵は女人禁制とされ、今もそのしきたりを守るところもある。杜氏や蔵人は厳冬期に大量の水やコメを扱い、泊まり勤務もある重労働という壁もあったが、社会の変化と機械化、また後継者不足という側面から00年以降は女性杜氏が増え、現在30人を超えるとみられる。杜氏とは製造部門のトップであり、その蔵の味を決める立場にある。厳密な定義はなく、南部杜氏や丹波杜氏など地域の杜氏集団に属するか、単に製造責任者を指す場合もある。●日本酒造杜氏組合連合会の調べによると17年度の加盟杜氏は681人。全国に稼働中の蔵は1200程度あり、製造責任者というくくりであれば同数以上の杜氏がいるとみられる。杜氏はかつては農閑期の出稼ぎという職業で、地域の組合に所属して派遣されるという形態だったが、日本酒業界の衰退もあってフリーランスは減少し、国税庁の調査では全国の蔵の製造責任者は半分が代表者とその家族となっている。●女性杜氏の進出は、業界を取り巻く環境の厳しさがもたらしたとも言える。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38190090W8A121C1LC0000/?n_cid=NMAIL007
最新の画像[もっと見る]
-
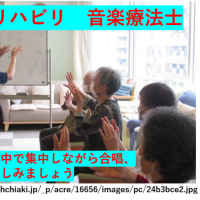 NOTHING’S GONNA CHANGE MY LOVE FOR TOU/ George Benson
6時間前
NOTHING’S GONNA CHANGE MY LOVE FOR TOU/ George Benson
6時間前
-
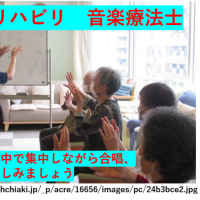 🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 追悼 橋幸夫 子連れ狼(おおかみ)
6時間前
🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 追悼 橋幸夫 子連れ狼(おおかみ)
6時間前
-
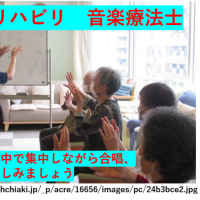 🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 追悼 橋幸夫 霧氷
6時間前
🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 追悼 橋幸夫 霧氷
6時間前
-
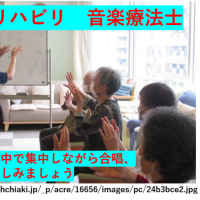 🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 追悼 橋幸夫 いつでも夢を
6時間前
🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 追悼 橋幸夫 いつでも夢を
6時間前
-
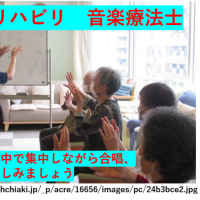 🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 追悼 橋幸夫 潮来笠
6時間前
🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 追悼 橋幸夫 潮来笠
6時間前
-
 2025/9/7(日)#二十四節気#白露0日#新月15日#東京都#天気痛#調査時間:1時~7時#「少し痛い~痛い~かなり痛い」と感じる方😨の割合83%
15時間前
2025/9/7(日)#二十四節気#白露0日#新月15日#東京都#天気痛#調査時間:1時~7時#「少し痛い~痛い~かなり痛い」と感じる方😨の割合83%
15時間前
-
 2025/9/7(日)#二十四節気#白露0日#新月15日#東京都#天気痛#調査時間:1時~7時#「少し痛い~痛い~かなり痛い」と感じる方😨の割合83%
15時間前
2025/9/7(日)#二十四節気#白露0日#新月15日#東京都#天気痛#調査時間:1時~7時#「少し痛い~痛い~かなり痛い」と感じる方😨の割合83%
15時間前
-
 2025/9/7(日)#二十四節気#白露0日#新月15日#東京都#天気痛#調査時間:1時~7時#「少し痛い~痛い~かなり痛い」と感じる方😨の割合83%
15時間前
2025/9/7(日)#二十四節気#白露0日#新月15日#東京都#天気痛#調査時間:1時~7時#「少し痛い~痛い~かなり痛い」と感じる方😨の割合83%
15時間前
-
 2025/9/7(日)#二十四節気#白露0日#新月15日#東京都#天気痛#調査時間:1時~7時#「少し痛い~痛い~かなり痛い」と感じる方😨の割合83%
15時間前
2025/9/7(日)#二十四節気#白露0日#新月15日#東京都#天気痛#調査時間:1時~7時#「少し痛い~痛い~かなり痛い」と感じる方😨の割合83%
15時間前
-
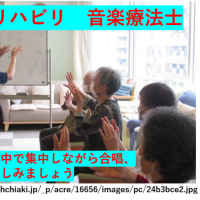 🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 ゴダイゴ/銀河鉄道999
1日前
🧑🎤「sing(歌う)」+「along(一緒に)」🧑🎤 ゴダイゴ/銀河鉄道999
1日前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます