人口減少局面に入ったとみられる中国。
神田外語大の興梠(こうろぎ)一郎教授は産経新聞に対し、中国の人口減少により国際的な影響力が低下する可能性があるとの見方を示した。
主な発言内容は以下の通り。
中国は改革開放以降、世界の工場として多くの外資企業を誘致し、国内総生産(GDP)世界第2位になるまでに経済成長を遂げたが、それを支えたのが低賃金の若年層だった。
人口減はその成長モデルが崩れることを意味する。
低廉な労働力を潤沢に提供できなくなり、経済成長に間違いなく影響が及ぶだろう。
伝統的に若者が老人を養う家族観がある上、生活費高騰もあり、子供を産みたがる若者は少ない。
成長維持には教育や技術革新で労働生産性を高める必要があるが、民間企業への締め付けも厳しくなり、今は若者が夢を持てない社会だ。
ゼロコロナ政策撤回の引き金が若者による抗議だったように、社会に閉塞(へいそく)感を感じる若者は多い。
16~24歳の失業率も約17%で高止まり。
頑張れば生活が良くなるとの雰囲気も見えづらい。
中国の少子高齢化の勢いは先進国より速く、社会保障を手厚くする必要があるが、過度な公共事業で地方政府の債務が膨らむなど課題山積。
言論統制や権力者に富が集中する構造も含め抜本的変革がなければ若者のやる気も出ないし、持続的成長は見込めない。
人口減は国際的な影響力や国力の低下につながる可能性もある。(聞き手 桑村朋)















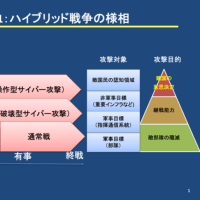



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます