 1963年制作、米映画
1963年制作、米映画製作:監督:ジョン・スタージェス
原作:ポール・ブルックヒル
脚本:ジェームズ・クラベル
W・R・バーネット
撮影:ダニエル・L・ファップ
音楽:エルマー・バーンスタイン
出演:スティーブ・マックィーン:ヒルツ(独房王)
ジェームズ・ガーナー:ヘンドリー(調達屋)
リチャード・アッテンボロー:バートレット(ビッグX)
ジェームズ・コバーン:セジウィック(製造屋)
チャールズ・ブロンソン:ダニー(トンネル・キング)
デビッド・マッカラム:アシュレイ・ピット(監視係)
ドナルド・プレザンス:コリン(偽造屋)
ハンネス・メッセマー:ルーガー(収容所、所長)
ジェームズ・ドナルド:ラムゼイ(先任将校)
解説
「OK牧場の決闘」(’57年)、「ゴーストタウンの決闘」(’58年)、「ガンヒルの決闘」(’59年)の決闘三部作や、「荒野の七人」(’60年)で切れ味の良い西部劇を作りつづけてきたジョン・スタージェス監督が、第二次大戦中の出来事。ドイツの誇る、第3捕虜収容所に収容された連合軍将校たちが、大脱走を敢行した一大史実の原作を元に描いた脱走劇です。
この原作は元イギリス軍将校、当時英空軍スピットファイヤー・パイロットで、ドイツ軍捕虜となり、実際にこの大仕事に参加していたポール・ブリックヒルによる脱走記録・和名「大脱走」で、1950年に出版された著書“ザ・グレート・エスケープ"は大ベストセラーとなりました。収容所の外にある森の位置まで100メートルも地下トンネルを掘り、276人もの捕虜を脱走させるという大胆不敵な計画と実行。逃げる連合軍捕虜たちとそれを追うドイツ軍、まさに全編、当時の背景を忠実に描き出したスリル万点の力作。
戦時国際法での捕虜の扱いは定められていますが、この作品では、この収容所はフェアーな環境にも見えますが、日本軍での捕虜の扱いでも、比較的良心的な所もあり、私の父の話ではありますが、当時ビルマ、スマトラに進駐していた事から、おそらくイギリス、オランダ軍の捕虜だと考えられますが、捕虜の母国赤十字からのパラシュート降下による空輸物資は、日本軍から見れば高価な物で、当然日本軍が、基本的に全て頂く物資ではなく、その事から情けない事に捕虜の方が、日本軍より良い食べ物を食べていたと言っていました。よって父は、捕虜とハリウッドのスター達の事を片言の英語で話し、仲良くなり、チョコレートやその他の食べ物を捕虜から頂く事が出来たと申していましたが、その事が、上官にバレタ時には、当然の如く、その場で袋叩きにあわされた物もあった様です。父も召集令状組では低い階級ではなかったのですが、一度見つかり同様な目にあわされ、致し方ないのは解っていても、当時若くてやんちゃな父には、受け入れ難く思ったのか「あいつの顔は、今でも覚えている」とかなり怒っておりました。敵、味方にかかわらず、国の命令で戦争に駆り出された物同士は、少しの時間を共有する事で、互いを理解して、友情とは言えないまでも、心通じあえるものが、あった事は、慰められる様でした。又、荷物の運搬作業に従事させるも、規定の労働時間が来ると、荷物はその場で置き作業を即辞める文化には驚いたとも言っていました。そんな話からも全ての収容所が、酷かった事ではなかった様ですね。
製作者兼監督は「荒野の3軍曹」のジョン・スタージェス。撮影は「ウエスト・サイド物語」でアカデミー賞を獲得したダニエル・L・ファップ。脚色は「アスファルト・ジャングル」の著書で知られるW・R・バーネットとジェームズ・クラベルが共同で担当している。音楽は「終身犯」のエルマー・バーンスタイン。
「荒野の七人」で人気者となったスティーブ・マックィーン、チャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーンの3人を再起用し、更に「噂の二人」(’61年)のジェームズ・ガーナー、「ナポレオン・ソロ」シリーズのイリヤ・クリヤキンことデビッド・マッカラムと、豪華な顔ぶれです。
又、大脱走を指揮するバートレットにイギリスの名優で後に「遠すぎた橋」(’77年)や「ガンジー」(’82年)で監督も手がけるリチャード・アッテンボローが加わります。近年では「ジュラシック・パーク」(’93年)の博士役を演じています。
それに、多くの映画の常連、スキンヘッドのドナルド・プレゼンスと、「ロベレ将軍」のハンネス・メッセマーなど。主役級の俳優が勢ぞろいの過去例のない超大作。
実生活ではアマチュアのオートバイレーサーだったスティーブ・マックィーンがオートバイで爆走するシーンは名場面の一つになっています。
そういえば、この映画で有名な、スティーブ・マックィーンが、バイクで鉄条網を飛び越えるシーンですが、あれは、かなり長い間マックィーン本人が、運転操作していたと思われていましたが、実は、このジャンプシーンは、スタントマンが変わってやっていた事をマックィーン自信が、生前語っていました。又、バイクを奪われるドイツ兵は、こっそりマックィーンが、演じていたのだそうです。
マックィーンは後年、「パピヨン」(’73年、フランクリン・J・シャフナー監督、ダスティン・ホフマン共演)でも脱獄を繰り返す役で主演していました。
このロケについてきたジル・アイアランドは当時デビッド・マッカラム夫人でした。でも、このロケで知り合ったチャールズ・ブロンソンと恋に落ちてゴールイン。マッカラムとブロンソン。タイプが正反対の二人。ジルの趣味も面白いものが、ありますね。そのジルは、何年か前に亡くなり、それまでブロンソンとは、有名なおしどり夫婦で通しました。別れたマッカラムとも良い友人だった様です。3人の人生を変えた映画でもあるのです。
果たして大脱走は成功となるのか。逃げきる者、逮捕される者、銃殺される者と運命の分かれ道が明暗を分けますが、この男達の使命感や意志の強さ行動力そして潔い行動力からも爽快感が残ります。
テクニカラーの緑原を往く独軍の車列。バーンステインの勇壮なマーチが高鳴り、“THE GREAT ESCAPE”の真っ赤なタイトルが浮かぶ。幕開けから1分、早くも武者震いが抑えられない。今となっては、マックィーン、コバーン、ブロンソンと亡くなってしまい、映画の中でしか会えない事からも寂しい気がしますが、その若き日の我等のシネマ・ヒーローが一同に会し、捕虜収容所からの脱走劇を繰り広げる男性娯楽活劇の金字塔といえるでしょう。
又、エルマー・バーンスタインの軽快なテーマ曲も大ヒットしました。
物語あらすじ
第2次大戦末期。ドイツの北部、サガン近郊の捕虜収容所に、連合軍の戦争捕虜が移送されてくる。彼らは過去に何度も脱走を試みた要注意メンバーばかり。その処遇に手を焼く独軍は、彼らを1ヶ所に集め、
 特別な監視体制で脱走を防ぐ計画だった。そして、この第三捕虜収容所に連合軍空軍の捕虜が何台ものトラックで送り込まれてきた。
特別な監視体制で脱走を防ぐ計画だった。そして、この第三捕虜収容所に連合軍空軍の捕虜が何台ものトラックで送り込まれてきた。過去17回の脱走歴を誇る米空軍のヒルツ大尉は、来た早々、周囲を取り囲む鉄条網に監視の死角を見つけ、ボールを拾う振りを装って鉄条網に近づくが、折悪く巡回兵に見つかり、
 監視塔からの銃撃を足元に喰らう。「何をしている」駆けつけたルーガー所長に、「脱走しようとしていたんだ」と、ヒルツ。独房20日間の罰。
監視塔からの銃撃を足元に喰らう。「何をしている」駆けつけたルーガー所長に、「脱走しようとしていたんだ」と、ヒルツ。独房20日間の罰。仲間のアイブスもドイツ兵をからかった罰で独房20日間。到着早々独房送りとなるのだった…。
又、トンネル掘りの名人、ダニー(チャールズ・ブロンソン)は、「森までは60メートル、いや90メートルか、長いな」と、早くも計画を頭で計算した。
そこは周りを鉄条網で張り巡らせた広大な収容所だった。所々に設置された監視塔からはドイツ兵が銃を構えて見張っている。
ルーガー所長(ハンネス・メッセマー)は、連合軍捕虜の指揮官ラムゼイ大佐(ジェームズ・ドナルド)に言い渡した。
「過去4年間、我が軍は脱走捕虜の再収容に多大な兵力と時間を費やしてきた。この収容所は脱走経験者ばかりを収容するために作った。脱走は許さん」
ラムゼイ大佐は、「ありがたい心遣いだ。だが、脱走は全将兵の義務だ。何度失敗しようとも脱走を企てる。それが我々に残された唯一の任務である」と言い返す。
「腐った卵はひとつの籠に入れて見張るのだ。ここにはスポーツ、図書館、娯楽室がある。園芸用具も貸す。そういうことにエネルギーを使うことだ」ルーガー所長は言い放った。
この捕虜達に心強い味方が来る。ゲシュタポがバートレット(リチャード・アッテンボロー)を収容所に連行してきたのである。バートレットはこれまでに多くの脱走を指揮してきた男だ。
「今度、脱走して逮捕されたら銃殺だぞ。分かってるな」ゲシュタポは捨て台詞を残して去った。しかし既にバートレットは脱走を計画していた。ラムゼイ大佐に言う。そしてその意義は、後方撹乱と示す。
「かってなかった大規模な脱走をやります。200~300名をドイツ中に散らす」無謀にも思える計画であり、驚き顔を隠せない関係者に、具体安を更に示す。
「森に一番近いのは104号棟と105号棟だ。第一トンネルは105号棟から東に向けて掘る。100メートルある。縦に9メートル掘り、横へ進める。これで音は消せる」バートレットが力説する。
さっそく、役割が分担された。洋服屋、道具屋、調達屋とそれぞれ勇気と闘志を持ち実行を承諾する。
トンネル掘りの名人、ダニーはストーブの土台を偽装し、下穴を掘る音は外部作業のくい打ちの音と合わす事で見破られない様にし、下穴を掘り始めた。


独房から出てきたヒルツとアイブスはまったく別の脱走計画を立てた。監視塔の死角を見つけ、鉄条網の地面を1メートル掘ってそこから向う側へ抜け出すというものだ。そして実行するも再び独房へ逆戻り。
トンネルは、ドイツの監視を巧みな連係により、見事にカムフラージュされ進められた。
掘りは進んでいき、掘った土の処理は服の内側に隠した袋に入れ、外でズボンの中から捨てるという繰り返しの根気のいる作業となる。
そんな中、トンネル内に空気を送るダクトとふいごを器用なセドウィック(ジェームズ・コバーン)が作り、
 ヘンドリー
ヘンドリー
 (ジェームズ・ガーナー)はドイツ将校と巧みに仲良しになったふりをして、隙をみて盗む事から身分証明書、切符などを偽造した。
(ジェームズ・ガーナー)はドイツ将校と巧みに仲良しになったふりをして、隙をみて盗む事から身分証明書、切符などを偽造した。バートレットは脱走の必然情報を得る為、難題をヒルツに要請した。「一人なら脱走できる。君は脱走して森の外の地理情報を得てきてくれないか」 「つまり、脱走して又戻れと?」 「そうだ」
一旦は断ったヒルツだが、アメリカ独立記念日でお祭り騒ぎをしている時に、
 トンネルの一つがドイツ軍に見つかり、望みを絶たれた様に思い込み、自棄状態を起こし、突発的に鉄条網をよじ登り逃げようとしたアイブスが銃殺されるの目の当たりに見た事から、バートレットの要求を聞き入れるのであった。
トンネルの一つがドイツ軍に見つかり、望みを絶たれた様に思い込み、自棄状態を起こし、突発的に鉄条網をよじ登り逃げようとしたアイブスが銃殺されるの目の当たりに見た事から、バートレットの要求を聞き入れるのであった。トンネルはあと二つ残っている。「ハリー」と名づけられたトンネル掘りが昼夜交代で断行された。土壌が柔らかく落盤が相次ぐ。トンネルの支柱とする材料のため、壁の板、ベッドの下板、天井の板とドイツ側に気付かれない、あらゆる板が投入されていく。
トンネル掘りの名人ダニーは狭所恐怖症である事からいざ、全員が脱走となった時、パニックを起こし迷惑をかけないかと悩むのだった。
そんな夜、ヒルツが鉄条網を破って脱走した。しかし、まもなく捕まり、独房入り。しかし、ヒルツはバートレットの要求どおり森の外側の地理をつかんできたのだった。
やがて、トンネルは完成にこぎつけた。ヒルツも独房から出てきて、いよいよ決行の夜がきた。監視塔のライトを避けてトンネル「ハリー」の棟へぞくぞくと集まる捕虜たち。まず、ヒルツがトロッコでトンネルの先端まで行く。そこから僅かに残された縦穴を地表へ抜く。地表へそっと顔を出し、周りを見ると、何と、森まではまだ6メートルもあり、銃を構えた歩哨が歩いているのが見える。
直ぐさま穴の下に待機しているバートレットとマクドナルドに不具合を伝える。しかし各証明書の日付が今日である為、決行するしかない。ヒルツの合図で一人づつ地表へ抜け出し森の中へ走りこむ事となる。途中空襲等で照

 明が消されるも、それらも利用して、76名が脱出した時、あせった一人の物音に気付いた歩哨がやってきてトンネルが発覚してしまった。ドイツ軍はただちに脱走者に追ってを差し向ける。
明が消されるも、それらも利用して、76名が脱出した時、あせった一人の物音に気付いた歩哨がやってきてトンネルが発覚してしまった。ドイツ軍はただちに脱走者に追ってを差し向ける。 列車に乗るバートレットとマクドナルド、そしてアシュレイ(デビッド・マッカラム)ヘンドリーは目の見えないプライス(ドナルド・プレゼンス)をかばいながらの逃走となる。自転車を盗み、のんびり田園を走っていくセドウィック。ボートに乗り河へ漕ぎ出すダニー達。そして、ドイツ兵のオートバイを強奪し爆走するヒルツ。
列車に乗るバートレットとマクドナルド、そしてアシュレイ(デビッド・マッカラム)ヘンドリーは目の見えないプライス(ドナルド・プレゼンス)をかばいながらの逃走となる。自転車を盗み、のんびり田園を走っていくセドウィック。ボートに乗り河へ漕ぎ出すダニー達。そして、ドイツ兵のオートバイを強奪し爆走するヒルツ。

脱走者たちは目的に向かいそれぞれ散っていった。しかし、ドイツ兵とゲシュタポの追求は甘くはない。
列車から乗り換える際には、ドイツの検問。顔がわれた事に気付いたアシュレイは、バートレットとマクドナルドを助ける為、自ら犠牲となる。又助けられたバートレットとマクドナルドもバスに乗り込もうとする際、巧みな検問にひっかかり逮捕され、その他の逮捕者のもとに送られる。アッテンボローとゴードン・ジャクソンが「我々は間違っていなかった」ってしみじみ語り合うシーンは最も心に残りました。やがて、トラックにて護送の間に偽りの休憩地で公約通り銃殺される。
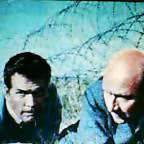 又、ヘンドリーとプライスは、ドイツ空軍の練習機を強奪し、スイス国境を目指し飛行に成功したかに思えたが、機が故障、国境手前で不時着するも、ドイツ軍に見つかりプライスは銃撃に倒れ、ヘンドリーに感謝の言葉を残し、息耐える。見届けたヘンドリーもその場で拘束されるのでした。
又、ヘンドリーとプライスは、ドイツ空軍の練習機を強奪し、スイス国境を目指し飛行に成功したかに思えたが、機が故障、国境手前で不時着するも、ドイツ軍に見つかりプライスは銃撃に倒れ、ヘンドリーに感謝の言葉を残し、息耐える。見届けたヘンドリーもその場で拘束されるのでした。 そしてヒルツも、
そしてヒルツも、
 国境線で追い 詰められ、国境越えを図り鉄条網突破を敢行するも、失敗する。
国境線で追い 詰められ、国境越えを図り鉄条網突破を敢行するも、失敗する。そんな中、セドウィックは、途中立ち寄った対枢軸国地下抵抗組織偽装のカフェにてレジスタンスの急襲に遭遇し、後パルチザンの助けを借り、まんまとスペインへと逃げ切るのであった。
同じく、ボートにて逃走したダニー達も、湾に無事到着し、ドイツ圏外へ出航する船に乗り込む事に成功する。
脱走したのは76名、その多くは逮捕され、あるいは銃殺された。指揮者のバートレット以下50名が機関銃の的になり、ヘンドリー以下11人が送還され、逃げきったのはたった15人であった。
収容所ではラムゼイ大佐に死亡者の名簿が手渡された。ラムゼイ大佐は苦渋に満ち、脱走出来なかった捕虜たちに死んだ者の名前を発表した。
そこに、オートバイで国境越えを図り、鉄条網を越えることができなかったヒルツが戻ってきた。そして決められた如く、自らも独房へと。そのうち、名シーンの一つでもある、ヒルツの独房からは壁にボールをぶつける音が以前と変らず力強く聞こえてくるのだった。

物語の特異性も然る事ながら、映画の方向性は的確に出すも極力戦争の残虐性を見せない演出や主演級の若き大スター達のその後の個性を上手く引き出し導かした演出も見事につきる。女優の起用一切なされていないのであるが、男同士の絆や当時の風景の美しさも一つの清涼感をもたらせ、全体的に力強く、爽やかに感じられた作品であった。
又今では、我等世代には、銀幕の中で彼らに出会える喜びから、映画の同窓会の様な感覚にもなる数少ない貴重な娯楽大作の一つになりました。














と何時も思います。
新鮮なんですね~。
オールスター作品と言うこともあり、
アカデミー会員も映画の素晴しさを
見逃したんじゃないでしょうか・・。
シナリオに関しては
オールスター作品なので気を使ったところは
ありますが、撮影、音楽、勿論・名優達の演技
とどれをとっても最高に面白い映画です。
SUKIPIOさんのブログ・・
丁寧な書き込み感心しております。
これからも期待しております。
旅の話も待っています。
先日、この映画が、テレビにて放映されていましたね。
あまり、戦争映画は、見ないのですが、SUKIPIOさんが仰る通り、戦場の場面が少なく、見終わった後には、スポーツ観賞の様な爽やかさの様なものが、感じられました。
痛快さとほのぼのとした中、戦争の非情さが、上手く織り込まれた作品ですね。
スティーブ・マックィーン、チャールズ・ブロンソンは、私でも知っています大スターですし、皆さんが凄く若々しく、カッコ良く、やはり味のある役者揃いで、物語より俳優を見入ってしまいました。
特にチャールズ・ブロンソンは、愛妻家でしたので、私には理想の亭主像なんですが、亡くなられた事は、非常に残念でなりません。
でも、スクリーン上での元気な姿を見られました事で、何か元気を頂いた様な気がしております。
この時代の映画は、これからも見続けたいものですね。
私も、この映画は、1970年頃ロードショーしておりましたのを、かわきりに何度も見ておりますが、最近は出演者の多くが亡くなられた事で寂しくもなり、時代の流れの速さに戸惑っている次第です。
しかし、この作品での、過ってのスター達の若く、元気な姿を見られる事で彼等の作品とリアルタイムに生きていた事が、何故か誇らしく思える事もありますね。
最近の若い人達から見れば、スティーブ・マックィーン、ジェームズ・ガーナー、ジェームズ・コバーン、チャールズ・ブロンソン、彼等のイメージが重なる人がおられる様なのですが、それも寂しい限りです。
私達の世代では、彼等それぞれの役作りから東洋人に無い西洋の個性に憧れ、無理とは解っていましても仕草やファッション、スタイルに近づきたいと思った事もありました。だからこそ、彼等の個性の違いも理解出来たのでしょうか。
最近の映画はよく見ておりませんので、私自身が理解しようとしていないのか、深くは解りませんが、今活躍されている若い俳優は器用なのか色々なジャンルに出演されており、上手く演じておられますが、その分個性と申しますか自身の生き様、アクをも消している様にも思えます。これも、過去の様な映画の手作り感が無くなった影響かもしれません。
少し生意気な表現になりましたが、今少し役者に比重をかけた映画制作を希望したいですね。
チャールズ・ブロンソンは、当時のロシア移民の子(詳しくはリトアニア、リプカ・タタール人の子孫)としてアメリカで生まれ、本作品でもロシア語を話せる処にその片鱗が窺えました。
俳優になる前は、炭鉱夫、ボクサーから、陸軍航空隊を志願し、B-29の射撃手として東京大空襲にも参戦し、戦後、美術学校に入学し、ここで舞台の裏方となり、エキストラも経験し芝居に目覚めていき、その後にニューヨークに行き、レンガ職人やウェイターをしながら舞台に端役として出演するようになる。以後、カリフォルニアに移り、本格的に演技を勉強し、その様に苦労されて俳優になった人ですので、演技にもその人としての味わいが、垣間見る様にも思えます。
監督のジョン・スタージェスに見出された事が、ブロンソンの俳優人生を変え、良き巡り合わせになったのでしょう。
私自身も、タフなイメージがあり、亡くなられた事が、ピンとこない現状なのですが、81歳だったんですね。
又、本作品を見れば、なお更そう思いますね。
愛妻家であった事からも、先に夫人のジル・アイアランドを亡くされた事が、こたえられたのではないかとも、勝手に思っている次第です。
私も、そんな意味からも、aniseさんの様にこの映画を見る度に元気を貰っています。本当に良い作品です。
脱走捕虜を処刑した責任者に仕返しをする「復讐編」も見ましたがやはり、本作品から見ると格落ちしますね。
大作ですからまだ拝見している途中ですが、ゆっくり読ませて戴きますますね。
最近は、哀愁の様な気もしています。
自身の若い時代を思い出す、それに似た様な感じなのですが、出演者の勇ましく、カッコの良さを見れば、余計にスクリーン上でしか、彼等を見られない事が、寂しくもありますね。
それと、これは、最初に見ました時からなのですが、背後の風景も何故か好きな映画でした。
効果的な音楽、スポーティな描写、敵方の寛容さ等が入り交じっていたからでしょうか。
その一面に於いて、脱走失敗者の悲劇も見逃すことはできませんでしたけど、、。
なるべく、戦争の悲惨なシーンは少なくしている様に思います。オールスターの共演ですので、難しい面はあったと、想像しますが、個性もよく出ており、全てに応えて頂いた様な作品でした。
痛快な進行の中、やはり、敵・味方無く戦争の空しさが垣間見える映画でもありましたが、ラストシーンのマックィーンの壁での一人キャッチボールは、救われる気がいたしました。
TB&コメント、ありがとうございました~。
う~ん、私もみなさんと同様にもっと楽しく観られたらよかったな~と思いました。
どうも、殺害された捕虜のことを思うと、なんていうか、それまでのドキドキやらが一気に重くなってしまって・・・。
でも、改めてまた観てみたいと思いました!
仰るとおり、実際は、多くの捕虜が犠牲になられた事と思いますし、もっと悲惨な事であったと思います。
そう云った事を和らげながら、彼等の個性と自由への意思の強さを魅せる事で史実を印象づける目的もあったのでしょうか。
残念なのですが戦争映画は、どうしても、その様な場面は必要不可欠でしょうね。