流鏑馬とは「やぶさめ」と読むのだが、最近までこの漢字が書けなかった。
走る馬の上から鏑矢で的を射る射芸で、平安時代から鎌倉時代にかけて
武士のあいだでは盛んに行われていたそうだ。
そういえば、大河ドラマか時代劇のTVドラマかなんかで、
この流鏑馬のシーンを何度か観たことがあるような気がする。
まあ、武士のいわゆる嗜みとして流行していたのだろう。
さて、体育の日の今日(10/13)、高田馬場の流鏑馬が奉納される日である。
都の西北早稲田の森に程近い(というか、かつてはそのものだったんじゃないか?)
都立戸山公園において、穴八幡宮に奉納されるという流鏑馬が公開されるのだ。
上京した頃から、一度、これを見たかったのだが、今日、ついに念願かなった。
武士の格好をした人が、駆けとる馬の上から弓矢で的を射るすごい伝統行事なんぞ。
と、数日前から子供達と話をして一緒に行こうと、結構楽しみにしていたのだが、
今日になって、兄も妹も友達と遊ぶから行かないと言い出し、ふられてしまった。
子供等に相手にされなくなった親父は、仕方なく一人で出かけることになった。
まあ、身軽になった分、好きなように歩き回れるからいいか!

穴八幡神社から夏目坂を会場に向かう騎馬行列
東京メトロ「早稲田」駅から早稲田通りを西にすぐのところに穴八幡神社がある。
この神社の階段の脇に、「高田馬場の流鏑馬」という案内板がある。
それによると、高田馬場の流鏑馬は・・・
享保13年(1728年)、八代将軍徳川吉宗が、世嗣の疱瘡平瘉祈願のため、
穴八幡神社に奉納した流鏑馬を起源とし、以来、将軍家の厄除けや若君誕生祝いに
高田馬場で流鏑馬が奉納されるようになったものとされている。
明治維新以降は中断し、昭和9年の皇太子誕生祝いのために再興され数回行われたが、
先の大戦のため再び中断された。
昭和39年流鏑馬の古式を保存するため、水稲荷神社境内で復活し、
昭和54年からは都立戸山公園内に会場を移して、毎年10月10日の体育の日、
高田馬場流鏑馬保存会の人々によって公開されている。
古式豊かで勇壮な高田馬場の流鏑馬は、小笠原流によって現在に伝えられており、
貴重な伝統行事である。
昭和63年3月4日、新宿区の無形民俗文化財に指定されている。
・・・とのことである。
午前中、手伝いに参加していた市響ジュニアオーケストラの練習が長引いたため、
出発が大幅に遅れ、早稲田駅を降りた時は既に13時半をゆうに回っていた。
駅の階段を慌てて地上に出た途端、流鏑馬の装束で身を固めた射手と馬が目に入る。
今まさに穴八幡神社を出て、流鏑馬の会場となる都立戸山公園に向かうところだ。
聞けば、夏目坂を上って、ぐるっと国立医療センターや統計センター前を経由して
箱根山通りを下って会場の戸山公園に向かうとのことである。
早めに会場入りして場所取りしようと思ったが、行列に同行した方が面白そうだ。
で、私のように一緒に歩く見物人はやっぱりそれなりにいるのだが、
年配の方が多いのと、いわゆる外国人が目に付いた。
こういう日本古来の伝統的、儀式的な行事は、文化の異なる外国人にとっては
とても興味深いイヴェントのようである。
道端でシャッターを切っていたら、何か話しかかれらたが何のことやらわからん。
“オー・アイム・ソーリー、アイ・キャント・スピーク・イングリッシュ、
オンリー・ジャパニーズ!”などとやり返したら。
「あ、じゃあ日本語で。・・・この先、戸山公園にはどうやって行くのですか?」
といきなり日本語でしゃべるもんだから、ちょっとたまげたが、
「一本とられましたね。・・・ここをこういけば良いですよ。」
「おーっ!ジュードーですね?ありがとう。」と言って、足早に先を急いで行った。
この行列と行動を共にしていては、流鏑馬の会場では良い見物場所が取れないそうだ。
・・・まあ、今から行っても、状況は変わるまい・・・
案の定、というかなんというか、戸山公園の流鏑馬会場は見物人でいっぱいだった。
馬場の横は人が幾重にも並んでいて、さながら人の壁である。
しょうがないので、馬場と人混みから離れた、少し地面が高くなったところから、
しかし、全体が見渡せるところから、先ずは、遠目に見物することにした。


素人の私からすれば、もう、馬に乗って走るってことだけでも凄いことだが、
その上、馬上で弓を射るってんだから、これはタダごとではない。
会場では、多分、ご自身もかつて射手であったのではないかと思われる
長老格のような司会者が、いろいろと解説していらっしゃったが、
今日の射手は、この道四十年近いベテランから、未だ二年足らずの若輩者まで
広い世代が十人程度登場するということである。
射手の名前や馬の名前を、都度、丁寧に話されていたが、よく覚えていない。
やることは、会場の端から端に設けられた直線の馬場を一気に駆け抜けながら、
途中に設けられた三箇所の的を、順に射抜いていくというもので、
射手を変え馬を変え、これがひたすら繰り返されるだけのことなのだが、
とにかく、初めて目の当たりにする私、かなりの興奮を覚え、やや熱くなった。
と同時に、こりゃなかなか大変なことだと思った。
今日は、結果的に三つの的をパーフェクトに射抜いた射手はいなかったが、
二つまで的を射抜いたのは何度も見た。
私など、的が射抜かれて割れると、その都度、素直に歓声をあげた。
花火大会で「たまや~!」とかいう感じである。
しかし、私の隣で観ていたおじいさんは、射手が鏑矢を外すたびに
「下手くそっ!昨日あんだけ練習したのに、終業が足りんぞ!」と
一人一人の射手を野次っていた。
どうも関係者のようであるが、見る人でその反応も違うようだ。
このじいさん、とにかく口が悪く、姿勢が悪いとか、手許がもたもたしとるとか、
厳しいお言葉の連発であった。
特に、鏑矢を射たもののがはずれたときよりも、弓を切ってしまったり、
矢取りでモタモタしたり、タイミングを失して射ることができなかったりすると、
「お話になりませんな・・・」と手厳しかった。
このあたりは、射手に問題があるのだろうが、馬との相性もあるようで、
馬にもメチャメチャ速いのがいて、こいつが駆け出すとどうも仕事させてもらえない。
射手は三つの的それぞれに到達するまでの間、矢を取り構えて討つという動作を
三回繰り返さなくてはならないが、馬の足が速すぎて間に合わなかったりする。
これには、この道二十数年や三十数年の大ベテランといわれる免許保持者も
なかなかその腕前を披露できないでいたようだ。

颯爽と馬を駆り、今まさに射んとす
まあ、失敗話ばかりしていてもしかたない、この流鏑馬の会の後半は見応えがあった。
あと一本でパーフェクト!という見せ場が続いたからであるある。
そういう時は、観衆の気持ちも「当たれ!」という無言の“気”が自然と生まれ、
この馬場一体の時間が止まるような、空気が張りつめるような、そんな感じになる。
そこに、的が射抜かれて「スコーン」とか「カーン」と快く鳴り響いて割れると、
「おーっ!」という歓声と拍手喝采が巻き起こる。
なんともいえない瞬間だ。
隣ので見物している口の悪いじいさんも、射手が綺麗な形で的を射抜いたときは、
目を細めて「それでええんじゃ。それでこそ武士じゃ。」とうなずいたりしていた。
この神事は、高田馬場流鏑馬保存会という団体が伝統を受け継いでいるそうだが、
この技(というか武芸というか)を維持していくことは並大抵ではないのではないか?
新宿区の無形民俗文化財に指定されているとはいうが、次代を担う後継者を
しっか育てていって、いつまでも受け継がれ維持されることを願いたいと思った。
今日は流鏑馬には登場しなかったが、馬を駆る小学生の姿もお披露目され、
彼が将来の射手として活躍するのだなと頼もしく感じた。
流鏑馬が終わると、再び行列になって穴神社に戻って奉納である。
見物人の多くはここでお開きとなるが、私は最後までついていったが、
穴八幡神社での奉納は、やはり神事である。
何か侵しがたい雰囲気があった。
それにしても、これは十分に一見の価値があった。
多少、無理強いしてでも、子供達を連れて来て見させるべきだったと思った。

穴八幡神社の流鏑馬像
 ←励ましの一本締めで一押しお願いします
←励ましの一本締めで一押しお願いします
走る馬の上から鏑矢で的を射る射芸で、平安時代から鎌倉時代にかけて
武士のあいだでは盛んに行われていたそうだ。
そういえば、大河ドラマか時代劇のTVドラマかなんかで、
この流鏑馬のシーンを何度か観たことがあるような気がする。
まあ、武士のいわゆる嗜みとして流行していたのだろう。
さて、体育の日の今日(10/13)、高田馬場の流鏑馬が奉納される日である。
都の西北早稲田の森に程近い(というか、かつてはそのものだったんじゃないか?)
都立戸山公園において、穴八幡宮に奉納されるという流鏑馬が公開されるのだ。
上京した頃から、一度、これを見たかったのだが、今日、ついに念願かなった。
武士の格好をした人が、駆けとる馬の上から弓矢で的を射るすごい伝統行事なんぞ。
と、数日前から子供達と話をして一緒に行こうと、結構楽しみにしていたのだが、
今日になって、兄も妹も友達と遊ぶから行かないと言い出し、ふられてしまった。
子供等に相手にされなくなった親父は、仕方なく一人で出かけることになった。
まあ、身軽になった分、好きなように歩き回れるからいいか!

穴八幡神社から夏目坂を会場に向かう騎馬行列
東京メトロ「早稲田」駅から早稲田通りを西にすぐのところに穴八幡神社がある。
この神社の階段の脇に、「高田馬場の流鏑馬」という案内板がある。
それによると、高田馬場の流鏑馬は・・・
享保13年(1728年)、八代将軍徳川吉宗が、世嗣の疱瘡平瘉祈願のため、
穴八幡神社に奉納した流鏑馬を起源とし、以来、将軍家の厄除けや若君誕生祝いに
高田馬場で流鏑馬が奉納されるようになったものとされている。
明治維新以降は中断し、昭和9年の皇太子誕生祝いのために再興され数回行われたが、
先の大戦のため再び中断された。
昭和39年流鏑馬の古式を保存するため、水稲荷神社境内で復活し、
昭和54年からは都立戸山公園内に会場を移して、毎年10月10日の体育の日、
高田馬場流鏑馬保存会の人々によって公開されている。
古式豊かで勇壮な高田馬場の流鏑馬は、小笠原流によって現在に伝えられており、
貴重な伝統行事である。
昭和63年3月4日、新宿区の無形民俗文化財に指定されている。
・・・とのことである。
午前中、手伝いに参加していた市響ジュニアオーケストラの練習が長引いたため、
出発が大幅に遅れ、早稲田駅を降りた時は既に13時半をゆうに回っていた。
駅の階段を慌てて地上に出た途端、流鏑馬の装束で身を固めた射手と馬が目に入る。
今まさに穴八幡神社を出て、流鏑馬の会場となる都立戸山公園に向かうところだ。
聞けば、夏目坂を上って、ぐるっと国立医療センターや統計センター前を経由して
箱根山通りを下って会場の戸山公園に向かうとのことである。
早めに会場入りして場所取りしようと思ったが、行列に同行した方が面白そうだ。
で、私のように一緒に歩く見物人はやっぱりそれなりにいるのだが、
年配の方が多いのと、いわゆる外国人が目に付いた。
こういう日本古来の伝統的、儀式的な行事は、文化の異なる外国人にとっては
とても興味深いイヴェントのようである。
道端でシャッターを切っていたら、何か話しかかれらたが何のことやらわからん。
“オー・アイム・ソーリー、アイ・キャント・スピーク・イングリッシュ、
オンリー・ジャパニーズ!”などとやり返したら。
「あ、じゃあ日本語で。・・・この先、戸山公園にはどうやって行くのですか?」
といきなり日本語でしゃべるもんだから、ちょっとたまげたが、
「一本とられましたね。・・・ここをこういけば良いですよ。」
「おーっ!ジュードーですね?ありがとう。」と言って、足早に先を急いで行った。
この行列と行動を共にしていては、流鏑馬の会場では良い見物場所が取れないそうだ。
・・・まあ、今から行っても、状況は変わるまい・・・
案の定、というかなんというか、戸山公園の流鏑馬会場は見物人でいっぱいだった。
馬場の横は人が幾重にも並んでいて、さながら人の壁である。
しょうがないので、馬場と人混みから離れた、少し地面が高くなったところから、
しかし、全体が見渡せるところから、先ずは、遠目に見物することにした。


素人の私からすれば、もう、馬に乗って走るってことだけでも凄いことだが、
その上、馬上で弓を射るってんだから、これはタダごとではない。
会場では、多分、ご自身もかつて射手であったのではないかと思われる
長老格のような司会者が、いろいろと解説していらっしゃったが、
今日の射手は、この道四十年近いベテランから、未だ二年足らずの若輩者まで
広い世代が十人程度登場するということである。
射手の名前や馬の名前を、都度、丁寧に話されていたが、よく覚えていない。
やることは、会場の端から端に設けられた直線の馬場を一気に駆け抜けながら、
途中に設けられた三箇所の的を、順に射抜いていくというもので、
射手を変え馬を変え、これがひたすら繰り返されるだけのことなのだが、
とにかく、初めて目の当たりにする私、かなりの興奮を覚え、やや熱くなった。
と同時に、こりゃなかなか大変なことだと思った。
今日は、結果的に三つの的をパーフェクトに射抜いた射手はいなかったが、
二つまで的を射抜いたのは何度も見た。
私など、的が射抜かれて割れると、その都度、素直に歓声をあげた。
花火大会で「たまや~!」とかいう感じである。
しかし、私の隣で観ていたおじいさんは、射手が鏑矢を外すたびに
「下手くそっ!昨日あんだけ練習したのに、終業が足りんぞ!」と
一人一人の射手を野次っていた。
どうも関係者のようであるが、見る人でその反応も違うようだ。
このじいさん、とにかく口が悪く、姿勢が悪いとか、手許がもたもたしとるとか、
厳しいお言葉の連発であった。
特に、鏑矢を射たもののがはずれたときよりも、弓を切ってしまったり、
矢取りでモタモタしたり、タイミングを失して射ることができなかったりすると、
「お話になりませんな・・・」と手厳しかった。
このあたりは、射手に問題があるのだろうが、馬との相性もあるようで、
馬にもメチャメチャ速いのがいて、こいつが駆け出すとどうも仕事させてもらえない。
射手は三つの的それぞれに到達するまでの間、矢を取り構えて討つという動作を
三回繰り返さなくてはならないが、馬の足が速すぎて間に合わなかったりする。
これには、この道二十数年や三十数年の大ベテランといわれる免許保持者も
なかなかその腕前を披露できないでいたようだ。

颯爽と馬を駆り、今まさに射んとす
まあ、失敗話ばかりしていてもしかたない、この流鏑馬の会の後半は見応えがあった。
あと一本でパーフェクト!という見せ場が続いたからであるある。
そういう時は、観衆の気持ちも「当たれ!」という無言の“気”が自然と生まれ、
この馬場一体の時間が止まるような、空気が張りつめるような、そんな感じになる。
そこに、的が射抜かれて「スコーン」とか「カーン」と快く鳴り響いて割れると、
「おーっ!」という歓声と拍手喝采が巻き起こる。
なんともいえない瞬間だ。
隣ので見物している口の悪いじいさんも、射手が綺麗な形で的を射抜いたときは、
目を細めて「それでええんじゃ。それでこそ武士じゃ。」とうなずいたりしていた。
この神事は、高田馬場流鏑馬保存会という団体が伝統を受け継いでいるそうだが、
この技(というか武芸というか)を維持していくことは並大抵ではないのではないか?
新宿区の無形民俗文化財に指定されているとはいうが、次代を担う後継者を
しっか育てていって、いつまでも受け継がれ維持されることを願いたいと思った。
今日は流鏑馬には登場しなかったが、馬を駆る小学生の姿もお披露目され、
彼が将来の射手として活躍するのだなと頼もしく感じた。
流鏑馬が終わると、再び行列になって穴神社に戻って奉納である。
見物人の多くはここでお開きとなるが、私は最後までついていったが、
穴八幡神社での奉納は、やはり神事である。
何か侵しがたい雰囲気があった。
それにしても、これは十分に一見の価値があった。
多少、無理強いしてでも、子供達を連れて来て見させるべきだったと思った。

穴八幡神社の流鏑馬像
 ←励ましの一本締めで一押しお願いします
←励ましの一本締めで一押しお願いします











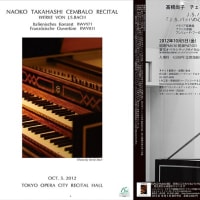
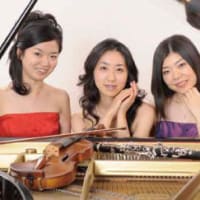



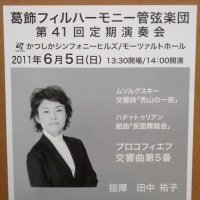



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます