英国音楽随想(04/01/03)
記念すべき第1回は、私の敬愛するエルガーの2番を取り上げます。CDを持っていない人は今すぐCD屋さんに走りましょう。売ってないかもしれませんが(苦笑)。
実は私が最初にハマったのは交響曲2番ではなく交響曲1番の方でした(いずれ取り上げるでしょう)。まあ、一般的な人はそうなんだと思いますが。ボールト翁は違ったようですね。最初から2番の方を評価していたようです。で、この交響曲にはまるきっかけになったのが、バルビローリ指揮ハレ管の1955年録音(EMI)でした。(これより新しい録音もあります。おまちがえのないよう。)しかしこのハレ管がヘボいこと....。まあ、指揮者のテンポ設定も凄まじいのですが。
それで、この演奏のどこが良かったかというと、第4楽章のコーダ、エルガー自身のことばによると、「荘重で光り輝くばかりの静けさ」で第1楽章第1主題が回想されるシーンです。私は勝手にこの部分を「天使の告別」の場面と呼んでいます。(ジェロンティアスの夢みたいですね。)
この天使の告別の場面にはエルガーが好んで用いたハープ2台が第1主題の回想の伴奏として書かれているのですが、この1955年の演奏ではそのハープの美しいこと!。歓びの精霊(註1)がこの交響曲の主人公(エルガー自身でしょうか)に別れを告げ、ハープの上行グリッサンドとともに空へ帰っていくところは何度聴いても涙を禁じ得ません。さらに木管と弦からクラリネットの2重奏に旋律が引き継がれるとその後ろに、天使の羽が落ちてきたかのようにハープがそっとつぶやきます。この部分の音楽は、うまく表現できませんが、長年一緒にやってきた最高の仲間の引退、といった感覚に近いでしょうか。(実際にエルガーは最大の理解者であったエドワード7世陛下に捧げるべくこの交響曲にとりかかりましたが、陛下の崩御により「亡き国王エドワード7世陛下の追悼に」捧げられることとなりました。)
こういう感覚は、交響曲1番の喜びの爆発に比べて、理解に時間がかかるものと思われます。人生経験を積んでいって、それを手放すときに初めて解る感覚なのでしょうね。そういう感覚を、バルビローリ1955年盤はオケ全体から滲ませています。また作曲家として、まだ私にはこの音楽を書くことはできないと思わせられる瞬間です。
註1:この交響曲のスコアの冒頭には、パーシー・ビッシー・シェリーの「詩神への祈り」と題する詩より冒頭の2行「めったに、めったに、お前は来ない、歓びの精霊よ!」が掲げられています。ちなみに、三浦淳史先生によると、イギリスの音楽評論家アーネスト・ニューマン(1868-1959)は、この詩の8節あるうちの最終節(もちろん引用されなかった部分です)の最後の3行、「精霊よ、お前を愛している-お前は愛であり、生命だ!戻ってきて、もう一度この胸に宿っておくれ」の部分こそが、この交響曲の本質をついているものだと言ったことがあるそうです。
まったく同感です。

















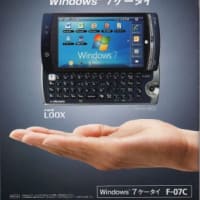


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます