実は今日千葉まで行ったのは、買い物よりも別に目的がある。
と言うのも、千葉県下を走っている、
ちょっとマイナーな私鉄三線の乗り比べをしてみたかったのだ。
その三線とは、
・山万ユーカリが丘線
・新京成電鉄
・総武流山電鉄
全くもって普段の生活の中では乗ることがまず無いし、
更に言えば別に観光地を走っているワケでもない路線なので、
「乗ろう」と思って乗りに行かない限り、
なかなか乗る機会に恵まれないと言う線だったりする。
まずは海浜幕張の駅からバスで、幕張本郷へと向かう。
そこから京成線に乗り、ユーカリが丘の駅へ。

ユーカリが丘の駅はホテルが隣接していて、
更に駅前に広場があったりするので、
なんかやたらと立派で豪勢な雰囲気だ。
でもそんな駅の片隅に、なんだか寂れた一角がある。

ここが山万ユーカリが丘線の駅だ。
ちなみにこの山万ユーカリが丘線だが、
元々、山万と言うのは不動産会社らしく、
ユーカリが丘の開発事業を行っているのだとか。
で、自社が造った街を走る路線として、
運営しているのがこのユーカリが丘線らしい。
鉄道路線としてはかなり変わった形態の路線だ。

これがユーカリが丘線の車両。
「こあら1号」と言う名前らしい。

小さな車体で、車内はロングシート。
そしてこの車両、なんと今どき珍しい非冷房。
でも窓が少ししか開かないのでちょっと暑い。
真夏は大丈夫なのか?
このユーカリが丘線、いわゆる「新交通システム」の一種で、
レールはモノレールの様に一本の線になっている。
そのせいか乗り心地もまさに出来損ないのモノレール。
ユーカリが丘の中をぐるっと一周する環状線の様な造りで、
全線乗りとおしてもほんの15分程度。
せっかくなので、途中下車してみた。
「中学校」と言う駅で降りる。

別にこの駅を選んだのに大した理由は無い。
ただ、一番奥地にある駅だったから、と言うだけだ。
しかしこの駅名。
「中学校」って…なんともそっけない。
他の駅も「公園」だとか「地区センター」だとか「女子大」だとか。
そんなのばっかり。
しかも「女子大」に至っては、
元々予定していた女子大の誘致が取りやめになってしまった為、
そんな駅名にも関わらず実際には近辺に女子大は無い…
と言うのが本当のところだったりする。
このユーカリが丘線。
利用者は基本的にこの住宅地区に住んでいる人達なんだろうが、
ほとんど乗客がいなかった…。
まあ、平日の真昼間って言う時間帯のせいもあるだろうけど。
次に、再び京成線で移動し、津田沼の駅へ。
ここから新京成電鉄に乗り換える。
やって来た車両は8000形。
新京成の主力車両なのだが…何とも言えない、この表情。

単純に「カッコイイ」だとか「カッコ悪い」だとかの世界じゃない、
ちょっと一言では言い表しがたい独特のマスク。
この顔にちなんでこの車両、「たぬき」と呼ばれているのだとか。
しかしこの個性的なスタイル…これなんだよな。
最近の車両に欠けているものって。
この、見た者を「あっ」と言わせるその個性。
それが最近の車両には無さ過ぎる。
いわゆる「走るンです」だとかもう論外。

車内は一見オーソドックスなロングシート。
でもよくよく見ると、至る所にどこかおかしな部分個性が。
天井には、今どきありえない、ばかでかいクーラー。


でもそんな立派なクーラー付いているのにも関わらず、
なぜか扇風機も一緒に添えられている。
ロングシートにはこんなキャラクターが描かれている。

ツバメなのかペンギンなのかよく分からないキャラクター。
これが、座席の一人分ずつに描かれているのだ。
最近の車両は、ロングシートを一人分ずつ、
バケット形状や色で分けているものが多いけど、
キャラクターでそれをやっているのは初めて見た。
ちなみに、車体の側面にもこのキャラが描かれている。

新京成線は、千葉の街の住宅地の中をずっと走っていく。
ハッキリ言って車窓は別に何も観るべきものも無い。
だが、車両自体が面白いのでもうそれで充分に満足。
40分かそこらで、終点の松戸に到着。
ここで常磐線の普通列車に乗り換え、馬橋へ。
馬橋の駅の端の方に、総武流山電鉄のホームがある。

常磐線のホームとはうって変わって、
なんともひっそりとした感じがいい。
総武流山電鉄の車両は、全て西武鉄道のお古。

ただし、編成ごとにカラーリングが変えてあって、
しかもそれぞれに愛称まで付けてある。
この青い車両は「青空」号。


水色の「流馬」に鮮やかなイエローの「なの花」。
他にも色々ある。
車内はロングシート。
このロングシートが妙に長く感じる。

天井を見ると何とも物々しいラインデリア。
最近のものには無い感じで、何とも時代を感じる。

馬橋を出発すると、
列車は独特のモーターの唸りを上げながら市街地を抜けて行く。
カルダン駆動方式のハズなのだが、
妙に釣り掛けっぽくも聞こえる、なんとも変わったモーター音だ。
そして、列車が速度を上げるにつれ、車体がゆっさゆっさと揺れる。
とにかくよく揺れるのだ。
ここ最近の鉄道車両では経験出来ない揺れ。
…でも昔の電車は皆こんな感じに揺れていたよなぁ。
運転席真後ろのシートに腰掛けると、前面がよく見渡せる。
風景自体はどうと言うことは無いのだが、
それでもやはり、迫力溢れる前面展望は魅力的だ。

途中駅はほんのわずか5駅程度。
20分くらいで終点の流山に到着だ。

小さいながら風情のある、なかなかに感じのいい駅だ。
関東の駅百選にも認定されているらしい。
せっかく来たので、少し街中をぶらぶらと歩いてみる。
この流山は新撰組ゆかりの地らしく、
近藤勇の陣屋跡なんかがあった。
駅へと戻りがてら、
一軒の小さなスーパー兼土産物屋が気になって入ってみる。
ここでなんと、総武流山電鉄の湯のみが売られていた。
青空号が描かれている。

店の人曰く、他の車両の絵のもあったらしいが、
もう売れてしまって青空号しか残っていないとのこと。
意外にもこの総武流山電鉄、グッズに力を入れている模様で、
そう言えば駅でも色々と売られていた。
(そして帰りにそのうちの幾つかを買ってしまったのだが)
関東近辺の他のローカル私鉄(銚子電鉄や小湊鉄道等)に較べて
イマイチ(「鉄」的な)注目度が低い路線の様にも思えるのだが、
流山の新撰組など、もっと観光的要素を掘り起こせば、
色々な形で売り出せる可能性のある、そんな路線にも思える。
何にせよ、千葉の私鉄三線乗り比べ。
普通ではまず乗る機会の無い路線ばかりだけれど、
どれもなかなか個性的で楽しめるものだった。
遠くへ旅に出かけるのも勿論良いのだけれど、
たまにはこんな、「身近な新発見」的な小旅行も面白い。
と言うのも、千葉県下を走っている、
ちょっとマイナーな私鉄三線の乗り比べをしてみたかったのだ。
その三線とは、
・山万ユーカリが丘線
・新京成電鉄
・総武流山電鉄
全くもって普段の生活の中では乗ることがまず無いし、
更に言えば別に観光地を走っているワケでもない路線なので、
「乗ろう」と思って乗りに行かない限り、
なかなか乗る機会に恵まれないと言う線だったりする。
まずは海浜幕張の駅からバスで、幕張本郷へと向かう。
そこから京成線に乗り、ユーカリが丘の駅へ。

ユーカリが丘の駅はホテルが隣接していて、
更に駅前に広場があったりするので、
なんかやたらと立派で豪勢な雰囲気だ。
でもそんな駅の片隅に、なんだか寂れた一角がある。

ここが山万ユーカリが丘線の駅だ。
ちなみにこの山万ユーカリが丘線だが、
元々、山万と言うのは不動産会社らしく、
ユーカリが丘の開発事業を行っているのだとか。
で、自社が造った街を走る路線として、
運営しているのがこのユーカリが丘線らしい。
鉄道路線としてはかなり変わった形態の路線だ。

これがユーカリが丘線の車両。
「こあら1号」と言う名前らしい。

小さな車体で、車内はロングシート。
そしてこの車両、なんと今どき珍しい非冷房。
でも窓が少ししか開かないのでちょっと暑い。
真夏は大丈夫なのか?
このユーカリが丘線、いわゆる「新交通システム」の一種で、
レールはモノレールの様に一本の線になっている。
そのせいか乗り心地もまさに
ユーカリが丘の中をぐるっと一周する環状線の様な造りで、
全線乗りとおしてもほんの15分程度。
せっかくなので、途中下車してみた。
「中学校」と言う駅で降りる。

別にこの駅を選んだのに大した理由は無い。
ただ、一番奥地にある駅だったから、と言うだけだ。
しかしこの駅名。
「中学校」って…なんともそっけない。
他の駅も「公園」だとか「地区センター」だとか「女子大」だとか。
そんなのばっかり。
しかも「女子大」に至っては、
元々予定していた女子大の誘致が取りやめになってしまった為、
そんな駅名にも関わらず実際には近辺に女子大は無い…
と言うのが本当のところだったりする。
このユーカリが丘線。
利用者は基本的にこの住宅地区に住んでいる人達なんだろうが、
ほとんど乗客がいなかった…。
まあ、平日の真昼間って言う時間帯のせいもあるだろうけど。
次に、再び京成線で移動し、津田沼の駅へ。
ここから新京成電鉄に乗り換える。
やって来た車両は8000形。
新京成の主力車両なのだが…何とも言えない、この表情。

単純に「カッコイイ」だとか「カッコ悪い」だとかの世界じゃない、
ちょっと一言では言い表しがたい独特のマスク。
この顔にちなんでこの車両、「たぬき」と呼ばれているのだとか。
しかしこの個性的なスタイル…これなんだよな。
最近の車両に欠けているものって。
この、見た者を「あっ」と言わせるその個性。
それが最近の車両には無さ過ぎる。
いわゆる「走るンです」だとかもう論外。

車内は一見オーソドックスなロングシート。
でもよくよく見ると、至る所に
天井には、今どきありえない、ばかでかいクーラー。


でもそんな立派なクーラー付いているのにも関わらず、
なぜか扇風機も一緒に添えられている。
ロングシートにはこんなキャラクターが描かれている。

ツバメなのかペンギンなのかよく分からないキャラクター。
これが、座席の一人分ずつに描かれているのだ。
最近の車両は、ロングシートを一人分ずつ、
バケット形状や色で分けているものが多いけど、
キャラクターでそれをやっているのは初めて見た。
ちなみに、車体の側面にもこのキャラが描かれている。

新京成線は、千葉の街の住宅地の中をずっと走っていく。
ハッキリ言って車窓は別に何も観るべきものも無い。
だが、車両自体が面白いのでもうそれで充分に満足。
40分かそこらで、終点の松戸に到着。
ここで常磐線の普通列車に乗り換え、馬橋へ。
馬橋の駅の端の方に、総武流山電鉄のホームがある。

常磐線のホームとはうって変わって、
なんともひっそりとした感じがいい。
総武流山電鉄の車両は、全て西武鉄道のお古。

ただし、編成ごとにカラーリングが変えてあって、
しかもそれぞれに愛称まで付けてある。
この青い車両は「青空」号。


水色の「流馬」に鮮やかなイエローの「なの花」。
他にも色々ある。
車内はロングシート。
このロングシートが妙に長く感じる。

天井を見ると何とも物々しいラインデリア。
最近のものには無い感じで、何とも時代を感じる。

馬橋を出発すると、
列車は独特のモーターの唸りを上げながら市街地を抜けて行く。
カルダン駆動方式のハズなのだが、
妙に釣り掛けっぽくも聞こえる、なんとも変わったモーター音だ。
そして、列車が速度を上げるにつれ、車体がゆっさゆっさと揺れる。
とにかくよく揺れるのだ。
ここ最近の鉄道車両では経験出来ない揺れ。
…でも昔の電車は皆こんな感じに揺れていたよなぁ。
運転席真後ろのシートに腰掛けると、前面がよく見渡せる。
風景自体はどうと言うことは無いのだが、
それでもやはり、迫力溢れる前面展望は魅力的だ。

途中駅はほんのわずか5駅程度。
20分くらいで終点の流山に到着だ。

小さいながら風情のある、なかなかに感じのいい駅だ。
関東の駅百選にも認定されているらしい。
せっかく来たので、少し街中をぶらぶらと歩いてみる。
この流山は新撰組ゆかりの地らしく、
近藤勇の陣屋跡なんかがあった。
駅へと戻りがてら、
一軒の小さなスーパー兼土産物屋が気になって入ってみる。
ここでなんと、総武流山電鉄の湯のみが売られていた。
青空号が描かれている。

店の人曰く、他の車両の絵のもあったらしいが、
もう売れてしまって青空号しか残っていないとのこと。
意外にもこの総武流山電鉄、グッズに力を入れている模様で、
そう言えば駅でも色々と売られていた。
(そして帰りにそのうちの幾つかを買ってしまったのだが)
関東近辺の他のローカル私鉄(銚子電鉄や小湊鉄道等)に較べて
イマイチ(「鉄」的な)注目度が低い路線の様にも思えるのだが、
流山の新撰組など、もっと観光的要素を掘り起こせば、
色々な形で売り出せる可能性のある、そんな路線にも思える。
何にせよ、千葉の私鉄三線乗り比べ。
普通ではまず乗る機会の無い路線ばかりだけれど、
どれもなかなか個性的で楽しめるものだった。
遠くへ旅に出かけるのも勿論良いのだけれど、
たまにはこんな、「身近な新発見」的な小旅行も面白い。
















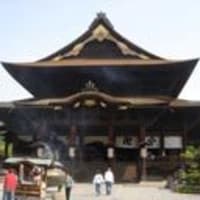



今は京成千葉線に乗り入れています。
今時片開きの車両もあるし。
京成と新京成と北総の新車は同じやつの色違いで、やることが京成グループらしい。
総武流山は儲かっていたのですが、つくばエキスプレスのせいで乗客20%減らしいです。
流山と聞くと、埼玉だっけ、千葉だっけ?と思ってしまいます。
東武野田線も全線乗るとすごいですよ。
千葉なんだか埼玉なんだか。
どっちでもいいですが。
新京成線の車両、確かに京成線内でも見かけましたよ。
でもあの最新型の車両はつまらないですね。
京成版「走るンです」て言うか。
総武流山、あの規模のローカル線にしては本数多いし、
それでいて料金も安く
(ローカル私鉄ってバカ高いところが多い気がします)
元気な鉄道なのかな?て思ってたんですが…。
乗客20%減はもの凄く痛いでしょうね…。
現在、ワンマン化に向けての動きもあるっぽいですね。
野田線、車両が釣り掛け車とか、
あるいは昔の急行りょうもうの改造車とか、
変わったのがあれば是非乗りに行きたいと思うんですけどね。