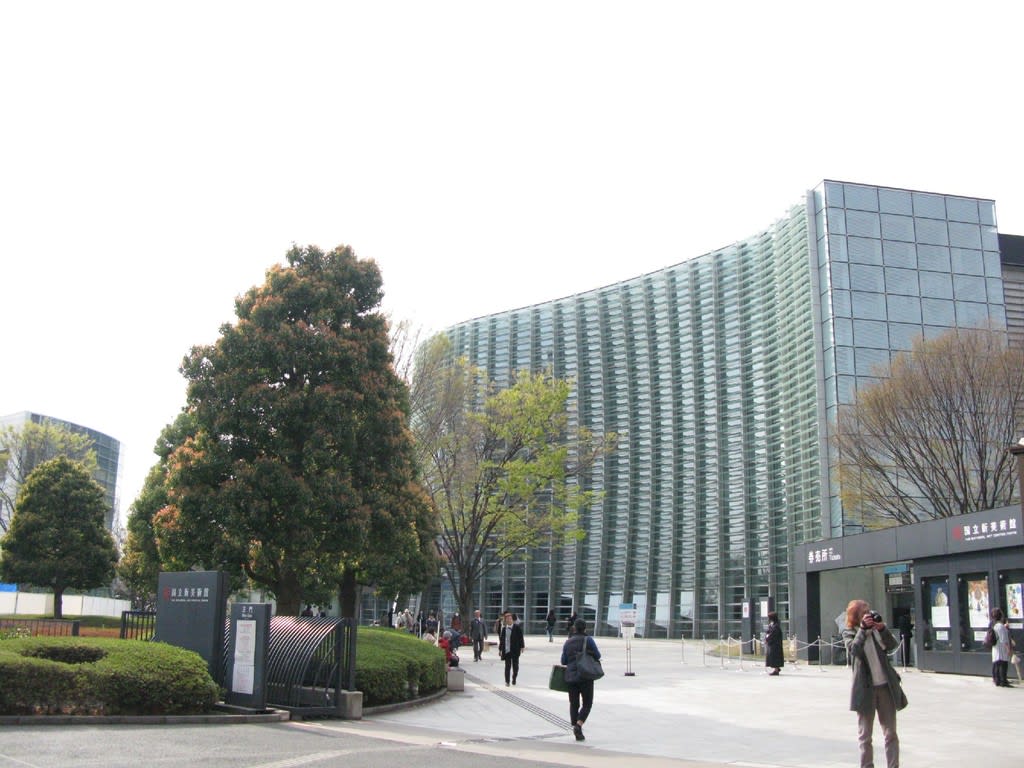狐も花見をしているだろか。
卯月二日は花曇り、桜は満開でひらりひらりと花びらが降りてくる。

王子は若一宮(王子神社)も稲荷社もあり、古来聖地として人々が寄った。
王子の飛鳥山が、桜の名所と名高いのは、江戸の頃から。
将軍吉宗が、紀州と繋がりのある王子神社に飛鳥山を寄進し、桜を植えたのが始り。

吉宗公の施策で飛鳥山に桜が植えられ、十数年かけて桜は見事に咲きそろうようになった。
水茶屋も多く建てられ、庶民が花見の宴ができる場として開かれる。
こうして飛鳥山は、桜の名所として今もなお賑わう所となった。

当地は、すでに平安の頃から聖地であったとされる。
後の鎌倉時代になって、若一王子宮(にゃくいちおうじぐう)と飛鳥山と呼ばれるようになった。
この辺りを安堵していた豊島氏が、熊野から勧請したのが由来とされる。
(熊野の阿須賀神社は、裏山の蓬莱山が御神体。神社と山が隣接したあたり、熊野と王子の神社が似ている。王子神社の御祭神は五柱で、総称を王子大神と呼ぶ。)

飛鳥山を下りて神社へ向かう途中で、音無川の傍に扇屋がある。
時々立ち寄る店で、関東に来て気に入りの店の一つ。
江戸時代には料理屋だったが、今は名物の卵焼きだけを売っている。

これが絶妙の甘さと食感で、卵の香りと旨味が豊かで見事。
花と共に忘れられぬ名物。
参考:北区岸町二丁目町会「王子神社の歴史」/王子神社御由緒/新宮市観光案内「阿須賀神社」/
北区飛鳥山博物館「飛鳥山碑」/北区飛鳥山博物館だより36「コン吉のへえ~そうなんだ飛鳥山」/
国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」/
北区飛鳥山博物館 浮世絵ギャラリー「江戸高名会亭尽えどこうめいかいていづくし)」