【6年生】
 『しあわせ(あなたへ)』
『しあわせ(あなたへ)』
レイフ・クリスチャンソン(文),ディック・ステンベリ(絵),二文字理明(訳)/岩崎書店
しあわせってなに
夏の太陽 それとも ふりつづいた 雨のあとの太陽だろうか
しあわせってなに
勝つこと それとも ベストをつくすことだろうか
しあわせってなに
つぎつぎと成功をおさめること それとも できないと あきらめていたことを やりとげることだろうか
しあわせってなに
ほしいものを すべて手に入れること それとも ほしいものを さがし求めることだろうか
しあわせってなに
王様のように おもいのままにできることだろうか それとも たいせつだと思ったら 勇気をだしてやってみることだろうか
しあわせってなに
人気者になること それとも ひとりぼっちで悲しいとき だれかが気付いて 心配してくれることだろうか
しあわせってなに
なにかを やりとげること それとも なにかに取りくみはじめることだろうか
しあわせってなに
自信をもつこと 自分をたいせつにすること
そして 自分とおなじくらい ほかの人も たいせつにできること
(全文掲載)
スウェーデンでロングセラーを続け、日本でも話題の小さな絵本シリーズのひとつ。
詩のような文とさわやかな絵がとても魅力的です。
シーンと聴いていた6年生。
今自分は幸せですか?
自分にとっての幸せとはなんですか?
6年生,この冬休み,静かに,考えて欲しいことがいっぱいです。
 『でっかいでっかいモヤモヤ袋』
『でっかいでっかいモヤモヤ袋』
ヴァージニア・アイアンサイド(文),フランク・ロジャース(絵),左近リベカ(訳)/草炎社
ジェニーはいつも幸せでした。
ところが、心がだんだんモヤモヤしてきて、色々なことがすっきりしなくなってきました。
そして、ある日起きたら、でっかいでっかい、モヤモヤ袋があったのです。
それは、どこにもついてきて、ひっついて離れません。
何とかしようとがんばっても、全く歯が立ちません。
ジェニーは,お兄さんや両親や学校の先生に相談しようとしますが,
うすうす,なんと言われるか分かってしまい,あてにならないと諦めて思いとどまります。
自分なりに解決しようとしますが…。
そんなとき,となりの優しいおばあさんが手伝ってくれます。
「モヤモヤにっとて,みられるのが一番いやなの。ひとつひとつ,ゆっくり出してごらん]
おばあさんは,モヤモヤのグループ分けをし,ひとつひとつ,取りだして解決してくれます。
あけてみると,モヤモヤは,なんてちっぽけ。
どうにもならないものはおばあちゃんが引き受けてくれた。
他の人のモヤモヤもあったから,それはその人の返した。
あって当たり前の,大人も子供のも先生も,誰でも持ってるモヤモヤもあった。
最後は,モヤモヤ袋は空っぽに。
えいっと,袋を投げ飛ばして,すっきりです。
人に言えない不安や不満、心配、疑いを抱えた女の子が主人公の絵本。
身の上相談の回答者としても活躍している作者ならでは、そんな年頃の子供たちの不安の数々をモヤモヤ袋に表現した秀作です。
大人になると,あんなことでなぜ悩んでたんだろ …と分かる日がくるのに,今,渦中にいる子供たちには,まだまだ,分からない。自分も経験がある。
…と分かる日がくるのに,今,渦中にいる子供たちには,まだまだ,分からない。自分も経験がある。
だから,親として,もどかしい。
でも,大丈夫だよ!みんなそうだったのよ!
モヤモヤ袋は,大人だって持ってるんだから…。あんなこと,こんなこと…。
そんなとき相談するのは,やっぱり,経験者の年長の方だったり,尊敬できる友人だったり…。
お酒でクダ巻いて発散したり…(おっと失礼 )
)
尊敬できる大人,先輩,友達,いますか?
親子でぜひ読んでみてはいかがでしょうか?
 『ピンクのれいぞうこ』
『ピンクのれいぞうこ』
ティム・イーガン(作),まえざわあきえ(訳)/ひさかたチャイルド
ネズミのドズワースは,いつもボーっとしたり,テレビを観て毎日を過ごしていました。
ある日,がらくた置き場でみつけたピンクの不思議な冷蔵庫。
「絵をかいてみよう」とメッセージが張ってあります。ドアを開けると、絵具とスケッチブックが。
最初は自分のお店で売ろうとしましたが,自分で絵を描いてみることに。
次の日は本が、その次の日はトランペットが…、毎日違うものが入っているピンクの冷蔵庫。
ドズワースは,そうこうするうちに,いろいろとやってみることが楽しくなってきました。
そんなある日、冷蔵庫を開けると中はからっぽで…。
ドズワースは途方にくれ,また元の生活に戻るかと思いきや…。
自分の世界を広げるために,これまで冷蔵庫に入っていたものをいっさいがっさい積み込んで,未知の世界に自転車をこぎ始めるのでした。
旅立つ前に立ち寄ったがらくた置き場。おんぼろだったピンクの冷蔵庫が,ドズワースには輝いてみえました。
新しいことにチャレンジしてみたら、毎日がどんどん楽しくなったネズミ のおはなし。
のおはなし。
6年生にはどんな風に捉えられたでしょうねぇ?このお話。
挑戦しないと失敗もしない。
「そんなこと,つまんねぇよ… 」「一生懸命やる=ダサイ」と言って,何も行動しない。好きなことばかり,気に入ったことばかりやって,それ以外は気が乗らないからと,いい加減な態度,挑戦するチャンスを与えてくれる大人や先生に対して失礼な態度で臨む風潮がみられます。
」「一生懸命やる=ダサイ」と言って,何も行動しない。好きなことばかり,気に入ったことばかりやって,それ以外は気が乗らないからと,いい加減な態度,挑戦するチャンスを与えてくれる大人や先生に対して失礼な態度で臨む風潮がみられます。
本当は子供時代って,損得なしでいろんなことに無謀に挑戦できる時期でもあるのですがね。未知の分野を覗いてみる,敢えて苦手なことに挑戦してみる試してみる,そんな勇気を持って欲しい。
成功する事よりも失敗した事から学ぶことは多いのですよね…。
自分の子供が「失敗する」のを過剰に恐れる親もまた多し。
私は失敗したことがない。うまくいかない方法を一万通り見つけただけだ。
I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work
私たちの最大の弱点は諦めることにある。
成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ。
Our greatest weakness lies in giving up.
The most certain way to succeed is to try just one more time
(トーマス・エジソン Thomas A. Edison )
 『おおはくちょうのそら』
『おおはくちょうのそら』
手島圭三郎(作)/リブリオ出版
北の国へ帰らなければならないオオハクチョウの家族。
1羽,病気の子どもがいます。その子を置いて旅立つ家族。
悲しい決断。
ところが,家族は舞い戻って来て,その子の最後を看取ります。
再び北の空へ向かう家族。昼夜を問わず飛び続け,北の国へ着くと…。
空には,逝ってしまった子ハクチョウが…。
手島圭三郎(北海道在住)さんの版画による素晴らしい芸術作品ともいえる北の動物シリーズのひとつ。
1988年、ニューヨークタイムズ紙選、世界の絵本ベストテンに選出された名作です。
その他にも「しまふくろうのみずうみ」「ひぐまのあき」「きたきつねのゆめ」など,ぜひ手にとって読んでみて欲しいと思います。
厳しい自然の中で逞しく生きている動物の生活をありのまま紹介しつつ,家族の愛,親子の愛をも匠に,その素晴らしい版画技術で表現されています。
余談ですが…,私の姉が北海道江別市に住んでおり,地元の本屋さんに勤めていますが,手島圭三郎さんご本人が,絵具を買いにいつもやってきては,ほとんどの絵具を買い占めて困らせている…とか。羨ましい限り。私もぜひお会いしてみたい
 『めがねやとどろぼう』
『めがねやとどろぼう』
桂 文我(作),東 菜奈 (絵) /童心社
こちらは,5年生にも読み聞かせした紙芝居です。
ストーリーはこちらからどうぞ。
⇒http://blog.goo.ne.jp/ehonnokai/e/e4d0a3ff900ca380484d576595ee9ece
メッセージ性の強いおはなしが続いたので,最後は上方落語の紙芝居で「クスッ!」と笑ってもらいました。まだまだあどけない笑顔。その笑顔がたくさん見たいのですよ,私たちは。
最後の冬休み,有意義にお過ごしください。
3学期も,旅立ちに向け,はなむけになるようなお話をお届けしたいと思います。
メリークリスマス
 『しあわせ(あなたへ)』
『しあわせ(あなたへ)』レイフ・クリスチャンソン(文),ディック・ステンベリ(絵),二文字理明(訳)/岩崎書店
しあわせってなに
夏の太陽 それとも ふりつづいた 雨のあとの太陽だろうか
しあわせってなに
勝つこと それとも ベストをつくすことだろうか
しあわせってなに
つぎつぎと成功をおさめること それとも できないと あきらめていたことを やりとげることだろうか
しあわせってなに
ほしいものを すべて手に入れること それとも ほしいものを さがし求めることだろうか
しあわせってなに
王様のように おもいのままにできることだろうか それとも たいせつだと思ったら 勇気をだしてやってみることだろうか
しあわせってなに
人気者になること それとも ひとりぼっちで悲しいとき だれかが気付いて 心配してくれることだろうか
しあわせってなに
なにかを やりとげること それとも なにかに取りくみはじめることだろうか
しあわせってなに
自信をもつこと 自分をたいせつにすること
そして 自分とおなじくらい ほかの人も たいせつにできること
(全文掲載)
スウェーデンでロングセラーを続け、日本でも話題の小さな絵本シリーズのひとつ。
詩のような文とさわやかな絵がとても魅力的です。
シーンと聴いていた6年生。
今自分は幸せですか?
自分にとっての幸せとはなんですか?
6年生,この冬休み,静かに,考えて欲しいことがいっぱいです。
 『でっかいでっかいモヤモヤ袋』
『でっかいでっかいモヤモヤ袋』ヴァージニア・アイアンサイド(文),フランク・ロジャース(絵),左近リベカ(訳)/草炎社
ジェニーはいつも幸せでした。
ところが、心がだんだんモヤモヤしてきて、色々なことがすっきりしなくなってきました。
そして、ある日起きたら、でっかいでっかい、モヤモヤ袋があったのです。
それは、どこにもついてきて、ひっついて離れません。
何とかしようとがんばっても、全く歯が立ちません。
ジェニーは,お兄さんや両親や学校の先生に相談しようとしますが,
うすうす,なんと言われるか分かってしまい,あてにならないと諦めて思いとどまります。
自分なりに解決しようとしますが…。
そんなとき,となりの優しいおばあさんが手伝ってくれます。
「モヤモヤにっとて,みられるのが一番いやなの。ひとつひとつ,ゆっくり出してごらん]
おばあさんは,モヤモヤのグループ分けをし,ひとつひとつ,取りだして解決してくれます。
あけてみると,モヤモヤは,なんてちっぽけ。
どうにもならないものはおばあちゃんが引き受けてくれた。
他の人のモヤモヤもあったから,それはその人の返した。
あって当たり前の,大人も子供のも先生も,誰でも持ってるモヤモヤもあった。
最後は,モヤモヤ袋は空っぽに。
えいっと,袋を投げ飛ばして,すっきりです。
人に言えない不安や不満、心配、疑いを抱えた女の子が主人公の絵本。
身の上相談の回答者としても活躍している作者ならでは、そんな年頃の子供たちの不安の数々をモヤモヤ袋に表現した秀作です。
大人になると,あんなことでなぜ悩んでたんだろ
 …と分かる日がくるのに,今,渦中にいる子供たちには,まだまだ,分からない。自分も経験がある。
…と分かる日がくるのに,今,渦中にいる子供たちには,まだまだ,分からない。自分も経験がある。だから,親として,もどかしい。
でも,大丈夫だよ!みんなそうだったのよ!

モヤモヤ袋は,大人だって持ってるんだから…。あんなこと,こんなこと…。
そんなとき相談するのは,やっぱり,経験者の年長の方だったり,尊敬できる友人だったり…。
お酒でクダ巻いて発散したり…(おっと失礼
 )
)尊敬できる大人,先輩,友達,いますか?
親子でぜひ読んでみてはいかがでしょうか?
 『ピンクのれいぞうこ』
『ピンクのれいぞうこ』ティム・イーガン(作),まえざわあきえ(訳)/ひさかたチャイルド
ネズミのドズワースは,いつもボーっとしたり,テレビを観て毎日を過ごしていました。
ある日,がらくた置き場でみつけたピンクの不思議な冷蔵庫。
「絵をかいてみよう」とメッセージが張ってあります。ドアを開けると、絵具とスケッチブックが。
最初は自分のお店で売ろうとしましたが,自分で絵を描いてみることに。
次の日は本が、その次の日はトランペットが…、毎日違うものが入っているピンクの冷蔵庫。
ドズワースは,そうこうするうちに,いろいろとやってみることが楽しくなってきました。
そんなある日、冷蔵庫を開けると中はからっぽで…。
ドズワースは途方にくれ,また元の生活に戻るかと思いきや…。
自分の世界を広げるために,これまで冷蔵庫に入っていたものをいっさいがっさい積み込んで,未知の世界に自転車をこぎ始めるのでした。
旅立つ前に立ち寄ったがらくた置き場。おんぼろだったピンクの冷蔵庫が,ドズワースには輝いてみえました。
新しいことにチャレンジしてみたら、毎日がどんどん楽しくなったネズミ
 のおはなし。
のおはなし。6年生にはどんな風に捉えられたでしょうねぇ?このお話。
挑戦しないと失敗もしない。
「そんなこと,つまんねぇよ…
 」「一生懸命やる=ダサイ」と言って,何も行動しない。好きなことばかり,気に入ったことばかりやって,それ以外は気が乗らないからと,いい加減な態度,挑戦するチャンスを与えてくれる大人や先生に対して失礼な態度で臨む風潮がみられます。
」「一生懸命やる=ダサイ」と言って,何も行動しない。好きなことばかり,気に入ったことばかりやって,それ以外は気が乗らないからと,いい加減な態度,挑戦するチャンスを与えてくれる大人や先生に対して失礼な態度で臨む風潮がみられます。本当は子供時代って,損得なしでいろんなことに無謀に挑戦できる時期でもあるのですがね。未知の分野を覗いてみる,敢えて苦手なことに挑戦してみる試してみる,そんな勇気を持って欲しい。
成功する事よりも失敗した事から学ぶことは多いのですよね…。
自分の子供が「失敗する」のを過剰に恐れる親もまた多し。
私は失敗したことがない。うまくいかない方法を一万通り見つけただけだ。
I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work
私たちの最大の弱点は諦めることにある。
成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ。
Our greatest weakness lies in giving up.
The most certain way to succeed is to try just one more time
(トーマス・エジソン Thomas A. Edison )
 『おおはくちょうのそら』
『おおはくちょうのそら』手島圭三郎(作)/リブリオ出版
北の国へ帰らなければならないオオハクチョウの家族。
1羽,病気の子どもがいます。その子を置いて旅立つ家族。
悲しい決断。
ところが,家族は舞い戻って来て,その子の最後を看取ります。
再び北の空へ向かう家族。昼夜を問わず飛び続け,北の国へ着くと…。
空には,逝ってしまった子ハクチョウが…。
手島圭三郎(北海道在住)さんの版画による素晴らしい芸術作品ともいえる北の動物シリーズのひとつ。
1988年、ニューヨークタイムズ紙選、世界の絵本ベストテンに選出された名作です。
その他にも「しまふくろうのみずうみ」「ひぐまのあき」「きたきつねのゆめ」など,ぜひ手にとって読んでみて欲しいと思います。
厳しい自然の中で逞しく生きている動物の生活をありのまま紹介しつつ,家族の愛,親子の愛をも匠に,その素晴らしい版画技術で表現されています。
余談ですが…,私の姉が北海道江別市に住んでおり,地元の本屋さんに勤めていますが,手島圭三郎さんご本人が,絵具を買いにいつもやってきては,ほとんどの絵具を買い占めて困らせている…とか。羨ましい限り。私もぜひお会いしてみたい

 『めがねやとどろぼう』
『めがねやとどろぼう』桂 文我(作),東 菜奈 (絵) /童心社
こちらは,5年生にも読み聞かせした紙芝居です。
ストーリーはこちらからどうぞ。
⇒http://blog.goo.ne.jp/ehonnokai/e/e4d0a3ff900ca380484d576595ee9ece
メッセージ性の強いおはなしが続いたので,最後は上方落語の紙芝居で「クスッ!」と笑ってもらいました。まだまだあどけない笑顔。その笑顔がたくさん見たいのですよ,私たちは。
最後の冬休み,有意義にお過ごしください。
3学期も,旅立ちに向け,はなむけになるようなお話をお届けしたいと思います。
メリークリスマス














 『1つぶのおこめ-さんすうのむかしばなし-』
『1つぶのおこめ-さんすうのむかしばなし-』 )に,子どもたちが要所要所でウケてくれました。
)に,子どもたちが要所要所でウケてくれました。 。
。 のコーチ、ピーボディ先生は、小学校の歴史の先生。
のコーチ、ピーボディ先生は、小学校の歴史の先生。 をお金も払わず、カバンに入れているところを、
をお金も払わず、カバンに入れているところを、

 が1匹で…「ウラパン」
が1匹で…「ウラパン」 が2本で…「オコサ」
が2本で…「オコサ」


 以下のように変更になりました。
以下のように変更になりました。 や童話の紹介とおはなし会用絵本の選定
や童話の紹介とおはなし会用絵本の選定
 など
など お待ちしておりま~す。
お待ちしておりま~す。

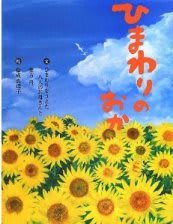
 最近感動した言葉から
最近感動した言葉から



 のチェックをしておる。
のチェックをしておる。 )を問われたり、サイエンス系時事問題のチェックも欠かせないので受験生は大変だなぁ~。
)を問われたり、サイエンス系時事問題のチェックも欠かせないので受験生は大変だなぁ~。 なんちゃって。
なんちゃって。