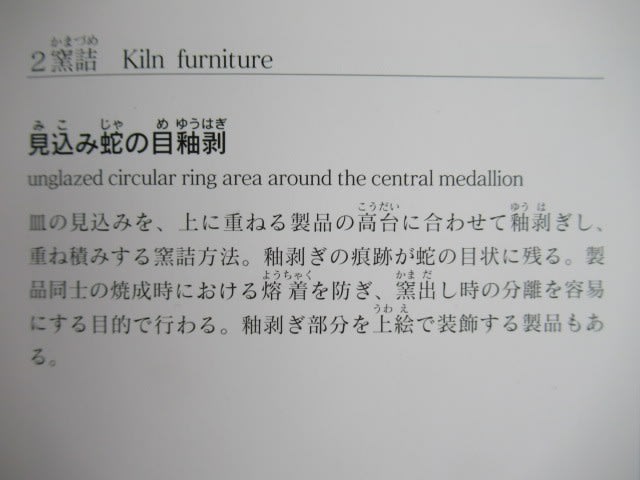今回は、「染付 桜唐草文 中皿」の紹介です。
この中皿は、先日の、7月20日(木)の古美品交換会で競り落としてきたものです。
なお、この中皿の名称につきましては、7月20日(木)付けの「古美品交換会」の記事の中では「染付 桜文 中皿」として紹介しましたが、その後、図録等で調べてみましたら、この手のものを「染付 桜唐草文 中皿」としている場合が多いようですので、この中皿につきましても、それに倣い、「染付 桜文 中皿」ではなく、「染付 桜唐草文 中皿」として紹介したいと思います。
また、この中皿の製作年代につきましても、7月20日(木)付けの「古美品交換会」の記事の中では、「江戸時代中期の終り頃~後期の初め頃」として紹介しましたが、やはり、その後に調べた図録等では「江戸時代中期」としている場合が多いようですので、この件につきましても、それに倣い、「江戸時代中期」として紹介したいと思います。
ところで、この中皿の入手に際しましては、ちょとした出来事がありましたので、まずは、そのことから紹介したいと思います。
ご存知の方もおられるかとは思いますが、競り市では、競りにかけられる商品は、事前に、大きなお盆のようなものの中に乗せられ、ぐるっと、参加者全員の前を通過するようになっていて、その際、参加者は、その商品をじっくりとチェックするという仕組みになています。
私は、その際、この中皿の口縁には5mm程のソゲ疵が1か所あることを知りました。そんなものですから、この中皿は疵物ですので、それほど高くはないだろう、2,000円~3,000円程度のものだろうと値踏みしたわけです。まっ、3,000円程度までなら競り落としてもいいかなと思ったわけです。
ところが、この中皿は、いざ競りにかけられましたら、発句が4,000円でした。
しかし、競り人が「4,000円」と発句を告げましても、誰も槍を入れません。シーンと静まりかえったままでした。この皿に興味を抱いていた参加者は、この皿が疵物であることを知っていたからですね。競り人が、疵を見逃したのかもしれません。確かに、この中皿の口縁のソゲ疵は、よ~く見ないと気付きにくいような存在でしたから、、。疵物なのに発句が高すぎるな~と思った方が多かったのでしょう。
それで、私は、競り人に、「この皿には疵があるんですけど、、、」と言ったのです。
そうしましたら、競り人は、「ん? そうだった。どこに、、」ということで、この中皿をよ~く点検し、「あっ、これね」と、ようやく気付いたようです。
やはり、この皿の口縁に疵があることに気付かないで発句を発したようですね。それで、競り人は、「じゃ、1,500円か」と発句を修正しました。
そこで、私は、すかさず、「2,000円!」の槍を入れました。
それに対して、その後、私の槍を越える槍を出す者はおらず、目出度く私が落札者となりました(^_^) 私の気合い勝ちというところでしょうか(^-^*)
結局、最初の発句の半値の、私の値踏みに近い額の、2,000円で手に入れることが出来たわけです(^-^*)
ということで、前置きが長くなりましたが、次に、その「染付 桜唐草文 中皿」を紹介いたします。

漂泊前の表面
ご覧のように、この中皿には、上の写真の下部に、時計の針で示しますと口縁の6時の方角に約5mm程のソゲ疵が1か所あります。ただ、よ~く見ないと気付かないほどです。
なお、そのソゲ疵部分を拡大した写真は、次のとおりです。

ソゲ疵部分を拡大した写真
そこで、私は、何時ものとおり、さっそく、この中皿を漂白剤の中に入れ、綺麗にする作業にとりかかりました。
漂白後の写真は、次のとおりです。

漂白後の表面
ところが、上の写真からも分かりますように、漂白して綺麗にしましたら、このソゲ疵は、余計に目立つようになったように感じます(~_~;) これじゃ、ソゲ疵部分を補修しなければなりませんね。
また、漂白してみましたら、「漂白前の表面」の写真上部の花びらの左上に見られた汚れが消えていることに気付きました。私は、この部分は、焼成時の降り物に更に汚れが付着したものだろうから、その汚れは、それほど綺麗には落ちないだろうと思っていましたので、予想外れでした。この部分は釉剥げになっていて、そこに汚れが付着していただけなので綺麗になったようですね(^_^)
また、同じく、「漂白前の表面」の写真の口縁の、時計の針で示しますと3時の方角に黒くポチッとしたものが見られますが、それは、小さな降り物なのかなと思っていたのですが、それが消え、代わりにノミホツが現われてきました(~_~;) これは、小さいとはいえ疵ですね(><) でも、この程度の小さな疵は無視することとし、補修はしないことにしました。
以上の、花びら部分の汚れが消えた状態、ノミホツが出現した状態の拡大写真は、次のとおりです。

花びらの左上の汚れが消え、口縁(上の写真では右下)にノミホツが出現した写真
ということで、全体を漂白して綺麗にし、口縁にあった5mm程のソゲ疵に補修を施したわけですが、それらの作業を行った後の中皿の写真は次のとおりです。
染付 桜唐草文 中皿

表面

補修したソゲ疵部分を拡大した写真

側面

裏面

裏面の一部を拡大した写真
生 産 地 : 肥前・有田
製作年代: 江戸時代中期
サ イ ズ : 口径19.9cm 高さ3.0cm 底径12.1cm