

後に、日本中を巻き込んでのムーブメントを引き起こし、一気に社会現象化してゆくニャロメだが、このニャロメを登場間もない段階から熱烈に支持していたのは、「週刊少年サンデー」の中心読者層である小中学生ではなく、所謂インターン闘争に端を発し、新たに導入された登録医制度の改定と医学部学生の不当処分の撤回を求め、東大安田講堂を占拠した、全学共闘会議の主流派を中心とする若き学生運動家達だった。
カール・マルクスの『資本論』やジャン=ポール・サルトル、シモーヌ・ド・ボーヴォワールといった実存主義哲学を思想的立場とするフランス系作家の諸作品と並んで、彼らの愛読書の一つとして数えられていたのが、『忍者武芸帳』や『カムイ伝』といった一連の白土劇画であり、オンタイムで連載されていた『あしたのジョー』、そして『バカボン』、『ア太郎』に代表される赤塚漫画であった。
その中でも、何故ニャロメの人気が特段に高かったのか……。
それを知る鍵として、全共闘系各派全学連、新左翼系の若者達の政治意識が急進性を増し、その活動が極左的なトロツキズムを目指した武力闘争へと傾斜してゆく以前、即ち、学生運動が第二次日米安全保障条約の廃止、権威主義的な大学運営に見られる管理秩序総体の解体などを求めた純粋な正義感の発露として、作家・小田実を象徴的存在とするベ平連(ベトナムに平和を! 市民連合)の反戦運動と同様に、幅広く民衆の理解を得てい た時代背景を無視してはなるまい。
騒然としたポリティカルの季節の中で、一般国民の間においても、誰もが政治的無関心でいられなかった時代、政治音痴を自嘲し、実際ノンポリティカルな立場にあった赤塚もまた、自己変革理念と造反有理を掲げ、左翼の国士として反権力闘争に挺身するデモ学生達の熱き精神の躍動にシンパシーを寄せ、警察権力に鎮圧されても、敢然と立ち向かう彼らの不屈の生き様を存在の共鳴に準え、ニャロメのキャラクターの一部に投射していたことがその最大の理由としてあるのだ。
*
こうして、少年期を過ごした大和郡山で出会った、ふてぶてしいまでに剛胆な件の野良猫と、左翼学生の烈々たる激情を重ね合わせて、ニャロメのキャラクターは確立してゆく。
ニャロメを『ア太郎』に登場させる少し前、米軍の軍事的介入により泥沼化したベトナム戦争への反対を標榜した新左翼諸派の街頭闘争は、更なる激しさを増し、国際反戦デーである1968年10月21日、米軍タンク車輌輸送阻止を掲げた全共闘学生らが、その輸送基点であった新宿駅構内を占拠し、翌日四五〇名もの逮捕者を出すこととなる「新宿騒乱事件」が勃発する。
当時、まだ新宿十二社の市川ビルにスタジオを構えていたため、学生と機動隊の小競り合いによる物々しい喧騒がダイレクトに伝わり、野次馬根性が沸いた赤塚は、スタッフ達を引き連れ、現場へと見物に出掛けたという。
その時の生々しい出来事を赤塚はこう振り返る。
「学生たちが、二つ三つ石をなげると、機動隊が、「ウォーッ!」とものすごい声をあげて、ボクらのほうに突進してきた。すさまじい迫力で、いまにも、なぐりかかってきそうないきおいだったので、見物のボクらは、びっくりしてにげだした。
~中略~
猛獣のようにたけりたって、警察官に必要な冷静さは、少しも見えなかった。ボクは、警察官だった父親は、信用していたつもりだが、ただやたらなぐりたがる警察官がいることも、このとき知った。」
(『落ちこぼれから天才バカボンへ』ポプラ社、84年)
時同じくして赤塚は、ヒステリックにピストルを発砲しては、権力に物を言わせて暴れまくる、ゲバルトの権化とも言うべき警察官・目ん玉つながりを『バカボン』、『ア太郎』を股に掛けて登場させ、その作品世界に、容赦ない不穏な笑いを撒き散らしてゆくわけだが、この時、機動隊の獰猛ぶり、延いては警察権力のダークサイドを目の当たりにしたことが、赤塚漫画史上最低最悪と呼ばれる、悪名高き名キャラクターを生み出すヒントになったのだ。
そんな理由からも、後期『ア太郎』で頻繁に描かれることになるニャロメと目ん玉つながりの抗争劇には、この時期の学生運動の右肩上がりの高揚が如実に映し出されていることがよくわかる。
安田講堂の攻防戦で、国家警察に完膚なきまでに叩きのめされた左翼学生達が、目ん玉つながりをはじめとする卑劣な人間どもに、幾度となく踏み潰されても、しぶとく立ち上がっては、玉砕覚悟の反撃を繰り返すニャロメのレジスタンスの精神に、自らの反逆心と挫折感を重ね合わせ、熱い視線を寄せたのも、理にかなう必然性を備えていた。


















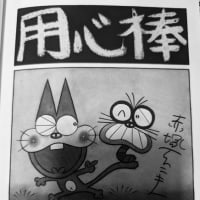
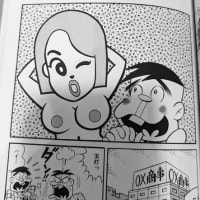
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます