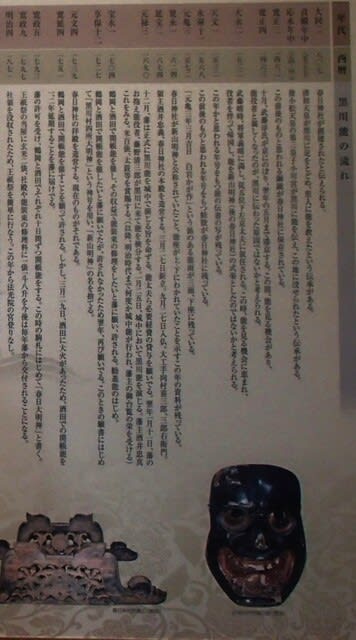物価高騰で実質消費が減りつづけているのに、なぜ政府・日銀は「物価と賃金の好循環」を押し通すのか?~追加引き上げでもまだ低い政策金利
Yahoo news 2025/1/25(土) 現代ビジネス 野口悠紀雄(一橋大学名誉教授)
(🍓立憲民主党や共産党はアベインフレによる円安物価高の終息を中心政策にすべき)
物価上昇が収まらないので、実質消費支出が減少を続けている。人々は、物価高騰を受け入れていないのだ。それにもかかわらず、政府・日銀は、物価上昇を推し進めようとしている。
物価高騰のため、食費を払えない人が増えた
炊き出しに集まる人が増えているそうだ。これまでは炊き出しの行列を横目で見て通るだけだったが、いまは行列に並ばなければならなくなったという人の話もあった。物価高騰のために、食費を払えない人が増えているのだ(朝日新聞1月7日)。
物価が高騰すれば炊き出しにすがる人は増える。しかし、その一方で、炊き出しの継続も難しくなってきているという。日本はなんと哀れな国になってしまったのだろう。
しかも、日本を全体として見れば、これは地震などの自然災害で起こされた事態ではない。政策の誤りによって引き起こされた事態だ。
それにもかかわらず、政府・日銀は、物価と賃金の好循環が始まっているという。つまり、物価が上がるのはよいことだとしている。そして、物価が上がる状態を確実にしようという。つまり、誤った政策を、これからも続けようとしている。
政策判断の基本の基本がおかしくなってしまったとしか考えようがない。
消費者は節約志向を強め家計消費支出はマイナス
物価が上がるので消費を減らさざるをえなくなったのは、一部の人だけのことではない。日本国民全体がそうだ。
家計調査には、これが明確に表れている。
消費者物価上昇率は、2022年4月から2%以上が続いている。このため、実質消費が減少している。
2024年2月に発表された家計調査によると、2023年平均の結果は、つぎのとおりだった(数字は対前年比、%)。
名目 実質
* 実収入
勤労者世帯の実収入(総世帯) △ 2.4 △6.0
勤労者世帯のうち二人以上の世帯 △ 1.5 △5.1
* 消費支出
(総世帯) 1.3 △2.4
(2人以上の世帯) 1.1 △2.6
つまり、実収入が減少し、物価が上昇するため、消費支出は名目では増えるが、実質では減になっている。
この状態は、現在に至るまで続いている。2024年9月の家計調査(2025年1月10日発表)によれば、つぎのとおりだ。
*消費支出(2人以上の世帯) 名目 実質
2024年9月 1.8 △1.1
2024年10月 1.3 △1.3
2024年11月 3.0 △0.4
2022年以降ほぼ継続的に、実質消費支出の伸びがマイナスになっている。
なお、 勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は、11月で、名目 3.7%の増加、 実質 1.1%の増加となった。
人々は、ゆとりがなくなり、生活保護も増えた
日銀が実施した「生活意識に関する調査」(2024年9月)によると、1年前と現在の比較結果は、つぎのとおりだ(数字は、%)。
物価に対する実感: かなり下がった(0.4)、かなり上がった(63.8)
暮らし向き: ゆとりがでてきた(5.3)、ゆとりがなくなってきた(52.7)
国民は物価上昇を容認しているわけではない。容認できないから拒否し、それが前項で述べた消費の減少につながっているのだ。
一方、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、23年11月の現金給与総額は、23年同月と比べて3.0%増えたものの、実質賃金は4か月連続でマイナスとなった。
2024年10月の全国の生活保護の申請件数は2万1561件となり、23年の10月から3.2%増加した。生活保護の受給を昨年10月に新たに始めたのは1万9807世帯で、前年同月に比べて977世帯、率では5.2%増えた。
輸入価格は下落しているのに物価が上がる
これまでは、輸入物価の上昇が消費者物価を引き上げてきた。
輸入物価の上昇は、アメリカで発生したインフレーションや、ロシアのウクライナ侵攻によって資源価格が上昇したことで引き起こされたものだから、日本にとってはどうしようもなかったと言えるかもしれない。
確かにそうした側面があった。しかし、円安が進んだことが輸入価格の高騰を加速させたことも間違いない。そして、為替レートは、日本の金融政策によって影響を与えることが可能だ。それを行なわなかったという意味で、日銀の責任は大きい。
さらに重要なのは、つぎのことだ。
日銀の統計によれば、円ベースの輸入物価の対前年同月比は、2025年9、10、11月は、マイナスだった。
さらに、日本政府は、物価対策として、ガソリン代を抑えているし、電気ガスの物価対策も復活させた。これによって、消費者物価の統計値を実態より低く抑えている。
こうしたことにもかかわらず、物価上昇は止まらず、実質賃金が上昇しないのである。
輸入物価が下がるのに物価が上がるのは、2024年11月29日の本欄で説明したとおり、企業が、生産性の上昇や企業利益の圧縮によってではなく、消費者物価に転嫁することによって賃上げを行なっているからだ。
日銀は物価上昇をさらに進めようとしている
これまで、物価が上がらないから経済が停滞すると言われてきた。このため物価を上げることが必要と言われてきた。
しかし、上述した家計調査のデータが示しているのは、家計の実質消費の伸びが、物価の上昇によってマイナスになっていることだ。家計は明らかに物価の上昇に対して拒否反応を示しているのである。物価が上がれば、人々は買い控えるのである。
家計の消費が減り、それによって経済が衰退し、生活保護が増えるのは、決して望ましいことではない。それをなぜ「物価と賃金の好循環」だとして進めようとするのだろうか?私には全く理解できない。
日本の政治的な仕組みでは、物価高に苦しむ人々の声を吸い上げ、政策に反映させる仕組みがない。その人たちの声は政策に反映されないのである。
石破政権は、実質賃金の引き上げが重要な政策課題だと宣言した。ところが、実質賃金が下落を続けているにもかかわらず、何の対策も取ろうとしない。なぜこの状態を放置することが許されるのか? 私は全く理解できない。
なお、日本銀行は、1月23、24日の金融政策決定会合で、政策金利を引き上げた。引上げ自体は適切な判断と思うが、諸外国と比較した場合に、日本の政策金利が低すぎることは変わらない。これがさまざまの歪をもたらしている。日銀は、中長期的な利上げの見通しを明らかにすべきだ。