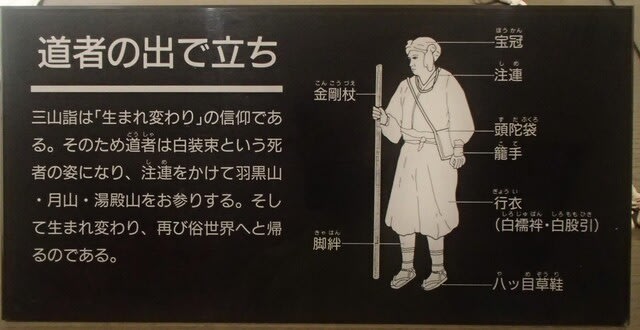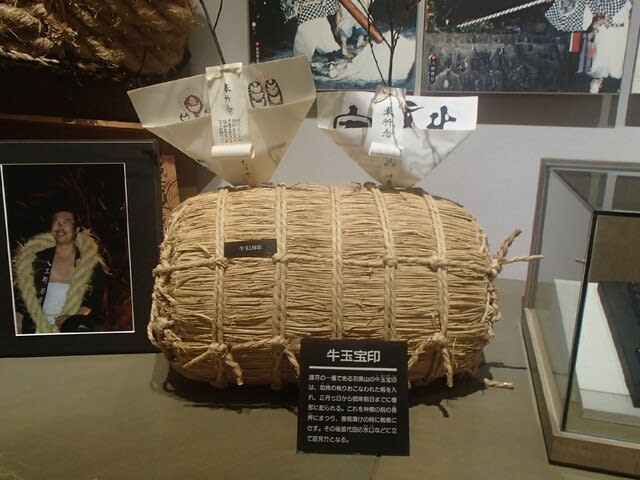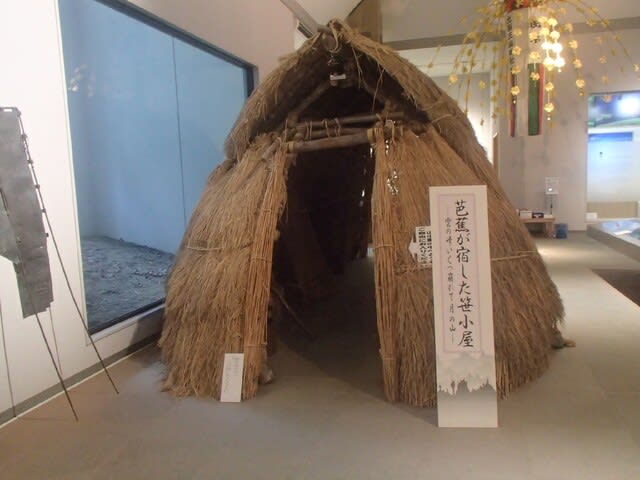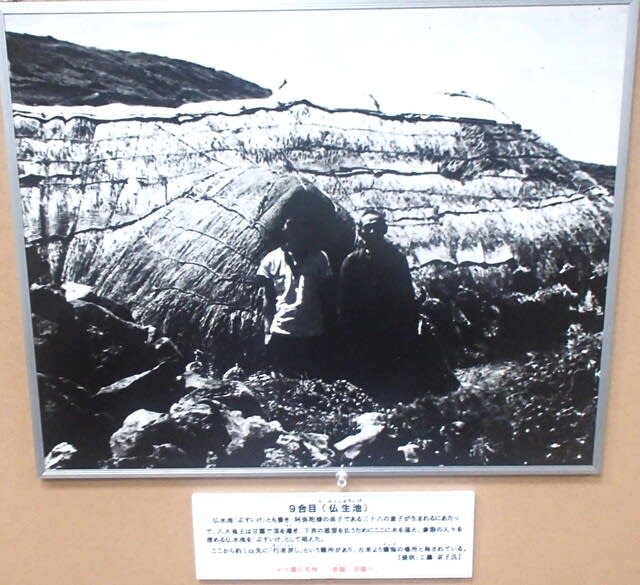致道博物館。山形県鶴岡市家中新町。
2024年9月11日(水)。
致道博物館は酒田市の本間美術館とともに1980年代初めに見学した。致道博物館は明治建築で有名なので見学したのだが、40年前なので記憶を新たにしたいと思い再訪した。
午前中に鼠ケ関跡や加茂水族館、午後には羽黒山頂の出羽三山神社や麓の国宝・羽黒山五重塔を見学して、14時45分頃に着いた。
致道博物館は鶴ヶ岡城三の丸跡地にあり、かつては藩主の御用屋敷があった。現在は、御隠殿と呼ばれる藩主の隠居所の一部と酒井氏庭園に加え、広大な敷地を利用して旧西田川郡役所、旧鶴岡警察署庁舎、旧渋谷家住宅が移築され、さらに収蔵庫・民具の蔵がそれぞれ独立して配置されている。庄内藩校致道館の資料、書院造の庭園、民具など、重要有形民俗文化財8種5,350点を収蔵・展示している。


重文・西田川郡役所。
1878年(明治11年)に山形県初代県令となった三島通庸の命令により、現在の鶴岡市馬場町に建設され、棟梁の高橋兼吉や石井竹次郎らの手により1881年(明治14年)に竣工したルネッサンス風の擬洋風建築である。
中央玄関2階にバルコニー、建物中央に時計塔が付いた木造2階両翼1階建てで高さは20メートルである。
内部は庄内地方の考古学資料などを展示している。



越中山(えっちゅうやま)遺跡。
山形県鶴岡市越中山にある後期旧石器時代から中石器時代にかけての遺跡群の総称。赤川と梵字川の右岸に発達した立岩段丘群中,洪積低位の大鳥苗畑面 (GtII面,標高 100m) と中位の越中山開拓地面 (GtI面,標高 130m) の二つの広大な段丘面に立地している。石器群の包含層はいずれも段丘を覆う鶴岡ローム層の最上部である。 GtII面のA遺跡は,1958年東北地方で最初に発掘調査された旧石器時代遺跡である。その後,致道博物館 (鶴岡市) ,山形大学,朝日村教育委員会が協同調査を実施。少なくとも四つの階程の石器文化が明らかにされており,(1) 国府型ナイフ形石器を主体とするもの (K遺跡) ,(2) 半両面加工尖頭器,ナイフ形石器を伴うもの ( A' 遺跡) ,(3) 細石刃を主体とするもの (S,M遺跡など) ,(4) 両面加工尖頭器を主体とするもの (A遺跡) があることがわかった。
5遺跡からは北海道と同じ作りの石器が見つかっている。K遺跡からは、近畿地方など、西日本に見られる作りの石器が見つかっている。これらから、石器の材料となる石が遠くの地域から運ばれてやって来たと考えられ、当時の人々が大移動をしていたと推測されている。



吹浦(ふくら)遺跡。
牛渡(うしわたり)川北岸台地上にある縄文時代前期末葉~中期初頭の集落跡で、鳥海山泥流台地の西南麓、吹浦川の北にあり、縄文時代前期の吹浦式土器の出土地として知られている。
庄内平野と庄内砂丘の北端を限る山裾にあり、眼下の牛渡川が遺跡の西で月光(がつこう)川(吹浦川)に合流してすぐ日本海に注ぐ。縄文海進時には河口から内陸深く潟湖であったと推定される。
1951~53年に致道博物館が4次の調査を行ない,台地上から住居跡,袋状土坑,石器製作跡,台地崖面から洞穴,ヤマトシジミ主体の小貝塚を発見。
土器には長胴の深鉢形土器と球胴の鉢形土器があり,当遺跡を標識として吹浦式土器と呼ばれ,東北北部の円筒式文化圏と東北南部の大木式文化圏の接触型式とされていたが,その後の検討で大木式系を主体に一部円筒式の影響を受けた土器群と考えられている。
石器は鏃 (やじり) ・槍・錘・擦切磨製石斧 (せきふ) ・砥石 (といし) 等のほか 玦 (けつ) 状耳飾りが見られ,縄文前期の特色が見られる。イシガメ・クジラ・イノシシ・シカ等の動物,オニグルミ・クリ等の植物も検出された。 83,84年にはバイパス工事に伴い山形県教育委員会が再調査し,縄文期の竪穴住居跡,土坑多数のほか,平安時代前期の竪穴住居跡,大型掘立柱建物跡が確認され,拠点集落の存在が推定される。


遺跡近くには大物忌神社や神宮寺があるが,『三代実録』によれば,885 (仁和元) 年6月,出羽国飽海郡神宮寺西浜の地で石鏃が発見され,それに関連して大物忌神社に奉幣した記事が見える。吹浦遺跡との関係が注目され,9世紀の正史に天変地異として石鏃発見の記録があることは興味深い。
山形県の縄文中期前半の文化動態 多賀城市埋蔵文化財調査センター 菅原哲文
1 はじめに
縄文時代中期前半は、今から約 5,500 年前から約 5,000 年前の時期である。山形県内の状況は、中期初頭から前葉、中葉にかけて遺跡数の大幅な増加が認められ、各盆地に拠点的な大規模集落が形成されていく。また、そのような拠点的集落跡には、10mを超えるような大型住居跡が建てられ、全体として放射状や環状の配置がとられていた。集落の中で不要となった土器、石器などを廃棄した捨て場も形成され、数百箱や千箱を超えるような出土数量となる。また、土偶や石棒を用いる縄文時代の祭祀が盛んに行われるようになる時期でもある。
ここでは、県内の縄文時代中期前半の文化の様相を、縄文土器を中心に検討していきたい。
2 縄文土器に見られる活発な文化交流
大木式土器は東北地方南部を中心とする縄文時代前期から中期の土器型式であり、山形県も分布域に含まれる。宮城県七ヶ浜町大木囲貝塚の土器を標識とし、山内清男により土器型式が設定された。大木式土器は幾つかに細分されており、中期前半は、大木 7a・7b・8a 式である。
県内の中期前半の大木式土器が出土している代表的な遺跡として、最上町水木田遺跡(中期初頭・前葉)があげられる。
当遺跡の出土資料は、中期初頭・前葉の大木7a 式土器、大木 7b 式土器が中心であるが、中期中葉の大木 8a 式土器も報告されている。遺物出土箱数は 1000 箱に及ぶ。平成 23 年に出土資料は重要文化財に指定された。
水木田遺跡で出土している大木 7a 式土器には、関東や中部地方を主な分布域とする五領ヶ台式土器の影響を受けたと考えられるものが認められる。この五領ヶ台系の土器は、山形県内だけではなく、福島・宮城・岩手・秋田県の広域にわたって出土している。
次の時期の大木 7b 式土器は、当遺跡の出土の主体を占めている。大型の長胴の深鉢、4単位の大波状口縁、波頂部の装飾、体部の Y 字状懸垂文や縦方向の綾絡文などが特徴的で、押圧縄文による装飾も多用される。この時期も引き続き五領ヶ台系の土器が伴う。他の地域からの影響が見られる土器として、北陸の新崎式土器が少量ながら出土し、北東北に由来する円筒上層b式土器も認められる。
山形県内の中期前半の縄文土器は、大木式を主体としながらも、関東地方、北陸地方、北東北などの他地域の影響が見られる土器が含まれ、広域にわたる土器文化の交流が顕著に表れる時期といえる。また県内の各地域では、その影響の受け方について、それぞれ特徴的な在り方が見られる。
庄内平野と周辺地域の様相
当地域は日本海沿岸に面しており、海沿いのルートを通じて縄文時代前期から北陸地方や北東北の影響を受けてきた地域である。遊佐町吹浦遺跡では、前期末大木 6 式期を主とする時期であるが、北陸地方や北東北に見られる土器が出土している。この傾向は、中期初頭・前葉を通じて認められる。
中期前葉の時期であるが、鶴岡市(旧羽黒町)郷の浜 J 遺跡は前期末大木 6 式期から大木 7a 式期の土器が出土している。内容を見ると、北陸の新崎式が出土の多くを占めており、大木 7a 式土器は客体的である。円筒系土器も量的に多くはないが出土している。
鶴岡市西向遺跡は、中期前葉の時期に位置づけられる。北陸地方の新保・新崎式土器が出土の主体を占め、全体の 74%と報告されている。北陸系土器は 6 群に分類され、2 段階の変遷が想定されている。大木式土器については大木 7a 式、7b 式土器が出土しているが、北陸系土器の手法を用いて文様が描かれたものがある。北東北に由来する、円筒上層 a~c 式土器が少量ながら出土している。
北陸系土器の出土が顕著な傾向は庄内地方の他遺跡にも認められる。
酒田市飛島に位置する蕨山遺跡では中期前葉の北陸系土器、大木 7b 式土器、円筒上層 b 式を主とする土器が出土している。
遊佐町小山崎遺跡でも、前期末~中期前葉の時期の北陸系土器が出土している。
中期中葉の大木 8a 式期になると、北陸系土器の出土割合は少なくなる。円筒上層式土器も稀である。
鶴岡市岡山遺跡では、第 6 次調査で大木 8a 式土器が出土の中心を占めているが、少量ながら馬高式土器の出土が認められる。
遊佐町柴燈林遺跡では、全体の器形が把握できる火焔形の馬高式土器が出土している。大木 8a 式期に伴うものである。同地点で出土している 8a 式土器は、突起の形状などが馬高式土器の影響を受けたとみられるものや、県内の内陸では見られない形態のものも確認される。



岡山遺跡。
岡山集落背後の通称岩台(いわだい)という台地頂上部にある。標高約61m。岩台は「大泉旧聞抄」に石鏃出土地とあり、江戸時代中頃から幾多の研究者が訪れている。縄文時代の集落跡であるが平安時代の遺物も出土し、山頂に遠賀(おが)神社跡がある。遺跡の範囲は頂上を中心に南北350m、東西250mと広範で、標高50mの傾斜面まで含まれる。
この遺跡から出土した「中空の大型土偶の頭部」は、致道博物館旧西田川郡役所内で展示されている。



杉沢の土偶。複製。山形県遊佐町杉沢遺跡出土。
1952(昭和27)年、遊佐町杉沢地区から縄文晩期中葉(約2500年前)のものと推定される「杉沢の土偶」が出土した。高さ18.3cm、頭部の一部が欠けたほかはほぼ完全な状態である。現在は奈良国立博物館に国の重要考古資料として収蔵されている。
ほぼ完形の中空の土偶であるが、右の頭髪部などを若干欠損する。目はいわゆる遮光器(しゃこうき)状に表現され、肩や腰の文様は縄目文様を施した後に部分的に縄目をすりけす、磨消縄文(すりけしじょうもん)の手法で飾られ、腹部を縦に貫く線は、2重の隆線で強調されている。また臍(へそ)の部分は内部に連なり、腰部の文様も巧みに強調して表現されている。
出土状況は特異で、北側と東西に、約20センチメートルの川原石を置いて作った石囲の中に、頭部を北に向けて仰臥した状態で埋納され、その上に長径約30センチの蓋石が被せられていた。あたかも人間が埋納されたかのように置かれ、土偶の性格を考える上に貴重な出土例である。


環状注口土器。山形県有形文化財。
縄文時代後期の土器で、松森胤保(たねやす)が『弄石(ろうせき)餘談』で「夷五器」として、この土器を挿図入りで紹介している。江戸時代に岩手県一ノ戸の条右衛門の所持であったが、明治に庄内の研究家達の手を経て現所蔵となっている。出土地は岩手県一ノ戸町あたりと考えられる。
胴部がドーナツのように環状で、肩部に大きな注入口、反対側に注出口をつけた痕跡があり、底には高台をもつ特殊な器形である。器高は15㎝、胴部上端までが7.5㎝、胴径12.5㎝、高台の高さ1㎝、底径4㎝、胴部の容積は約390ccである。注入の口縁部は波状の起伏があり、沈線の間を刺突文で埋めた文様がある。胴部は縄文を地文として、弧状の沈線で連結文を施し、文様の接点に小さな瘤を貼り付け、部分的に縄文を磨り消している。
精緻精錬されたみごとな土器で、祭祀などの特別な用途とみられる。



玉川遺跡。縄文時代晩期。
羽黒街道の大鳥居から南に約1km、標高100m前後の地にある。昭和26年(1951年)から発掘調査が実施され、縄文時代中~晩期の遺物と集落跡が発見された。
中期と晩期の竪穴住居跡5軒は、平面が直径5m前後の円形ないし楕円形で、石囲炉や地床炉があった。B地点で23個、C地点で29個と集中的に出土した埋甕は、人骨を納めた晩期の甕棺墓で、日常の深鉢を使っており、磨製石斧や硬玉製勾玉が入っていたものもある。また、組石棺や集石遺構も出土している。多くの土器とともに打製・磨製の石器類、土版・岩版・土偶・三角土製品も発見されており、ことに玉類の出土数は、実に約150点を数え特筆される。
庄内でも有数の広大な遺跡で、長期にわたり縄文人の生活が展開していた。C地点の一部が指定され保存されている。


玉川遺跡は縄文時代中期から晩期の遺跡で、江戸時代から多量の玉類が出土する地として知られていた。この玉類は晩期の遺跡から出土し、不老長寿などの霊力をもつものとして首や胸飾りにもちいたと考えられる。勾玉、丸玉、小玉などの形で、翠緑色をしたヒスイ製のものは、その原産地が新潟県糸魚川周辺に求められる。
玉川遺跡から出土した硬玉製主体の玉類は、致道博物館、鶴岡市、個人など6件でそれぞれ所蔵し、合計149点が指定されている。
大半は地元民の採集品であるが、致道博物館所有の一部は、発掘調査による出土品である。玉類の種類は勾玉・丸玉・臼玉・小玉で全長55㎜の勾玉を最大とし、小玉の径6㎜を最小とする。硬玉を用いているが、緑色の見事な翡翠(ひすい)も使われ、縄文時代晩期の製品とみられている。
これらの玉類は縄文人の首飾りやペンダントである。翡翠は原産地の新潟県糸魚川(いといがわ)市姫川流域からの移入で、縄文人の広範な交易を示しており、高度な研磨や穿孔(せんこう)の製作技術、さらに玉類着用に係わる独特な信仰など、魅力的な課題を含んでいる。


重文・青銅刀子。複製。遊佐町三崎山出土。
所蔵:東京国立博物館。殷時代・前11世紀. 青銅製. 長26cm 刃長16.6cm 脊厚0.75cm 。
吹浦地区の三崎山から出土した。日本列島において最古級の金属器であり、大陸との交流を考える上で極めて貴重な文化財である。
青銅刀子は昭和29(1954)年晩秋、遊佐町三崎山で採石作業中に出土した。その後、致道博物館や山形大学柏倉亮吉教授などが出土地周辺(三崎山A遺跡)を調査し、縄文土器やシカ骨などが確認された。学会に報告されるや、「中国から渡来した日本最古の青銅刀子」と話題をよんだ。国の重要な文化財として買い上げられ、現在は東京国立博物館に収蔵されている。日本がまだ縄文時代後期のころ、大陸の青銅文化が鳥海山麓三崎山にどのようにして渡来したのだろうか。刀子は、中国・シベリアなどでの出土例も報告されている「オルドス型」である。
昭和62(1987)年にソ連の学者グループが現地を踏査するなど国際的な研究もなされ、平成13(2001)年に東京文化財研究所が行った分析の結果、中国商時代の特に殷墟(いんきょ)出土の青銅器と同じ鉛の成分率であると報告された。日本列島での金属器文化渡来を考える上で重要な資料である。

刻文付有孔石斧(刻文付石鉞)。縄文時代中期。
山形県鶴岡市羽黒町の中川代遺跡から出土した古代中国の刻文付有孔石斧。付着した土の成分分析から中川代遺跡からの出土と確認された。縄文時代中期中葉の大木8a土器に伴って出土した。
形・厚さ・石質・孔の開け方が、古代中国と類似している。
広島大学教授(当時)李国棟氏の説では、古代中国長江デルタに栄えた良渚文化(BC3400~2250)のもので、甲骨文字風刻文は、「之」と「生」の合体字で「之越而生」。良渚国の亡命者が身分証明書として刻字、携えたもの、とする。

田川太郎と奥州合戦。
田川行文(ゆきぶみ。田川太郎)は奥州藤原氏の郎党で、平安時代後期に出羽国田川郡(現・鶴岡市田川)を本拠地として、田川郡郡司となり庄内南部一帯を治めて栄えた豪族である。奥州藤原氏の命を受け、羽黒山本社を修造したとの伝記が残り、源義経の「義経記」にも田川太郎が登場する。
文治5年(1189年)、鎌倉幕府の奥州征伐に際し、主君・藤原泰衡の命を受け、秋田致文と共に、越後国方面より北進してきた比企能員と、宇佐美実政の率いる幕府軍と戦って敗れ、さらし首にされた。
行文の墓は、田川氏の菩提寺である蓮華寺があった所と言われる鶴岡市田川字蓮花寺の北端にある