先日のブログで、『葉型陽刻色絵網漁人図変形皿』を紹介しました。しかし、この品は、はたして古九谷なのか、古九谷写しなのか、はたまた、悪意のある贋物なのか、判然としませんでした。
この皿を入手してから数年後、同じような皿をみつけました。それが今回の品です。



13.7㎝ x 16.4㎝。高台 8.7㎝ x11.0㎝。高 2.4㎝。明治。
楕円形の変形皿です。大きな葉形の陽刻があります。中央の縦形のキャンバスには山水紋が描かれています。

先日のブログで紹介した『葉型陽刻色絵網漁人図変形皿』と同手の皿です。
葉形模様の配置が違うように見えますが・・・

180度回転すれば、同じ配置です。

この二つは単なる模様違いの同手皿か?
せっかくですから、少ししつこく(^^;二つを較べてみることにしました。
まず、今回の品は以前の物より少し大きいです。そして高さが少し低い。扁平です。
また、素地が今回の品は白いです。さらに、染付けは併用されておらず、赤絵のみの絵付けです。
高台の違いは大きいです。

以前の皿の高台はやや内向きに作られていますが、今回の品は垂直な高台で、少し低いです。
先の皿は見込みが厚く、端は薄くなっています。
光にかざすと陽刻の葉脈も見てとれます。

今回の皿は、全体が薄造りです。はっきりとはわかりませんが、陽刻の葉脈はどうも無いようです。

以前の品(向こう側)の高台畳付には、融着を防ぐためでしょうか、細かい砂が付いています。今回の品(手前)には、付着物は全くありません。

この皿の周囲には、鎬が3か所あります。二つの皿でその位置は同じなのですが、凸凹の具合が微妙に異なります。

以前の皿(上側)と今回の皿(下側)を較べると、下の皿では鎬の数が少ないように見えます。その理由は、両端の稜線が下側でははっきりしない(無い?)からです。
また、今回の品には、以前の皿の右上にあった一本の稜線がありません(5枚目の写真)。

裏側面の折松葉模様自体は同じですが、描線の走りに大きな違いがあります。

上側はピュッと走った直線的な松葉紋なのに対して、今回の品では筆の運びが遅く、でこでこした曲線になっています。描きなれていないのですね。
どうやら、今回の品は、少し手抜きをして、以前の品の写しを作ったと考えてよいでしょう。


染付を併用せず、赤絵のみを使った絵付けや簡略化された地紋の放射線なども、そのことを裏付けています。
以上の事柄を総合すると、今回の皿は、以前紹介した『葉型陽刻色絵網漁人図変形皿』と同時代に造られた物ではなく、近年の作であろうと推定されます。
絶対的な製作年代を特定することは困難ですが、このような手の込んだ変形皿が江戸前期に造られたとは考え難く、1700年代に入ってからの作でしょう。その意味では、『葉型陽刻色絵網漁人図変形皿』は、骨董屋が言う江戸中期の古九谷と言ってよいのかもしれません(^.^) 一方、今回の品、『葉型陽刻色絵山水紋変形皿』は、明治以降につくられた写しと思われます。













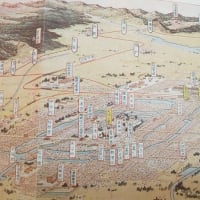




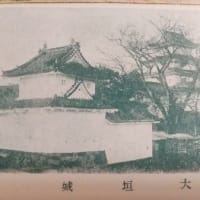
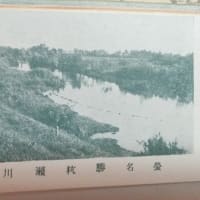







同じ手のものを手に入れられていたんですね(^^)比較検証ができるのがすごいです。。
確かに前回の品の方がスレなどもあり古格を感じました。放射状のデザインのあたりは松ケ谷手を感じさせる雰囲気もあるなあと思っていました。
伊万里でも江戸時代を通して造られているデザインはありますもんね!?
そういったところも参考に後世で造っているのかなあと。
ただ時代推察はかなり難しいですね。
全くもって悩ましい所ですね(⌒-⌒; )
でもその辺りが面白いところでもあるんでしょうね(^^)
私も、遅生さんの考察に賛同いたします。
これは、以前とりあげた、「色絵 丸散文 草花陽刻 瓢簞形小皿」と共通する問題ですよね。
昔は、「古九谷」は、九谷で作られたものとされ、超高級品として扱われ、極く少数の物のみが「古九谷」とされてきましたよね。それだけに条件が厳しくなり、ちょっとでもその条件に反すると偽物とされましたものね。
それが、産地論争で有田説が優勢になってくると、今度はその反動で、ワ~ット市場に登場してきて、どのようなものまでが古九谷様式の範疇に属するのかが分らなくなりましたよね。
でも、考えてみますと、一つの様式というものは、ワーット出現しても、或る時を堺にパタリと無くなるわけではないですよね。人気のある様式のものは、その後も、量の多少はあるにしても、作り続けられますよね。
今後はその辺を整理すべきではないかと思っているんです。
その意味でも、私は、様式区分には強くこだわらず、様式区分から外れたものは全て偽物とするのではなく、何時作られたかを重視すべきではないかと思っているんです。
が、あくまで一応です。
要するに、ある様式にピタッと当てはまるわけではない物が、結構あるのではないかと思うのです。それはそうですね。様式は後の時代の人間が作った区分けですから。もちろん時代のトレンドや雰囲気は品物に反映されるのでしょうが、そこから外れる物も当然あるはずです。
私などはへそ曲がりですから、そういう物に妙に惹かれてしまいます(^^;
松ケ谷は恐れ多いので、杉ケ谷手くらいなら何とか(^.^)
古染付もそうですが、本当に文字通りの古九谷といわれる品は、そうそうその辺に転がっているはずはありませんね。ボーダーが広がってあやふやになり、前期の色絵磁器なら何でも古九谷では、古九谷の有難みが低下するばかりです。
以前にもコメントで書いた思いますがと、古九谷椿紋皿をいただいた戦前コレクター関係者の所にうあった五彩手のブチ割れ大皿(40㎝オーバー)を勇気を出してもらっておけばよかったと、今でも悔やんでいます(^.^)
改めて自分の中の古九谷の経験値の少なさを痛感する次第です。
こういった珍しいタイプの品であるがゆえに、「ありそうで無い」のか「無さそうである」のかが
判断できないのかも知れません。
時代は別にして、珍しい古九谷様式の品という点は二つの品に共通しているのように思います。
極端なことを言えば、その日の気分によって見え方が変わってきます(^^;
ゆれ動くコレクターごころですね(^.^)
実は、このタイプの皿で、もう一種、鶏の絵付けのを見た事があります。いつか入手して、三枚を比較すれば、もう少しはっきりしたことが言えると思います。
今日のぽぽさんのブログにあるように、古九谷論争はまだまだ続きそうですから、こういうニッチ物に陽が当たる時が来るかも知れません(^.^)