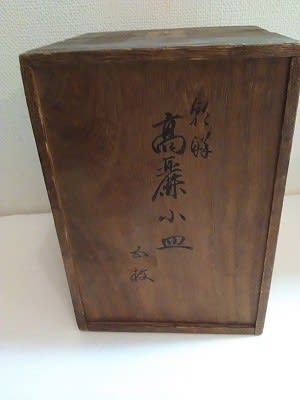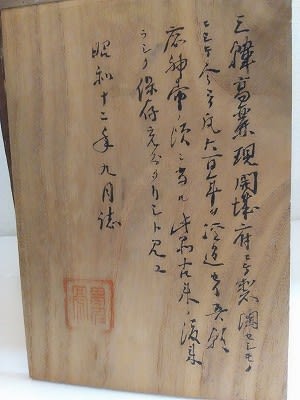青磁象嵌雲鶴紋梅瓶です。





最大径 23.4㎝、口径 7.0㎝、底径 8.9㎝、高 40.6㎝。時代不詳。
大きな青磁の壷です。青磁釉は透明で、ビッシリと貫入があります。
胴には黒丸の内外に多くの鶴が、その間には雲が配置されています。
肩と裾には連弁紋、鶴の間を雲が配置されています。
この種の壷は、高麗青磁の定番の一つで、現在でも盛んに造られています。

黒丸の中の鶴は40匹、丸の外側には24匹の鶴がいます。

丸の中の鶴は空へ、外の鶴は下向きに飛んでいます。


奇妙な事に気が付きました。丸の中央(鶴の腹)には、必ず小さな穴が開いているのです。外側の鶴には穴は開いてません。これは一体どうしてでしょうか。丸く削る時に、コンパスのような道具を用いたのでしょうか。穴くらい、埋めておいてほしい(^.^)
もう一つ、不思議があります。

よく見ると、鶴の腹部が凹んでいます。丸の内側の鶴も、外側の鶴も、同じように腹部が凹んでいるのです。ツルの腹部を指でグッと押さえたように思えます。
一体、何のために?


よーく見ると、凹んだ部分は、外の部分よりも青磁釉が厚くなっているので、少し青色が濃いです。丸の内の鶴、外の鶴、いずれも青味が他よりも少し増しています。
こうやって鶴を強調しようとする試みだったのでしょうか。

下部の連弁紋です。
よく見ると、弁の中央に、◯が縦にならんでいます。これは本来、真中に黒点がある白の◯なのです。
本歌の青磁象嵌雲鶴紋瓶(『世界陶磁全集18 高麗』)が本に載っています。

本歌と較べてみるとわかります。
この品は、削った所に、白、黒の土を入れるのを忘れているのです(^^;
そして、底部。

巧妙な直しがあります。0時、2時、6時、9時の辺りに共色直しが施されています。窯の中で底がくっつくの防ぐために、土を置いて焼成したのですが、焼成後、取り出す時に、数カ所、大きな疵が出来たのだと思います。その部分を補修したのですね。
この品、いくつか不思議な点があります。試作品、よく言えば、新たな試みに挑戦した品?いずれにしても、立派なコピー品を作ろうとしたとはとても思えません。普通なら、物原行きの品ですね(^^;
解せないのは、そんな品に、立派な(^^;)直しを施したことです。以前の李朝染付草紋大徳利のように、駄品に直し?
フシギの品です(^.^)